 |
|
|
12月6日、「1分間自己紹介」の設定は、町内会に新居住者があった。この歓迎の席のこと。新居住者から挨拶があったのに続いて、現在の住民(町内会役員)から、自分や家族の紹介、この町内の良い点などを織り込んで自己紹介をするというパターンに挑戦である。ポイントは住んでいる場所をわかりやすく詳しく紹介すること。
公園の西出口の所です。とか○○商店の斜め前です。とか、バス停の近くです。とか。小・中・高校生がいればちゃんと学年まで紹介する。ただし就職や結婚で県外へ出ている子弟は「上二人は県外におります」程度に省略する。なかなか結婚しませんで…とか、福岡県で教職についております、などの詳しいことは略する。
学級長が休憩時間に〈自主講座で継続するか〉について意見を各人に求めた。継続が多かった。忘年会の決定と場所のPRをした。
忘年会というのはただ「酒を飲んで騒ぐ」場ではない。プライベートな情報交換の場でもあるから貴重だ。2分間スピーチは「結婚式の祝辞」。教室の受講記念のヒデオ撮影も行なった。
12月13日、最終回。1分間自己紹介は「カラオケボックスでの自己紹介」。これはぐっとくだけて楽しく短く自己紹介をする必要がある。自分の愛称、たとえば蛯原さんなら「今夜はエビちゃんと呼んで下さい!」とか、美智代さんなら「今夜はミツチーと呼んで下さい、」とかの紹介をする。
そして好きな歌の曲名を1〜2曲紹介するとその人のイメージがわかりやすい。歌う場にきて、「私は歌はニガ手で…」と紹介するのはその場の雰囲気をもり下げるので愚作。せめて「歌は下手ですが聞くのは大好きです!」等の気配りは必要。
2分間スピーチは自由題だが、特になければ「話し方教室に参加して」の感想を述べてもらった。感想は「きびしかった」という人や「この種の勉強は初めてだが有意義だった」の声があった。いずれもビデオ撮影を行なった。
12月は師走で私も本業が忙しいので、ビデオは収録したが編集の時間が作れず、そのまま置いている。暇になったら編集してDVDにして手渡すことにしている。
修了式は岩元指導員が声帯を傷めているため加藤さんが代読し、来期も開設予定であることを述べた。
翌14日は忘年会があり、佐土原ビデオクラブ会員と合同で賑わった。ふだん1分自己紹介スピーチなどで「人となり」がわかっているせいか、とてもうちとけて楽しい座になった。
Kさんが「自分はこういう教室がないか探していた。今回あったので喜んで参加した。これからも自主講座に参加して研鑚をしたい、」と語られたことが印象に残った。宮崎市内の人だが、佐土原も宮崎市になったことで佐土原の公民館へ出席することが可能になった。 |
|
|
|
今回が最終回。前回撮影した映像を編集してDVDとVHSで希望者に配布した。
前週欠席したKさんについても録画した。1分間自己紹介は「カラオケボックスで自己紹介」。それと2分スピーチは自由題だが「話し方教室に参加して」の感想が中心となった。
内容的には上段の那珂公民館と同じなので省略する。ビデオ(DVD)を見れば、自分のありのままの姿がよくわかる。よい教材である。自分がしゃべっている姿を見る機会は少ないので、驚かず、欠点は直し、良い点は認めてやる心構えが大事である。はじめは「欠点」ばかりが目立つが、それにとらわれてはいけない。
「話し方」は受講希望者はあっても指導者がいないのが現状だ。むずかしい分野といえば確かにそうだ。私が大阪まで勉強に出かけ学んだことが宮崎の皆さんに役立つことは意義あることで、指導してくれた「上六話し方教室」の三品先生、そして何かにつけて協力してくれた同期生にあらためて感謝したい。
私は「口下手な人」にエールを送る役でありたい。なぜなら私がそうであったからだ。
〈思い〉はあっても、それがうまく言葉にできない。世の中にはそんな人が多いのではなかろうか?これは「練習」することでかなり改善する。しかしその練習の場がどこにあるだろう。なければ私が作ろう、そんな思いで教室をはじめた。
言葉というのは気持を伝える手段だ。言葉だけ先行してはいけない。まず「気持」があって、それを言葉にすべきである。コトバという語は古語では「コトダマ」と言い表す。言魂である。言葉には魂があり気持が付いているものだ。「言葉あやつり」だけ上手になってはいけない。
時には「沈黙」もいい。沈黙や間は値千金である。 ただし沈黙だけでは「無」である。
小戸公民館も那珂地区公民館も「自主講座」で継続することになった。私なりに新しい工夫を入れて特色ある講座にしていきたい、と意欲を燃やしている。
映画「しゃべれども、しゃべれども」を観たとき、話はただしゃべればいいものではない…ということがわかった。間が必要なのだ。しゃべりはロジカル(論理的)なものだが、間は(感情を)表現する。両者一体となって気持が相手に伝わる。ペラペラと「立て板に水」のしゃべりは、うまいようだが「セールスマンしゃべり」といってむしろ相手に嫌われる。きき手の気持を汲む「間」が必要だ。うまい演説は「間」で聴衆を引き込む。
新宿の末広亭という寄席に行ったときに、「お囃子」にのって話し家が登場した。もしあの「お囃子」がなく−無音で−噺家が登場したらどうだろう…おそらく盛り上がらない。テーマ音楽というものは雰囲気助成に絶妙な効果を発揮する。
最近では野球選手や拳闘家の登場シーンにまでテーマ音楽が使われる。そこで「話し方教室」でも、Aさんが登場するときはAさんのテーマ音楽が流れたらどうだろう…きっと気持が昂揚して「のる」に違いない。自主教室ではこれを試みてみたい。
「話し方」といっても所詮は趣味である。今から真剣に話し方を勉強して就職しようというわけではない。楽しみながら勉強できれば最高だ。 下欄は忘年会の写真です。 |
|
 |
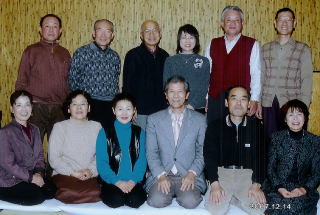 |
| 忘年会/小戸公民館の受講生 |
那珂公民館の受講生 |
|
この講座の特徴は写真でわかるように年齢層が幅広い。それぞれに人生経験が豊かな人ばかりである。いまさら「話し方」でもあるまいに…との声がきこえてきそうだが、現実に人との折衝が多い立場の人ほど「話し方」で苦労をしている。勉強や訓練の場がほしいのは当然ともいえる。
「話し方」の究極の目的は「話し方がうまくなること」ではない。《人間関係の円滑化》にある。
次頁から「自主講座」になるので、大まかな計画を示しておく。興味のある人はご覧下さい。 |
|
|
|