宮崎千年神楽シリーズ1
プロローグ
創作神楽悪七兵景清(久保伝説) ![]()
宮崎千年神楽シリーズ1
プロローグ
時は、平安時代、平家軍団の中でもつわものと言われた悪七兵衛景清がいた。京都清水の観音菩薩は景清が信仰した唯一の仏様です。平家滅亡後、熱田に身を隠していた景清も観世音菩薩の斎日である毎月18日には清水寺に参詣していました。この観音信仰があだとなって源頼朝に捕らわれますが、自分に敵対する気がないことを悟った源頼朝は景清を許し日向勾当(こうとう)とし、宮崎郡北方、南方、池内村、計三百町を与えた。景清は高妻八郎兵衛政藤と家森越中守忠都の諸氏を引き連れて日向に下り、下北方古城に住まいを定めました。しかし、景清に怨みを持つ源氏の一部が日向に下る景清を討ち取ろうと構えるが、観音菩薩の化身により平家相伝の神刀を授かり源氏の悪鬼を退治し一命を救われます。景清は無事日向の地に赴くと、深く神仏に帰依し、神社、寺などを建立、天下泰平、庶民の健康を祈願し上村に久保千手観音堂を建て、村人はこれを村の守り神として祭ってきました。ここに久保千手観音の御霊に神楽を奉納するものである。
一幕 「日向勾当」(鎌倉落ち)
景清:そもそもこの所に進み居でたる者、平家の一門上総七郎兵衛景清。
また、これなるは我が家臣にして高妻八郎兵衛政藤と申す者にて候。(礼)
我この所に出できたる事は、余の義にあらず。このたび源氏との戦により平家一門は滅び我頼朝に捕われしが追放され、日向の国へ宮居を定めんと駒足を進めばやと思うなり
二幕 「悪鬼追討」
近経:そもそもここに忍び現れたるは、悪七兵衛景清に恨み持ちたる我が名は源氏の本田二郎近経、またこれなる榛沢八郎と申すものなり、景清が日向の国に下りしと聞き、待ち構え、景清討ち取らんぞと思うなり。景清が鎌倉をい出たるを聞き及びたるは頼朝公警固武士大将美尾屋十郎国俊に言上つかまつるべく道を急がんぞと思うなり。
近経:警固武士大将美尾屋十郎国俊に言上申して候。景清が日向に下向するため鎌倉を出たことを聞き及びて候。
国俊:なんと悪七兵衛景清が鎌倉を出たと・・さらばここで待ち構え、平家一門の怨みみごと放してくれようぞ。
近経:心得申して候。
三幕 「悪鬼待ち伏せ」
景清: そこに立ち向かいたるは、汝如は何なる者ぞ。我を景清と知りてのことなるか。
国俊: おお我はこれ、源氏は頼朝公警固武士大将美尾屋十郎国俊なり、屋島の合戦に勝負を分かち別れしが、我を見忘れは致すまい。平家への我が一族の怨みいかばかんなるものぞ。景清、汝の首をここで打ち取らんぞと待ち構えし候。
景清: いかにも覚えあり国俊よ、屋島にて我がために鎧のしころを千切られし、それが恥をそそがんと思うての見参なるか。
国俊: 景清、最後の勝負つけてくれん。いざや立ち合い勝負勝負。
国俊: ああ・・うれしやなあ!我らがはかりごとにはまりし景清。ついに景清倒れたり。かくなる上は、我ら夜叉となりまた、我も鬼と化しこれよりやつらの首を討ち取るなり。
四幕 「観音菩薩のお告げ」
観音菩薩: 我は清水の観音菩薩の化身なり、我ここに居できたること世のぎにあらず、信仰厚き景清の一命怪うしと思えたり。よって汝らを助けるなり。汝らにこの神刀、また我が太刀を授けるものならば、速やかに源氏悪鬼退治するもなり。
(太刀を置く)目を覚ましそうらえや景清よ
景清:あら夢かうつつか幻か、清水の観音菩薩現われ、これなる神刀授かり、ありがたしもったいなし、観世音菩薩また天地神のご加護を頂き、天つ御神の御稜威を背に受け、天の神刀の威徳をもって、ここに源氏悪鬼追討軍を速やかに成敗いたさん。
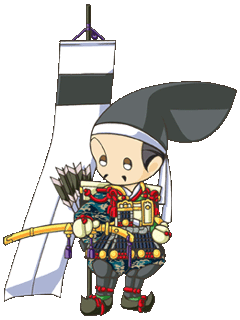
五幕 「神刀」
景清:我も観音菩薩のご加護を頂き、ここに汝らを退治せばやと思うなり。我がこの神刀切っ先受けそうらえや。
国俊:何の!観音菩薩ごときご加護で我らを成敗するとは片腹痛し、いざ勝負勝負。
景清:えいっ、やぁっ
六幕 「最後の戦い」
国俊: あら残念なり無念なり、我、鬼となり千年も万年も生き長らえて平家一族を滅ぼさんと思いしが、今我が兵ら汝らの神刀の錆になるとは無念なり。返す返すも無念なり。さらば我が妖術をもって汝らを悩ません。
景清: えいっ、やぁっ
七幕 「勝利の舞い」
景清: あら、嬉しやの、清水寺の観世音菩薩及び天地神のご加護により源氏の追討軍も退治したならば、平家の御霊を祀り、天下泰平を祈り、民の病を癒さんと神仏に帰依する所存なり、これよりは観世音菩薩の導きにより日向の国に宮居を定めんとし喜び勇んで立ち行かん。
エピローグ
平家の勇将である景清については、各地に様々な伝承があるように宮崎にも古くからその伝説が残っています。瓜生野の久保千手観音堂には景清の遺品とよばれている千手観音が安置されています。景清は静かな余生を送りたいと考えていましたが、源氏の隆盛を見聞することにより煩悶し続け、その苦しさから逃れるため、両眼をえぐり空に投げ、現在目の神様の生目神社にその景清の両眼を祭っているといわれます。また霧島山の参詣のため登山しましたが、その帰途、建保二年八月十五日、山中の池のほとりで病死します。享年六十二才。遺骸は宮崎市下北方町景清廟であると言われています。神楽での高妻八郎兵衛政藤は生目八幡で景清の霊を慰め奉ったと云われ、また本田二郎近経は神楽では追討軍になっていますが来宮し景清に勾当の官を許し頼朝公の御墨付きを与えます。頼朝公の厚遇に景清の付人高妻八郎兵衛政藤と家森越中守忠都は只々感泣して有難くそれをお受けしたと云われています。
歌「かげ清く照らす生目の水鏡、末の世までも雲らざりけり」
| 原稿作:Kanai | 曲:日向橘寿獅子七人衆 | 協力:宮崎市大坪保育園 |  |
| 平家 | 源氏 | 演奏 | |
| 上総七郎兵衛景清:小林 | 美尾屋十郎国俊:長友 | 大太鼓 :金井 | |
| 高妻八郎兵衛政藤:石村 | 本田二郎近経 :畑中 | 締太鼓 :清水 | |
| 榛沢八郎 :横山 | 観音菩薩 :図師 | 笛 :山下 | |
| 手打鉦 :伊崎 |
![]()
![]()