【会えない悩み語りませんか(3)】 11月28日(水)
「kネット九州@宮崎」さんの交流会に参加して、子どもや孫に会えない人たちの話を聞くうちに、昔の感情がよみがえってきた。
やはり基本的な考え方は、「ファーザーズ・ウェブサイト」と同じだった。
12年前の自分たちがそこにいる、という感じを受けた。
私も、自分なりにもがいてきた過去の話を、ありのままにさせていただいた。
どんなに注意しても、経験話には自慢めいたにおいがしてしまうものだ。
それでも私には、どうしても伝えたいことがあった。
「絶対にあきらめないでください」
離婚して、親権を奪われ、愛する子どもに会えなくなった。
そのことが意味するのは、過去の後悔と、孤独な現在と、希望の持てない未来だ。
心が折れて、子どもの存在すら手放してしまいそうになることは、これからいくらでも起こってくる。
娘へのメッセージ本『HOW TO 旅』を自費出版したとき、それまで尊敬していたある先生から、一通の手紙をもらった。
「そんなに寂しいなら、なんで離婚なんかしたの?」
「それを言ったらおしまい」の言葉は決して発してはならないと、今も私を戒めてくれる、いちばん寂しい言葉だった。
「いつかきっと、あなたの愛情は娘さんに伝わりますよ」
こんななぐさめの言葉さえも、当時の私のすさんでいた心を逆なでした。
経験のない人の安易なアドバイスは、たとえ好意のつもりでも、今でいう「上から目線」に聞こえてしまう。
「いつか」では困るのだ。
たしかにその「いつか」は私に訪れようとしているし、現在その渦中にある人たちも、そうなるものと信じている。
しかし現実には、私は十数年もの間、娘の日々の成長を喜ぶことや、家族としてのコミュニケーションを失った。
いちばん励みになったのは、同じ経験から自力ではい上がった人の、シンプルなひとことだった。
「今はただ、心と体の健康が第一です」
長期戦の覚悟を決め、その力を蓄える作業(食事・睡眠・運動・遊び)に集中することで、必要以上に落ち込まなくなった。
私はカウンセラーとして、両親が離婚した多くの高校生たちから、会えなくなった親への本音を聞いてきた。
さんざん悪口を聞かされて育っても、いまさら会うのが不安でも、口では会いたくないと言っていても、いっしょに住む親には言えないけれど。
「本当は、会いたい」
小学生の娘の登校を、毎朝遠目に見送り続ける私を知った、父親に会えない女子生徒の言葉は忘れならない。
「先生、子どもにとっては、あきらめの悪い父親がいい父親なんです」
この言葉を、kネットさんのメンバーをはじめ、全国の同志のみなさんに伝えたい。
自分の人生の中で、いちばん大きな感情エネルギーを消費したできごとなので、この話題になると止まらなくなる。
「長く静かな闘い」のトンネルを過ぎるまで、ファーザーズの初期メンバーが守ったルールを書いて、終わりとしたい。
私たちは、自分の子どもに恥ずかしくない生き方をして、将来子どもが誇りに思えるような父親をめざした。
+++++
(1)「別れた相手の悪口を、決して言わない」
私も離婚後に周りからあれこれ言われ、自己弁護したくなることも多かったが、すべて「自分がいたらなかったから」と答えた。
血のつながっている子どもとの関係は永遠だが、いろいろあった男女の仲は、離婚によってピリオドだ。
いつまでも相手にこだわるのは、「離婚しきれていない」証拠で、自分には人を見る目がないと告白し続けるようなもの。
(2)「子どもには、母親への感謝を伝える」
子どもの母親(父親も!)を否定することは、「子どもの存在を半分否定すること」と同じだ。
そもそも、別れた相手がいなかったら、今自分が愛している子どもは生まれていないのだから。
最悪の事態を避けるためにやむなく離婚したが、「今までありがとう」という立場で、子どもには接してやりたい。
(3)「相手の新しい家族の、幸せを願う」
なぜなら、今子どもがいっしょにいる家族が幸せであることが、本人の幸せにもつながるからだ。
ネガティブな感情は理性で抑えて、まちがっても相手家族の生活を邪魔するようなことはしない。
子どもと面会したとき、家族で仲良くやっていると聞くと、私はややひきつった笑顔で「よかったね」と応じていた。
(4)「子どもの誕生日には、プレゼントを贈る」
そのほかにもクリスマスや正月などに、毎年お祝いを送り続けた。
相手に迷惑にならない範囲で、子どもへの気持ちの表現がしたかったので、途中からほとんどが祝電とお金になった。
元妻の再婚相手が気分を害さないかと心配したが、特に返送されるようなことはなかった。
(5)「子どもに会えるようになった人を、祝福する」
ファーザーズに頼りきりだった人が、子どもに会えるようになると、手のひらを返したように寄りつかなくなる。
やや複雑な心境ながら、それもまたひとつのファーザーズの成功例だと、彼らの幸せをともに祝った。
この世の中から、不幸な親子関係がまたひとつ、なくなったのだから。
(6)「実名で勝負する」
子どもへのメッセージ本を出すときも、ホームページでも、新聞の取材でも、ペンネームなどは使わず本名で打って出た。
いつかどこかで、成長した私の子どもが、自分の父親の名前を目にすることを信じて。
その影響で面倒なことも出てきたが、子どもと会える日まではと、自分の名を広げることを優先させた。
(7)「公的活動と私的活動のバランスをとる」
ファーザーズをやる以上、よほど趣旨を理解してもらえないかぎり、どうしても相手側との対立構造ができてしまう。
だからその一方で、「法改正」に期待しすぎることなく、個人としての行動で補うようにした。
それが上の(1)〜(6)や、何年間も朝の勤務前に、子どもの登校を見守り続けることだった。
+++++
こうして書いてみると、いかにも誠実ぶった、言ってみれば「きれいごと」ばかりのように聞こえる。
まさにその通りで、私たちはダメな素の人格とは関係なく、タテマエを「究極のホンネ」にまで昇華させようとした。
人生の限定された一場面においてさえ、理想の姿を保てない自分たちに、世間への説得力など生まれるはずはないから。
「離婚しても、親子は親子」
これは、人によってさまざまな事情があることを含んでもやはり、私の揺るぎない信念となっている。
もちろん、自分の弱さからくるマイナス感情を、必死で抑えながらのあえぎ声だが。
たとえばの話だが、元妻がまた離婚をしてしまったとする。
私に娘を会わせなかった彼女の元夫が、皮肉なことに、今度は自分が子どもに会えなくなった場合はどうか?
元妻の再婚を認める条件として、娘から私を切り離した彼の両親が、「因果応報」で孫に会えなくなったら?
自然にわいてくる感情はご想像にまかせるが、それでもやはり、私は元妻に「会わせてやってほしい」と訴えるだろう。
そうでないと、今まで主張してきたことが、すべてウソになってしまうからだ。
「すべては、子どものために」
おわり
*****
【会えない悩み語りませんか(2)】 11月27日(火)
「ファーザーズ・ウェブサイト」は、やがて「面接権の明文化・共同親権の法制化」をめざすようになる。
世界の常識からみて、それはもはや「めざすべきもの」ではなく、基本として「あるべきもの」だからだ。
だがそれは、「会わせない側」にしてみれば宣戦布告にも見えるため、激しい反発や妨害も引き起こした。
「やっと別れた相手に、なぜ子どもを会わせないといけないのか!」
「ひどい目にあったのに、これ以上こちらが下手に出たくない!」
「子どもと会わせてなんかやるものか。もっと悲しめ、ざまあみろ!」
誹謗中傷も含めて、日々明け方まで、「会わせたくない母親」の反論が掲示板に書き込まれた。
今でいう「炎上」の状態だ。
それでも私たちは、寝不足になりながらも、できる限り誠実に回答を続けた。
言うまでもないが、ファーザーズ会員の父親で、養育費を払わない人はいなかった。
最低限の義務を果たさないで、権利ばかり主張するのは恥ずかしいことだ。
少なくとも離婚後については、相手や子どもに対して誠実であろうと誓い合った。
何かを主張すると、必ずといっていいほど「極論」をぶつけてくる人がいる。
「DVで元夫に殺されかけた。そんな危険な父親にも、子どもを会わせろというのか?」
そんな無茶なこと誰も言ってないだろう、と思わずため息が出ることもあった。
私たちがいちばん伝えたかったのは、離婚しても子ども「に」会いたい、ということではない。
離婚しても、子ども「が」両方の親に自由に会えるような社会にしたい、これが本筋だった。
「kネット」さんも同じだろうが、「子どもに会えない親のため」以上に、「親に会えない子どものため」の活動だ。
父親だけでなく、母親たちも次々と参加してくれたことで、この信念が少しずつ浸透していく手ごたえを感じた。
父親3人で始めたので、「ファーザーズ」と名づけたものの、一時期は改名も考えたほどだ。
国内外のメディアから次々と取材を受け、組織は急速に全国に広がっていった。
ただ当時の私は、自分の性格的なものから、「法改正」よりも「人間性」のほうに希望を見出したかった。
公的な「闘い」よりも、個人的な「癒し」のほうが大切だと感じていた。
ファーザーズの原点もそこにあったが、組織が大きくなるにつれて、方向性が変わっていった。
法律だからしぶしぶ会わせる、というのでは、理解のない親は子どもに無言のプレッシャーを与えるだろう。
法律があっても「犯罪」は減らないし、道路標識の制限速度のように、本当に守られるのかも疑問だ。
ロマンチストの理想論と言われようが、「離婚しても親子は親子」というシンプルな気持ちで会わせてほしかった。
九州支部長の内示があったとき、私は自分がファーザーズの言いだしっぺでありながら、丁重にお断りした。
私はある目標達成に向けて組織的な活動をしたり、集団を引っ張っていくタイプではない。
これからは一会員としてファーザーズを見守りながら、「個人として」どこまでできるか、やってみようと思った。
船上のレストランで、ある外国人が酔っ払って、たった一人で踊り始めた。
それを見て笑っていた周りの人たちも、一人、また一人と、楽しそうに彼と踊る。
しばらく経つと、その場にいたほとんどの人たちが立ち上がり、レストランは大騒ぎのダンス会場と化した。
のちにその外国人は、「自分が火つけ役だったが、それはもはや止められるものではなかった」と語った。
「私は途中で疲れてやめたが、みんなは踊り続ける。これもひとつのリーダーシップなのかもしれない」。
勝手な言い分だが、もし私にわずかでもリーダーシップがあるとすれば、やはりそのようなものだと思う。
地元の新聞記事で目に止まった、「kネット九州@宮崎」さんの集まり。
しばらく迷っていたが、やはり私は、行ってみることにした。
いちばんの理由は、たぶん、宮崎の代表者が「おじいちゃん、おばあちゃん」だったことだ。
子どもに会えない親もつらいだろうが、孫に会えなくなった祖父母の寂しさもまた、とても深いものだろう。
実家で草むしりをする父が、「シエリちゃん…」とつぶやいくのを聞いたとき、胸が張り裂けそうになった。
自分の親不幸を思い知った私は、何もしないではいられなくなり、元妻の再婚相手に手紙を書くことにした。
その背景には、彼らの間に子どもが生まれたことがあった。
今なら、子どもと引き離されたり、自分の両親が孫に会えなくなったらどう感じるか、想像できるはずだ。
「私はともかく、年老いていく祖父母には、せめて孫から電話の一本だけでも…」と書いた。
ワープロ文字で印刷された返事は、残念ながら、私のささやかな期待に応じる内容ではなかった。
「話せばわかる」はずの難しさや、人の考え方が実にさまざまであることを学んだ、ある意味貴重な経験だった。
今は、私の娘を明るく元気に育ててくれたことを感謝している。
私は、なんだかんだ言っても、離婚の原因は「お互いさま」だと思っている(相手を選んだ過去も含めて)。
子どもとに会えないのは「自業自得」の部分もあるが、両親にまで悲しみを背負わせるのは忍びない。
昔の両親への罪ほろぼしといった気持ちもどこかにあって、私は開始ギリギリに会場に入った。
つづく
*****
【離婚しても親子は親子】 11月24日(土)

宮崎駅西口で、「kネット九州」メンバーのみなさんが署名活動。
勤務日だったので、昼休みにちょっとだけ行かせてもらった。
幸い予想より多く集まったと、招かれた夜の打上げで聞いた。
離婚後に子どもに会えない人、それではいけないと思う人が、増えてきているようだ。
アメリカ映画に見るように、離婚後の親子の交流が「常識」である社会になってほしい。
そう願いながら、気持ちをこめて一文字一文字、自分の名前を書いた。
*****
【コスモス牧場】 2012年11月18日(日)

息子が3歳になって初めて来た、小林市の「コスモス牧場」。
なんとあと一週間で閉園してしまうというので、楽しい思い出にと、また家族でやってきた。
ポニー乗馬、子ヤギの散歩、ウサギのエサやりと、息子は動物たちとのふれあいに大喜びだった。
トラトレインに乗って、心地よい風を受けながら、広い牧場内を回った。
バッテリーカーに、息子一人で乗れるようになったのも、コスモス牧場だった。
スーパースライダーで何度もすべり降りては、スロープカーに乗って戻ってきた。
思えば、同じ3歳の頃に娘を連れて行っていたのは、シーガイアのオーシャンドームだった。
プールのすべり台からすべり、流れるプールで泳ぎ、メロンソーダを飲みながらダンスを見た。
そのオーシャンドームも、今はもうやっていない。
あれほどにぎわっていた、コスモス牧場もオーシャンドームも、なくなってしまった。
でも、あのとき確かにその場所で、親子で楽しく過ごした事実は、ずっとなくならない。
子どもの頃、両親と霧島温泉に泊まった思い出が、この年になっても記憶に残っているように。
*****
【一織珈琲】 11月22日(木)

息子が、初めていれてくれたコーヒー。
30年間自分でいれてきたけど、いちばん味わい深かった。
*****
【水に流せます】 11月9日(水)
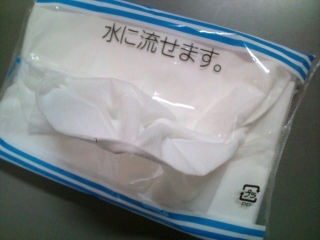
そりゃあ、いろいろあったけど。
ポケットティッシュごときにできることなら、オレだって。
*****
【ひとりツイッター(1)】 11月9日(金)
「悟れないと悟ること」が、「悟り」なのかもしれない。
最後まで軸がブレて、中途半端なまま終わった『方丈記』のように。
+++++
自分を高める努力と、ダメな自分を受け入れる努力。
大人に必要なのは、後者のような気がする。
+++++
「ごきげんであるため」「ハッピーでいるため」を目的とすれば、今やっていることの80%はやめても困らないだろう。
習い性となっている読書や文章書きも、本当はやらなくてもいいことのはずだ。
+++++
仕事帰りに夕焼けを見ると、家族で見なければと焦ってしまう私のくせ。
素晴らしい風景を見たとき、娘がそこにいなかった昔のトラウマ。
+++++
写真集のような「できすぎ」の風景より、仕事帰りに建物や電柱の間から見る夕焼けのほうがいい。
リゾート地の夕暮れも好きだが、雑多なものや人のシルエットのほうが性に合っている。
+++++
クリアなデジタル音源もいいが、古いレコードやカセットテープの音でも十分。
小中学生の頃、AMラジオから流れてくる歌謡曲を心待ちにした世代だから。
音楽も本も考え方も、アナログな部分を自分の中に残しておきたい。
+++++
娘が3歳のときに別れた私は、3歳以上の子どもを育てた経験がない。
今年の夏、息子は3歳になった。
これから先は、かつて失ってしまった日々。
+++++
保育園に息子を迎えに行くと、息子が「パパ―!」と私の足にしがみついてくる。
今の息子には、離れて暮らす娘が3歳だった頃のおもかげがある。
一瞬にして、15年前に父親だったあの頃がフラッシュバックする。
+++++
夜中にふと目がさめると、かたわらで妻と息子が寝息をたてている。
暗闇の中でも、「そこにいてくれる」というだけで、孤独感は消える。
毛布の下で、ひそかに手を合わせる。
+++++
息子はママにべったりで、私を肩車の乗り物代わりくらいにしか扱わず、ナメた態度をとる。
それでいい、そう思っている。
私のいちばんの役目は、「いつもそこにいてあたりまえ」を、できるだけ長くしてやることだから。
+++++
「最近はダイエット中」というのは、「最近は筋トレ中」と同じくらいオカシイ。
健康管理は一生のもの、引き締まった体はついてくるもの。
人間的成長が目的で、豊かさはその結果にすぎないのと同じこと。
+++++
フェイスブックって、「つながっている」のか?
無理やり「つなげられている」のではないか。
24時間「つながれている」人もいるようだが。
+++++
親の死を報告しても、「いいね!」(ある本の帯より)。
クリックひとつで形だけの共感が得られる半面、共感されたい欲求はますます強まる皮肉。
+++++
サウナのテレビで、野球の日本シリーズをやっていた。
自分より何百倍もの年俸をもらう人を夢中で応援する心理が、いまだに理解できない。
若いゴルファーが不振から脱したと喜んでいて、ちゃんと家族を食わしていけるのか?
+++++
ビジネス書の速読が好きな人は、本を読むとき「実行にうつすことだけ」ページの角を折る。
私はハッとするたとえ話、うまい言い回し、美しい言葉や表現のほうに目がとまる。
+++++
映画『ブレア・ウイッチ・プロジェクト』で、恐ろしい森に迷い込んだ若者が、「くだらないテレビやゲームでヒマをつぶすような生活に戻りたい」みたいなことを言っていた。
「なんでもないようなことが幸せだったと思う」という歌が昔流行った。
ドラマで不幸なときの回想シーンは、決まって家族で笑い合っていた平凡な場面がスローで流れる。
釣り上げられる前に、水の中を泳げる今こそが「幸せ」なのだと、気づいている一匹の魚でありたい。
+++++
通っているジムのオーナーの名言。
↓
1.ライフスタイルが変わったとき、体のスタイルも変わる。
2.トレーニングそのものよりも、ジムに「来ること」で若くなる。
3.己のため自らに与えたストレスは、しっかり吐き出すことができる。
+++++
同感。
↓
時間や社会にとらわれず 幸福に空腹を満たすとき
つかの間 彼は自分勝手になり 自由になる
誰にも邪魔されず 気をつかわずものを食べるという 孤高の行為
この行為こそが 現代人に平等に与えられた 最高の癒しといえるのである
(ドラマ『孤独のグルメ』)
+++++
シンプルだが、とっても深い。
↓
「それは、あなたが決めることです」
(ドラマ『家政婦のミタ』)
*****
【会えない悩み語りませんか(1)】 11月6日(火)
10月31日の宮崎日日新聞、「会えない悩み語りませんか」という記事が目にとまった。
↓↓↓↓↓
離婚や別居で子供、孫と会えなくなった、親や祖父母が互いの悩みなどを語り合う交流会が11月3日午後6時から、宮崎市民プラザ内の市民活動センターである。
宮崎市の任意団体「kネット九州@宮崎」主催。
第1回は10月に開催し、鹿児島県の4人が参加、毎月第1土曜日に開くことにしている。
団体の代表を務める小原大八さん(70)と妻夏代さん(64)は長男夫婦の別居・離婚に伴い、孫と会えなくなった。
小原さんは「私たちも県外の交流会などに参加することで、少し気持ちが楽になった。悩みを話し合うことで、解決策を探っていきたい」と参加を呼び掛けている。
↑↑↑↑↑
「kネット(共同親権運動ネットワーク)」さんのことは、以前から名前を聞いていた。
私も12年前に「ファーザーズ・ウェブサイト」を立ち上げ、活動していた過去があるからだ。
北海道と東京そして宮崎と、たった3人の父親で始めた草の根運動は、現在では全国規模の市民運動に拡大している。
当時、私が伝えたかったこと。
http://www.miyazaki-catv.ne.jp/~nakamoto/fathers-menu.html
当時、娘への思いをつづったもの。
http://www.miyazaki-catv.ne.jp/~nakamoto/musume-menu.html
1997年の秋に離婚した私は、しばらくは家庭裁判所での調停で決められた通り、3歳の娘と月2回の面会ができていた。
しかし【地獄に仏】10月22日(月)に書いたように、元妻の再婚がきっかけで、唯一の心の支えだった娘と会えなくなる。
離婚に続くその精神的なダメージは、実際に経験してみないとわからない、想像以上のものだった。
本当は神経質で弱い性格なのに、明るく元気なキャラを演じてきたため、期待に反する周囲の反応にも落胆した。
ある夜、職場の飲み会で「暗い部屋に帰ると寂しい」ともらした私に、冗談だと思った上司が笑いながら言った。
「うそつけ!独身貴族に戻って、毎日楽しんでるんだろ?」
私の異常に気がついたのは、いつもバカばかり言い合っていた悪友、アメリカ人の同僚ウェルトン・ネコタ(Welton Nekota)だった。
正直、こいつにだけはホンネを言ったところで、笑い飛ばされるだけだと思い込んでいた。
しかし彼はある日突然、「オレの車に乗れ」と言って、私をパソコン専門店まで引っ張って行った。
「カードを出せ。これを買うんだ」
半ば強制的に、立体の三角形で評判になっていた(らしい)水色のiMacを私に買わせた。
ウェルトンはそのまま私のアパートまで来て、そのパソコンをまだ電話回線だったインターネットにつないだ。
典型的文系の私はパソコンなどいじったことがなく、インターネットについてもまったく無知だった。
ウェルトンはiMacに音楽CDを入れ、BGMを流しながら、Yahoo!に語句を入れて情報を検索する方法を教えてくれた。
「今のおまえに必要なのは、とにかく視野を広げることだ」
その夜、私はなんとなく検索窓に「離婚」と入れて、教えられた通りにクリックしてみた。
そこからたどり着いた「ばついちたちの憩いの場」(現在は閉鎖状態)で初めて、同じ悩みをかかえた人がたくさんいることを知った。
自業自得ともいえるが、私が本当に苦しんでいることを理解してくれそうな人は、当時周囲には誰もいなかったのだ。
ある夜、「ばついちたちの憩いの場」掲示板に、意を決して初の書込みをした。
「愛する娘に会えなくなってしまいました。死ぬほどつらいです」
自分がたった今書いた言葉が、全国で見ることができるインターネット上に表示されるのが、不思議な感じがした。
次の夜、ドキドキしながらパソコンを開いてみると、なんと千葉県に住む女性(ハンドルネーム海さん)から返事がきていた。
「つらいですね…」
そのタイトルを見ただけで、私はずいぶん長い間、その場で声をあげて泣き続けた。
「海さん」には、その後お互いに行き来する機会があって、直接何度か会っている。
出会った経緯から、お互い将来のことを考える展開もあったかもしれないが、そういった意味での縁はなかったということだろう。
それでも私は、彼女のことは私の人生の中でかけがえのない存在として、今でも深く感謝している。
当時のインターネットは、なにしろ電話回線なので、今では考えられないほど表示に時間がかかった。
それでも私は毎日のように、深夜か明け方まで「ばついちたちの憩いの場」に没頭した。
人から励まされ、また逆に励ますことで、ギリギリのところで自分を保っていた。
後日ウェルトンに、こう言ったことがある。
「まさかおまえに理解してもらえるとは、申し訳ないけど予想してなかった」
ウェルトンは、次のように答えた。
「陽気に見えるオレだって、若い頃は『自分は何者か』ということでずいぶん悩んだんだ。
ハワイ生まれで日系のオレは、アメリカに留学すればチャイニーズといじめられ、外見が日本人なのに日本語が話せない。
おまえだって意外に思うかもしれないが、昔は何度も枕を涙でぬらしたもんだ。
顔は笑っていても、心の中では号泣してることがあるってことくらい、オレにもわかる」
「それに、離婚したあとに子どもを父親に会わせないなんて、信じられない話だ。
おれは世界中に多くの友人がいるが、誰に聞いても『ありえない!』と驚いていた。
こんな非常識がまかり通ってるのは、日本だけじゃないのか?」
「ばついちたちの憩いの場」で、私の書込みに毎回必ずコメントしてくれる人たちがいた。
北海道の太田達志(ハンドルネーム悲別)さんと、東京の美由直己(ハンドルネームNaoki)さんだ。
つらい気持ちを語り合えるありがたさを痛感した私たちは、新たに3人で「ファーザーズ・ウェブサイト」を始めることにした。
「ファーザーズ・ウェブサイト」は間もなく、「朝日新聞」の記事に取り上げられた。
幸せそうな家族が背景の皮肉な?リンクの写真は、左から私、太田さん、美由さんだ。
記事の反響はすさまじく、全国から次々と問い合わせが寄せられた。
一方で私は、たとえ会えなくても、いつか娘に愛情が伝わることを信じて、一人の父親としても行動を始めた。
計画したわけではないが、今ふり返ってみれば、私は主として3つのことに全エネルギーを注いだ。
娘へのメッセージ本『HOW TO 旅』の出版、個人ホームページ「文武両道」の開設、毎朝同じ場所に立って娘の登校を見送ることがそれだ。
今になって、人から「すごいですね」と言われることがある。
しかし実情は、何かをしていないと自分が壊れてしまいそうで、やるせない気持ちのまま続けてしまっただけだ。
当時まだ字も読めない幼い娘が、いつか私の文章と出合うことになるなど、期待もできそうになかった。
まったくひどい心理状態だった。
今もし心療内科で診てもらえば、たぶん「うつ病」と診断されるかもしれない。
いや、仕事中は無理やりテンションを上げていたから、「そううつ」か。
離婚後の自分を思い出すことは、いまだに私の心を重くするので、意識して避けるようにしている。
冒頭の記事を読んだとき、同じ経験をした者として、直接足を運んで父親たちを励ますべきだと思った。
しかし同時に、自分のトラウマのスイッチを押しかねないこともあって、当日まで参加を迷っていた。
(つづく)