【そのまんまクッション】 1月31日(土)

丸で、薄緑色で、ふわふわしている。
部屋に置いてある、何の変哲もないクッション。
でもこれはこれで、そのまんまでオーケーな存在。
このクッションが、四角になろうとか、赤になろうとかすると、悩みが始まる。
すでに妻のお気に入りなんだから、何も変える必要はない。
せいぜい日なたに干して、太陽のにおいがするくらいのバージョンアップで十分。
人も、このクッションと同じようなもの。
「足りない、もっと」と、自分を無理に変えようとしたら、苦しくなるだけ。
大切な家族から受け入れられていれば、それでいいんだよ。
自分を磨き、高めようとする努力は、素晴らしいこと。
でもそれは、何もしない今の自分でもオーケーであることが、出発点。
楽しみながら、ゆっくり、少しずつプラスを積み重ねていこう。
ちょっと元気になったら調子に乗って、また全分野でトップレベルをめざして焦る、ワンパターン男。
実は今日の「落書き」、妻から私へのお説教でした。
偉大なる女性の前では、下に書いた男の哲学ごときは、ものの見事に粉砕されてしまう。
*****
【人生観ロゴ】 1月30日(金)
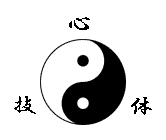
同僚のオーストラリア人(サーファー&アーティスト)に、私の人生観を表したロゴを試作してもらった。
シンプル・イズ・ベストで、「陰陽」のシンボルに「心技体」のトライアングルを合わせただけのものだ。
これが、私の思考と行動の指針となっている。
「陰・陽」はワンセットで絶妙に混じり合い、厳密な境目がない。
白の中の黒丸は「陽の中にも陰あり」、黒の中の白丸は「陰の中にも陽あり」。
この視点を、人や物事を見つめるときに活用している。
人生の目的は「人間としての成長」だと考えているので、生活レベルに落として「心・技・体」に分けた。
それぞれの目標をブレイクダウンして、最小単位を実行することで、ボトムアップ式に自分を高めていく。
1日・1週間・1ヶ月のスパンで、「心技体」の活動に偏りがなければオーケー、というわけだ。
「心」を高める主なものは、読書・文筆・思索。
「技」を磨く分野は、英語・カウンセリング・格闘技。
「体」をつくる手段は、睡眠・食事・トレーニング。
*****
【日本人でよかった】 1月19日(月)
日本の携帯で使われる
外国では、笑顔と見なされないことが多いらしい。
ガイジンにとって、笑顔のイメージは「目」ではなく、「口」なんだそうだ。
そういえば、あっちのスマイルマーク
日本では「目が笑ってな〜い!」というと、ちょっとコワイが。
そういえば、モナリザの「謎の微笑み」も、口もとだけだ。
日本と外国のイメージの違いは、けっこうたくさんある。
英語授業でよくやるが、動物の鳴き声なんてのも、その1つ。
犬は「バウワウ」だし、ニワトリに至っては「コッカドゥードゥルドゥー」なんである。
くしゃみは「アチュー!」だと言ってきかない。
おれ、絶対「あちゅー!」なんて言ってないのに。
一緒に魂が抜けると信じてて、「ブレス・ユー(神のご加護を)!」とか、大げさなこと言われるし。
日本の「君が代」は、「平和な世の中が続きますように」と穏やか。
外国の国歌なんて、「行け行け、戦え!」なんて、戦争の歌ばかり。
ボクシングの世界戦で、和を重んじる「君が代」をやられると、戦意喪失しそうだ。
月の表面に見える模様も、「餅つきをするウサギ」とか、日本はロマンチック。
外国は「吠えるライオン」「片腕のカニ」「ヒキガエル」「ワニ」…。
これじゃ「禅」の思想も生まれまい、ああ、日本人でよかった。
*****
【読了日記「パパラギ」】 1月16日(金)
始業式の校長訓話で、「パパラギ」の話が出たので、さっそく注文して読んでみた。
私が買ったのは、わかりやすく編集された「絵本 パパラギ」。
ううむ、忘れかけていた価値観を取り戻させてくれるような、インパクトある内容だ。
「パパラギ」とは、白人をはじめとする先進国の人々。
サモアの酋長ツィアビさんが、初めてヨーロッパを旅して、その印象を島の人々に語ったものだ。
この時の話が詩人ショイルマンによって翻訳され、1920年にスイスで出版された。
物には、2種類ある。
人間が作る「物」と、自然が生み出す「もの」。
これだけで、察しのいい人ならピンとくるだろう。
「物」や「お金」だけでなく、自然が生み出す「もの」まで、パパラギは「私の物」にしようとする。
サモアにも「ラウ」という言葉があるそうだが、それはなんと「私の」「あなたの」の両方を意味するそうだ。
そもそも、地球のものである土地や植物に、なんで人間の「所有者」がいるの?
「職業」や「時間」その他についても、人間にとって本当に豊かなのはどちらか、わかりやすく語っている。
国民総生産(GNP = Gross National Product)でなく、国民総幸福量(GNH = Gross National Happiness)の価値観といえる。
「パパラギ」としての生活に限界を感じた時、読み返す意味のある本だ。
*****
【教育効果】 1月15日(木)
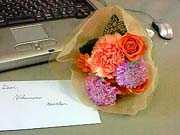
3年生の最後の授業が終わって、花束と手紙をもらった。
今どき、こんなことをしてくれる学級は珍しい。
いい気分で弁当を食べていると、東京で不動産の店長をしている友人から電話。
「中元、人っていいよな、うん」
「メシ食ってんだ。
突然しみじみしてないで、さっさと話せ」
「部下に無愛想な若造がいたんだよ。
オレに反抗してるのかと思ってた。
今日、腹割って話したら、『店長が客にナメられるのが嫌だった』って。
商売で下手に出てるだけなのに、そんなこと考えてたなんて、うれしかったよ」
「ああ、それわかる。
生徒でも、見かけと考えてることって違うことが多いもんな」
「こんなダメなオレの下でも、ちゃんと育ったなあって」
「巣立ったやつも多そうだけどな(笑)」
「ロクなことしてきてないのに、たまにはいいこともしたのかなって」
「プラスマイナスゼロだよな」
「少しはほめろよ(笑)」
「これでも十分ほめてる」
「こういうことがあるから、中元も続いてるんだろうな」
「おかげさまで、まだセンセーのふりさせてもらってる」
「無理しない、でも頑張る。
人にはやさしく、ほめて、受け入れる。
これがリーダーの条件だな」
「とても元チンピラとは思えない言葉だが」
「というわけで、続きを食べろ」
「おいおい、いい年した男が、ただ聞いてもらいたかっただけか?」
「まあ、そんな感じだな」
「おれはカウンセラーか!?」
「カウンセラーだろ、じゃ〜な〜」
*****
【今宵の月のように】 1月12日(月)

晴れ渡って空気が乾燥し、風の強い三連休が終わった。
久しぶりに、生活が落ち着いてきたような気がする。
夜、ベランダに出て空を見上げたら、暗闇に丸い月がぽっかりと浮かんでいた。
なぜだか急に、あの歌が聴きたくなった。
10年前の寂しさと悔しさが入り混じった、エレファント・カシマシの「今宵の月のように」。
古いMDを引っ張り出してきて、大音量で流しながら、心の中で絶叫するように歌った。
+++++
くだらねえとつぶやいて 醒めたつらして歩く
いつの日か輝くだろう あふれる熱い涙
いつまでも続くのか はきすてて寝転んだ
俺もまた輝くだろう 今宵の月のように
+++++
あの日、私は独りで夜道を歩きながら月を見上げ、この歌を口ずさんでいた。
自分の未熟さから、いちばん大事な家族を失って、抜け殻のようにただ生きているだけだった。
今日は温かい家庭から同じ月を見上げ、辛かった日々を思い出しつつ、満たされた生活に感謝している。
「あふれる熱い涙」がいつの日か輝くのか、「今宵の月のように」俺もまた輝くのか?
あの頃は疑問だったし、信じられなかったし、想像もできなかった。
それでも時は流れ、さまざまな移り変わりを経て、今こうしてここにいる。
気がかりなのは、当時自分も辛い状況なのに、私を励まし続けてくれた東京のMさん。
「何?男なんだから」という件名のメールで、私は最悪の結末を避けることができた。
残念ながら今年に入って離婚することが決まり、愛する息子さんとも、遠く離れ離れになってしまう。
「あふれる熱い涙」がいつの日か輝き、「今宵の月のように」Mさんもまた輝く。
そう信じて、別の形で続く親子関係の幸せを、ただひたすら祈るだけだ。
こんなダメな私にも新しい幸せが与えられたのだから、Mさんもいつかまた、今宵の月のように。
*****
【「禅 ZEN」とポメラ】 1月11日(日)
映画「三十九枚の年賀状」を見る。
朝一番の映画館は普段はガラガラだが、舞台が地元宮崎とあって、珍しく満席状態。
見覚えのある場所がいくつも出てきて、宮崎弁だらけの映画はさすがに初体験だった。
宮崎出身の役者が何人も出ていて、あの東国原知事も、歌と演説で特別出演。
この映画は、やはり宮崎県民としては、映画館まで見に行かないと。
戦時中から昭和を過ごした自分の人生が重なったのか、館内からはすすり泣く声も聞かれた。

一度家に戻ると、待ちに待った「ポメラ(ポケット・メモ・ライター)」がタイミングよく届いて大喜び。
私がずっと欲しがっているのを見て、妻が通販で買ってくれたものだ。
この文章も、さっそくポメラで書いている。

夕方からまた映画、「禅 ZEN」。
これは武道家として絶対に見たかった。
「春は花 夏ほととぎす 秋は月 冬雪さえて すずしかりけり」…いいねえ。
映画の中に、水に映った月を斬る場面が出てくる。
月はぐちゃぐちゃになるのだが、しばらくすると何事もなかったように、再び美しく整う。
怒りや悲しみに一度は取り乱しても、間もなく落ち着きを取り戻す、そんな人間でありたい。
「雲がかかっても、闇に消えても、月がなくなったわけではない」という言葉もよかった。
禅の「自分の中に仏がいる」という教えも、妄想や執着のために見えないだけということだろう。
心の中の仏に出会うために、私たちは一生修行を続けていく。
教祖や神がこう言った、自分たちだけが正しいと主張し、戦争をくり返す宗教。
お金だけを目的に、だましたり洗脳してまで信者を増やそうとする、新興宗教。
禅はそれらとは異なり、自分で物事の真偽を判断し、間違わない心を養っていく。
「只管打坐(しかんたざ)」、ただひたすら坐禅を組むことによって、本来持っている力を自然に発揮する。
思えば私の英語も、「只管朗読」といって、ひたすら音読をくり返すことで身につけたものだった。
時代は、「日本の禅から世界のZENへ」なのかもしれない。
夜は、お気に入りの店「感食屋 Setten」で食事。
食材にこだわり、手作りにこだわり、空気にこだわり(もちろん禁煙!)。
何を食べても美味しくて安心なので、今年はここのメニューを制覇する予定。

今日この日のお客さまとの「接点」を大切にする意味で、「Setten」と名づけたそうだ。
写真は、「Setten」テーブルの一輪ざし。
この小さな心づかいもまた、料理人の「禅」である。
*****
【そのまんま日記】 1月10日(土)
昨日書いた「サイレント・マジョリティ」について。
サウナで話した東国原知事が、私の発言をちょっとだけブログに書いてくれている。
単純にうれしかった(笑)。
http://ameblo.jp/higashi-blog/entry-10190514966.html
「心無い批判や誹謗中傷に負けず、頑張って下さい。
僕も色々なことがありましたが、その度に知事の生き方に励まされています。
サイレントマジョリティといいますか、声無き大勢が知事を応援しています」
*****
【サイレント・マジョリティ】 1月9日(金)
行きつけのサウナで汗を流していたら、たまたま東国原知事が入ってこられた。
お仕事が終わって数十キロ走ったあとだった様子で、かなり消耗した表情だった。
こうして平気で素顔と素っ裸を見せるあたり、やはり普通の知事とは一味違う。
「おくつろぎのところ誠に申し訳ありませんが、少しだけお話ししてもよろしいですか?」と話しかけた。
40を過ぎてから学問を志し、どん底から這い上がってきたあなたを見て、私も生まれ変わる決心をしたこと。
地方自治だろうが国政だろうが、男の生き方のモデルとして、陰ながら応援していることを伝えた。
以前から地元の新聞が、東国原知事に批判的である。
マスコミの立ち位置として必要な態度なのはわかるが、やや感情に走り過ぎているのが気になる。
同じ文章を書く者として、匿名という安全な場所から、行動している人に対して言葉だけぶつけるのはアンフェアに感じている。
こういう図式を見るたび、「じゃあ、あなたがやってみたら?」と言いたくなるのだ。
ボクシングの観客席から、リングの上で闘っている人に対して、ああだこうだ言うのは簡単だ。
しかし一度でもリングに上がって殴り合ってみたら、二度とそんな口はきけなくなるだろう。
「あの人はパフォーマンスだけだ」と、そのパフォーマンスさえできない人が批判する。
マイナーだった宮崎を1ミリさえ動かしていない人が、自分の口ばかり動かしている。
だから私は、「評論家」や「毒舌」のタイプから距離を置く。
任期中の県知事が国政に色気を出していると、古い青春ソングにたとえた批判もあった。
「私には鏡に映ったあなたの姿を見つけられずに 私の目の前にあった幸せにすがりついてしまった」と。
これに対し知事は、自身のブログで「国政転進は幸せどころか、途方もない艱難辛苦を覚悟せねばならない。今のままのほうが百万倍幸せである」と返している。
私は自他共に認める、「たとえ話」大好き人間だ。
だからこそ、真剣に議論すべき事案に対して、あいまいに煙に巻いてしまう「たとえ話」の危険性も十分に承知している。
私はまったく政治的な人間ではないが、果たして政治的な議論の場で「たとえ話」を用いるのが妥当かどうか。
「任期途中で国政転進をにおわせた」と批判するのは、「ずっとそばにいるよ」と言ったのに別れるなんて許さない、と泣きわめく未熟な女の子みたいなものだ。
もしこんな「たとえ話」をしたら、「政治と恋愛をいっしょにするな」と言われるだろう。
しかし新聞という公的な機関を使って、そのレベルのたとえ話が使われているのが、残念ながら宮崎の現状なのだ。
インターネット書店「Amazon」のブックレビューでも、1冊の本さえ書いたことのない人が、匿名で「つまらない本」とこきおろしている。
たとえ話をすると(笑)、街のチンピラが世界最強のヒクソン・グレイシーに挑戦できるという、ありえない資格がまかり通るのがインターネット。
マスコミで目立つのはいつも、ごく少数のクレイマーたちである。
しかしその背後には、「サイレント・マジョリティ」と呼ばれる、表舞台には出てこないが圧倒的な数を誇る賛同者たちがいる。
長年ホームページをやっていて思うが、非難中傷や皮肉めいた書込みのほうが、今後の展開への期待もあるのか人目を引く。
その一方で、好意的な感想やお礼のメールをくれる少数の読者を代表とした、「サイレント・マジョリティ」の存在も確かに感じられるのだ。
*****
【well-being】 2009年1月7日(水)
1週間が過ぎましたが、新年おめでとうございます。
「今年の目標」を作らない私ですが、正月にたまたま出合った言葉が気に入ったので、これにします。
“well-being”(ウェル・ビーイング)
“well-being”は、「幸福(感)・幸せ・満足のいく状態・快適な暮らし・安らぎ・健康」の意。
モノやカネを手に入れる“having”や、他人の評価を得ようとする“doing”は、無理して求めない。
「何を持つか、何をするか」よりも、「どんな状態であるか」を選ぼうと思います。
思えば、疾風怒濤の高校時代、うめくようにノートに書いた言葉が「心の安らぎ」でした。
それなのに私は、なぜか次々と事を起こし、まったく逆の人生を歩んできています。
心の安らぎから遠ざかる、逆療法的な体験を、これ以上ないほどくり返してきたわけです。
その中で、私は俗に成功と呼ばれる小さなカケラを、いくつかつかみ取りました。
しかし、「光」が強くなるほど「影」も濃くなる道理で、何度も「闇」に突き落とされるはめに。
おかげで私たちに影響している「法則」に気づき、軌道修正を余儀なくされたわけです。
40歳を境に、「法則」にのっとった生き方にシフトチェンジしたつもりでした。
それでもまた学びの経験が与えられたのは、心のどこかに隙があったからでしょう。
一見華やかな舞台の裏で、「まだわかっていないようだな」と雷を落とされたのが、昨年後半のこと。
体も心も動けなくなって、妻の送り迎えで最低限の仕事をこなす以外は、家の万年床で粗大ゴミ状態。
弱々しく年末の復活をめざす私を、彼女は嫌な顔ひとつせず支えてくれました。
改めてこの場を借りて、ありがとう。
ある日、いちばん活動していた頃の手帳を開いてみました。
ビッシリ詰まったスケジュールの片隅に、小さく書かれたこんな言葉を見つけました。
「毎日夕焼けを眺めるような生活」
あの頃の自分に、謝りたいような気持ちになりました。
見かけや他人の評価とは裏腹に、本当の自分はキツくて悲鳴を上げていた。
本来はテンションの低い、人と交わるのが苦手で、頑張りたくない私なのでした。
今欲しい物、特になし。
今したい活動、特になし。
頭に浮かぶのは、河島英五「時代遅れ」のサビ。
「目立たぬように はしゃがぬように
似合わぬことは 無理をせず
人の心を 見つめつづける
時代おくれの 男になりたい」
もちろん、仕事は一生懸命やりますよ。
でもそれ以外のすべては、家族のためにも“well-being”を最優先させます。
「楽書き」に近い「落書き」は、寝たきりの日々に頭に浮かんだ「暮らしのプチ哲学」を綴っていきます。