■その1 「愛は動詞である」

毎朝ジョギングをしている川辺で、今日は仲良く並んだ四つ葉のクローバーを見つけた。
4つ葉の意味は、「faith(誠実)」「hope(希望)」「luck(幸運)」「love(愛)」である。
肝に銘じておきたい。
誠実に生きていれば、希望が見えてくるし、幸運にも恵まれる。
要領よく立ち回って目先の得をしたところで、ウソやウラがあることは、鏡の中の自分にはバレている。
「心の平安」を幸福と呼ぶならば、その条件は誠実しかないではないか。
そして何よりも大事なことは、「愛する」は「動詞」であることだ。
「食べる」「寝る」「遊ぶ」と同じく、自分の意志で起こす「行為」に分類される。
恋はするものではなく「落ちる」ものだが、愛は行動なのだ。
社会心理学者エーリッヒ・フロムは、その著作『愛するということ』の中で、「愛は技術である」と断言している。
愛が心の中にあるだけでは、幸せにもなれないし、相手にも伝わらないと。
「技術だとしたら、知識と努力が必要だ」
私はかつて、ひとつの「愛」を失った。
愛を、いつでもそこにある「名詞」だと思っていたからだ。
人生の文法を間違えていたのだ。
「素敵な人さえいれば、素敵な恋愛ができる」という考えは、誤りである。
「美しい風景さえあれば、美しい絵が描ける」という考えが、誤りであるように。
*****
■その2 「あの人があなたであること」
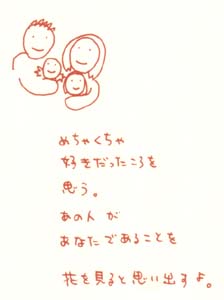
『ふたりの絵本 結婚。』より
ずっと以前、前川清が藤圭子(宇多田ヒカルの母親)と離婚するときの会見で、「離婚の理由は?」と問われてひとこと。
「結婚したことです」
ジョークなのか、深いのか。
人から聞いた結婚式のスピーチで、心に残っているもの2つ。
(1)ケンカをしたとき、相手が悪いと思ってはいけない。
家族や友人たちの中では、どちらもそれなりに立派な人なのだ。
ただ、「中が悪い」のだ。
自分でも相手でもなく、ちょうど二人の真ん中あたりが悪いのだと思いなさい。
中が悪いのだから、その中(=仲)を良くしなさい。
(2)好きだった理由を思い出せること。
どんなに好きだったかを憶えているということ。
恋愛したそのことを思い出せる夫婦が、幸せなのだと思います。
最近ある事実を知って、知らなかったがために、ちょっとした衝撃を受けた。
前妻との離婚が決まったあと、彼女が一人で私の母親に会いに来たというのだ。
「ここまでよくしていただいたのに、こんなことになって申し訳ありません」
そう言って、涙を流したのだという。
私の前では、決して見せなかった涙を。
10年が過ぎてこれを聞いた今、前妻への気持ちすっかり変わってしまった。
家族を失ってはじめてその大切さがわかり、元に戻ろうともちかけたときには、彼女には新しい相手がいた。
そうさせてしまったのは、元はといえば、他でもない私自身だった。
私が感じる自責の念を、彼女が新しい家族で幸せに暮らしていることが、少しだけ中和してくれる。
私もまた、この世でいちばん大切な宝物である娘に会えなくなり、地獄の10年間に耐えてきたのだから。
過去に流れていった数々の場面は、泣こうがわめこうが、もう二度と取り返しはつかない。
恩返しができないときは、別の誰かに「恩送り」を。
親孝行ができないときには、次の世代に「子孝行」をするしかない。
君は目の前の夫を真剣に愛せ、おれも目の前の妻に誠実であり続ける。
多くの夫は、今目の前にいる妻が、あの頃夢中になっていた女と同一人物であることを忘れている。
多くの妻は、今目の前にいる夫が、あの頃大好きだった男と同一人物であることを忘れている。
週末に花を買って、二人で眺めよう。
そして、あの頃の気持ちを思い出そう。
いろんなことが変わっていたとしても、それがあの頃の続きであることに、変わりはないのだから。
Stop and smell the roses.
(立ち止まって、バラの香りを)
(2008/5/4)