「頂きはどこにある?」(スペンサー・ジョンソン)に、おもしろいたとえ話がある。
人生の好調期を「山」に、不調期を「谷」になぞらえる。
そして、登場人物は次のように語る。
「山と谷は、つながっている」
「人生プラスマイナスゼロ」論者の私としては、一瞬でピーンとくるものがあった。
山ばかりあることを期待していては、間違いなく裏切られ続けることになる。
プラス思考の落とし穴は、そこにある。
「山と山の間には、谷がある」
これもその通りで、そもそも谷がなかったら山も存在しない。
自然の一部である人間は、決して自然の法則から逃れることはできない。
だがよく考えてみると、次のようにも表現していいことに気づく。
「谷と谷の間には、必ず山がある!」
もちろん、山と谷だけではない。
山の中腹には、高原もある。
「高原は、休息と再考の場所である」のだと思う。
次のようなたとえはどうだろう。
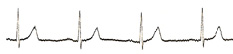
「生きている人」の正常な心電図は、常に上がり下がりがある。
これがもし「直線」になったら、何を意味するのか…。
―――――――――
「人生山あり谷あり」で、「上り坂・下り坂・まさか」があって当たり前、生きていくなら最低限の「覚悟」が条件。
中年以降になれば誰でもわかる話だが、意外と目先のトラブルには応用できないものだ。
カウンセラーとして数百人の相談に応じてきたが、99%の根本的原因は「睡眠不足・運動不足」そして「覚悟不足」だった。
自然の法則といえば、季節には「春夏秋冬」があり、死ぬまでそのくり返しを体験し続ける。
それならば、人間にも「喜怒哀楽」があり、死ぬまでそのくり返しを体験して当然ではないか。
「不動心」など、生きている間は不可能ということだ。
ある人が、アインシュタインに質問した。
「どうして人は喜んだり、怒ったり、哀しんだりするのでしょう?」
アインシュタインは、こう答えた。
「人間の体の70%は、水でできている。
それは食塩水で、いわば体の中に海を持っているようなものだ。
海であれば、さざ波があり、嵐があり、引き潮があるのは当然ではないか」
(2009/9/18)