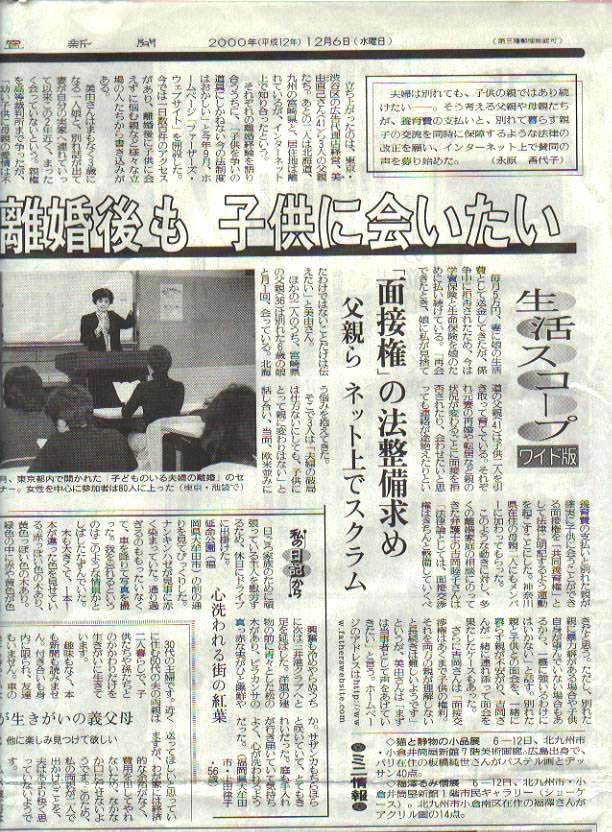
離婚後も 子供に会いたい
「面接権」の法整備求め
父親ら ネット上でスクラム
夫婦は別れても、子供の親ではあり続けたい――。
そう考える父親や母親たちが、養育費の支払いと、別れて暮らす親子の交流を同時に保障するような法律の改正を願い、インターネット上で賛同の声を募り始めた。 (永原 香代子)
立ち上がったのは、東京・渋谷区の広告代理店経営、美由直己さん(41)ら3人の父親たち。
あとの2人は北海道、九州の宮崎県と、居住地は離れているが、インターネット上で知り合ったという。
それぞれの離婚経験を語り合ううちに、「子供を争いの道具にしかねない今の法制度はおかしい」と今年9月、ホームページ「ファーザーズ・ウェブサイト」を開設した。
今では一日数百件のアクセスがあり、離婚後に子供に会えずに悩む親など様々な立場の人たちから書き込みがある。
美由さんはまもなく3歳になる娘と、別れ話が出て妻が自分の実家へ連れていって以来この2年近く、まったく会っていないという。
親権を高等裁判所まで争ったが、「幼い子供に母親の愛情は不可欠」と退けられ、面接も取り決められなかった。
毎月5万円、妻に娘の生活費として送金してきたが、係争中に拒否されたため、今は学資保険と生命保険を娘のために払い続けている。
「再開できたとき、娘に私が見捨てたわけではないことだけは伝えたい」と美由さん。
ほかの二人のうち、宮崎県の父親(36)は別れた6歳の娘と月1回、会っている。
北海道の父親(41)は子供二人を引き取って育てている。
それぞれ元妻の再婚や転居など親の状況が変わるごとに面接を拒否されたり、会わせたいと思っても連絡が途絶えたりという悩みを抱えてきた。
そこで3人は「夫婦の破局は仕方ないにしても、子供にとって親に変わりはない」と話し合い、当面、欧米並みに養育費の支払いと別れた親が確実に子供に会うことができる面接権を「共同養育権」として法律に明記するよう運動を起こすことにした。
神奈川県在住の母親2人にもメンバーに加わってもらった。
このような動きに対し、多くの離婚家庭の相談にのってきた弁護士の吉岡睦子さんは「法律論としては、面接交渉権はきちんと整備していくべきだと思う。ただし、別れた親に暴力癖がある場合や子供自身が望んでいない場合もあるから、一概に強いるわけにはいかない」と話す。
別れた親と子供との面会を、一緒に暮らす親が不安がり、吉岡さんが一緒に連れ添って面会を果たしたケースもあった。
さらに吉岡さんは「面接交渉権はあくまで子供の権利。それを両方の親が理解しないと長続きは難しいようです」というが、美由さんは「まずは当事者として声をあげていきたい」と言う。
ホームページのアドレスはhttp://www.fatherswebsite.com/
*****
民法に規定なく 切実な願い
増加する離婚件数
親権 約8割が母親
現実は難しい 別居後の交流
厚生省の人口動態統計によると、全国の離婚件数は1990年から毎年過去最高を記録、昨年は25万件を越えた。
結婚年数5年未満が4割を占め、幼い子供がいるケースも増えている。
そうした場合、民法では夫か妻のどちらかに親権を決めるようになっているが、養育費や別れた親との交流については規定がない。
法務省が94年にまとめた民法改正要綱試案には、離婚後別れた親との「面接交渉権」を明記する項目があった。
しかし、夫婦別姓論議の陰で進展せず、97年から民主党などが超党派で国会に提出している民法改正法案にも入っていない。
「離婚について日本は法整備が遅れている」という指摘も法曹関係者にはある。
家制度や父権意識が薄れたのを反映したのか、離婚の際、父親が親権を持つケースは一貫して減り続け、今では離婚の際、母親が親権を持つケースは全体の8割近い。
だが、厚生省が全国5000世帯の離婚家庭を対象に行った調査では、別れて暮らす親と子が「月1、2回会う」「それ以上会う」は合わせて3割に過ぎず、手紙を書いたりはするが、「ほとんど会わない」と「全く会わない」で半数を占める。
家族心理に詳しい文教大学教授の岡堂哲雄さんは「子供が別れて暮らすもう一人の親に会ったり相談したりできる環境を整えていくのは、子供の心の成長を保障する意味で大切」と話す。
親の離婚で、子供自身が傷つく裏には「自分は望まれて生まれてきたのか」「自分のせいで親は離婚したのでは」などの疑問や思い込みがあることもあり、これを払しょくするのも親の役割といえるからだという。
ただ、やみくもに会えればいいというわけではなさそうだ。
社団法人家庭問題情報センター(東京)は、6年前から「親子の面会交流支援サービス」を実施しているが、子供の気持ちに負担をかけたり混乱させることがないように、別れた親同士が互いに相手の悪口は言わない、別れた相手の様子を子供に根掘り葉掘り聞かない――などをアドバイスする。
「理想は、離婚を機に夫と妻という関係から、子育てのパートナーになっていければいい。親自身も傷ついているので、なかなか難しいのが実態ですが」と同センターの竹前ルリさんは話している。