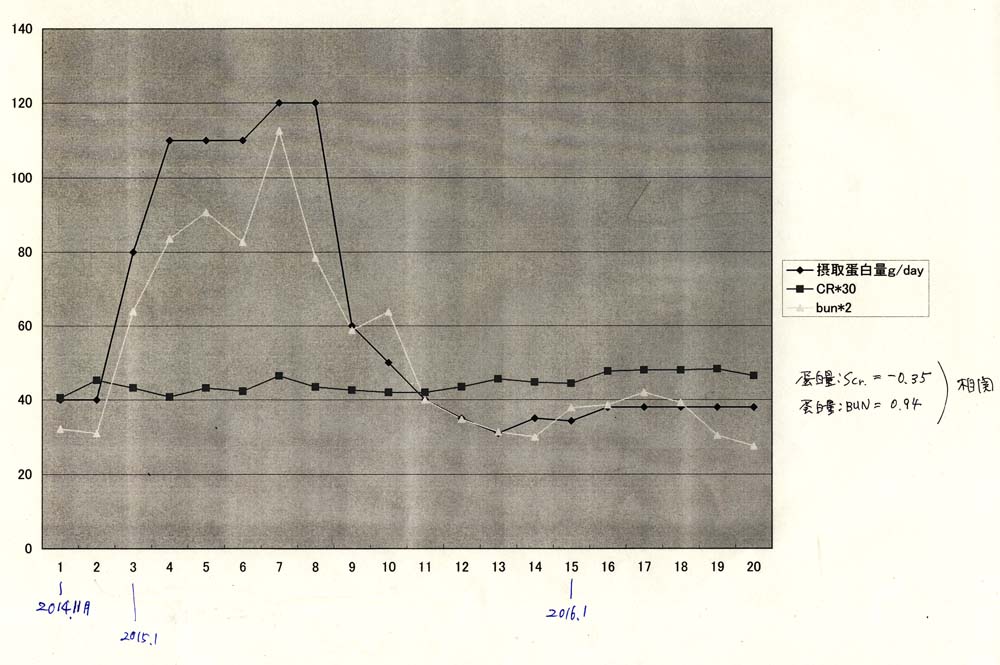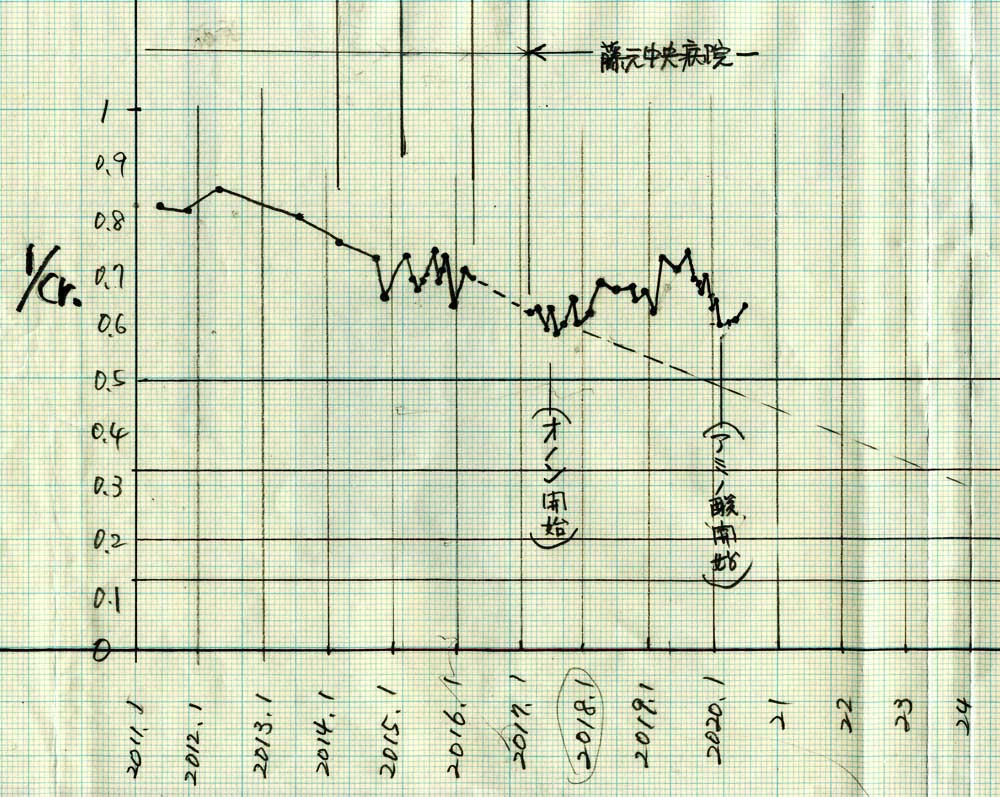�@���͉�����߂����āE�����̍H�v�@ �@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�u���҂ɂ�銳�҂̂��߂̐t���a�������v�@���V�����Y
�i2020.9.25�@�X�V�j�lj����e�E�E�K�{�A�~�m�_�H�̋�̗�
�u8-14-3�v�@�u8-14-3-1�`�U�v
�@
�ڎ� �@
1 �@�@���߂ɁA���̃T�C�g�ɂ��ā@ �@
�@
�Q �@���͂������ׂɁ@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@
�R �@�X�e�[�W�ieGFR�j�@ �@�@
3-1�@�E�E�����̃X�e�[�W(�����̒��x)��m���@
3-2�@�E�E�����t���a(CKD)�̐i�s��m���@�@
�@
�S �@����ɂ�����^�C�~���O�H�@
�@
�T �@�H���̍H�v�@ �@�@�@�@�@ �@�@
5-1 �E�E�H���̊Ǘ����@�@
 5-2 �E�E�e�h�{�f�̊Ǘ����@
5-2 �E�E�e�h�{�f�̊Ǘ����@�@�@�@�@
5-2-1 �E�E�����Ǘ��@�@
5-2-2 �E�E�`���i����ς��j���Ǘ��@�@�@�@�@
5-2-3 �E�E�J���E���Ǘ��@�@�@
5-2-4 �E�E�J�����[�Ǘ� �@�@�@�@�@�@�@�@�@
5-2-5 �E�E�����Ǘ��@�@�@
5-2-6 �E�E�����Ǘ��@�@�@
5-2-7 �E�E�����Ǘ��@ �@�@�@�@
5-2-8 �E�E�h�{�Ǘ��@�@
5-2-9 �E�E�h�{�v�Z�̌덷�@�@�@�@�@
5-2-10 �E�E�T���͂��J���H�H�@ �@�@�@
5-3 �E�E�t���a�p�H�ނ̔������@�@�@�@�@�@
5-4 �E�E�Ⓚ�������@
5-5 �E�E�h�{�Ǘ��̓G�N�Z���Ł@
5-6 �E�E���s�ɍs�����̐H���Ǘ��@
5-7 �E�E��ԐH�̊��߁@
�@
6�@ ��������A��������̍H�v�@�@�@
6-1 �@�ƒ댌���̋L�^�@�@
6-2 �@�������̌}�����@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@
7�@�@�t���ɗǂ��Ȃ��ƌ����邱�Ɓ@
7-1 �E�E�������@
 7-2 �E�E�A�~�m�_�X�R�A�̒Ⴂ����ς����̐ێ�@ �@
7-2 �E�E�A�~�m�_�X�R�A�̒Ⴂ����ς����̐ێ�@ �@
7-3 �E�E�ߘJ�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
7-4 �E�E�\���\�H�@
7-5 �E�E�T�v�������g�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
7-6 �E�E�H�i�Y���� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
7-7 �E�E�R�ۍ܁A�ɂݎ~�߁A��M�܁@
7-8 �E�E�����s���@
7-9 �E�E�X�g���X�@
7-10 �E�E�얞�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
7-11 �E�E�O�a���b�_�@�@�@�@�@�@
7-12 �E�E�^�o�R�@ �@�@�@�@�@�@�@�@
7-13 �E�E���A�a�@
�@
�@8�@�������s�������� �@�@�@�@�@�@�@ �@�@
�i�O�q�ƈꕔ�d������L�q������܂��j�@
8-1 �E�ECcr..��GFR�̕��ACcr.�������Œ��ׂ�@
8-1-1 �E�N���A�`�j���E�N���A�����X�iCcr.�j�������Ōv�Z����@
�@
 8-1-2
8-1-2 �E�E24���Ԓ~�A������@�@
8-1-3 �E�E24���Ԓ~�A�ɕK�v�ȗp��@
8-1-4 �E�E�̔A�菇�@�@�@�@�@�@�@�@
8-1-5 �E�E�N���A�`�j���E�N���A�����X(Ccr)�̌v�Z
8-1-6 �E�ECcr.�̐����@
8-1-7 �E�EGFR�Ƃ́@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
8-1-8 �E�E�t�����h�߁i�납�j�@�\�̒m���@�@
8-1-9 �E�ECcr.�Ƃ́@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
8-2 �E�E�����A�`���ێ�ʂ�A�������玩���Œ��ׂ���@
8-3 �E�E�����̔A�ʂ��L�^����@�@
8-3-1 �E�E�O�o��ł̔A�ʂ̐�����@�@
8-3-2 �E�E�r�ւ̎������L�^����@�@
8-3-3 �E�E�x�X�g�̏d��m��@�@�@�@�@�@
8-4 �E�E�A�����M�[��������@�@
8-5 �E�E�֔��@�@
8-6 �E�E�S�ẴT�v�������g����߂�@�@
8-7 �E�E�y���^�����n�߂�@�@
8-8 �E�E���t�����E���ʂ̈��艻�̍H�v�@
8-9 �E�E�C�O��CKD�����Q�l�ɂ���@�@
8-10 �E�E���̌����̑�����̍H�v�@�@
8-11 �E�E���ʂȑ̗͎͂g��Ȃ��@�@
8-12 �E�E�������̐������Ƃ�@�@
8-13 �E�E�����������n�߂�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
8-14 �E�E�K�{�A�~�m�_�������ꂽ�H�����n�߂�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
8-14-1�E�E�K�{�A�~�m�_���烁�j�����l���� �@
8-14-2�@�E�E�K�{�A�~�m�_���烁�j���̍���
8-14-3�@�E�E�K�{�A�~�m�_�H�̃T���v��(new)
8-14-3-1�@�E�E�K�{�A�~�m�_�H�̒�ԃ��j��(new)
8-14-3-2�@�E�E����u�߁E���i�A�W�j(new)
8-14-3-3�@�E�E���ԓ��ē��E�Ă�����(new)
8-14-3-4�@�E�E�p�X�^�E�L�q�i�M���[�U�j(new)
8-14-3-5�@�E�E���g���g�J���[�E�f�ˁi�����߂�j(new)
8-14-3-6�@�E�E�O�H�̗�E�X�^�[�o�b�N�X�E�J�v���`���[�U(new)
8-14-4�@�E�E�g���v�g�t�@�������炷�K�v���H
 �@9�@�@���̑����낢��@�@
�@9�@�@���̑����낢��@�@�@
9-1 �E�E�Ⴝ��ς��Ă̂��Ɓ@�@�@�@�@�@�@�@�@
9-2 �E�E�a�@�I�с@
9-3 �E�E���N�f�f�ɖ]�ނ��Ɓ@�@
9-4 �E�E�����������@�@
�@
�P�O�@�E�E���s���������݁A�����Ȃǁ@
10-1 �E�E���������Ŏ��s�@�@
10-2 �E�E���Ⴝ��ς��������Ŏ��s�@�@
10-3 �E�EBCAA�T�v�������g�Ŏ��s�@�@
10-4 �E�E�^���������Ŏ��s�@�@
�@
�P�P �E�E���Ɛt���a �@�@
�@
�P�Q �E�E����CKD�̐��� �@�@
�@
�P�R �E�E�A����@ �@ �@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�P�@�n�߂ɁA���̃T�C�g�ɂ��ā@ �@�@ �iCKD=�����t���a�j
�@
�����́uCKD�ۑ����A�����̍H�v�v�́A���i1946�N���܂�E�j�E�X�e�[�WG3b�@�t�d���NJ��ҁj�̌��ݐi�s�`�̐����L�^�ł��B���҂̗��ꂩ��̌��Ɋ�Â��A���́uCKD�ۑ����iCKD���ǂ��瓧�͂ɓ���܂ł̊��ԁj�̐����̍H�v�v�Ȃǂ��ACKD���S�Ҍ����ɁA�ł��邾��������₷���\���ŏЉ�����Ǝv���Ă��܂��B
�@
�H�v�̓��e�́A��{�I�ɂ͓��{�t���w��̃K�C�h���C���ɏ]���Ă��܂����A�K�C�h���C���ɂȂ����ƂɊւ��ẮA�����Ő������Ă�邵���Ȃ����߁A�ԈႢ�����邩���m��܂���E�E�����A�f�l�̂�邱�Ƃł�����K�����������ɂ������ȓ_������͂��ł��E�E�B
���w�E������Β������A���ǂ����e�ɂ��Ă��������Ǝv���Ă���܂��B
�@
�@���A�l�b�g��Ɋw�����Ƃɂ��K�C�h���C������������ꍇ�ɂ́A�o���邾�������̃T�C�g���Љ���Ē����A�����N����悤�ɂ��Ă��܂��i�����N���Ȃ��ꍇ��URL���R�s�|���y�[�X�g���Ă݂ĉ������j�B
�@
�����́u�����̍H�v�v�̋L�^�́A�����v���������Ƃ���Â�ɏ�������ł��܂��̂ŁA�d�������L�ڂȂ邱�Ƃ�����܂��B�܂��O�ɏ��������Ɣ����ɐ��l�Ȃǂ�����Ă���\��������܂��B�^��ȓ_�͂��q�˒�����A������͈͓��ł��Ԏ��v���܂��B
�@
�A���� k-yazawa��miyazaki-catv.ne.jp�@
�@�@�@�@�i�������ɂ����Ă��������j���V�����Y
�@�@�@�@�Z�����ڍׂ͈�ԍŌ�̃y�[�W�ɂ���܂�
�@
�����̃T�C�g�ɓ���������Ƃ���A���Ԃ̓�̂��Ƃ��Ǝv���܂��B
�@Ccr.(�N���A�`�j���E�N���A�����X)���������{���Ă��Ȃ��a�@�A�N���j�b�N���ŁA�ʏ�̌��t�����ƔA��������ACcr.��A�H��������ۂɐH�ׂ������A�J���E���A����ς����̗ʂׂ��̓I�ȕ��@�̐����B
�@
���Q�ƁE�E8-1�@ Ccr.��GFR�̕��ACcr.�������Œ��ׂ�j��46�@
�@
�A����ς����������ł̐H�����j�����A�]���̒`�����ł͂Ȃ��A�K�{�A�~�m�_�̗ʂ����g�ݗ��Ă鎖�̈Ӌ`�ƁA���̋�̓I���@�ɂ��Ă̐����B
�@
�@�@�����L���Q�Ɖ������E�E
�@�@�@8-14�@�K�{�A�~�m�_�������ꂽ�H�����n�߂�E�Ep76�@
�@
�@
�Ȃ��A�����Ŏ��グ����e��CKD�Ɋւ���S�Ă̎�����ԗ����邱�Ƃ�ړI�ɂ��Ă���܂���B���̌l�I�Ȑ����̍H�v�A���Âɑ���l���Ȃǂ���X�k�R�ɏ������߂������W�߂����̂ł��B
�@
�@�W�c���f�ȂǂŎn�߂Đt���a�̎w�E����ꂽ���́A�܂����L�̓��{�t���w��̃K�C�h���C����A�s�̂���Ă���t���a�̏��Ђ��Q�A�R���ǔj����A�t���a���Â̑S�e����ʂ�ڂ�ʂ���Ă���A���̃T�C�g�𑽏��Ȃ�Ƃ��u�^���̖ځv�������Č��Ă�����
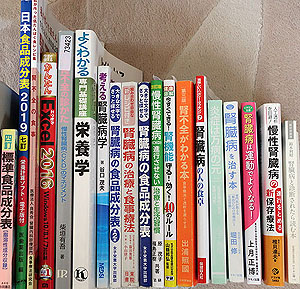
���̂����S���Ǝv���܂��B�Ȃ��A��w�I�ȓ��e�̕����Ɋւ��ẮA���͈�t�ł͂Ȃ��̂Œf��I�ȕ\�����ł��Ȃ����Ƃ����������������B
�@
�@�J��Ԃ��ɂȂ�܂����A���̃T�C�g��CKD�̈ꊳ�҂̎��ȗ��̐����̋L�^�ł��B���̃T�C�g�����āA�����V���������������͎厡��Ƒ��k�̏エ���Ȃ��Ă��������B
�@���Ɏ��ȗ��̌������H�������͊댯�ȐېH��Q�i�h�{��Q�j�Ɋׂ�A�����ǂȂǂ������N�����\��������܂��̂ŁA�K���厡��̎w���̂��Ƃɍs���悤�ɂ��肢�v���܂��B
�@
�����a���������X�ɂƂ��Ĉ�ł��Q�l�ɂȂ邱�Ƃ�����܂�����K���ł��B�����Ċ�킭�Έ�l�ł������̕���������CKD�ۑ����̓K�Ȑ����ɐ�ւ����A���U�A���͂�����ł��邱�Ƃ�S�������Ă���܂��B
�@
(�Q�l)
�@
�@
�����{�t���w��̃K�C�h���C��(�S��)�F
�@
���t���w����H���K�C�h�F�����ǂ߂ACKD���҂����ׂ������̂قڑS�Ă�������܂��B������ʈ�t��Ǘ��h�{�m�����ł��̂ŁA���ł����͂ł��E�E
�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�Q�@���͂������ׂɁ@
�@
�����B�������A�����t�s�S�Ȃ�l�H���͂��邱�Ƃ������ɂ͑��������A�����̐H���̉��P�A�����̎��ÊJ�n�i�����������铙�j���d�v���Ǝv���܂��B���ׂ̈ɂ͌����N�Ǝv���Ă���l���A�N�Ɉ�x�͔A�������鎖�����������߂������܂�(�s�̂̎���
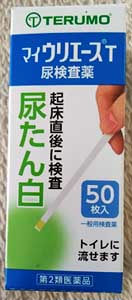

�����g���Ύ����Œ��ׂ鎖���o���܂�)�B�@�@�@
�@
�i�摜�́j�}�C�E�E���G�[�XT�@(�A�`���̂�)�A
�@�@�@�@�}�C�E�E���G�[�XBT�i�A�`��+�A���j
���ɁA�}�C�E�E���G�[�XKC�i�A�`��+�A��+�A�����j
(50������A30������)������܂��B
(��ǁA�y�V�E�A�}�]�����ōw���ł��܂��j
�@
�����A�����Œ`���A�i+�P�ȏ�j���o����A�t���Ɉُ킪����\��������܂��̂Ō��t���������}��ׂ��ł��B���̌��ʁA�����N���A�`�j���l�iCr�D�j��1.0mg/dl�ȏゾ�����珉���̐t���a�̉\��������܂��B���������̐t���a�Ɛf�f���ꂽ��A�o���邾�������A��x�t���a�̐���̐f�f���邱�Ƃ������߂��܂��B�����Ă����A�t���������܂��傤�E�E�Ɗ��߂�ꂽ��A�����ׂ��Ǝv���܂��B
�@
�t�@�\�ቺ�̌����𐳊m�ɓ��肵�Ȃ���A���̌�̎��Õ��j�����܂�Ȃ��͂��ł�����E�E�l�I�ɂ͎����̐t���a�ɑ��鎡�Â̒m����g�ɂ��E�E�ǂ������珫���̓��͂��������̂���ǂ�������K�v������Ǝv���܂��B�@Cr.1.0���x�ł́A�債�����ƂȂ��A�Ɖƒ�ォ���莋����Ȃ����Ƃ����邩������܂��A�H������̌������i�Ⴆ�A������`������ۂ肷���Ȃ��Ƃ��A�Ȃ�ׂ��������^���������Ƃ��j���ӎ����Đ������������ǂ��Ǝv���܂��B
�@
���͓��͂ɂ�锜��ȏo�����ɂ�������炸CKD�����ۑ����̋�̓I�Ȏw������Ë@�ցi���ɉƒ��j�ɋ`���t���Ă��Ȃ����̂悤�Ɍ����܂����A�{�������čl���悤�Ƃ��Ă��Ȃ����̂悤�Ȉ�ۂ��܂��B�N�Ɉ�x�̌��N�f�f���Ă��邩����S�A�Ȃǂƈ��S�����A����������CKD�Ɛf�f���ꂽ�Ȃ�A����̖��@���ׂ��ł����A�������ł�CKD�̖{��ǂނȂ肵�āA�H������̉��P�������n�߂Ȃ��ƁA����������邱�ƂɂȂ邩������܂���E�E�t���͒��ق̑���ƌ����Ă��܂��B�@�����̉��P�������A��������ォ��u���낻�������Љ�܂��傤���E�E�v�ƌ���ꂽ���́A�N���A�`�j���l���Q�ɂȂ��Ă��āA�����̓��͂��قڊm�肵���Ǝv��ꂽ�̂����m��܂���E�E
�@
�@
�i���P�j�A�`���ʂƂ��A�A�Ɋ܂܂��`�����̗ʂł��B�`�����͐g�̂�����ȉh�{�f�ł�����A�{���͌������^����J���ł����Ȃ�����A�A����R��o�邱�Ƃ͂���܂���B�t���������́i���Q�j�͌��t����L�Q�����h�������ĔA�Ƌ��ɔr�o�����ł����A�����̂Ƃ́A����R�[�q�[���[�J�[���h�����̗l�Ȗ�ڂł��B�R�[�q�[���[�J�[�̏ꍇ�ɂ́A�h����������Ō��������Ă�����A��������R�[�q�[�����o�Ă��܂��ł��傤�E�E
�l�̂̎����̂Ƃ������̌��t�h�ߑ��u���A�����̂�����Ȃ�A�Ԃ̖ڂ͔��ɏ������ĐԌ����╪�q�ʂ̑傫�Ȓ`�����Ȃǂ͒ʂ邱�Ƃ͖{�������͂��ł��E�E
�@�����������̂��敾���Ă���ƖԂ̖ڂ��j�����肵�āA�`�����R��o�Ă���ƌ����Ă��܂��B
�@
�@�i��}���Q�Ƃ��������j
�A���ד������玅���̂ɓ��������t�͎����̓����Ŕ�r�I�����ȕ����i�����A�i�g���E���A�J���E���A�u�h�E���A�A�~�m�_�A�N���A�`�j�����j���h��(�h���o)���܂����A�A�ǂ�ʂ��Đt������o��܂ł̉ߒ��ŁA�i�g���E����u�h�E���A�A�~�m�_�A�ƌ������L�p�ȕ����́A�قƂ�ǔA�NJO(�Ԏ�)�ɐ��ݏo�ėA�o�ד����ɍċz������܂��B�i���}�Q�Ɓj�܂����������̂X�X���������悤�ɗA�o�ד����ɍċz������g�̂ɖ߂�܂��B�N���ɗ�����̂́A�����̂��h���������̂ق�̂P���Ȃ�ł��ˁE�E�B�����̂ɑS�Ă̍�Ƃ킹�邱�ƂȂ��A�����̂͂Ƃ肠�����A�����������͑S���h�߂��Đg�̂ɗL�p�ȕ������N���ɗ�����܂ł̊ǁi�A�ǁj����O�i�Ԏ��ƌĂ��g�D�j�ɕ��o���A�����эǁi�A�o�ד����j���z�����Đg�̂ɖ߂��A�Ƃ�����ƂŌ��t�����Ă����ł��ˁE�E�]���Ď����͈̂����Ȃ����ǁA�A�ǂ������E�E�A�A�ǂ̎��͂̑g�D�i�Ԏ��j������(�Ԏ����t���j�E�E�ƌ����\�����łĂ��܂��E
�@
�i���Q�j�����̂Ƃ��E�E���t���̍\���Ɠ���(���{�t���w��)�E�E�@
�@
�@
��1���̔A����r�o�����`���̗ʂ�0.3���ȉ��Ɍp���I�ɗ}�����Ă���l��98���̊m���œ��͂ɂ͈ڍs���Ȃ��ƌ����Ă��܂��B����͑�ϕ�����₷���ڈ��ɂȂ�Ǝv���܂��B�A�`����ʌ������d�v�ȈӖ��������ƂɂȂ�܂��B
�������ӂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂́A�������������ꂾ���A�`���A��0.5g/day���z���Ă��܂�����A���͂ɂȂ�m���͑������Ă��܂��܂��̂ŁA���U�ɂ킽��A�����A�`���A�J�����[�R���g���[���ƓK�x�ȉ^���A���������Ȃ������A�ȂǁA�������ꂽ�l���𑗂�˂Ȃ�Ȃ��E�E�Ƃ����A�Ȃ�Ƃ���邹�Ȃ��ɂ͂Ȃ�܂����A�A�ŏǂ̋ꂵ�݂�A���͂���ƌ������Ƃ��ǂ��������Ƃ���m��A���������������ꂽ�ɂ��䖝�ł��邱�Ƃł��傤�E�E
�@
�����m�ȔA�`���ʂ𑪂�ɂ�24���Ԓ~�A�i1��24���Ԃ̔A��S���e��ɒ��߂邱�Ɓj�����āA���̈ꕔ�̔A��a�@�Ɏ����čs���āA��ʕ��́i1dL=1�f�V���b�g����100cc������̒`���ʂ𑪒�j���Ă��炢�A���̐��l�img/dL�j��1���̑��A��(dL)���|�����1���̔A�`���r�o�ʂ�������܂��B
�@
mg/dL�ƌ����P�ʂ́A�A�PdL������̒`���ʁimg�j�ł����A�ƒ�ł�cc�������̕����i�L�b�`���X�P�[���Łj���m�ɑ����̂ŁA�A100g������ƌ��������������ނ��됳�m���Ǝv���܂��B�i�W�|�P�ɒ~�A�̏ڂ����������ڂ��Ă��܂��j�B�@
�@
�܂�����قǐ��m�ł͂Ȃ��Ă��A����̔A�ʂ����W���[�J�b�v�Ɏ��A����̔A�ʂ����ɋL�^����1���̑��A��(dL)�����߁A�s�̂̔A�`�����������g���ċN����i���P�j�̒`���̏�ԁi�|,±�A�{�P�C�{�Q�C�j�ׁA�������ɕt���̔���\����A1dL�P�ʂ̒`������(mg/dL)��m��A�A��(dL)���|����Α�̂̔A�`���ʂ͕�����܂��B��ʓI�ɂ͔���\�Ł{�P�ȏ�ɂȂ�����a�@�����������ǂ��Ǝv���܂��B�i����+�Q�ɂȂ�����A���������i�����j����ׂ����Ǝv���܂��j
����łł���u�ג������������v�ɂ��A�����́A�������_�̔A�̏�Ԃ����Ă���̂ŁA1��̌����ŁA1���̑��`���ʂׂ邽�߂ɂ́A���ׂ鎞�_�̔A�̔Z�k�x��1���̕��ϓI�ȏ�ԂłȂ���Ȃ�܂���B�����̔A��ߑO���̔A�͐g�̂̐����s���ŔZ�k����Ă��鎖�������̂Őt�@�\�̈������͒`���ʂ������o��\��������܂��B���͐Q��O�̔A�ϓI�ȔZ�x�̔A�Ƃ��Ė����A�`���̃`�F�b�N���Ă��܂��B
�@
3���b�g���ʓ���e���1���̔A��S�����߂ĝ��a���ċψꉻ���Ă���i�����������ĐF������j��萳�m��1���̔A�`���ʂ�������܂��B�ł����m�ȕ��@��24���Ԓ~�A���ĕa�@�ŔA�����i�A�`����ʌ����j�����Ă��炤���Ƃł��B
�i�~�A�̕��@�͂W�|�P�ɏڂ����ڂ��Ă��܂��j
�@
�@�u�`���������@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�u�}�C�E���G�[�X�s�v�@ ��A�`���̕]���\�E���l��mg/dL�
�@
�i�h�A�`���������h�E�E�A�}�]���A��ǂȂǂŎ�ɓ���܂��B�`�������̕��A�`���Ɠ������ׂ��镨�Ȃǂ���܂��B
�a�@�ł̔A�����́A�t�@�\������Ȃ�A���O�Ɍ������^���ł����Ă��Ȃ�����A�A�`�����i+�P�j�ɂȂ�Ƃ������Ƃ͂܂�����܂���B���̈Ӗ��ł́A�t�@�\�̒ቺ������ɂ́A�Z�k����₷�������A�������������������₷���ƌ����邩���m��܂���B
�@
���A�`���������́i�|�j�͂P�`�Xmg/dL
�@�@�@�@�@�@�@�@ (±) ��10�`29
�@�@�@�@�@�@�@�@ (�{1) ��30�`99
�@�@�@�@�@�@�@�@ (+2) ��100�`299
�@
�A�`��0.5g/���Ƃ����̂́A1���̔A�ʂ�1.5L�̎��A500mg/15dL=33mg/dL�Ȃ̂ŁA���������i�{1�j�ɂȂ�����댯�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�i±�j�̒i�K�ŗ}���Ă����������̂ł��B�A�`���̗ʂ����炷�ɂ́A�`�����o�錴���ƂȂ��Ă���t���a�̎��Ái�������Ȃǁj�����鎖�͖ܘ_�ł����A�������^����J������߂�K�v������܂��B�^������߂邱�Ƃ͊ȒP�ł����A�J���͂����ȒP�ł͂Ȃ��ł��ˁE�E�A�����A�`����+�Q�ƂȂ��Ă��A�d�����y�����邱�Ƃ͏o���܂���ł����E�E
�@
����ς�����H�ׂ�ʁi�ێ�ʁj�́A�̏d1kg������0.6�`0.8���Ɍ��炷�����t���w��Ő�������Ă��܂��B�`�����͐l�Ԃ̐g�̂�����Ă���d�v�ȗv�f�ł�����A�s��������A�H�ׂ���������[���Ȗ�肪�N����Ƃ���Ă��܂��B�܂��A�����ǂɎキ�Ȃ邱�Ƃł��傤�E�E������Ƃ������ŁA���ׂ���������A���s����ꂽ��A�̒������ꂪ�o�Ă��邱�Ƃł��傤�E�E
�@
�@
�@3�@�@�X�e�[�W�ieGFR�j
�@
�@
�@3-1�@�@�����̃X�e�[�W�i�����̒��x�j��m��
���t���a�̐i�s�x���X�e�[�W(Stage�F�i�K)�ŕ\���܂��B�@
�����̂�ߗʁiGlomerular Filtration Rate = GFR)�̓������������G1�`G5�ŕ\�����܂��B���������قǏd�ǂł��B�����̃X�e�[�W��m��A�X�e�[�W�ɉ������A���݂̈�w���ǂ��Ƃ��鎡�Â��A���������邱�Ƃ��ۑ����̊�{�ƂȂ�܂��B
�@
�X�e�[�W�́A���t���̃N���A�`�j���Ƃ��������̗ʂƔN���v�Z����܂����A���Z���ꂽ�iestimated�j�̓�����e��O�ɕt����eGFR�Ə����Ă��܂��B�N���A�`�j���Ƃ��������͉^���Ȃǂŋؓ����g�����ۂɋؓ�����i�ŏI��ӕ��Ƃ��āj���o�����ƌ����Ă��镨���ł��̂ŁA�ؓ����������g������ɂ͑��ʂ̃N���A�`�j�������t���ɗ��܂�܂��B�@�����O2�`3���͑�l�������Ă��Ȃ��ƁA�����̓x�Ɍ����l���傫���ϓ����Ă��܂��ƌ������Ƃ��N���肦��ł��傤�E�E
�@
���v�I�ɂ�G1�`G2�͓���(��1)�ɂ͂Ȃ�Ȃ������m��Ȃ��O���[�v�ƌ����܂����A40�˂�Cr.1.0�̕��͊��ɃX�e�[�W��G2�ł����A60�˂�Cr.1.0�̓X�e�[�W��G3a�ł��B
�@
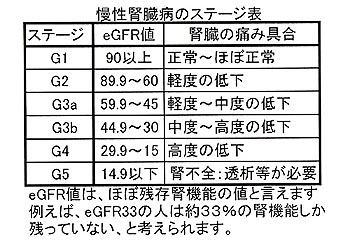
�i��1)���͂Ƃ́E�E�@�\���Ȃ��Ȃ����t���̑���Ɍ��t��l�H�I�ɏ����ƂŁA�r�̐Ö��ɓ_�H�̂悤�ɐj���h�����t���A���̌��t���h�ߊ�ɑ����ĘV�p���̖w�ǂ��h�߁A�������A���ꂢ�ɂȂ������t���̐Ö��ɖ߂��܂��B
�@
�@�������́A�r�̐Ö������ʂ̌��t���j�͒��a1.6mm������܂��B�r�̐Ö��ׂ͍����߁A���̂܂܂ł�1.6mm�̐j���h���������Ƃ��o���܂���B���ׁ̈A�����Ö����K�v�ł����A���̈���@�Ƃ��āA�r�̐Ö��ɓ������q���A�����̍������͂ŐÖ������錌�ǂ̐ڑ���p���K�v�ł��B�����ɐڑ�����3�T�Ԃ�����ƐÖ��͑����j���h����قǂɑ����Ȃ�܂��B�����Ȃ����Ö��̓V�����g�iShunt�F�e���Ƃ����Ӗ��j�ƌĂ�܂��B
���̂��Ƃ͉����Ӗ����邩�Ƃ����ƁA�V�����g�͎�p���č���Ă������ɂ͎g���Ȃ��ƌ������Ƃł��B�]���ċ}���ʼn^�э��܂ꂽCKD�������҂́A�r�ł͂Ȃ��A��̐Ö��⑾�����̕t�����̑����Ö��Ɋ�(�J�e�[�e��)��}�����āA���t�����Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���B���͂͐����邩���ʂ��̖��ł��E�E
�@
�@
G3b�`G4�́A�u���͓�����x���ł���\��������v�A�ƕ\�������悤�ɁA�������������̓��͓����͔����������A�P�ɒx���̓w�͂����邵���Ȃ��A�ƌ����Ă���悤�ɕ������܂��B�펯�I�ɂ͓��͂ɂȂ�\���́u���Ȃ荂���v�ƂȂ�܂��BG4�͓��͂��������Ȃ��X�e�[�W�Ƃ��ē��͐���֏Љ�A�Ƃ̋L�q�������ł����AG4��50�˂̕���Cr.2�ɂȂ������̃X�e�[�W�ł��BG5�͓��͂ɓ���A�܂��͓��͂̏����i�V�����g�쐬��p�j������X�e�[�W�ƌ����Ă��܂��B
�@
�����̒ŊL�N���j�b�N�i���L�T�C�g�j�͓��͎{�݂������Ȃ��A�t���a�ۑ������Â̐��N���j�b�N�ł����AG4�ɂȂ��āA�u�����ׂ��p������܂��瓧�͂̏��������܂��傤�A�ƈ�t�Ɍ������ꂽ�l�B����R�W�܂��āA���͉���̎��Â��Ă��܂��B���{�ł͐����Ȃ����͎{�݂������Ȃ��uCKD�ۑ������v�̃N���j�b�N�ł��B�ŊL�N���j�b�N�ɏW�܂銳�҂̓����́A��t�̎w����������Ǝ���A���ɐ^�ʖڂœ��͉���ɔM�S�Ȑl�B�������ł��B
�@
�@
�@
�@
�@
�@3-2 �����t���a�iCKD�j�̐i�s��m��
�@
���t�@�\�̈����̏�m��ɂ́u�����N���A�`�j���FCr.�v�̋t���i�P�^Cr.�j�̃O���t��t����Ɛi�s��������₷���ƌ����Ă��܂��B�����Cr.�̐��l�͒����ł͂Ȃ��Q�����I�ɉE���オ��ɃJ�[�u��`���Ĉ������Ă������̂ł����ACr.��Ɏ����ė����N���A�`�j���l�̋t���u1/Cr.�v���O���t�ɂ���Ƃقڒ����I�ɂȂ�A�����̗\�������₷���ƌ����Ă��܂��B�����̌��݂̏Ə����̗\���������ŁA�O���t�Ɏ����̐��l(1/Cr.)��u���Ă����ƁA�����̐i�s��������₷���Ǝv���܂��B
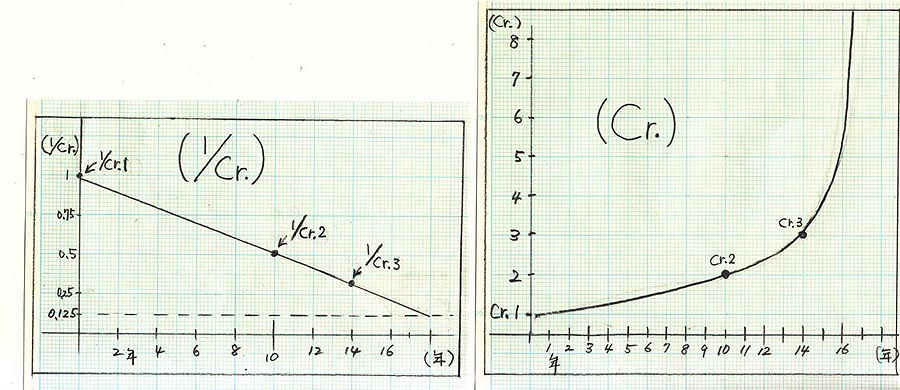
�@
�i�����Ӂj��ʓI�ȌX�����ȗ��I�ɕ\�����}�ł��B��ɂ��̐}�̂悤�ȒP���Ȍo�߂�H��킯�ł͂���܂���B��ԍŌ���P�Q�@����CKD�̐��ځ@�Ɏ��̂P�^CR.�̃O���t������܂��̂ł��Q�Ƃ��������B
�@
�@
�@�S�@����ɂ�����^�C�~���O�H�@
�@
���t���a�Ɋւ��錻�ݔ̔�����Ă���{��ǂ݂܂��ƁA���������́A���҂����t�����ŃN���A�`�j���l��2���z�����������Љ��Ɨǂ��A�Ə�����Ă���{�����X����܂��B�����̑����͂��Ȃ�O�ɏo�ł���A���݂ł����X��l�b�g�Ŕ̔����Ă��镨�Ǝv���܂��B���݂ł͐t���w��̊���݂Ă��A�����Ƒ������������Љ��悤�ɕς���Ă��Ă��܂��B
�@���͈�ʘ_�Ƃ��ĎႢ���i60�˖����̕��H�j���N���A�`�j���l��2�ɂȂ��Ă��玡�Â��n�߂�̂ł͂��Ȃ�x������̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă��܂��B���������ɂ��ۑ����̊Ǘ����\���ɂ͏o���Ȃ�������l����ƁA���������A�t�@�\�̈������҂��o�Ă������ɂ͐���ɉ��A�����̓��͂��قڊm�肷��Cr.��2.0�ɂȂ�܂ő҂��āA����ɏЉ�܂��傤�E�E�ƌ����Ă���悤�ɂ����������܂��B
�@
�����Ō�������Ƃ͂ǂ̂悤�Ȉ�t�ł��傤���H
�t���w��̒�`�ɂ��ƁE�E�u�����������������w���܂ł�����ɓ���āA�ǍD�Ȍ��N�Ǘ��A�\�h��w������f����C���Ƃ���S�l�I�Ȑt���a�f�Â����H����v�Ƃ���܂��B
�@
�@���{�̏ꍇ�A��l�̐t�����オ��̉��l��CKD���҂�f�Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł��傤���H�@2019�N5�����݂̓o�^�t�����㐔��5,317���i���͎{�݂��܂ށj�A����ɑ��Ē��x�ȏ��CKD���Ґ��͖�1330���l(��1100���l�ȏオ�X�e�[�WG3�ȏ�)�B�y�x�ȏ��CKD�\���R��6000���l�ȏ�E�E�����̖��ɂ̂ڂ�܂��i���P�j�B
�@
�@����1����2500�l�̒��x�ȏ��CKD���҂�f�Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Z�ɂȂ�܂����A�t���w��̓o�^����ƌ����Ă��A���ۂɂ͕K�������{�Ƃ��t�����ȂƂ����킯�ł͂Ȃ���t����������Ⴂ�܂��B�܂����ۂɊ��҂�f��Տ���ł͂Ȃ���w�̌����҂Ƃ����������邱�Ƃł��傤�E�E�Ȃ�ɂ��Ă��A�S�R���オ����Ȃ��ƌ������Ƃ͊m���ł��傤�E�E
�@
����ʂ̕a�@��CKD���Â�w�����Ă��Ă��A���v�I�ɁA�����N���A�`�j���l��1����2�ɂȂ�̂�10�N�A2����3�܂ł�4�N�A3����A�����̕������͂ɓ���8�܂ł�2�N�ƌ����Ă��܂��B�܂�30�˂�Cr.1.0�̐l�͍�����^���ȕۑ������Â��n�߂Ȃ��ƁA�����̐l��16�N���46�˂œ��͂��K�v�ɂȂ�A�ƌ������ƂɂȂ�܂��B����ւ̏Љ���Cr.2�Ƃ���ƁA�Љ�ꂽ�l�̑�����6�N��ɂ͓��͂ɓ��邱�ƂɂȂ�\���������ƌ������ƂɂȂ�܂��B
�@�ܘ_����͓��v��̂��ƂŁA����Cr.��2�ł����Ă��A���i�ȐH���Ö@�Ə\���ȋx�������A�d�J���̎d��������Ă�����́A���ׂ̏��Ȃ��d���ɕύX���A�t���̕ی���ŗD��ɍl���������ɐ�ւ��āA�{�C�Őt���×{������A������傫���x�炵�A�N��ɂ���ẮA���͂ɓ��炸�ɍςމ\�������Ȃ��炸����Ǝv���Ă��܂��B�d����ς��邱�Ƃ͊ȒP�ł͂���܂��A���ς��Ȃ���߂��������͂ɓ��邱�ƂɂȂ�E�E�ƌ������Ƃ��ǂ��䂤���Ƃ���m��A���̖��̐[�����𗝉�����A���͂ɓ���Ȃ��悤�ɐ���t�̓w�͂����悤�Ƃ����C�����������ė��邱�ƂƎv���܂��B
�@
�����͓��ɎႢ�����A�ʏ�̌��f�ŔA�`����+�P�ȏ�Əo����A�����N���A�`�j����1.0mg/dL���Ă������A������eGFR��60ml/min/1.73�u�ȉ��ł�������A��������ォ��t���a�ۑ�������i�t�����Ȃ̂���a�@�j���Љ�Ă��炤�ׂ��Ǝv���Ă��܂��B�Ȃ�ׂ��傫�ȕa�@�ŁA�t���a�̎�ނ̊m��A�h�{�w���A�����w������ׂ��ł��B�̒��͐�D���Ȃ̂ő��v�Ɗy�ώ����Ă���ƁACr.�l�͉����x�I�ɓ��͂ւƏ㏸���Ă����܂��i1/Cr�͉��~���Ă����܂��j�B
�@
�������̑����a�@���Љ�Ȃ��Ă���f�o���܂��B�i�Љ�Ȃ��ƕʓr�萔��5000�~���x���|���邱�Ƃ�����܂����A���̉��l�͂���Ǝv���܂��j
�������t���a�ƌ���ꂽ��A����̎w���ōX�Ȃ錟���⎡�Â��n�܂�܂����A������̕��͈�t�ɔC���āA���B�͎����łł����Ƃ��āA���͈ȍ~�́u�H���̍H�v�v�Ȃǂ�����܂��B
�@
�i�Q�S���Ԓ~�A�����{���Ă���Ǝv�����Ë@�ւ̗�j
�����̂ق��A�l�b�g�ŁA�u24���Ԓ~�A�����v�Ō�������Ǝ��{���Ă���{�݂��T����Ǝv���܂��B
�@
�@�T�@�H���̍H�v�@�@�@
�i�Q�l�j
���h�{�Ɋւ�����{�t���w��̃K�C�h���C���uCKD�Ɖh�{�v�@�@ �@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@�T-�P�@�H���̊Ǘ��@
�@
�t���a�͐H���̊Ǘ�����Ϗd�v�ł��BCr.��1.0�`1.4�ʂ̌y�x�Ȃ����́A�����A����ς����A�J�����[�����̊Ǘ��ł��ǂ��Ǝv���܂����ACr.1.5�ȏ�Ɉ��������ꍇ�ɂ̓J���E���iK�j�A�ƃ����iP�j�̊Ǘ����n�߂�悤�Ɏ厡�ォ��w��������Ǝv���܂��B���݂ɉ����ߑ��͍������A����ς����ߑ��͐t���̕��S���A�J���E���ߑ��͐S�s�S�A�����ߑ��͌��Ǖǂ̐ΊD���ɂ�铮���d���̌����ɂȂ�ƌ����Ă��܂��B�i5-2-5�����̊Ǘ��Q�Ɓj
�@
���݂̓��{�̈�ÃV�X�e���ł́A�H�������Ɋւ���S�Ă̐ӔC�͈�t��Ǘ��h�{�m�ł͂Ȃ��A���̊��Ҏ��g�ɂ���A�Ƃ������ƂɂȂ��Ă��܂��B
�@���t�����A�A�����Ȃǂ̌��ʂ���A��t���牖���A����ς����A�J�����[���̎w��������܂��̂ŁA���҂͂��̎w���𒉎��Ɏ��Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���B�@��������邩���Ȃ����͊��҂̎��R�ł��E�E��t�͉ƒ���̗����ɂ܂Ŋ��͂ł��܂���E�E�����̓x�Ɉ�t�̓A�h�o�C�X�����Ă���邱�Ƃł��傤�A���������Ď�邩�ǂ��������Ҏ���ł��B�]���Ă��̌��ʂ̐ӔC�͊��Ҏ��g�ɂ���Ƃ������ƂɂȂ�܂��B���{�̑�a�@�ɂ́uCKD������@�v�Ƃ����V�X�e��������܂��̂ŁA�ǂ����������̐H�����ǂꂭ�炢�H�ׂ��炢���̂��A�Ƃ�����������܂��B�F�X�Ȓ�`���H�̗��p���@�Ȃǂ������Ă��������܂��E�E
�@
���āACKD���҂̃��j���Ƃ����ƁA�����Ƃ���ς����ƃJ�����[���ł��d�v�Ƃ���܂����A�����ƃJ�����[�͕�����₷���ł����A����ς����̐ۂ���́A�P�ɒ`���������O�����ȉ��ɂ���A�Ƃ��������ł͕s�\���ŁA�̓��Œ`���������̌��ƂȂ�K�{�A�~�m�_���l���ɓ���Ȃ���Ζ{���̈Ӗ��Ő��m�Ȓ`���������ɂ͂Ȃ�܂���B�����́A1��3�H�̒��ɁA���A���A�����e30g�i����ς����e��T���j�ƁA�����i��1��150g(����ς�����5g)���x��ۂ�A�������`������65���ȏ�ۂ�A�őP�ł͂Ȃ��ł����A�K�{�A�~�m�_�͏\���ۂ��Ǝv���܂��B
�@
�őP�ł͂Ȃ��Ƃ����̂́A�������`������65�����Ƃ�ƁA�m���ɕK�{�A�~�m�_�͏\������ł��傤���A9��ނ̕K�{�A�~�m�_�̃o�����X�������A�u�t�F�j���A���j���v�Ƃ�����̃A�~�m�_���]���Ă��܂���������Ȃ�����ł��B���̗]�����A�~�m�_�̓J�����[�Ƃ��ď����A���̔R���J�X�i�A�f���f�j�����t���Ɏc��A���̏���������t���ɕ��ׂ��|���邱�ƂɂȂ邩��ł��B�K�{�A�~�m�_�Ɋւ��Ă̏ڍׂ́A�u8-14�@�K�{�A�~�m�_�������ꂽ�H���v�����Q�Ɖ������E�E
�@
���H�i�̉h�{�����̓l�b�g��ł����ׂ邱�Ƃ��o���܂�
�@
�i��ȐH�i�́A�K�{�A�~�m�_�̗ʂ�������܂��E������Ȃ����������̂ł����E�E�j
�����������牖���A�`�����ׂ��܂��E
�@
���{�ł́u�t���a�̐H�i�����\�v�ƌ����̂����X�ɂ���܂����A�A�}�]���Ȃǂł���ɂ͂���܂��B
��1���̉h�{�̍��v��\�ɂ���ɂ́A�G�N�Z�����g����l�̓G�N�Z���\�v�Z�𗘗p����̂��悢�Ǝv���܂��B�G�N�Z���͎Ⴂ�l�Ȃ�Α����̕����g����Ǝv���܂����A����҂ł��A�p�\�R�����g������ł�����A�����̃G�N�Z�����发���ēƊw����Δ�r�I�ȒP�ɐH�����j���[�i�h�{�\�j���쐬�ł���Ǝv���܂��B
�@
�܂���1���̉h�{�f�𐧌����ɉ�������ɂ͂ǂ������炢�����A�Ƃ������Ƃł����A1���̐����l������ɐH�ׂ�2�H�������A��������3�H�ڂɐH�ׂ��鉖���ʁA����ς��ʂ��v�Z�ł��܂��B��v�Z�ł������ł����A�G�N�Z���Ȃ�Ύ���͂ł����v�Z�͎����ł���Ă���܂��B
�@
���O�H���悭���p����l�́A��v�Z�A�����̓G�N�Z���v�Z�̂ǂ���ł��A�\�����ۂɁA1���̐H�����ӂł͂Ȃ��A���H�A�[�H�A�������H��3�H�̍��v��������1�����Ƃ��ĉh�{�v�Z����ƁA���H���[�H���O�H�ɂȂ��Ă��܂����ꍇ�ł��A�����ł�����x�������ł��A1��3�H���v�̐��l�������₷���Ȃ�܂��B
�@�@�@�@�@
�܂��A1���̐H���ʂ̒����ӂŊǗ�����ꍇ�ł́A������2�H�̔�d��傫�����A�[�H�����Ȃ߂ɂ��Ă����ƁA�ˑR�[�т��O�H�ɂȂ����ꍇ�ł��Ή������₷���ł��E�E���̏ꍇ�͊O�H�ʼn�b�͑�R���Ă��A�H���͖w�ǐH�ׂȂ��A�Ƃ����������t���܂��E�E���̐l���r�t�e�L�𒍕����Ă��A�����̓T���h�C�b�`�Ƃ��A���̓X�ōł������A����ς��������Ȃ��Ǝv���闿���𒍕����邱�Ƃł��E�E
�@
�@���̓J�����[�⋋�̂��߂ɁA�g�߂���`���ۃp����A��`�����т̊C�ۊ���������Ď����Ă������肵�܂��E�E���̍ہA��������͖̂�T���_�Ȃǂł��O�O���⋛��H�ׂ�Ƃ��͂S0g���x(������1/3�H)�Ŕ���u������������ł��E�E�ǂ����Ă��X�e�[�L��H�ׂȂ���Ȃ�Ȃ��d�v�ȐȂ̎��́A�o������߂ĐH�ׁA����120���̃X�e�[�L�������Ȃ�A����ς�����16g��(1���̖��̗ʁj�ł�����A�����̓��E���E�����i�����炵�A����ς����ʂ����܂��O�O
�@
���h�{�Ǘ����������K�v�ȏ��������������܂��B�����g���Ă�����̂́A
�P�D���i�͂���j�E�E2kg�p�i�ł���ŏ��\��0.1g�j�A500g�̌g�їp���i�O�H�̎��Ɏg���܂��j�A�X�ɁA�X�v�[���^�̔��Ȃǂ�����ƁA�����Ɍv�鎞�Ȃǂɕ֗��ł��B����1�����2�䂠�������������ƕ֗��ł��B2kg���d�����ł��A2kg����2���ׂď悹��A2�̔��̍��v���A��ɏ�������̏d���ɂȂ�܂��B���̏ꍇ�͂Skg�܂Ōv��܂��B
�@
�Q�D�v�ʃX�v�[��5cc�A10cc�A�ȂǁE�E����ݖ��Ȃǂ�ʂ�܂��B�Ȃ�ׂ��[���X�v�[�����g���₷���ł��B
�R�D�u�t���a�̐H�i�����\�v�E�E�H�i�̉����₽��ς����̗ʂׂ�{�ł��B�i�l�b�g�ōw���ł��܂��B�j
�S�D�����v�i�~�l�������̑��������ł͋������Ƃ�����܂����A���������ł͔������܂���̂ŁA�����Ă��Ă��g�������Ƃ�����܂���E�E�j
5�DCKD�����̎Q�l��
�@
�@
�@
�@
�@
�@
2kg���E1kg���E500g���E�X�v�[���^���E�����v�E���x�v
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
 �@�T-�Q�@�@�e�h�{�f�̊Ǘ����@�@
�@�T-�Q�@�@�e�h�{�f�̊Ǘ����@�@
�@
�@5-2-1�@�����Ǘ��@�E�E
�i�Q�l�E�E�t���w��K�C�h���C���j
�@
�������ێ���E�E�t���w��ł́A1���ɐۂ��ėǂ������ʂ̓X�e�[�W�ɊW�Ȃ�1���R���ȏ�6�������ƋK�肳��Ă��܂��B�H�i�̉����ʂ͐��m�ɂ͕�����Ȃ����̂ł��B�����琳�m�ɏd����ʂ����Ƃ��Ă��A�H�i���̉����ܗL�ʂɂ̓o���c�L������܂����A����1�H�ł��O�H��s�̂̑y������Γr�[�ɐ��m�Ȍv�Z�͂ł��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂��B���S�ʂ���Œ�K�v�ʁu1��1.5g�v��2�{��3g���u�ێ悷�ׂ������ʂ̉����v�Ƃ��Ă���悤�ł����A���͍X�Ɉ��S���l���A���j���ł�1����3.6����ڕW�ɂ��Ă��܂��B
�@���ۂ�1���S���ȉ�(3g�ȏ�)��ڕW�ɂ��Ă܂����A���j���ł�3.6g���x�ɗ}���Ă��܂��B���R�́A�����S�̌��@�Ȃ̂ł����E�E�ǂ����Ă��\��O�̐��݂�H�ׂ���A�Ȃ̉��̗��������������܂ݐH�������肷�邩��ł��O�O
�@
���Ȃ��A�O�H����ꍇ�́A�Ȃ�ׂ������A�J�����[�\���̂���X�ɓ���܂��B�@�t�@�~���X���ƁA�����A�J�����[��\�����Ă��郌�X�g�����͔�r�I�����ł��B�J�����[�����ł�������A�����ɂ���Ă̓l�b�g��̏��A�d�����v�Z�ł��邩���m��܂���B
�Ⴆ�u�i�|���^���v�u�q���X�e�[�L�v�ȂLj�ʓI�ȃ��j���[�ł���A�J�����[����A�`���A�J���E���A�����A�����Ȃǂ�������x���ׂ��܂��B�j�܂������ς݂̐H�i���ۂ͉h�{�����\���̂��镨���܂��B�O�H�ɂ���A�X�[�p�[�̑y�ɂ���E�E�A�����������ޗ��̗ʂ��͂����肵�Ȃ���������ƁA1���̉h�{�R���g���[���͂��Ȃ�j�]���܂��E�E�����������Ƃ͏T��1�x�ʂɂ��Ă����ׂ����Ǝ����Ɍ����������Ă͂��܂��E�E�E
�@
���R���r�j�Ȃǂł́A�����łȂ��A�i�g���E���iNa�j�̗ʂ�������Ă��邱�Ƃ������ł��B����͉����ʂ�������Ȃ��悤�ɂ����킩�H�Ƌ^�肽���Ȃ�܂����ANa�͐H�������łȂ��A�Y�����ɂ��g���Ă���̂ŁA��萳�m�ȕ\���ƌ�����̂��낤�Ǝv���Ă��܂��B�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂͐H���Ƃ������́ANa�̑��ʂ��Ǝv������ł��E�E
�H�����Z������ɂ͓X���ŃX�}�z�v�Z����͖̂ʓ|�ł����ANa(mg)×2.54÷1000���H��������(g)�ł��B�T�Z�Ƃ��ẮANa��400mg�ʼn������Z��P���ł��B
�@
�i�Q�l�E�v�Z�̍����jNa�̌��q�ʂ͖�23�A���fCl��
��35.5�ŁANaCl�ł͖�58.5�@
NaCl/Na��58.5/23��2.54 �E�E�E
����āA�i�H���jNaCl�́ANa×2.54�ƂȂ�܂��B
Na�̗ʂ�mg�ŏ�����Ă��܂��̂ŁA2.54�{����1000�Ŋ���ΐH���̂����ƂȂ�܂��E�E
�Ⴆ�ANa394mg×2.54÷1000��1.0���i�H��1g�����j
�@
�������ߏ聨�����㏸�E�E�E�ێ扖���i�����i�g���E���FNaCl�j�̗ʂ�������ƁA�����Ɏ�荞�܂��i�g���E���iNa�j�Z�x���㏸���A�g�͍̂�������Na�Z�x�������悤�Ƃ��Č����ɐ�������荞�ތ��ʁA���t�ʂ������A�d�ʂ̑��������t��g�̒��ɑ���o�����߂Ɍ����͏オ���Ă��܂��܂��B�������錌���͐t���̓����ŔA���h���o���u�����́v�ׂ̍������i�ד����j���A���̍������͂ő������A�����̂����ł��Ă����ƍl�����Ă���悤�ł��B�����̂����ł���Ƃ������Ƃ́A�c���Ă��鎅���̂̕��ׂ����傷��Ƃ������ƂɂȂ�A�t�@�\�͏��X�ɂł͂���܂��������i�ቺ�j���Ă����Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
�@
�@�ቺ�̑��x�͒����I�A�ł͂Ȃ�2�����I�Ɂi��������`���悤�Ɂj�����Ă��Ă����܂��B���̗��R�́A�l�����������邽�߂ɐt������r�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��V�p���̗ʂ́A�����������������X�e�[�W�ɊW�Ȃ����ŁACKD�����ɔ��������̂̌����������N�قڈ�肾����ł��B(������Ƃ����āA�������ɒ[�ɐۂ�Ȃ��ł���ƁA�i�g���E���̌����Z�x����������(��i�g���E������)�A�z���A�ӎ���Q�Ȃǖ��ɂ�������ςȎ��ɂȂ鋰�ꂪ����ƌ����Ă��܂��E�E)
�R���`�U���̉�����ۂ�A�Ƃ������Ƃ͍ł���Ȏ��ƌ����Ă��܂��B
�@
�@
�i��������t�@�\�̈����j
��������₷���Ⴆ�Ƃ��āA�ǂ����������ł����E�E�E���ɐg�̂ɂƂ��ĕK�v��1���̘V�p���̏����ʂ�100g�A�c�������̐���50���ŁACKD�����ׂ̈ɖ��N10���������̂����ł���Ɖ��肵���ꍇ�E�E
�@��̗�ł͏��N�͎�����1��������̕��ׂ�2g���������̂��A1�N���2.5���ƂȂ�A�Q�N��ɂ�3.3���ɁA3�N��ɂ�5���A������4�N��ɂ�10���ƂȂ�A5�N��ɂ͂Ƃ��Ƃ����ׂ́��ɂȂ��Đt�@�\�͔j�]���Ă��܂��B�t���̈����Ƃ����̂͂��̗�Ɠ����ŁA1���ɏ������Ȃ���Ȃ�Ȃ��p�����̗ʂ͂قڈ��Ȃ̂ɁA������������鎅���̂̐������N�قڈ��ʏ������邽�߁A��̗�̂悤�ɉ����x�I�Ɉ������܂��B��̗�ł͖��N���ł��Ă��������̂̐���10���ƌŒ肵�܂������A�c�������̐�������A���ׂ����N�������Ă����̂ł�����A�����̖̂��N�̌������������x�I�ɑ�����͂��ł��B�]���Ď��ۂ́A5�N��ł͂Ȃ��A�����Ƒ����c�������̂�0�ɂȂ��Ă��܂����Ƃł��傤�E�E
�@
�����ۂ̎����̂̐��͌��S�҂ŕБ���100����,�����Ŗ�200������ƌ����Ă��܂��B�t�@�\�������ɂȂ��Ă��܂����l�ł��A�܂���100���̎����̂��撣���Ă��܂��B�������g��100���̎����̂����̂Ă��A��ɂ��܂��傤�B
���t�����ɂ���ƌ������Ƃ́A�����̂̎d���ʂ����炵�A�_�f��t�̑N�����\���t���ɓ͂��悤�ɂ���Ƃ������Ƃł͂Ȃ��ł��傤���E�E
�@
�i�b�����܂������E�E�j
���ߏ�ɐێ悳�ꂽ�����͔牺���b�ɂ��~�����邽�ߔ牺���b�̉����Z�x���㏸���܂��B�牺���b�������Z�x�𐳏�l�܂ʼn����邽�߂Ƀ����p�t���琅������荞�ނ��ƂɂȂ蕂��i�ނ��݁j���N���܂��B�ނ��݂̂���l�́A�܂����������i3g�ȏ�6g�����j���o���Ă��邩��24���Ԓ~�A�����Ŏ��ۂ̉����ێ�ʂׂ邱�Ƃ͗L�����Ǝv���܂��B
�@�@�@�@
�@�@���Q�S���~�A�����͉��L���Q�Ƃ�������
�@8-2�@���ۂ̉����A�`���ێ�ʂ�A�������玩���Œ��ׂ���@�@
�@
�i���͉����Ǘ��́A1��3.7��±0.3g�����s���Ă������ł����A1�����̔A�߂�~�A�����Ŏ��ۂɐH�ׂ������ێ�ʂ��v�Z����ƁA��̎����̌v�Z����0.6���ʑ����o�܂��E�j�ԐH�Ƃ��ʼn����݂��E�E�����H�ׂĂ��܂���ł��ˁE�E�����̈ӎu�Ƃ͗����ɁA�g�̂��~���Ă���̂Ŏd���Ȃ��ł��E�E�����͑�̂ɂ����āA�v����������ۂ��Ă��܂����Ƃ������Ǝv���܂��̂ŁA�ڕW�͏��Ȃ߂ɂ��������ǂ��Ǝv���܂��B
�@
�����̑�p�͐|�ʼn\�E�E�����ێ�ʂ���������ꍇ�A����ɐ|���g�������o���܂��B�l�̖��o��A�u������ς��v�Ɓu�����ς��v�͎������o�Ȃ̂ŁA�|�������邱�Ƃʼn��̖������߂���A��������邱�Ƃ��o���܂��B
�@

�����������炷�ɂ́A�H���̌��������K�v�ł��E�E�a�H�̏ꍇ�A���������̂��߂ɂ͊���̓`���H����߂Ȃ���Ȃ�Ȃ���������܂���B
�@
�u��̏��Ȃ��݂��`�A�����̑����Ђ����A�ϕ��A�ώρA���̊����v���̑��Ƃɂ������т̗F�ƌ����ׂ������̂�������������͂��ׂĎ~�߂��Ȃ������������������ǂ��Ǝv���܂��B
�@��`�����тƒ�`���p����g�ݍ��킹�ĐH�ׂ�ƃJ�����[���ۂ�₷���Ǝv���܂��B
�@

��ʂ̃p��50���i��130kcal�j�ɂ͉�����0.6g�ʓ����Ă܂��B����A��`���p���ł́A�Ⴆ�A�ł������̏��Ȃ��u��`���p���v�ł�50���i146kcal�j�ʼn����͕��ʃp����10����1�ŁA�͂�0.06���ł��B�W������h���ĐH�ׂ�Ή���0.1g���x�ŐH�ׂ�܂��B�@������т̕��͈�ʓI�ɂ͉����̗��������̂��~�����Ȃ�܂��B���̂��Ƃ���A�����𐧌�����ɂ͂��ѐH�����p���H�̕����ȒP�ƌ����܂��B���ѐH�̗ǂ��_�́A���т���ꍇ�ɂ́A�J�����[�̔����ȃR���g���[�������Ղ��_�ł��傤�E�E�p���H�̏ꍇ�ɂ̓J�����[�̔�������
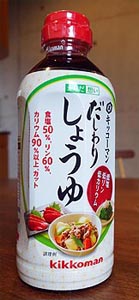
�u�����v���ł��邱�ƂɂȂ�ł��傤�E�E������1g ��4kcal�ł��B
�@
���т̂������̏ꍇ�ł��A�K�v�Ȃ̂͐��Ŋ����鉖�h���ł��̂ŁA�����͗����̊O�������ɂ��������ł��E�E�A�ݖ��Ƃ����Ƃ��͗����̓r���ō����邱�Ƃ������i�H�ނɐZ�݂���ʼn����������Ȃ�ׁj�A���~�߂Ă���ݖ���������Ƃ��A�����͒������ɂ͖���t�����A�H��ŏݖ�(�o������ݖ�)�������邩�A���M�ɓ���āA������ƕt���ĐH�ׂ�A�|�ƍ�����E�E�ƌ����̂������ɂ͗ǂ����@�Ǝv���܂��B
�@
�܂��X�v���[���̏ݖ��ŁA�P�v�b�V���O�D�P���Ƃ������̂����邻���ł��B�@�T���_�Ȃǂł́A�h���b�V���O������������ꍇ�́A��|�������U�肩����ƁA�������܂��ĉ�������������܂��B�h���b�V���O���g�킸�A��|�����ł���T���_�͐H�ׂ邱�Ƃ��o���܂��B
�������ƒ`�����Ȃ�ׂ��ۂ炸�ɃJ�����[�����𑝂₷�ɂ́F�����A���J�����[�[���[�A�I���[�u�I�C���A��`���āA��`���p���Ȃǂ�����܂��B
�@
�@
���������Ȃ�ׂ��ۂ炸�ɒ`������ۂ肽�����E�E���ʂ��сA䥂ł��T�c�}�C���A�������[�O���g�A�����Ȃǂ�H�ׂ�B�����͗ǎ��ȃ^���p�N���ŁA��ŋʎq�ɂ���Ɨ��������������Y��Ɏ��܂��B�ۑ��͏��������ėⓀ���A�𓀂͎��R�𓀂��A�ϕ��𓀂��ł��܂��B�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@

������������������ƕs�������Ƃ��E�E�P���ɉ���U�肩���܂��B��~�肪���O�����ɂȂ邩�A�v�Z���Ă����Ɨǂ��Ǝv���܂��B�Ⴆ��100��U���ďo�Ă������̏d�����T���Ȃ�Έ�~���0.05���ł��B�r�̌��̌�����������Ƃ��̓Z���e�[�v�łӂ����܂��B���C�͗v���ӂł��B�܂��A�s�̕i�ł�0.3g�A1g�A 2g���̏��ܓ���H��������܂��B�o������ݖ��̂R������Ȃǂ��֗��ł��B
�� �̔��X�́i5-3�u �t���a�H�̔������v�Q�Ɓj�@ �@�@�@
�@
�@5-2-2 �@�`���i����ς��j���Ǘ��@
�@
�i�Q�l�j�@JA�Ƃ�ő�����ÃZ���^�[
�@
���ێ悷�ׂ��`�����̗ʂ́H
�t���w��̃K�C�h���C���ł́A�u0.6�`0.8g×�W���̏d�v�ƂȂ��Ă��܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�W���̏d�ikg�j���g���i���j×�g���i���j×22
���̐��l�Ōv�Z����ƁE�E�E�@
�@�W���̏d�T�O�����̕��̏ꍇ
�@0.6×50��30g�A�@�@0.8×50��40g
�]���Đێ�`�����ʂ͒��Ԓl���Ƃ���35g±4g���x��ڕW�Ƃ��ă��j���[���l����Ɛێ�덷�������Ă����S���Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�B
�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q
�i�Q�l�j
�t���w��̒`�����ێ搧���ł͌��ʂ��o�Ȃ��A�ƈ٘_��������Տ��オ�A���Ȃ��炸���܂��B�h�{�w�̌��Ђł������i�́j�o�Y�ƚ��i���ł���Ă邭�Ɂj���֓��w�@��w�����́A�t���a�A�h�{�w�̐��ƂƂ��āA0.6�`0.8��/kgBW/day(�W���̏d1kg�������1���̐ێ��)�͖w�nj��ʂ��Ȃ��B����͕��ʐH�ł����Ē�`���H�Ƃ͌����Ȃ��B���ʂ邽�߂ɂ�0.3�`0.5g/kgBW/day�łȂ���Ȃ�Ȃ��A�Ƌ����咣���Ă��܂����B
�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q
�@(���P)�o�Y�����̎咣�@�K�C�h���C���ɑ���u��ȃp�u���b�N�R�����g�Ƃ���ɑ���v�̒��قǂŎ咣��W�J���Ă��܂��B
�@
����ς����̗ʂ�0.3�`0.5g/kgBW/day(1���A�̏d1kg������0.3����0.5g�̂���ς���)
���ƁA�W���̏d��50kg�̐l�́@1���P�Tg����Q�T��(�����l�͂Q�O���j�ƌ������ƂɂȂ�܂��B
�@
�@����͒���`���H�Ƃ������ׂ����̂ł����A���������̐g�̂Ŏ������Ă݂��Ƃ���A1���Q�O���̒���`���H(0.37g/kg/BW/day)��2�T�ԑ�����������Ŏ����������ǂ��܂����B�@�K�{�A�~�m�_�̃o�����X�͍l�����Ȃ��������߂ɁA���炭�����̕K�{�A�~�m�_�i���炭���W���A�o�����A���C�V���j�̕s���ɂ��h�{��Q�Ɋׂ����Ǝv���܂��B
�@�A�~�m�_�́A�P�ɋؓ��ɂ����g���镨�ł͂Ȃ��A�̂𐳏�ɕۂ��߂̐��X�̃z�������ɂ��Ȃ��Ċ�������̂�����Ă���Ă��܂��B
�@
�@���̌o������A��ʉƒ�ł̂���ς��������́u0.6g/kg�W���̏d�v����ʘ_�Ƃ��Ă͈��S�ȍŒ�l���Ǝv���܂��B�@�����u0.6g/kg�W���̏d�v�����̒�`���Ö@���������ۂ́A�H�i�̒`���ʂ���ł͂Ȃ��A�u�A�~�m�_�g���ɂ��^���p�N���v����K�{�A�~�m�_�̃o�����X�̎�ꂽ�H���ɂ���K�v������Ǝv���܂��B(����WHO�����ʂ�150����H�ׂ�����������̐g�̂Ŏ��s���ł��B�A�~�m�_�̃o�����X�����ō��ɗǂ���A����ς����͑��������ǂ��悤�Ȋ������ŋߎ����Ă��܂��E�E)
�@
�@���̌�A����ς����̌v�Z���@��ς��Ă݂܂����B�ڂ����́u8-14�@�K�{�A�~�m�_�������ꂽ�H�����n�߂�v�ŏ����Ă��܂����A�H�i�̊O���ɕ\������Ă��镁�ʂ̒`�����ʂł͂Ȃ��A���̐H�i�̒`�������\������K�{�A�~�m�_�̗ʂ��v�Z������@�ł��B�v�Z���ʂ́A���ʂ̂���ς��ʂƁA�A�~�m�_�g�������ɂ�������ς����v�Z�ł́A�`�����̐ێ摍�ʂ̓A�~�m�_�g���̕������ςŖ�1�T�����x���Ȃ��Ȃ�܂��B�i�������ׂ��͈͂ł́A�Œ�̓����S�̂O���A�ō��̓W���K�C���̂R�W���A�~�m�_�g���̌v�Z�̕�������ς����ʂ����Ȃ��Ȃ�܂��j
�@
�@�����A�ɂؓ����C��������A����������A�܂┯�̖т�z�����������ɂ͐H�ׂ��`���������ړI�ɍ�p�����ł͂Ȃ��A�H�ׂ��`�����͒����ۂɂ��`�������\������A�~�m�_�ɂ܂ŕ�������ď��߂Đg�̂ɋz������A�畆��ؓ��A�܂�тȂǂ̐g�̂̑g�D�̏C����e��̃z�����������o���܂��B�A�~�m�_�͑S����20��ނł��B���̂���11��ނ͐g�̂̒��œ����⎉���������܂�����J�����[������������ۂ��Ă���Ζ��͖����̂ł��傤���A�g�̂̒��ł͍��Ȃ��A�~�m�_��9��ނ����āA����͐H�ו�����ۂ�Ȃ���Ȃ�܂���B
�i����9��ނ��K�{�A�~�m�_�A�����͕s���A�~�m�_�ƌĂт܂��B�j
�@
�@���̕K�{�A�~�m�_�����ꂼ��̕K�v�ʂ��ߕs�������H�ׂ邱�Ƃ��d�v�Ȃ��Ƃł��B
����ς������Tg�H�ׂ�A�ƌ����A����H�ׂ悤���A���т�H�ׂ悤���A����ς����́u�ʁv�Ƃ����_�ł͓����ł����A���Ƃ����_�ł͑傫�ȈႢ������܂��B�ł��A��ʂ�CKD�̐H���w���ł́A����ς����̗ʂ������d�����āA���i�K�{�A�~�m�_�j�̕��͖���Ă��܂���E�E�E�͂��Ɂu����������ς������A�S����ς��ʂ̂U�T���ȏ�ۂ�܂��傤�v�E�E�Ƃ����\���ɗ��܂��Ă��܂��E�E�ł��A�g�̂��H������z��������̂͂���ς������������������ꂽ�A�~�m�_�Ȃ̂ł��B�g�̂��K�v�Ƃ��Ă���̂͑��̓I�ȁu����ς����v�ł͂Ȃ��A����ς�����̓��ōč������錳�ƂȂ�u�A�~�m�_�v�Ȃ̂ł��B
�@
�@���A��WHO(���E�ی��@��)�ɂ��A�g�̂��K�v�Ƃ��Ă���9��ނ̕K�{�A�~�m�_���ꂼ��̑̏d1kg������́u�����ێ�ʁv�����܂��Ă��܂��B1��ނł����Ȃ��K�{�A�~�m�_������ƁA����8��ނ̕K�{�A�~�m�_�܂ł��A���̏��Ȃ�1��ނ̕K�{�A�~�m�_���x��(�A�~�m�_�X�R�A�i��1)�������p�ł��Ȃ��Ȃ�܂��B����A9��ނ̕K�{�A�~�m�_��9��ނ��K��ʑ����ď��߂Ď���q����1�g�ƂȂ��Đg�̂����d�����ł���ƌ����܂��傤�E�E
�@
�@
��ł��K�v�ʂ�菭�Ȃ��ƁA����q����1�g�ɂȂ邱�Ƃ��ł����A����ς����������ł��܂���E�E�E�܂�����̕K�{�A�~�m�_���ˏo���đ����Ă��A�c�O�Ȃ������q�����肪���Ȃ����߁A1�g�ɂȂꂸ�{���̎d���͂ł��܂���B�P�Ɏ_�����āi�R���āj�g�̂����߂邱�Ƃ����ł��܂���B�������̏ꍇ�ɂ́A�L�Q�ȔR���J�X�i�A�����j�A�j���c��A�̑��œŐ��̒Ⴂ�A�f�ɕς��܂����A�b�j�c���҂ɂƂ��đ�R�̔A�f��t������r�o���邱�Ƃ͊ȒP�Ȃ��Ƃł͂���܂���E�E�t���ɕ��S���|���A�t���͒i�X���A�₪�Ă͌��t���ɔA�f���̓Ő���������R�c��A�A�ŏǂǂ��A���ɁA�f���C�ɋꂵ�ނ��ƂɂȂ�܂����A���͂����ɂ���Ίm���Ɏ��Ɏ���܂��B
�@
(�Q�l)�ŐV�����Ŗ��炩�ɂȂ����������^���p�N���̐ۂ��(����E�������w������)�@
�i�����N���Ȃ��Ƃ��̓R�s�y���ĉ������j
�@
�@�b�j�c���҂ɂƂ��ẮA����ς����̗ʂ��v�Z��������A�K�{�A�~�m�_�̗ʂ��v�Z����������ɂ��Ȃ��Ă���ƌ�����Ǝv���܂����A�K�{�A�~�m�_�̗ʂ��烁�j���[�����ƌ��������͑S�����y���Ă��܂���B�����Ă���H�i�ɂ��A�K�{�A�~�m�_�̗ʂ͏�����Ă��܂���B�Q�l�����قƂ�ǖ������A�����̗����̕K�{�A�~�m�_�̗ʂ��v�Z����ƌ������Ƃ͗e�Ղł͂���܂���E�E�E�ł��A�����ɂ���Ă͂�����x�͂ł��܂��B
�@
���ɒ��Ⴝ��ς����̐H�����������Ă���l�́A����ς�����g��H�ׂ�Ƃ��ł͂Ȃ��A
�K�v�Ƃ����K�{�A�~�m�_�̗ʂ��o�����X�ǂ��������H�����e�ɂ��鎖����ɕK�v���Ǝv���܂��B
�@
����������͍��{����H���v����������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ����Ƃ��Ӗ����܂��B�����āA�K�{�A�~�m�_�̌v�Z�������ɂ��Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���E�E���ꂪ�ŏ��̂����͑�ςȍ�ƂȂ̂ł��E�E���̂Ƃ���ƒ�ŊȒP�Ɏg����\�t�g��������܂���̂ŁA�d���Ȃ��A���̓G�N�Z���̊�b������āA�G�N�Z���ŕ\����邱�Ƃɂ��܂����E�E�E
�@
�����j���̏ڍׂ�8-14 �E�E�K�{�A�~�m�_�������ꂽ�H�����n�߂��������������B
�@
�@
(�o�ߕP)WHO����������K�{�A�~�m�_�ێ�ʂ҂�����̐H�������߂�3������ʂɁA�C���v�����g���͉�(������)�ǂ��܂����E�E�C���v�����g�̎��s�̉��ǂł��B�����͒`���ێ�s���ɂ��h�{��Q���Ɛ������Ă��܂��E�E
�@
���̌��ʂ���AWHO�́u�����K�{�A�~�m�_�ێ�ʁv�҂������ł͉h�{�͏\���Ƃ͌������A�t�@�\���ア�l,�Ɖu�͂̎ア�l�A�����z���̈����l�Ȃǂ́A�����ʂ�葽���ۂ������������̂ł͂Ȃ����ƍl�@���A�����ʂ̂Q�O�����ɂ������ʁA����3.6g�A�`�����ێ�ʖ�27��(�A�~�m�_�g���ɂ�邽��ς����̗ʂł��B��ʂ̂���ς����Ɋ��Z����ƂP�T�����x�������A��31���ɂȂ�܂�)�A���j����̃J���E���ێ�ʂ�1600mg(�~�A�ɂ�錟������ł͎��ۂ̐ێ�ʂ�1300mg���x)�A�J�����[1660kcal�B�������`������56�����x�A�]���̒`�����ł̐ێ�ʂ͖�0.55g/kg/���ɂȂ�܂��B
�@
�����������ʂ̂Q�O�����̐H�������Ȃ肫����ƐH�ׂ��̂ɁA�t�@�\�̈����X�������P���Ȃ����߁A2020�N5�����琄���ʂ̂T�O�����̐H�����n�߂܂����B
�@
�@�T�O�����ɂ������R�́A���钘���ȉh�{�w�̖{��CKD�̐l�̂��߂́u��`���H�̊�H�v�Ƃ����̂��ڂ��Ă��āA���̃��j���́u�A�~�m�_�g���ɂ�邽��ς��ʁv���v�Z���G�N�Z���̕\�����܂�����A���W���̂ݐ����ʂ�50������, ����ȊO��8��͑S�ĂقڂP�O�O�����ɂȂ��Ă��܂����B���̂��Ƃ���A���j���̐v�𐄏��ʂ̂T�O����(�����ʂ�150���j�ƌ��߁A���j��������Č��ݎ������ł��B
�@
���̊�H�͏ڍׂ��Ȃ����ߐ���ɂȂ�܂����E�E
�������F��U���A
���A�~�m�_�g���ɂ�邽��ς��ʁF��37��
���̏d�Pkg������̃A�~�m�_�g���ɂ��`�����ʁF��0.67g/kg�i�]���̒`���ʂł�0.8g/kg�j�ɂȂ��Ă��܂����B
�@
���̃O���t�͂悭�m��ꂽ�H�i�̕K�{�A�~�m�_�̗ʂł��B�\�̏c���̓A�~�m�_�X�R�A�ł��B�A�~�m�_�X�R�A100�ȏ゠��A�h�{�I�ɗǂ��Ƃ���Ă��܂��B
��}�ŁA�E��}�̂悤��9��ނ��S�ăA�~�m�_��100�̐H�i�͗��z�I�Ȃ̂ł����A���̂悤�ȓV�R�̐H�i�͑��݂��܂���B������ł����z�ɋ߂��̂ł����A�����A���[�O���g�Ȃǂ̓����i�͐l�̕���قǂł͂Ȃ��ł����A�����ٓ��ނ̎q�̂��߂̓�������ł��傤���A�l�ɂƂ��Ă���r�I���z�I�ȕK�{�A�~�m�_�̔z���ɂȂ��Ă��܂��B�@
�@
����̐}�͕��ʂ̐H�p���ł����A�K�{�A�~�m�_�́u���W���v���K�v�ʂ̔�����������܂���A���т����W��������Ȃ��̂ł����A���X��[���ⓤ���A�����͋��̓��W���������̂ŁA������g�ݍ��킹�邱�ƂŁA�s����₦�܂����A���W���ȊO�͐ۂ�߂��ɂȂ邩���m��܂���E�E���m�ɂ͕K�{�A�~�m�_�̌��������Ȃ����蕪����Ȃ����Ƃł��B�@
�i8-14-1�@�K�{�A�~�m�_���烁�j�������A�Q�Ɖ������j�B
�@
(�Q�l)
���i������₷����`���H����E�L����wHP�E�E�E
�@
(�Q�l)�@�����E�A�~�m�_�̓K���ێ�ʁiJ-stage�j
�@
���t���w��̉h�{�K�C�h���C���E�E�E
�@
���K�C�h���C���ɑ��锽�_(�`�����ێ�ʁj�E�E�E
�@
�@
�@
���`�����ێ�ʂ����炷�ɂ��E�E��`���H�𗘗p����̂���Ԃł��B�p�b�N���育�т̏ꍇ�A�`���������ʂ̂��т̂P/�T�i5����1�j �Ƃ�1/10�͑�ϔ��������ł��B1/25��

�ł͔����������������܂����A��������1/35�ɂȂ�Ƃ�����Ɩ��C�Ȃ���������܂���B���A��`�����тɂ͐t���җp����H�i�̔F���擾���Ă��镨������܂��B�F�i���ƈ��S���Ƃ͎v���܂�����ނ͏��Ȃ��ł��B���ʗʂƂ��Ă͒`����1/25�������悤�Ɏv���܂��B
�F�i�́A�`����1/5�ł́uPLC�v,�@1/25��1/35�ł́u��߂��сv�Ȃǂ�����܂��B
�@
���i���P�j���т������ʂ̂��тɂ�1�H180g�Ŗ�4g�̒`����������܂��B3�H���ʂ��т�H�ׂ��1��12g�̒`������ۂ邱�ƂɂȂ�܂��B�����Ⴆ��1/20��`������180g�ɒu���ւ����1�H��0.2g�B1��3�H�H�ׂĂ����v��0.6g�ɗ}�����܂��B
�@�`�����̐ێ�ʂ�3�H�Ŗ�11.4g����܂��̂ŁA���������̓A�~�m�_�X�R�A��100�ȏ�̓������`����(�Ⴆ����60g�Œ`����11g�j��H�ׂ��A�`���������Ƃ��Ă͊y�ɂȂ�͂��ł��B�Ȃ���`�����тƌ����݂��`�ƌ����Ђ����ł͒`�����s���ɂȂ�\��������܂��B
�@
�@��ʘ_�Ƃ��Ă͒`�����͐t���w����߂��u�̏d1����������0.6���ȏ�v�Ƃ����̂�����ł����A�A�����`�������S�̐H�����ƕK�{�A�~�m�_�̈ꕔ�i���C�V���A���W���A�o�����Ȃǁj���s������\��������܂��B�����h���ɂ͏��Ȃ��Ƃ��ێ�`������60���ȏ�����`�����ɂ��邱�ƂŕK�{�A�~�m�_���s�����邱�Ƃ͖h����Ǝv���܂��B
�@
�@�����������`��������肷����ƁA�A�~�m�_�̃o�����X������A�g�̂̕�C�ɗ��p�ł��Ȃ��������o�Ă��Ă��ꂪ�J�����[�Ƃ��ė��p�����ƁA�ŏI�i�K�Őt���Ɉ����A�f�ɂȂ��Ă��܂��܂��B
�@
�@
�u�A�~�m�_�X�R�A�v�Ƃ͏��Wikipedia�ɏ�����Ă���Ƃ���ł����A���ݍӂ��Č����ƁA����H�i�Ɋ܂܂��`�����̐����ł���u���f�iN�j�P���v����9��ނ̕K�{�A�~�m�_���AWHO�����߂���Ɣ�ׂĉ����ʊ܂܂�Ă��邩�H�ƌ����w�W�ł��B9��ޑS������ȏ゠��A�~�m�_�X�R�A�͂P�O�O�Ƃ��܂��B
�@9��ނ̕K�{�A�~�m�_�̓��A�����Ƃ����̏��Ȃ��K�{�A�~�m�_�̃X�R�A���A���̐H�i�̑�1�A�~�m�_�X�R�A�ɂȂ�܂��B�Ⴆ�Γ��◑������i�͖w�NJ�ȏ�܂܂�Ă���̂ŃA�~�m�_�X�R�A�͂P�O�O�ȏ�ł��B�܂����ĂȂǂ̓��W�������Ȃ��ׁA�A�~�m�_�X�R�A���Ⴂ�ł����A���W���̖L�x�ȓ��A���A���A�哤���ꏏ�ɐH�ׂ邱�ƂŃA�~�m�_�X�R�A��҉�ł��܂��B
�@
�@�A�~�m�_�X�R�A�P�O�O�̐H�i������H�ׂ�������Ƃ����ƁA����ł͖��ʕ�����ۂ��r�^�~���ނ��s�����邩������܂���A������x�͖��ʕ��Ȃǂ������ꂽ�A����ނ̐H����H�ׂ�悤�ɂ��Ȃ��Ɗ����ǂȂǁA�g�̂����킷���ƂɂȂ邩���m��܂���E�E
�@
����ς����Ɋւ��ẮA���m�������Ȃ�A�����H�ׂ�S�Ă̐H�i�̕K�{�A�~�m�_�ʂׂāA9��̕K�{�A�~�m�_�̂��ꂼ��̍��v�������ێ�ʂ��\���������悤�Ƀ��j���������邱�Ƃ��A���B�f�l���ł���`�����ɑ��鋆�ɂ̗��z���j���ƌ�����Ǝv���܂��B(�����I�ɂ́A�H�i�Ɋ܂܂��^���p�N���ɂ̓o���c�L������܂����A�l�̏����z���̑P�������̍�������܂��̂ŁA���͐H�i�̊ܗL�ʂ̃o���c�L�A������̌덷�Ɛl�̏��������l�����AWHO�����ʂ̂T�O�����Ń��j���[������Ă��܂�)
�@
���K�{�A�~�m�_�ɂ�郁�j�����Ɋւ��Ắu8-14�|1�E�E�K�{�A�~�m�_���烁�j�������v�ŏڂ������グ�Ă��܂��B
�@
�H���Ö@���ɂ߂����l�́A��x�͎����̐H���̕K�{�A�~�m�_�ێ�ʂׂĂ݂邱�Ƃ��L���Ȃ��Ƃ��Ǝv���܂��B���̌o���ł́A��ʂɒ�`���H�i�𗘗p���Ă���l�̃��j���ŕs�����₷���K�{�A�~�m�_�̓o�����A���C�V���C���W���Ǝv���܂����A�w�ǑS�Ă̐H�i�̓t�F�j���A���j�����ɒ[�ɑ�R�܂܂�Ă��āA�K�{�A�~�m�_�̐ێ�K�v�ʂɑ��A�ߕs���Ȃ��҂�����ɐێ悷�邱�Ƃ͕s�\�ł��B
�@
���B���ł��邱�Ƃ́A1��ނ̕K�{�A�~�m�_���s�����邱�ƂȂ��A�������A�ł��邾���t�F�j���A���j���Ȃǂ̎�肷����X���̂���K�{�A�~�m�_�͐ۂ�Ȃ��悤�ɁA�܂肷�����ł����z�ێ�ʂɋ߂Â���悤�ɍH�v���邱�ƂŁA����ς����Ƃ��Ă̗��p�������オ��Ǝv���܂��B
�@
���C�V���̓g�E�����R�V�A�R�[���t���[�N�ɑ����A�A�[�����h��s�X�^�`�I�Ȃǂ̃i�b�c�ނ����C�V���A�o�������L�x�ł��B������g�ݍ��킹��ƁA��菭�Ȃ��`�����ێ�ʂŁA�K�v�ȕK�{�A�~�m�_���ۂ��\���������ł��B
�ێ悵���H�ו��Ɋ܂܂�邽��ς��������ŕ�������A�K�{�A�~�m�_�ƂȂ��Đg�̂ɋz������A����炪�ɗ͖��ʂȂ��l�̂��\������`�����Ƃ��ė��p����A�V�p��������A�t���̕��S�͌��锤�ł��B
�@
�܂��A�K�{�A�~�m�_�̗ʂ����߂���@��2������A
�@��͏]���̕��@�ŁA�H�i������H�i100g���̒`�����̗ʂׁA���̗ʂ���K�{�A�~�m�_�ʂׂ�Ƃ��������ł��B���̕��@�Ŗw�ǂ̐H�i�̕K�{�A�~�m�_�ʂ����ׂ��܂��B
�@
�A������͍X�Ɍ����Ɍv�Z���邽�߂ɁA�H�i�̒��̂���ς������\�����钂�f�ʂ���
�K�{�A�~�m�_�̗ʂ����߂���@�ŁA�u�A�~�m�_�g���ɂ�邽��ς����ʁv�ƋL����Ă��܂��B
�@
�@���̕��@�͍ŋߎ��p����������ŁA�ꕔ�̑�\�I�ȐH�i�����u�A�~�m�_�g���ɂ�邽��ς����ʁv�͕������Ă��܂���̂ŁA����ł́A�]�����@�ƐV���@�̃~�b�N�X�Ƃ����`�Ōv�Z���Ă����Ȃ���Ȃ�܂���B�V���������u�A�~�m�_�g���ɂ�邽��ς����ʁv�ł́A�`�������ɒ��f�������Ȃ���A�K�{�A�~�m�_�ł͂Ȃ��J�t�F�C���Ƃ��A����̖������������O����A��萳�m�Ȍv�Z���o����Ƃ���Ă��܂��B
�@
���ĂȂǂ̎G���͉h�{�����������N�Ȑl�ɂ͌��N�H�ƂȂ�܂����A�i�s����CKD���҂ɂ̓J���E���iK�j,�����iP�j�Ȃǂ������ׁA�D�܂����Ȃ������m��܂���B�i�A���A���Ăł�CKD�ł����Ă��G���A�V���A���͐�������Ă��܂��j
�@
���`�����������������₵�����Ƃ��i��`���Ă�H�ׂĒ`���s���ɂȂ����Ƃ��j�E�E�E��ԊȒP�ȕ��@�͓����i�ł����A�u���v���X�N�����u���ɂ����肵�ė����ɍ����邱�Ƃ��ȒP�ł��B���̓A�~�m�_�X�R�A��100�ł�����A�����Ƃ����z�I�Ȓ`�����̈�ƍl�����܂��B�����Ƃ��i�b�c�Ȃǂ̎�q�ނȂǂ��A�q���������Ă�̂ɕK�v�ȉh�{�f���S�ē����Ă���̂ł�����A��{�I�Ɋ��S�h�{�H�ŁA�A�~�m�_�X�R�A�[���w�ǂ�100�ł��B
�@
�����f�B�J�����C�X�E�E�E���{��p�̐��ċ@�𗘗p���āA�`���ʂ������A�u�Ă̕\�ʕ����v�����Ƃ�`�����ʂ��������炵���Ă�����܂��B���f�B�J���ĂƂ������Ŕ����Ă܂����A���т��̂��͖̂ݕĂ̂悤�ȐH���ɂȂ蕁�ʂ̕Ă��������������Ăł��B�����A���ʂ̕Ă��͒�`���ɂȂ��Ă���͂��ł����A�l�̂֎��ۂɋz�������`�����ʂ��͂�����Ƃ͕�����Ȃ��̂ŁA���f�B�J���Ă��g���Ƃ���24���Ԓ~�A�����ĔA���̔A�f���f������ۂɐg�̂��z�������`�����ʂ��v�Z����K�v������Ǝv���܂��B
�@
�i�����v�Z�T�C�g�E�E���̃T�C�g�Ŏ��ۂ̒`�����ێ�ʂ��H�����j���̐��l�ƈ�v���邩�m�F�ł��܂��B
���̃T�C�g�ŏo�Ă��鐔�l�́A�W���I�ȑ̕\�ʐρi1.73�u�j�ɕ����Ă��Ȃ������l�ɂȂ�܂��B�@
�@
�@

 �@5-2-3�@�J���E�E���Ǘ��@
�@5-2-3�@�J���E�E���Ǘ��@
�@
���d�x�̂b�j�c�̕����J���E���iK�j��ۂ�߂�����S�s�S�Ȃǂǂ���댯��������Ƃ���Ă��܂����A���Ȃ�����Ƌؗ͒ቺ�A�E�͊��Ȃǂ������Ƃ���Ă��܂��B�e�j�X�I�肪�������Ɂu�o�i�i�v��u�i�c�����V�v��H�ׂĂ���̂��e���r�Ō������܂����A����͋ؗ͒ቺ��A�ؓ����z���\�h�̂��߂̃J���E���⋋�ƌ����Ă��܂��B
�@
�@���J���E���͖�E�ʕ��A���Ȃǂɑ����ł��B�J���E���͐H���iNaCl�j�Ɠ��������ɗn���₷���̂Ŗ�͑@�ۂ�f��������ɂȂ�ׂ��ׂ���A�\�ʐς�傫�����Đ���2���Ԉȏ����ƃJ���E���͂Q�O�����x�n���o��ƌ����Ă��܂��B2���Ԃ��҂ĂȂ��̂ŁA���͐��̒��ŝ���ŃJ���E����ǂ��o���Ă܂��E�E�ł��A�X�e�[�W��G3A���̐l�Ȃ�C�ɂ��Ȃ��ėǂ��Ƃ����Ă��܂��B
�@
���̓��j���ł́A���肬���1900mg�ȉ��ɂ��Ă��܂����A�ő���卪�A�W���K�C���Ȃǂ͍Œ�2��ς��ڂ����ăJ���E����ǂ��o���Ă��܂��̂ŁA���1500�Amg�ȉ��Ɏ��܂��Ă��܂��B���t�����ŃJ���E���iK�j��H(���l������)���t������厡�ォ�牽�炩�̃A�h�o�C�X�����锤�ł��B�J���E����1500mg�ȉ��ƌ����Ă��A0�ł��ǂ����Ƃ����Ƃ����������Ƃ͂Ȃ��Ǝv���܂��B��͂���ʕ�����1��700�`1000mg�̓J���E����ۂ�ׂ��ł͂Ȃ��ł��傤���E�E�E
�@
�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@5-2-4�@�J�����[�Ǘ��@ �@
�@
���u�Ȃ�ׂ��W���̏d�v�i���P�j�ɂȂ�悤�A���j���[�̃J�����[�v�Z�𐳊m�ɂ���K�v������܂��B�`�����𐧌�����ƁA���ʂ̂��т͏\���ɂ͐H�ׂ��Ȃ��̂ŃJ�����[�s���ɂȂ�₷���ł��B�H�������܂����A�s�̂́u��`���āv��A�u��`���p���v����H�Ƃ��ĐH�ׂ�悤�ɂ���K�v������܂��B
�@
���J�����[���s�������Ƃ��E�E��`�����т��`���p���̗ʂ𑝂₹�����̂ł����A�����������Ȃ��ƒ�`�����т�p�����H�ׂɂ������̂ł��B�s������100Kcal���x�Ȃ�A�J�����[�⏕�H�i���֗��ł��B�J�����[�⏕�H�i�́A�`������J���E������Ȃǂ̊ܗL������ϒႭ����Ă��܂��B
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
���J�����[�⏕�H�i�Ƃ��ẮE�E
������(1g���SKcal )�E�E�`�����O�ł��A���ɗn���镲����1g�P�ʂ̔������������g���₷���ł��B�B
���[���[��(1��100�`160kcal)�E�E�Â݂�����H�ׂ₷���ł��B
����߂���ׂ��i1��100kcal)�E�E�͂��ɉ������t��������҂ł��H�ׂ₷�����݂ł��B������ς��������r�X�R�i1��41kcal)�E�E�̐H�ׂ����Ƃ�����悤�ȃr�X�P�b�g�ł�
�����̑��A��̂��َq�I�ȕ��ɂȂ�܂����A�i���͑�R����܂��B
�@
���J�����[���ɖڕW�ʂ�ɂ������Ƃ��́A�����ōŌ�̔�����������Ƃ҂����荇�킹�邱�Ƃ��o���܂��B�����͒����̏퉷�ۑ����o���A�����Ŗ������L�A�����ɂ��������܂��B������A�␅�ɂ������n����̂Ŏg���₷���ł��B
�@
�i���P�j�W���̏d�Ƃ��ABMI=22�̑̏d�ł��B�W���̏d�͓��v�I�ɁA�a�C�ɂ�����ɂ����A�ł����S���̒Ⴂ�̏d�A�Ɗw��F�߂����̂ł����A���e�I�ɂ͎�����Ȃ��l�����邩������܂���B�@�W���̏d�́A�N��ɊW�Ȃ��g�������Ō��܂�܂��B����ɂȂ��Ă���Ƌؓ��ʂ������Ă��܂��̂ŁA�W���̏d����낤�Ƃ���ƁA�������ؓ��ʕ��͎��b�ŃJ�o�[���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ�r�⋹�͑����ׂ��ĕ��������o���̌^�ɂȂ�₷���ł��B���Ƃ��Ă͕W���̏d�ɂ͍���҂͔N����l�������ׂ��Ǝv���Ă��܂����E�E�B
�@
���W���̏d(kg)��(�g��m)×(�g��m) × 22
BMI�l��18.5�ȏ�25�������u���ʑ̏d�v�A18.5�����́u��̏d�v�ɕ��ނ���Ă��܂��B
�@
�@
�@
�@5-2-5�@�����Ǘ��@
���t�@�\�̃X�e�[�W��G3�ɂȂ�����A�厖�ォ�烊���iP�j�̊Ǘ����n�߂܂��傤�ƌ����邩���m��܂���B��̐�����900mg�ȓ��ł��B���̓��[�O���g�������̂ŁA���肬��900mg�ȉ��Ń��j���[������Ă��܂��B�����R�H�ׂ邱�Ƃ������������₷���̂ŗv���ӂł��B�����͋��A���A���ނȂǒ`�����̑����H�i�ɑ����̂ł����A�H�ׂ�ʂƂ����_�ł́A�����i�������Ȃ�₷���̂ŋC�����������ǂ��Ǝv���܂��B
�@
�@
�������iP�j�𐧌����Ȃ���Ȃ�Ȃ����R�͉��L�̃T�C�g�ɏڂ�����������Ă��܂����A�v��ƁACKD���҂̓r�^�~��D�̑̓��ł̓����������Ȃ��Ă���̂ŁA�H������J���V���E���iCa�j���z�����邱�Ƃ�����Ȃ�A������Ca��H�ׂĂ����t����Ca�Z�x���������Ă��܂��ƌ����Ă��܂��B�܂������iP�j�̔A���ւ̔r�o�������Ȃ邽�߂ɁA���t����P�Z�x���㏸���A������Ca��P�Z�x�����邽�߂ɕ��b��B�z�������̗ʂ��������܂����A���̃z�������͐H������ł͂Ȃ������̍�����Ca����茌���Ɉړ������邽�ߍ������낭�Ȃ��Ă��܂��A������Ca��P�̔Z�x���オ�邽�߁A�ΊD���i�����_�J���V���E�����j���Č��Ǖǂɒ�������ƌ����Ă��܂��E�E������A���Ǖǂ̐ΊD���ł��B�{���{���ɂȂ���Ď��ł��ˁE�E�����h�����߂Ƀ����iP�j�̐������K�v�ƌ������ƂɂȂ�悤�ł��B
�@
 �@5-2-6�@�����Ǘ��@
�@5-2-6�@�����Ǘ��@
�������d���̖ʂ��玉���͋ɗ͎��Ȃ��悤�ɂ��܂��傤�ƌ�����t�����܂����A�S�J�����[�̂Q�O�����x�������Őۂ�Ɨǂ��A����Ɏ����̔����͓������ɂ��܂��傤�ƌ�����t�����܂��B�B�ǂ���̈�t�ɂ����ʂ��Ă���_�́A���̏ꍇ�ł͎��g���������Ԑg�����ǂ��ƌ������Ƃ��Ǝv���܂��B�����͂P���łXkcal������̂ŁA�J�����[�m�ۂ̂��߂�CKD���җp�u�Ⓚ�������v�Ȃǂł͑�R�g���Ă��܂��B�������A�������p����Ȃ�Ύ_���x�̒Ⴂ�ǎ��ȃI���[�u�I�C���Ȃǂ��g���������̂ł��B
�������d���ɏڂ����T�C�g�i�^���N���j�b�NHP�j
�@
�@
�@5-2-7 �@�����Ǘ��@


���J�����[�ɂȂ�h�{�f�́A�`�����A�����A�����ē��������ł��B�`�����𐧌����A�����d�����Ă����鎉�����قǂقǂɂ���ƁA�J�����[���Ƃ��Ďc��͓�����������܂���B�����̖L�x�ȕ��ʂ̂��т�p���͒`��������R����̂ŁA��`���̓���H�i���g�킴��܂���B �@����𗘗p����ƁA�H��R�O����������Ƃ������Z������܂����A�m����1���R�p�b�N�H�ׂ�ƁA3�p�b�N×��200×365����219,000�~/�N�ł��B���̑��ɂ��F�X�o��������ő�ςł��E�E���߂ď���ł͖����ɂ��ė~�����Ƃ���ł��E�E
�@
�@
�@5-2-8 �@�h�{�Ǘ��@�@
���e�h�{�f�E�ێ�ʂ̌�����@�E�E��{�I�ɂ͐t�����ォ�琔�l�̎w�肪����܂��B���̏ꍇ�́A�W���̏d��55kg�A�����V���ȉ��A�`����44g�ȉ��A�Ɛ̈�t����w�肳��܂������A�����Ƃ��Ă͉h�{�����̖ڕW�l�́A���݂͉���3.7���A�`����38g�i�A�~�m�_�g���ɂ��`�����ʂł�33g�j�A�J���E��1900mg�A����900mg�A����2500g�i����1400��+�H��1100���j�ɂ��Ă��܂��B�i��1�j
�@
��g�ȉ��A�Ƃ����܂��ƁA�^�ʖڂȊ��҂́A���Ȃ��قǗǂ��̂ł͂Ǝv�������ł��E�E���܂�Ɋ撣�肷���Đg�̂��������܂��B�@���Xg�ȉ��A�Ƃ����\���͌���������₷���Ǝv���܂��B��͂�͈͂������āA�����ȏ�A�����ȉ��ƁA��̓I�Ɏ����ė~�����Ǝv���܂��B�F�X���ׂĂ݂�ƁA�K���Ȕ͈͂́A�X�e�[�W�ɊW�Ȃ��A�W���̏d55kg�O��̐l�̏ꍇ�A����3���ȏ�6g����(�w��)�A�`������30g�ȏ�40g�ȉ��A�Ƃ��������肪�Ó����Ȃƌl�I�ɂ͊����Ă��܂����A���͈̔͂Ŏ����ł���

�j��������Ă��܂��B
���ۖ��A�����Ȃǂ�3.7g�Ń��j���[������Ă��A�������݂Ɏ肪�o�Ă��܂��Ƃ��A�N�Ɉ�x�̐e���̏W�܂�ł́A���H�߂��Ă��̓��͂Wg�ʂɂȂ��Ă��܂����Ƃ�����܂��B��������������ƁA�e�Ɋp������ς��������������������A��ԐH�ׂ������́H�ƕ������A���킸�u���v�Ɠ����Ă��܂��܂��O�O
�i���P�j���̖ڕW�͉����A����ς����ʂ͊��ƒႢ���l�ɂȂ��Ă��܂����A24���Ԓ~�A�������瓾��ꂽ���ۂ̐ێ�ʂ́A��̂ɂ����ă��j���[��̐��l��荂���Ȃ��Ă��܂��B���ɉ����Ɋւ��ẮA�A���R�[�����������肷��Ɨ����̃^�K���ɂ�ŁA���]�v�ɐH�ׂ����ł��E�E���Ƃ��Ă͓��ɉ����͏�����߂̐ݒ�(�A���R���ȏ�)�Ń��j�������̂��ǂ��Ǝv���Ă܂��B�����ێ�͖ڕW��葝���Ă��܂����Ƃ͂����Ă��A���Ȃ��Ȃ邱�Ƃ͂܂������Ǝv������ł��B
�@�܂��A����ς����́A2020�N5�����݂͕K�{�A�~�m�_�̗ʂŃ��j���[���l���Ă��܂��B�v�Z���A�~�m�_�g���ɂ��`�����ʂł��܂��̂ŁA�K�{�A�~�m�_�ł̌v�Z���@�ł�32g�ɂȂ�܂��B���ʂ̂���ς����v�Z�Ɋ��Z����Ɩ�P�T�����ƂȂ�܂��̂Ŗ�36���ɂȂ�܂��B
�i���Q�Ɓ@8-14 �K�{�A�~�m�_�������ꂽ�H�����n�߂��j
�@
�@5-2-9 �h�{�v�Z�̌덷�@
�H�i���̂��̂ɂ��V�R�̕��ł�����蓖�R�`�����Ȃǂ̊ܗL�ʂɂ̓o���c�L������ł��傤���A�����@�ɂ���Ă��F�X�Ȍ덷���������܂��B��ʓI�ȉh�{�Ǘ��ł́A���Ȃ����Ă�±15���ʂ͂���悤�Ɏv���܂��B���ۂɎ����̃��j���ƌ����̐ێ�ʂ̈Ⴂ�́A24���Ԓ~�A�����ŁA�i�g���E���A�A�f���f�A�J���E���Ȃǂ����������Ă��炦�A���ۂɎ����̐g�̂��z������������`������J���E���̗ʂȂǂ��͂�����ƕ�����܂����A����ƂāA�����������̂R���O�ɐH�ׂ�����(���ɉ����Ȃǁj���t������̔r�o���x��Č��t���Ɏc�邽�߁A�A��������v�Z���ꂽ�����ێ�ʂ��A�������O���̐H���Őۂ��������ʂƂ������Ƃɂ͂Ȃ�܂���B�Ȃ̂ŁA���͌������O1�T�Ԃ͉h�{�����̂͂����肵�Ȃ����͐H�ׂȂ��悤�ɂ��Ă��܂��B
24���Ԓ~�A��������1���̉�����`�����̊T�Z�ێ�ʂ�m�邱�Ƃ͐H�����̂�������������Ӗ��ň��̉��l������Ǝv���܂��B
�@
���������ƁA���m���A�͈Ⴂ�܂��E�E�Ⴆ�A�ؓ��̗ʂ�ʂ�̂ɁA0.1���P�ʂ̃n�J�����g���u�����v�ɏd�����ʂ�܂��B�������ʂ������̓��̒`���ʂ��u���m�Ɂv�����������ǂ����͕ʖ��ŁA�̕��ʂ��ԈႦ�Ă�����A�ǂ�Ȃɐ����ɗʂ��Ă��Ӗ�������܂���B�Ⴆ�Α�^��E�̏ꍇ�A���[�X�ԓ���100���Œ`������22.7���ł����A�����[�X�ԓ���100����19.7���Ƃ���Ă��܂��̂ŁA���҂͓�����^��ؐԓ��ł�11�����`���ʂ��Ⴂ�܂��E�E�����琸���ɗʂ��Ă��A���ʂ����m�ɕ�����Ȃ���Β`���ʂ����m�ɕ����������Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ��̂ł��E�E��ؗނł������悤�Ȃ��Ƃ������A�Ⴆ�Ό��ؒő��͍̎���̑O�����̓V��ɂ��A�ܐ������傫���ς�邱�Ƃł��傤�E�E�ܐ������ς��A�P�ʏd�ʓ�����̒`�����ʂ��ς���Ă��܂��܂��E�E
�@����0.1�����C�ɂ��鎞���āA������ȂǍ��`���ŏ��ʐH�ׂ�H�ނƂ��A�Ă��C�ۂ̗l�Ȍy���č��`���ȕ���ʂ鎞�ł��ˁE�E��؉ʕ��Ȃǐ����덷���傫���A��`���ȐH�ނ�0.1���̐��x�ŗʂ邱�Ƃ̓i���Z���X�ȋC�����܂��E�E�B�����ɗʂ낤�Ƃ���O�ɁA���̌v�ʂ��ʂ����Đ��m�ƌ�����̂��ǂ������l���������̂ł��E�E
�@
�@
�@5-2-10�@�T���͂��J���H�H�@
�H����������邱�Ƃ͑�ςł��E�E�Y�����ł͂Ȃ��̂ł�����A���܂ɂ͂�����Ƃ͔�����������H�ׂ����Ȃ�܂��E�E
�@�ŋ߂͂��J���H�Ƃ����l�����L�����Ă��܂����E�E���܂ɂ͑�������������������������E�E�T��1�H�ʂ͂�����Ƌ֒f�̐H�ו���H�ׂāE�E�A�����Č��Ɉ�H�ʂ͐H�ׂ����������ʐH��H�ׂāE�E�A�ł��A��������͂܂����i�ȃ��j���[�ʂ�E�E�Ƃ����l�����ł��E�E
�C�O�̈�w���ł��A���i�H���������o���Ă���l�́A���J���Ƃ��ďT���ɂ́A�H�ׂ����������ʐH��H�ׂĂ��ǂ����A����͐t�@�\�ɂƂ��Ėw�lje���͂Ȃ��A�ނ��뒷��������A�Ƃ����f�[�^�����邻���ł��B���{�ł��T�Ɉ�x���x�́A�D���Ȃ��̂�H�ׂ�A�Ƃ������Ƃ����������悤�ɂȂ��������ł��B
�@�t�@�\�����Ƃ��J���H�Őۂ肷���������iNa�j�̔r�o�ɂ�1�T�ԁ`10���قǂ̓����������邻���ł��B�Q4���Ԓ~�A�����Ă���l�́A�������O��1�T�ԁ`10���͂��J���H�͂��a���ł��i�܁j
�@
�����}�͎������������i�`����40���`120g�j��19�����Ԏ��{�����Ƃ��́A����ς����ێ�ʂƌ����A�f���f�A����Cr.�̊W�}�ł��B
�@
�@
�@
�@
�@
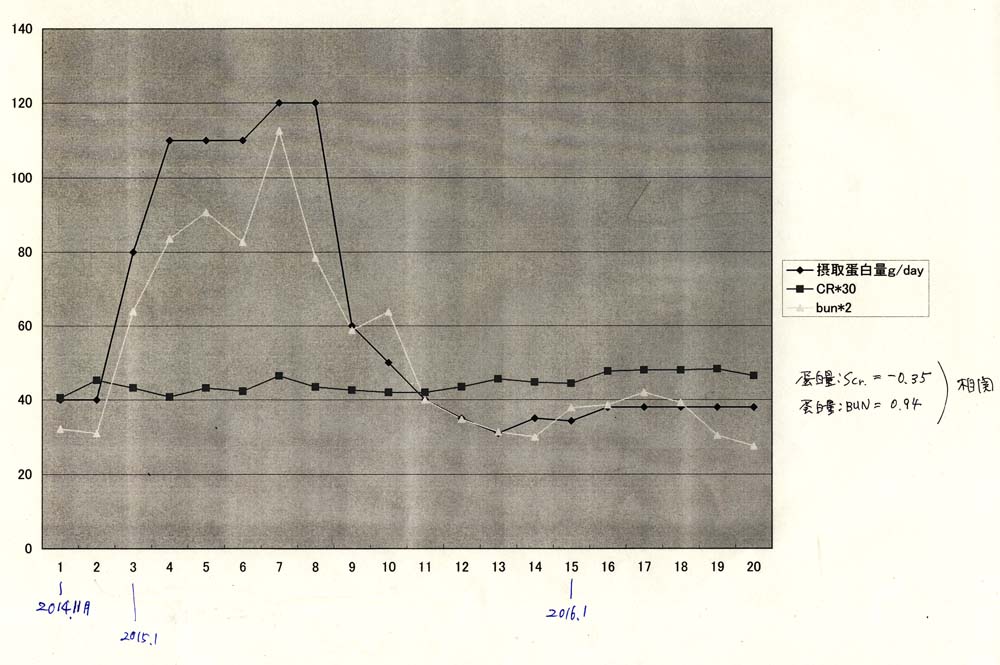
�@
���̃f�[�^����A�`�������R�ۂ�ƁA�A�f���f��+�X�S���̐����ւŒǏ]���܂����A����Cr.�́A-0.35�̋t���ցI�E�E�܂�A�`�������������R�H�ׂĂ������N���A�`�j���l�ɂ͑S���e�����Ȃ��E�E�ނ���A�`�������s������ƃN���A�`�j���l�͏㏸����I�Ƃ������ʂɂȂ�܂����B����͂����܂ŒZ���I�ƌ��������t���ł��B�`����120g/�������\�N���������炳�����ɃA�E�g�ł��傤�E�E�E
�@
�@�T-3�@�@�t���a�p�H�i�̔������@
�@���ꂾ��CKD���҂��������{�ŁA����قǎ��v������Ȃ���A�Ȃ��X�[�p�[��ʔ̓X�ɒ�`���H�i��


�u����Ȃ��̂ł��傤���H(����ł́A�̔������̒i�K�ŁA���p�҂ɐ������K�v�Ȃ̂ň��i�I�Ȉ����Ƃ����ׁA��ʏ����X�ɂ͒u���Ȃ������ƕ��������Ƃ�����܂��E�E)�@��`���ĂȂǂ̓���H�i�̐��X�̓l�b�g��ɑ�R����܂����A1���P�ʁi20�`30����j�ł��������Ă��Ȃ��Ƃ��낪�����A��`���Ăɋ����������Ă���ʂɔ����A�Ƃ����̂��S�O����l������Ǝv���܂��B�����ƐϋɓI�ɃX�[�p�[�Ƀo������Œu���Ă����A������1�g���ĐH�ׂĂ݂悤�E�E�Ƃ���������CKD���҂��o�Ă���̂ɂƎv���܂��B
�@
�l�b�g��ɂ͑�R�̔̔��X������܂��B�ǂ̓X�����i�͒艿�̔��ł��B�����͈��ȏ�(���1���~�ȏ�)�����Ɩ����ɂȂ�X�������悤�ł��B�A�}�]���ȂǑ����������A�Ƃ����X�͐H�i���i�ɑ������\�߉��Z����Ă���ꍇ������܂��̂ŗv���ӂł��B����ł���`�����т�1���������ɔ��������A�ƌ����l�̓A�}�]���Ȃǂł́u��`�����сv�̒P�i�̔�������悤�ł��E�E�A���������K�v�ł��B
�@���[�J�[�����̂����Ă���Ƃ��낪����܂��B���͔̂[�����Z���Ƃ������_������A�L�����y�[�������w���ň��������鎖������܂����A���Ђ̐H�i�͈����Ă��܂���B��ʂ̔̔��X�̏ꍇ�́A�ɂ̖����H�i�͎��ɂȂ邽�ߎ��Ԃ������邱�Ƃ�����܂����A�ǂ̃��[�J�[�̐H�i����x�ɔ�����Ƃ��������b�g������܂��B
�@���l�b�g�V���b�v�X�́A�Ⴆ���`���ģ�Ō�����������Ƒ�R�o�Ă��܂��B
�@
�@5-4�@�@�Ⓚ�������@
�@�ȑO�A���N�ԂقǂR�Ђ̗Ⓚ�������̂����b�ɂȂ������Ƃ�����܂����A���ɐH���̏������y�ł����B����ȕ֗��ȕ�����߂Ă��܂����̂́A��͂艽�������H�ב�����Ɩ��ɖO������������ł��B���ׂĂ̗Ⓚ�H�i����������ł͖����̂ł����E�E�E
�@
�@�T���ėⓀ�i�͉𓀁A���M����ƁA����Ȃ肵�܂����A�F�������Ȃ�܂��B�܂��J�����[���グ�邽�߂ɁA�����������Ȃ��R�����Ă���̂��C�ɂȂ�܂����B�h�{�����́A�Ⴆ�Ή����Ȃǂ����j���[���ɈႤ�ׁA1���̐ێ�ʂ����ɂ��邽�߂ɂ͌v�Z�Ɏ��Ԃ�������܂����A�Ⓚ�������͉������H�i�ɐZ�ݍ���ł��܂��̂ʼn����ʂ����\�����Đ������Ɏ��߂邱�Ƃ�����ɂȂ邱�Ƃ�����܂����B�B
�@
�@�Ⓚ�������͉𓀁A���M������Ɖ�������������܂`�����Ȃ�o�āA�Ō�Ƀp�b�N�̒�ɂ��Ȃ藭�܂�܂��B�`�ɂ͉����⎉�������Ȃ�܂܂�Ă��܂����A���[�J�[�Ɂu���̏`���S�����ނׂ����v��q�˂܂�����A�w����Ȃ̌덷�ł���x�Ə��Ă��܂��A�`�ɂ͉����������̂ɁA���Ȃ�K���ȂȁE�Ɗ����Ă��܂��E�E����ȗ������ō�鎖�ɂ��܂����B
�i���݂͒�`�����т̃p�b�N��1�H���̐H�ނ��l�ߗⓀ���Ă��܂��B�E�E�Ⓚ����̂ŗⓀ�������Ɠ����A�u����Ȃ�v���͔������Ȃ��̂ł����A���t���͒����̍Ō�ɂ��邽�߁A���������͂��₷���Ȃ�܂��B�Ⓚ�i���𓀂����ۂɏo�鐅���i�h���b�v�j�ɂ̓J���E�����n���łĂ���Ǝv���܂��̂ŁA�̂Ă邱�ƂŃJ���E�������������邱�Ƃ��ł��܂��E�E(�������̖��͗����Ă��܂��܂����E�E�E�j
�@
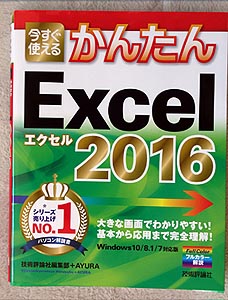 �@5-5�@�@�h�{�Ǘ��̓G�N�Z����
�@5-5�@�@�h�{�Ǘ��̓G�N�Z����
�@�m�[�g�Ɏ�v�Z��1���̃��j���[���l���Ă������ł����A���͔F�m�Ǘ\�h�����˂ăG�N�Z���𗘗p���Ă��܂��B����җp�̎Q�l�������X�ɂ���܂��̂ŁA�p�\�R�����������̕��ŃG�N�Z��(Microsoft office)���C���X�g�[������Ă�����͐���g����Ɨǂ��Ǝv���܂��B
�@
�w�Z���H��a�@�̐H���Ȃǂɗ��p�ł���h�{�m�p�́u�h�{�v�Z�\�t�g�v�������Ă��܂����A1�����̃��j���[�����O�Ɍ��߂�悤�ȑ傪����Ȓ����̏ꍇ�ɂ͗ǂ��Ǝv���܂����A�X�[�p�[�ŏ{�̐H�ނ�T���č��A�Ƃ����悤�ȃA�h���u�����ɂ͎g���ɂ����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
�@
�@�G�N�Z���Ń��j���[�����ꍇ�ɂ́A�ŏ��̂����͐H�i�̓o�^����ςƎv����ł��傤���A�܂���1����������3�H�̒�ԃ��j���[�����A�����H�ׂȂ���A�O����������A�����炵�����j���[���l���A�V�����g���H�ނ����̓s�x�o�^���Ă����A�i�X�ɓo�^�����H�ނ������Ă����A�֗��ɂȂ�܂��B
�@
�@�G�N�Z���Ȃ�A�ݒ莟��ŁA�H�i�̗ʂ���͂���Ίe�h�{�����������ŏo�Ă���悤�ɂ��o���܂����A�t�ɁA�Ⴆ�Ί�]����J�����[����͂���A��g�H�ׂ��炢�����������ŏo�����Ƃ��o���܂��B���v�Ȃǂ������ŊȒP�ɏo���܂��̂ŁA�G�N�Z���Ɋ����ɏ]�����j���[���͊y�ɂȂ�܂��B�G�N�Z���͐H���ȊO�Ɍ����Ǘ��⌌�t�������ʂ̊Ǘ��A�������̃f�[�^����e�v�f�Ԃ̑��ցi�Ⴆ�Ή����ێ�ʂƌ����̊W��A�`�����ێ�ʂƌ��t�����̔A�f���f���̑��ւȂǂׂ�̂��H���������l�����Ŗ��ɗ������m��܂���B�@�@�@�@
�@
�@5-6�@�@���s�ɍs�����̐H���Ǘ��@
���s����Ƃ������������Ǝv���܂��B���s���̐H���͗��̊y���݂ł���܂����A������`������ۂ肷���鋰�ꂪ����D�܂����Ȃ���ł����A�������s�Ȃ�A���Ȃ��Ƃ��z�e���ł̒��H�Ɨ[�H�́u��`���p�b�N���сv�������Ă����Ή��M���Ă��炦�܂��B�C�O���s�ł́A�u��`���ۃp���v�������Ă����A�����̓d�C�|�b�g�̒��ɓ���ĉ��M���邱�Ƃ͏o���܂��B
�@
���s���̐H�������{�ł̊O�H���̒��ӂƓ����ŁA�X�[�v���o�Ă��Ă��ق�̖������x�A����30g���x�i�E��̎ʐ^�Ȃ�A����1���ł��ˁE�E�j�E�E�r���b�t�F�Ȃ�Ύ����őI�ׂ܂����A�Z�b�g���j���[�̎��͐H�ׂėǂ��͓̂��⋛�ł͏o�Ă���������1/3�ł��ˁE�E�d���I�ɂ͂R�O�����x�܂łł��O�O�@��͑S���H�ׂĂ��ǂ��Ǝv���܂��B���s�̎�ނɂ���Ă͕������������ł����A�J�����[�͂�������ۂ�K�v������܂��B����͂Ƃ��������������ȕ����o�Ă�����A�o������߂ĐH�ׂ邵���Ȃ��ł��ˁE�E���ׂ̈ɗ��s�ɗ����̂ł�����E�E
�@
�@���H�ł̓`�[�Y��n���͉����ߏ�ɂȂ�܂��̂�1�������ł��B�E�E�C�O�ł͐��̓~�l�����E�H�[�^�[���A�z�e���̕����ň�x����������������ł��B�s�q���ȍ��ł͐����̐������߂Ȃ��Ƃ��������܂��E�E�����������ł́A�������Ő�����J�b�g�t���[�c�Ȃǂ��H�ׂȂ���������ł��B�ʕ��͔���ނ��Ă��Ȃ���Ԃ̕����Ɏ����A��A�����Ŕ���ނ��ĐH�ׂ�ׂ��ł��B����1��1.5L(�y�b�g�{�g��3�{)�ʂ����������ŒE���ɂȂ�Ȃ��悤�ɋC�����Ă��܂��B
�@
�@5-7�@�@��ԐH�̊��߁@
�@1��3�H�̒�ԐH���P����Ă����ƕ֗��ł��B���̒�ԐH�́A1���ɕK�v�Ƃ���h�{�f�ʂ�S�Ċ܂��z�I�Ȑ����H���j���[�łȂ���Ȃ�܂���B�����������j���[���Ƃ肠����1�ł�����ƕ֗��ł��B����������ԐH�p�ɂ܂Ƃߔ������o���܂����A1�H�����������ɂ��ėⓀ���Ă������Ƃ��ł��܂��B
�@
�@��ԐH�Ɏg���H�ނ́A�Ⓚ�ł�����́A�①�ɂł���r�I�����ۑ��ł��镨�������ł��ˁE�E��̓I�ɂ́A�����͗Ⓚ���o���܂����A��ł́A�ۑ����̗ǂ����̂́A�ʔK�A�W���K�C���A�T�c�}�C���A�l�Q�A�s�[�}���A�L���x�c�A���X��R����܂��B
�@
�ʕ��͏{�̂��̂ɂȂ�܂����A�����S�A���A�����A�݂���A�L�E�C�E�E�Ȃǂ���ԂɎg���₷���Ǝv���܂��B���Ɂu���v�̓A�~�m�_�I�ɂ͗D�G�ȉʕ��Ǝv���܂��B
�@
�����̒�ԐH�@
�����璩�H�A���H�A�[�H
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�i���j��L�̗����Ǝ��y�[�W�̌����\�Ƃ͑�̓����l���̐H���ł����A���S�ɂ͈�v���Ă��܂���B��̐H���͕K�{�A�~�m�_�����ʂ̂P�Q�O���ō���Ă��܂��B���̌�A�����h�{������Ȃ��C�����āA���݂͎��y�[�W�̐����ʂ̂P�T�O���ɑ��ʂ��ă��j���[������Ă��܂��B�����A�J�����[��1660kcal�œ����ł��̂ŁA�{�����[���I�ɂ͂قƂ�Ǖς��Ȃ��Ǝv���܂��B����̌��t�����Ŗ�肪�Ȃ�����̂܂܂ōs���܂����A��肪�o�Ă�����A�܂����P�����݂�ƌ������ƂɂȂ�܂��E�E�E�i����k�F���t�����̌��ʁABUN�i�A�f���f�j�͗ǂ������̂ŁA�b���͂P�T�O���𑱂��܂��j
�@
�@
���y�[�W�̐H���\�̓A�~�m�_�g���ɂ�郁�j���ł�
�@���ꂪ1���̕W����ԐH�ł��B���F���F��̃J�����[��9�F9�F7�ɂ��Ă��܂��B����͒����ł�������h�{��ۂ�A�[�H�͌y�߂ɂ������߂ł��B
�@
�O�H�ŐH�߂����ꍇ�́A�����̐H�����������܂��B�Ⴆ�Ή�����ۂ肷�����Ƃ��͏ݖ���A��T���_�̃h���b�V���O����߂āu��|�v�ɂ��܂��B�@
�@�`������ۂ肷�����Ƃ��́A���̗���[�O���g����߂܂��B���̌��ʃJ�����[�s���ɂȂ鎞�́A�s�����̗ʂɂ��A��`�����т��`���p���𑝂₷���A�J�����[�⏕�H�i�i�������j�ŕ₢�A���K�����킹�܂��B
�@
�@�ǂ����Ă��I�[�o�[���Ă��܂��ꍇ�ɂ́i�t��������A�N�ɉ�����܂��j�����̒��A��Ő��Z���܂��B���������v�Z�̓G�N�Z�����g��Ȃ��Ǝ��Ԃ�������܂��i���ꂩ�������邱�Ƃł��O�O�j�B
�@
�G�N�Z�����g��Ȃ����́A�F�X�ȊO�H��ŐH�ׂ��ꍇ��1���̃��j���[���O�H��̐���������Ă����ƕ֗����Ǝv���܂��B�O�H��ł͂Ȃ�ׂ����������𒍕�����ƌv�Z���y�ł��B
�@
���̏ꍇ�́A�O�y�[�W�̃��j�������Ē�����ƕ�����܂����A���H�̉��Ɂu���H+���H�v�̍��v�l���o��悤�ɂ��Ă��܂��B�����̍��v���O�H�p���j���̈�ԏ�Ɏ����ė��āA1���̕K�v�ʂ�������Ɨ[�H(�O�H)�ŐH�ׂ�ׂ��h�{�ʂ�������܂��B���͈̔͂ŊO�H�ƒ�ԈȊO�̃��j����K�v�Ȃ�������Ă����܂��B��ԃ��j���͏{�̐H�ނ����邽�߁A�p�ɂɕς��܂����A��Ԃ̒������v�������ŏo�Ă���̂ŁA�O�H���ԈȊO�̃��j����肪�y�ɂȂ�܂��B
�@
�O�H�������l�́A�h�{�̍��v�𒋁A��A������3�H��1�����Ƃ���ƁA�O�H�������Ă��A�����̒��H�ł�����x�������o����̂ŁA�L�^�\����鎞�ɐ��l���Y��ɑ����₷���ł��B
�@
�@CKD���҂ɕK�{�A�~�m�_�����Ƀ��j�����̎w�������Ă���{�݂ƌ����̂́A���炭���E���T���Ă��قƂ�ǂȂ��Ǝv���܂��i����Ƃ����NASA�ł��傤���O�O�j�B���\����Ă���A�a�@��CKD���җp�̃��j�������Ă��A����ł͂��Ȃ薳�ʂȕK�{�A�~�m�_���o�邾�낤�Ȃ��E�E�Ǝv�����j���������ł��E�E�B
�@
�@�K�{�A�~�m�_�������ꂽ���j���Ȃ�Čv�Z����ςŁA���߂��A�ƌ�����Ƃ͎v���܂����A�ł����̕��@���ł��t���̕��S�����Ȃ��]�܂������@���Ǝv���܂��B�����A�����A�f���f�̐��l�͖��炩�ɒႭ�Ȃ�܂��BCKD���҂��o����ł��L���Ȃ��Ǝ��ł͂Ȃ����Ǝv���Ă��܂��B�����K�{�A�~�m�_�x�[�X�̈Ղ����ƒ�p�\�t�g����肳������A�����̐l�����p�ł��A���͎҂̌����ɏ����͍v������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
�B
�@��̃��j���[�ł́A�����ێ�ʂ̂P�T�O���̃A�~�m�_��ۂ��Ă��܂����A�A�~�m�_�̉����炠�ӂ�o��ʁi����ς����Ƃ��ė��p�ł��Ȃ��A�~�m�_�ʁj�́A���ێ�ʂ�10%��, �����ێ�ʂ�150���ɑ��Ă�11����ɗ}���Ă��܂��B�܂����C�V���A���W���A�o������3�͐�����150���ɑ��ߕs��0�ɂȂ��Ă��܂��B�i����덷��±15���j
�@�i�NjL�B2020.7.18��萄���ʂ�140���ɕύX���Ă��܂��B140���̃��j����82�y�[�W������ɍڂ��Ă��܂��B�j
�@
�h�{�v�Z �E�E���u�t���a�̐H�i�����\�E���q�h�{��w�o�ŕ��v�������߂ł��B���X��A�}�]���ȂǂŔ����܂��B�h�{�m���g���u�H�i�����\�v�Ƃ����̂́A�f�l�ɂ͗��p���ɂ������ł��̂ŁA�P���ȐH�i�����\�𗘗p����̂�������₷���Ǝv���܂��B100g������̉h�{�������ڂ��Ă܂��B
�@
�@
���u�t���a�̐H�i�����\�v�E�E�E���X�ɒu���Ă���܂��B�l�b�g��ł������܂��B
�@
���K�{�A�~�m�_�̗ʂ��烁�j���[�����߂�ꍇ�́A
�@�D�u���{�H�i�����\2019�v����A���̐H�i100g������́u�A�~�m�_�g���ɂ�邽��ς����v�̗ʁi���j�ׁE�E
�@
�A�D�u���{�H�i�W�������\2015�N��(����)�A�~�m�_�����\�ҁv�́u�A�~�m�_�g���ɂ�邽��ς���1g������v�̕K�{�A�~�m�_�̗ʂɁA�@�̏d�����|����A�K�{�A�~�m�_�̗ʂ����߂��܂��B
�@
�ړI�́A�P���̐ێ�ʂ̍��v���u�����K�{�A�~�m�_�ʁv�i���L�̃T�C�g�Q�Ɓj�u�ȏ�v�ɂȂ�悤�ɐH�ו��̗ʂ����߂邱�ƂɂȂ�܂��B�u�ȏ�v�Ƃ����̂́A�l�l�̏����z�������s���Ȃ̂ŁA�����ʂ̉�������ێ悷�ׂ����͌��݂̏��A������ł��E�E�B�ێ�ʂƂ����̂͐g�̂��ێ�i�z���j����ʂł����āA�H�ׂ�ʂ��Ӗ�����̂ł͂Ȃ��Ǝv���܂��B
�@
���̏ꍇ�A�����ʂ�100���Ŏ����a�Ɋ������A120���ł����������N���A150���ɑ��₵�Ă���Ɩ�肪�����Ȃ��������ł��B150���ɂ������A�A�~�m�_�g���ɂ��`���ʂł�1����33.6g�ƂȂ�A0.6��/�̏d�A�ʏ�̂���ς������Z�ł�1��38.6g�ɂȂ�A0.7g/kg�̏d�ƂȂ��āA�t���w��̊���ɓ��鎖�ɂȂ�܂����B
�@
�@���̎��͈ꌩ���ʂ̂��Ƃ̂悤�Ɏv���܂����A�A�~�m�_�̉�������o�閳�ʂȃA�~�m�_�ʂ́A�ێ�ێ�ʂ�10���Ȃ̂ŁA���Ȃ菭�Ȃ��Ǝv���܂��B�A�~�m�_�̌v�Z�������ɓK���ɖ����A���A�����R�O���A����1�A�[��1�M�H�ׂ�E�E�ȂǂƁA�P�ɂ���ς����ʂ����Ń��j����������ꍇ�A���̎��Z�ł͖�30������������o�錋�ʂɂȂ��Ă��܂��B
�@
�@�����A�f���f�̒l�̕ω�������A�K�{�A�~�m�_�H�̌��ʂ͖��m���Ǝv���܂��E�E�E
�����A���̍�Ƃ͌��݂̏��A�\�t�g���Ȃ��̂ŁA���Ȃ莞�Ԃ�������܂��B(1���ŊȒP�ɒ��ׂ���悤�ɂ��ׂ��ł����A���̂Ƃ���Ö{(1991�N���s�̎l���j����������܂���B���X�A�u�A�~�m�_�g���ɂ�邽��ς����v�̗ʂ���K�{�A�~�m�_�̗ʂ��v�Z�ł���H�i�́A������{�I�ȐH�ނɌ��肳��܂��̂ŁA�]���́u�H�i100g������̕K�{�A�~�m�_�̗ʁv����v�Z�����邱�ƂɂȂ�P�[�X���o�Ă��܂��B
�@
�@�u�A�~�m�_�g���ɂ�邽��ς����ʁv�Ə]���́u�H�i100g������̒`�����ʁv�͂P�T�����x�����Ⴂ�܂���̂ŁA���҂�����������Ă��A�]���́u�K�{�A�~�m�_���l�����Ȃ�����ς����v�Z�v�Ɣ�ׂāA�����傫�Ȍ덷�Ƃ͌����Ȃ��Ǝv���܂��B
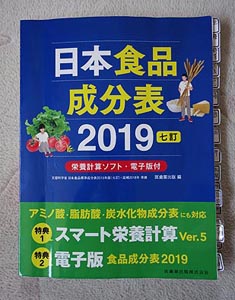
��8�|14�|1�ɂ��L��������܂�
�@
�@
(���{�H�i�����\2019)
�@�iURL���ύX����邱�Ƃ�����܂��̂ŁA�u���{�H�i�����\2019�v�ŃA�}�]�����������āA���̉摜��
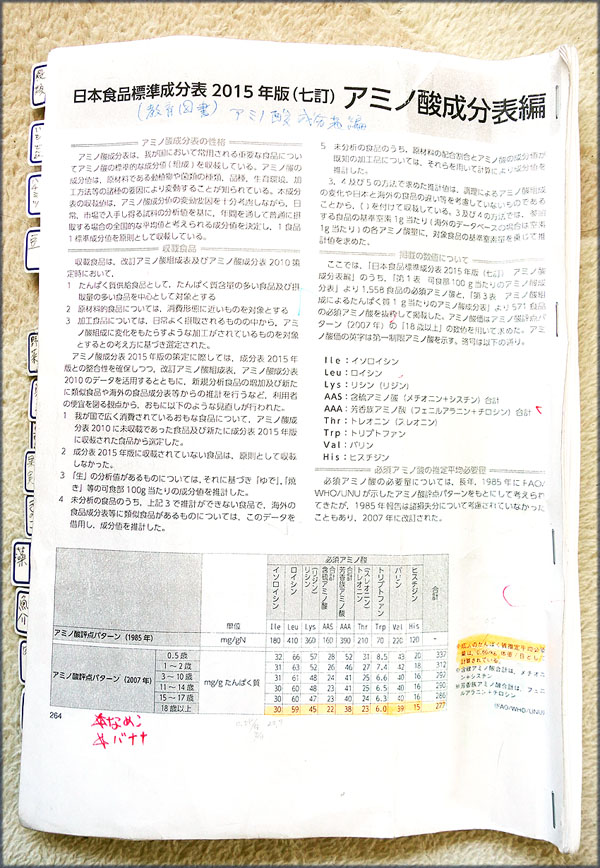
�{��T���Ă݂Ă��������B�j�@�X�ɁA�K�{�A�~�m�_�ʂׂ�ɂ́A
�u���{�H�i�W�������\2015�N�Łi�����j�A�~�m�_�����\�@����}���ҁv���K�v�ł��B
�����N���Ȃ��Ƃ��́A��LURL�����t�[��O�[�O���̃A�h���X���A�܂��͌������ɃR�s�y���Ă݂Ă��������B�o�Ă���Ǝv���܂��B
�@
�@
�@
�@
�U�@���������@��������̍H�v�@
�@�U-�P�@ �ƒ댌���̋L�^�@
�a�@�Ō����𑪂�ƁA����ꏊ�܂ŕ���������̑���ł�������,���ߍ������ő�\����

��悤�ɁA�{���̕��Î������Ƃ͌����Ȃ��ꍇ������܂��B�~���܂�K�v�ȏ�Ɉ��܂Ȃ��čςނ悤�A��t�ɓI�m�Ȕ��f�����Ă��炤���߂ɂ́A�ƒ�ő������������O1�������́u�����A�A�Q�O�����̕\�v���������Ɏ��Q����K�v������Ǝv���܂��B
�@
���̉ƒ댌������~���܂̗ʂ��������邱�ƂɂȂ�͂��ł��B�厡�オCKD�ۑ�������Ȃ�A1�����̉ƒ댌���̋L�^�����҂ɋ`���t����Ǝv���܂����A��ʉƒ��ł͂����܂ŗv�����Ȃ������m��܂���B���̏ꍇ�ł��A�����ŋL�^��t���āA��t�Ɍ��Ă��炤���Ƃ������߂��܂��B
�@
��������������̍H�v�E�E��ʂɏA�Q���͌���������������悤�ł��̂ŁA�ڊo�߂Ƌ��Ɍ����͕��펞�������������㏸���A���̌�������ƕ��펞�����܂ʼn�����ƌ����p�^�[������ʓI�ł͂Ȃ��ł��傤���E�E�t���w��ł͑����̌�������́u�N����A1���Ԉȓ��ɑ��肷��A�ƂȂ��Ă��܂��E�E��̓I�ɂ́u�N����A�g�C�����ς܂��A�֎q�ɍ����ĂQ�C�R���Â��ɂ�����ɂȂ�ׂ���r���ɂ����Č����𑪒肷��A�A���N��1���Ԉȓ��Ɂv�ł��B
�@
�@�����A�~�͐F�X�����ނ̂ŁA��r�ł̑���̂��߂ɒ�����ł���㒅��Z�[�^�[�A�����V���c�Ȃǂ�����グ��ƁA���̍�Ƃ̂��߂Ɍ������オ��܂����A�r����������邱�ƂɂȂ萳�����v��Ȃ������m��܂���B���������ł͎���v�̕����ǂ������m��܂���E�E�������A�S���Ɠ��������ő��邱�Ƃ�Y��Ȃ��ł��������B�S�����Ⴂ�ʒu�Ɏ���v������ƌ����͍����o�܂��B�S����荂�������グ��ƒႭ�o�܂��B
�@
�@�N����ɑ��鎞�Ԃ�����ƁA���茋�ʂ��o���c�L���傫���Ȃ�\��������܂��̂ŁA�����A�Ⴆ�A�N��30����i�t���w��w��́A�N��1���Ԉȓ��̒����l�j�ɑ���悤�ɂ���Δ�r�I�Ɉ��肵�����ʂ�������Ǝv���܂��B
�@
��̌����͒��ƈႢ�A�Ⴆ�A���Ă����e���r�̓��e�ɂ���Ă͌������オ�����肵�܂��E�E�܂��v�w�œ�������c�_���������肵�Ă��A�������オ�邩���m��܂���E�E�����ƈႢ�A��͌����𑪂钼�O�̍s����C�����̍��Ԃ�̉e���������₷���̂ŁA�C���������������Ă��瑪�肷�邱�Ƃ�����Ǝv���܂��E�E
�@�e���r�̉e���ŋ�����߂��ʎ��́A����v�������āA����ɂ��Ȃ��瑪��̂��ǂ���������܂���E�E�i�L�^����̂�Y��Ȃ��悤�Ɂj
�@
�@
�@�U-�Q�@�@�������̌}�����@�@�@
���t�����̃N���A�`�j���l�img/ml�j�������̓x�ɗǂ��Ȃ����舫���Ȃ����肵�Ĉ���J���邱�Ƃ�����܂��B����͌�������Ǝ����Ƃ��낪����悤�Ɏv���܂��B���ӑ��錌�����オ�����艺�������肵�܂����A����͑̒���\���Ƃ�������ł��傤���A�����̏�Ԃ�\���Ă���Ƃ�������Ǝv���܂��B�X�g���X���������肷��ƌ����͏オ��܂��B
�@
���ӂ̌���������Ȃ��̂ɂ���ɂ́A�C���������������Ă��鎞�ԂɁA�����v�̑O�ɍ����Ă�3���ԐÂ��ɂ��āA�������Ƃ����C�����Ō����𑪂�A�{���̐��l���o��͂��ł��B�܂�A���������Ō����𑪂��Γ����悤�Ȑ��l��������\���������Ǝv���܂��B
�@���l�ɖ����̌����������R���f�B�V�����Ō}������A�����Ɨ\�z�����͈͓��̐��l���o�Ă���̂ł͂Ǝv���܂��B���ׂ̈Ɏ��͎���2�̂��Ƃ����s���Ă��܂��B
�@
�P�D�����O�͒����Ԃ̉^���E�J�����T�����E�E�N���A�`�j���͋ؓ����g�������ɎY�o�����V�p���ł�����A��������2�C3���O�͒����Ԃ̌������^����J���͔�������Ȃ�Δ����������A�N���A�`�j���l�����肷��Ǝv���܂��B
�@
�Q�D�E���ɒ��ӂ����E�E�����N���A�`�j������͌��t���̃N���A�`�j���Z�x�img/dl�j�𑪂��Ă��܂��B�@�]���Đ����ێ�s���Őg�̂��E����ԂɂȂ��Ă�����A���t�͔Z�k����A�N���A�`�j���Z�x�͒ʏ��������Ȃ�͂��ł��B�t�ɏ\��������ۂ�A�E���Ō����������t�ʂ����A�����N���A�`�j���Z�x���{���̔Z�x�ɉ�����͂��ł��B
�@
�E���C���̎��Ɉ��ސ��́A�ق�̏����i0.1�`0.2���j�̉����������������̂ɓ���ނƌ����Ă��܂��B�@��ÓI�Ɉ��ތo���ߐ��t������܂����A���̉����Z�x�͖�O�D�R���ł��B���t�͂O�D�X���ł����炩�Ȃ蔖���ł��B�t�ɂO�D�X���̉����Ƃ����̂́A�@�������ɂ͗ǂ��ł����A���ʂɈ��ނƂ������Ƃ͑̂��t���Ȃ��ł��傤�B�E���C���̎��́A�����Z�x0.2���E�E�E500cc�y�b�g�{�g���łP���̉������Đ�����t������A�E���h�~�ɂ��傤�Ǘǂ������o���オ��܂��B�{�i�I�ȒE���̕⋋����0.3���ł��ˁE�E
�@
���l�ɁA�����������A���̔A�ʂ����Ȃ��A�g�̂��E���C�����ȂƂ����S�z������Ƃ��́A�����ɐ���������ꂽ500cc�̃y�b�g�{�g����1g�̉������A�傫�߂̃R�b�v��t���߂A�E���͂�����x�h����Ǝv���܂��B�ď�̌����̎��͌��ʁi�H�j������ł��傤�E�E�E
�@
�E���͐t���ɂƂ��ėǂ��Ȃ���Ԃł��̂ŁA�����������Ă��Ȃ��Ă�CKD�̐l�͒E����Ԃ����Ȃ����߂ɁA�����ێ�ʂƐ����⋋�ɂ͏\���C��z��ׂ��ł��傤�E�E
�@
�������̌}�����Ƃ��ẮA����g�̂����������Ō���������悤�ɁA�������O���̈��ÂƐ����⋋�ɋC�����ĒE�����N���Ȃ��悤�ɒ��ӂ����ė����̌����ɗՂނׂ��Ǝv���Ă��܂��B
�@
�@�l���K�v�Ƃ��鐅���ʂ́A�̏d1kg������50cc�炵���ł�(����͌�������ސ��̗ʂł͂���܂���B�g�̂̒��ō�������鐅��+�H���Ɋ܂܂�鐅��+�����̍��v�ł��B���̃T�C�g������������)
�@
���E���Ɛt�@�\�Ɋւ�����Ƃ̉��
�@
�@
�V�@�t���ɂƂ��ėǂ��Ȃ��ƌ����邱��
(�O�q�Ɛ������e�������d������L�q������܂��j
�@
�@7-1�@�@�������@
���������t����ɂ߂�Ƃ������Ƃ͈٘_���Ȃ��Ƃ���ł��傤�E�E�����������t���́u�����́v�ƌĂ��ю��̋ʂ̂悤�Ȗэ��ǂ��h�ߊ�ɉߑ�Ȉ��͂�����邱�ƂŎ����̂͑������܂��B���̌��ʁA�����̂̐������X�Ɏ��Ō������A�i�X�Ɍ��t���h�ߗʂ�����܂����A�g�̂͌������グ�邱�ƂŐ����ێ��ɕK�v���h�ߗʂ��m�ۂ��悤�Ƃ��܂��E�E
�@
�������オ�������ʁA�����͍̂X�ɔj��鑬�x�𑬂߂�E�E�ƌ������z���o���オ��A�h�ߊ�ł��鎅���͎̂��X�Ɣj����ł��Ă����܂��B�����̐������炳�Ȃ����߂ɂ͌����𐳏파���܂ʼn�����K�v������Ƃ������ƂɂȂ�܂��E�E�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
���Ⴆ�ΐt�@�\�����iCCr.50ml/min/1.73�u�j�ɂȂ����l�́A��200���������������̂���100�������@�\���Ă��Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ�܂��B���ɐt�@�\������10�N���Ɖ��肵���ꍇ�A���ς���1�N�ɖ�10���A1���ɖ�274�A��R����1�̑��x�Ŏ����͎̂��ł��Ă���E�E�Ƃ������ɂȂ�܂��B�g�̂Ɏc���ē����Ă���Ă��锼���̎����̂���������ɂ��������̂ł��E�E
�@
����74�˂ł����A�t���a����������65�˂̎��A������150/100�ʂ���܂����B���݂͍~���܁iARB+Ca�h�R�� �j�ƐH���Ö@�ɂ��ڕW�l��125/75�Ƃ��A115/70�`135/85���ɂȂ�悤Ca�h�R�܂̗ʂ��R���g���[�����Ă��܂��B�@������1�����v3�`4���ɉ������Ă��܂��B���ׂ̈ɂ͂ł��邾�����m�ȐH���̌v�Z���K�v�ł��E�E�i�H���ɂ��Ă͂T�D�H���̍H�v�Q�Ɓj
�@
�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@7-2�@�@�A�~�m�_�X�R�A�[���Ⴍ�A�o�����X�̈����`�����̐ێ�@
�l�̂̒`�������\�����Ă���20��ނ̃A�~�m�_�̒��ŁA�l�̑̓��Ő������鎖���o�����A�H�ו�����ۂ�Ȃ���Ȃ�Ȃ�9��ނ̃A�~�m�_���u�K�{�A�~�m�_�v�ƌ����܂��B�i����11��ނ̃A�~�m�_�́A�����⎉���Ƃ����`�����ł͂Ȃ�������̓��ō�鎖���o���邻���ł��j�̓��ō��Ȃ��u9��ނ̕K�{�A�~�m�_�v��1���ɐۂ�ׂ��e�X�̍Œ�ێ�ʂ����߂��Ă���9��ޑS�Ă��o�����X�ǂ����K�v������܂��B
�@
�@���ނł��K��ʂ�菭�Ȃ��K�{�A�~�m�_(�Ⴆ�u���W���̕s���v�Ȃ�)������ƁA���̕K�{�A�~�m�_����ԒႢ�u���W���v�̃��x����������ς����Ƃ��ė��p���鎖���o���܂���E�E�̓��ŃA�~�m�_���炽��ς����̍č���������ɂ́A9��ނ̕K�{�A�~�m�_���`�[���ɂȂ��ē����K�v������̂ł��ˁE�E�`�[�����g�߂Ȃ��A�܂藘�p�ł��Ȃ��K�{�A�~�m�_�́A�����⎉���Ɠ����悤�ɃJ�����[�i�M�ʁj�ƂȂ��ď����܂����A�����⎉���ƈ���āA�A�~�m�_�ɂ͒��f�iN�j�����邽�߁A���̔R���J�X�i�V�p���j�͍ŏI�I�ɔA�f�ɂȂ�܂����A����͐t������r�o���Ȃ���Ȃ�Ȃ����ߐt���ɕ��S���|���Ă��܂����ƂɂȂ�A�Ƃ������Ƃł��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�]���āA�A�f����������Ȃ��悤�ɁA�K�{�A�~�m�_�͉ߕs�������K�v�ʂ�ۂ�ׂ��Ȃ̂ł��B�����������I�ɂ́A���S�ɂ҂������Ƃ�����ɂ͂����܂���̂ŁA�H�����̂̉h�{�̃o���c�L��g�̂̏����z�����̒ቺ�ƌ������Ƃ��l������ׁA���Ȃ葽�߂ɐۂ��������ǂ��Ǝv���܂��B
�@
�@���͌��݁AWHO�����ʂ�150����ێ悵�Ă��܂��E�E�Ƃ����̂́A�ŏ��A�����ʂ�100�������s���Ă��܂������A�����a�Ȃǂ̊����ǂǂ������߁A�h�{�s���Ɣ��f�������ƂƁA�h�{�w�̖{�ɒ��ɂ������`�����R�O���̒�`���H�̃T���v���H�́u�A�~�m�_�g���ɂ��`���ʁv�ׂāA1���̃��j�����G�N�Z���̕\�ɂ��܂��ƁA�K�{�A�~�m�_9��ނ̂�����8��ނ͕K�{�A�~�m�_�̗ʂ������ʂ̂ق�200���ɂȂ��Ă����̂ł��B������O�������ă��W�������͂P�T�O���������̂ł��B���̂��Ƃ���A�����150���ł���Ă݂悤�Ǝv���A���s���Ă��܂��B
�@
�K�{�A�~�m�_��9��ނ̃X�R�A�������Ă���A�̓��Œ`�����ɍč�������܂����A�A�~�m�_�X�R�A��100�ȏ゠���Ă��A�P�O�O���z�������������ʂɂȂ�Ƃ͂����܂���B�ؓ��ɂ͂Ȃ�Ȃ��Ă��A�畆��܂⓪����A���X�̃z�������ɂȂ��đ̂̕�C�ɖ𗧂��Ă����ł��傤�E�E�ܘ_�����̂₻�̎��͂̑g�D���`�����ŏo���Ă���̂ł�����A�����̕�C�ɂ��𗧂��Ă���邱�Ƃł��傤�E�E
�@
�@�����̂͐V��������A���̐��������邱�Ƃ͂Ȃ��E�E�Ƃ����̂�����ł��E�E�������A�����̂̍זE�����̍זE�Ɠ������Đ�����Ă���͂��E�E�Ǝv���l�b�g�������|���܂�����A�Ȃ�ƁA�t���̍זE�͂��̂X�O����1�����ȓ��ɐV�����זE�Ɠ���ւ��A�Ƃ������Ƃł��I
�@
�@����Ȃ�A�V�����זE�Ɠ���ւ�邽�߁A�V�N�Ō��C�Ȓ`�����������Ղ�K�v�Ȃ̂ł͂Ȃ��ł��傤���E�E�ɒ[�Ȓ`�������������Ă��Ȃ���A�ߌ��ȉ^���ł�������E�E�ؓ��̍Đ��ɂ���A�~�m�_���g���A�t���ŁA����ւ��ׂ��V�����זE���A�~�m�_�s���ō��Ȃ��E�E�ƌ������Ƃ��N���Ȃ��ł��傤���H
�@�K�{�A�~�m�_�̃o�����X�����ɂ��܂��Ƃ�Ă��āA���ʂɂȂ�K�{�A�~�m�_�͏��Ȃ��A�������A�`�[�����g�߂Ē`���������ł���K�{�A�~�m�_�͑�R�ێ悷�ׂ��Ȃ̂ł͂Ȃ��ł��傤���E�E�E����͍��̎��̑傫�ȊS���ł��E�E
�@
���l�̂̍זE�X�V���x
�l�Ԃ̐g�͖̂���1���̍זE���V��������A�Â��זE�Ɠ���ւ���Ă���E�E�E�Ƃ������Ƃł��I
�@
�������A����ŁA�u�l�Ԃ̍זE�͐��N�ł��ׂē���ւ��̓E�\�H�v�ƌ����T�C�g������܂����E�E
���̒��ŁA�S���̍זE�Ȃǂ͍Đ����x���x���A���ʂ܂łɔ����ʂ����Đ����Ȃ��E�E��̔����͐��܂ꂽ�Ƃ��̂܂܂��A�ƌ����̂ł��E�E�E�E�܂�Đ����Ȃ��זE������A�ƌ����咣�ł��E�E���Ď����̂͂ǂ��Ȃ̂��ƒT���܂������A���̂Ƃ��댩����܂���E�E�E
�@
�@�����͕̂�����܂��A�ŏ��̃T�C�g�ł͐t���̍זE�͂��̖w�ǂ�1�����ȓ��ɓ���ւ��E�E�ƌ������Ƃł��̂ŁA�����M����Ȃ�A��͂�K�{�A�~�m�_�͂��Ȃ葽�߂ɐۂ��������ǂ��̂����E�E���Ȃ��Ƃ��A�s���͐�Ƀ_���ł��傤�E�E
�@
�@
�@7-3�@�@�ߘJ�@
�@�֎q�ɍ�������Ԃ��痧���オ��Ɛt���ւ̌����͂P�O���������A�����ƂQ�O����������Ɠǂ��Ƃ�����܂��B�^���ŋؓ����g���Ƌؓ��ւ̌����������ł��傤����A����͉������ʂ̕����̌��������邱�Ƃ��Ӗ����܂��ˁE�E���̌��炳��镔���́A���̉^���ɂ��܂�K�v�̂Ȃ������E�E�^����Ɉ݂�t���̌�������������̂ł��傤�E�E
�@
�^�������Ă���Œ��͐t���ւ̌��t�ʂ��������邽�߁A�^�����͈ꎞ�I�Ȑt�@�\�������邱�ƂɂȂ�܂����A���ꂪ30���Ƃ��ꎞ�I�Ȃ�^����ɂ͐t�@�\�͉��܂����A�����I�Ȕ�J�ƂȂ�ƁA�t���͌��t�k�h�{���͂����₹�ׂ邱�Ƃł��傤�E�E�B
�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@7-4�@�@�\���\�H�@
�@�H�߂��A���݉߂������I�ɌJ��Ԃ��ƁA�݂�̑���S���ւ̌����������錋�ʁA�t���ւ̌����ቺ�������t�@�\��ቺ�����A���X�ɐt����������ƌ����Ă��܂��E�E
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@
�@7-5�@�@�T�v�������g�@
�@�s�̕i�̑����̃T�v�������g�͑̓��ŘV�p���݁A���̏����ׂ̈ɐt���ɕ��S��������\��������܂��B�t���a�i�����ł͐t�d���ǁj�̐i�s���~�߂���A�t�����Đ��������⎡�Ö@�͍��̂Ƃ��둶�݂��Ȃ��悤�ł��E�E�܂��Ă�t���a�����P����T�v�������g�ȂǑ��݂���͂����Ȃ��ł��傤�E�E
�@
�@��������A�����S���ÁX�Y�X�̕a�@�ɑ��āA���̃T�v�������g�����i�Ƃ��Ďg���悤�Ɏw�����邱�Ƃł��傤�E�E�����ǂ��납�A�T�v�������g�������ŋ}���t�s�S�Ɋׂ�l�͑�R���܂��B�T�v�������g����p���Ă�����́A���̐�����厡��Ƒ��k����邱�Ƃ������߂��܂��B
�@
�@
�@
���������ȕ��i�̔������ӁE�E�E
�@���ʓI�Ȏ��Ö@�������܂܂ɓ��͊ԋ߂ƂȂ����A�m�����͂ގv����CKD���҂̎�݂ɂ����݁A�T�N���Ɂu����Ő��l���ǂ��Ȃ����I�x���ꂽ����ł���Ă݂�����P�����I�v�ƁA�E�\�̊��z�����������āA�؉H�l�܂������҂ɁA�u����ŗǂ��Ȃ邩������Ȃ��E�E�A�Ƃ������A���ꂵ�������v�Ɗ��҂�����悤�ȈÎ��I�ȕ��@�ŁA���\���~�����鍂�z�ȕ��i�킹�悤�Ƃ���Ǝ҂��A���̐��ɂ��K�����܂��B
�@
�@�ƎҎ��g�́A�@�Ɉᔽ���܂��̂ŁA�����āu����ŕa�C���ǂ��Ȃ�v�Ƃ͌����܂��A�I���ȕ��@�ŁA�u�����Ƃ���ŗǂ��Ȃ�E�E�v�Ɗ��҂��������܂��B���ꂮ����A���N�ی��̗����Ȃ����i����x����Ȃ��悤�ɒ��ӂ��ĉ������B�{���Ɍ��ʂ�����̂Ȃ�A���N�ی����K�p�����͂��ł��̂ŁA���̕��i��T�v�������g���ی��K�p���ǂ������A�{�����U�����̔��f�ޗ��ɂȂ�܂��B
�@
�������ȕ��Ƃ́E�E�����Ȃǂ̕�ΗށA�v���`�i���̋M�����A����g���̓d���g���A�F����A�����A�����͉����̐�����Ƃ��A�������Ȓ��ɍ܂��������t�̂ȂǂȂǁE�E�ECKD�����t���a�Ɍ��������͖������̂Ƃ��l���������E�E�����S�Ă̐t�����̐i�s����~�ł���(����)�A�����́A�ǂ��Ȃ芮��������@��������A�m�[�x���܂�3�ʂ��炢��w�̗��j�ɖ����c�邱�Ƃł��傤�E�E�B
�@
7-6�@�@�H�i�Y�����@
�@�l�H�I�ȐH�i�Y�����͐t����ɂ߂�\��������܂��B�ߋ��̓Y�����̗��j���݂Ă��A�T�b�J�����Ȃnj��݂ł͎g�p�֎~�ɂȂ��Ă��镨����R����܂��B�@�܂��Y�����ɂ́u�����v�Ȃǂ��܂܂�Ă���ꍇ������܂��E�E��ʘ_�Ƃ��Ă͐l�H�I�ȓY�����͓����Ă��Ȃ��ɉz�������Ƃ͂Ȃ��Ǝv���܂��E�E�@
�@
���H�i�Y�����ɂ����ӁF
�@
�@7-7�@�@�R�ۍ܁A��M���ɍ܁A���e�܁@
�@�����̖w�ǂ��t��ӂׁ̈i�t������r�o�����ׁj�A�t���ɑ傫�ȕ��S��������ƌ����Ă��܂��B��ނȂ��ꍇ�ȊO�A���ՂȎg�p�͔����������̂ł��B��t�A���Ȉ�t�ɂ�����ۂ́A������CKD�ł��邱�Ƃ��͂�����\�����ׂ��ł��B�R�ۍ܂̒��ł��A�̑��ŏ��������̑�ӂ̍R�ۍ܂�����ނ�����܂��̂ŁA��t�͍œK�ȍR�ۍ܂��o���Ă���邱�Ƃł��傤�B
�@
�@
���t�@�\�ɉ������R�ۍ܂̓��^�ʂɂ��āi�啪��w�j�E�E�i���ׂł悭�g����N���r�b�g�́A20��Ccr.��50�ł͏���1��1��500mg�A�����ȍ~��1��1��250mg�A�܂�Ccr.��20�ł�3���ڂ����1��250mg��2����1��A�Ƃ���Ă��܂��j�E�E�E����̓N���r�b�g�̐t������̔r�o�������A2���ڈȍ~�����ʕ��p����ƌ����Z�x���オ�肷���邽�߂ɁA2���ڂ���͏������炳�Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��A�Ƃ������Ƃ̂悤�ł��E�E�@ ���L�̃T�C�g�͂��������җp�ɖ�̈��ݕ��̈ꗗ�\�ł��B�@�@�@�@�@�@
�@
�@7-8�@�@�����s���@
�@�Q�s���͖��a�ɂƂ��ėǂ��Ȃ��ł��ˁB1���V�`8���Ԃ̐������Ƃ�A�K�����������������邱�Ƃ���Ȃ��Ƃ͖��l���m���Ă��鎖�ł��傤�E�E�Ƃ͌����Ă���ɗǂ��������Ƃ�Ƃ������Ƃ͊ȒP�ł͂Ȃ��ł��E�E�^���ʂ̏��Ȃ�����҂̏ꍇ�ɂ̓f�p�X�̂悤�Ȍy�����������܂��K�v�����m��܂���B���������܂͎厡��ɑ��k�����Ɨǂ��Ǝv���܂��B�B
�@
�����͉���̌��͐����i���A�a�l�b�g���[�N�E���̌������j�@
�@�@
�@7-9�@�@�X�g���X�@
�@�X�g���X�����ߍ��ނƊ��͂������A�����������Ȃ�ƌ����Ă��܂��E�E�X�g���X�̌����͕������Ă��Ă���菜�����Ƃ��o���Ȃ����̐l�����܂��E�E
�@���Ȃǂ́ACKD�ł��邱�Ƃ��̂��̂��X�g���X�ɂȂ��Ă��܂��B
�Ȃɂ��C���]�����K�v�Ȃ��Ƃ͕������Ă��܂��̂ŁA���̓E�H�[�L���O�Ƒ싅�����Ă��܂��B
�@
�@
�@
�@�@�@�@
�@7-10�@�@�얞�@�@
�@�얞�͓��A�a�A�������A�������ǂ̊댯���q�ł��B�t���ɂ��ǂ�����܂��A���Ǔ��ɒ~�ς��ꂽ�v���[�N�ɂ��A���ǂ��j���Δ]�쌌�A�l�܂�Δ]�[�ǁA�S�؍[�ǂ̌����ɂ��Ȃ�܂��BCKD�̉����A�`���A�J�����[����������Ζw�ǂ̔얞�͉��������͂��ł��B���Ȃ���Δ얞�����łȂ��A���̐�ɂ͓��A�ⓧ�͂��҂��\���Ă��邩���m��܂���B
�@
�@
 �@7-11�@�@�O�a���b�_�@
�@7-11�@�@�O�a���b�_�@
�@�퉷�ŌŌ`�̖��i���̎��g�A���[�h�Ȃǂ̖O�a���b�_�j�͌��Ǔ��ɉߏ�ɓ��荞�ނƃv���[�N�����܂錴���ɂȂ�A�ƌ����Ă܂��̂ŁA�����̂ɂ������悤�Ƀv���[�N���������A�����̖W�Q�ƂȂ聨�t�@�\�ቺ�i�v���[�N�ɂ��g�̑S�̂̌����������Ȃ�ƁA�d�v�ȐS����]�ւ̌������D�悳��A�t���ւ̌���������E�E�j�B���ۂ��H�ו��i���ɌŌ`�̖����j�͐H�߂��Ȃ��悤�ɂ��ׂ��ł��傤�B
�@
�@7-12�@�@�^�o�R�@
�@�э��ǂ̈ޏk���t���̌����ቺ���t���̖э��ǂ̎��Ł��t�@�\�̒ቺ�E�EWHO�ɂ��ƁA�^�o�R�͖Ɏw�肳��Ă��邻���ł��B
�@
�@
�@
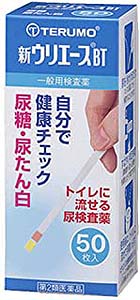 �@7-13�@�@���A�a�@
�@7-13�@�@���A�a�@
�@�t���a���҂œ��͂ɂȂ闦���ł������͓̂��A�a�̎��a��������ƌ����Ă��܂��B�����l�R���g���[�����s�\���ŁA�����l��������Ԃ����������Ɛt���̖э��ǂ��ɂ݁A�t�@�\���ቺ���鋰�ꂪ����A�Ƃ������ƂȂ̂ł��傤�E�E���A�a�̕��͐t�@�\����������I�ɎĂ����邱�ƂƎv���܂����A�a�@�Ŗ����A����������Ă��Ȃ����́A�������Ŗ���1��A����Œ`���������ɂ��A�����������Ɨǂ��Ǝv���܂��B�v���X�P�ɂȂ�����t���i�ۑ����j����̖��@���ׂ��Ǝv���܂��E�E
�����A�a���t�ǁi�S�t���j�@�@
�@
�@
�@�W�@�@�������s�������Ɓ@
�i�O�q�Əd������L�q������܂��j
���܂łɎ����H�v������A���s�������Ƃł��B
�@
8-1�@CCr.��GFR.�̕�,�@Ccr�������Œ��ׂ�
�@
8-1-1�@�N���A�`�j���E�N���A�����X�iCcr�D�j�������Ōv�Z����B
�@
�u�N���A�`�j���FCr�v�͋ؓ����g�����ۂɕ��Y���Ƃ��ċؓ�����Y�o����镨���ł����A�X�|�[�c�������������o����̂ł͂Ȃ��ł��ˁE�E�����ɕK�v�ȐS����x�Ȃǂɂ��ؓ��͂���킯�ł�����A�����Ă������Â��ɐQ�Ă��Ă��������ʂ̃N���A�`�j���͎Y�o����Ă���Ƃ������ƂɂȂ�܂��j
�@
���N���A�����X�Ƃ́A��|����Ƃ����Ӗ��ł��B�@�N���A�����X�Z�[���Ƃ����̂�����܂����A�Ɉ�|�Z�[���Ƃ����Ӗ��ł��ˁB�L�Q�����N���A�`�j���͐t�����炵���p������Ȃ����߁A�t���̔p�������i�A���ɔr�o�����Cr�̕��ϔZ�x�ɑ��錌�t����Cr.�Z�x�@��ACr./����Cr.�v�j���r���鎖�Őt�@�\�̕]�������܂��B�������҂̊W�ɕω����Ȃ���A�t�@�\�͈��肵�Ă���ƌ�����ł��傤�E�E�����O���萔�l���������Ȃ��(����Cr.�ɑ��āA�ACr.���������Ă���j�t�@�\���ቺ�����ƌ������ƂɂȂ�܂��B
�@
�@���t����Cr.�l�͉^����(�ؓ����g�x)�̉e�����܂����A�N���A�`�j���E�N���A�����X�uCcr.�v�͔A����Cr.�l�ƌ��t����Cr.�l�̔�r�Ȃ̂ŁA�^���ʂ��������Ă��A�r�o�ʂ������悤�ɑ������Ă���ACCr.�͖w�lje�����Ȃ��A�ƌ����A����Cr.�����M�����̂��錟���@�ƌ�����̂��Ǝv���܂��B
�@
���N���A�`�j���N���A�����XCcr�D�́E�E�E
(�A����Cr.�l÷����Cr.�l)×�����̕��ϔA����Ccr�D(�P�ʂ�mL/min)�E�E
���̌v�Z����o�Ă��鐔�l�́A�قځA1���ԂɎ����̂��h�߂��錌�t�ʂƂ���Ă��܂��B�@����Ɂi1.73÷�����̑̕\�ʐχu�j���|����ƁA
�@
(�A����Cr.�l÷����Cr.�l)×�����̕��ϔA��×�i1.73÷�����̑̕\�ʐχu�j
��1.73�u�ɑ̕���Ccr.�l�A�Ƃ���Ă��܂��B���̏ꍇ�̒P�ʂ�mL/min/1.73�u�ƂȂ�܂��B
�iCcr�D�ɂ��Ă͂��̍��̌㔼�ɏڂ��������Ă��܂��B�j
�@
����L�̎��ŁA�u�����̕��ϔA�ʁv�����߂�ɂ́A
1���i24���ԁj�̑��A��÷�i24����×60���j�����ϖ����A�� �i��L/min�j�@�ƂȂ�܂��B
�@
��24���Ԃ̑��A�ʂ́A24���Ԃ̔A�����ׂėe��ɒ��߂܂����A���ꂪ�u24���Ԓ~�A�v�Ƃ�������̂ł��B
�@
�@8-1-2�@�E�@24���Ԓ~�A������@
�@�厡��ɁA�N���A�`�j���E�N���A�����X�ׂ����̂ŁA����̔A�����̎���24���Ԓ~�A�����T���v���A�������ė��܂��̂ŁA�A�̃N���A�`�j���ʂׂĂ��������܂��H�v�Ƃ��肢���Ă݂܂��B
�@�厡��̋��͂������Ȃ��Ɩ����ł����A������Ccr.�����̒m�����L��A�����Ōv�Z�ł��鎖���A�s�[������K�v������܂��i�v�Z�̓l�b�g��̌v�Z�T�C�g�ł������v�Z�����Ă���܂��j�B�M���W���z���Ă���厡��Ȃ狦�͂��Ă��������邱�Ƃł��傤�E�E�A��24���ԕۑ������A�ɑ咰�ۂȂǂ̎G��(����)�������A���B�����Ȃ��Ƃ��������ŁE�E�B
�@
�@
�@�����́A�a�@�ł͍̌��̌�Ɏ��R�b�v��n����A���ʂ́A�����A�̒`���ܗL�ʂׂ�Ƌ��ɁA�A�Ɋ܂܂�Ă���ۂ��X�́i���j�זE�Ȃǂׂ�u�����A�̔A���w�����v�Ƃ����̂����܂����A���̎��R�b�v�ɁA����玝���ė���24���Ԓ~�A�̈ꕔ�i�����ɂ�10cc���ŗǂ��炵���ł����A���͂V�Occ���x�������čs���܂��j��a�@�̎��J�b�v�Ɉڂ��ăg�C���̏����ɒu�������ł��B
��͏o�Ă����������ʂ���Ccr.�������Ŏ�v�Z�A�����̓l�b�g��Ŏ����v�Z���܂��B
�@
�@�����Ƃ��ĕK�v�ȕ��͉��L�̒ʂ�ł����A�~�A�͐F�X�ȗ��R�ŎG�ۂ�����₷���A���ɉď�ɂ͎G�ۂ����B���A���������ł͖����̎G�ۂƂȂ��Č���A�R�{�ƋL������܂��B����܂�G�ۂ������ƌ���������ُ�L��A�Ƃ����A�����厡��ɓ���A�N������t᱐t�����^���Ă��܂��܂��B�厡��ɖ��f��������ʂ悤�A�G�ۂ����B���Ȃ��悤�ɒ~�A����10�x�ȉ��̗�p���K�v�ł��B
�@
(�Q�l)�E�E�G�ہi�A�����\�ł͞��ہF����F��Ƃ��đ咰�ہj�̔ɐB�͂͂����܂����A�����Ɖh�{���Ɛl�̑̉����x�̊�������A20�����Ƃ�2�{�ɑ��B���邻���ł��E�E�E40����4�{�A60����8�{�E�E���̂܂ܑ��B�����1�̑咰�ۂ�24���Ԃ�1000�C×100���C�ɑ����܂��B����̓R�b�v1�t���̑咰�ۂƂ̂��Ƃł��B�@
�@�����܂Ōv�Z��ł����E�E���̂܂ܑ��B����ƁA�Q���ڂɂ͎R�̂悤�ȑ傫���ɑ����A�R���ڂɂ͑��z�n�̖ؐ��̑傫���ɂȂ�Ƃ��I�E�E�Ƃɂ����A�G�ۂ̎w�����I�ȔɐB��h�~����ɂ́A�ێ�10�x�ȉ��̉��x�ŕۑ����Ȃ���Ȃ�܂���B�G�ۂ̑��B����ׂ��ł��E�E�i�������A���̂��߂ɉ��̎G�ۂ͑��݂���̂ł��傤�E�E�j
�@
�@
�@���̑咰�ۂ̔����I���B(�p���f�~�b�N)��h�����@�ɂ͗�p����K�v������܂����A�����g�C�����ɗ�p���u���ɂ́A���ނ��s�y�Ɏ����čs�����A�X�`���[�����̏��^�̃N�[���[�{�b�N�X����y���Ǝv���܂��B�N�[���[�{�b�N�X���ɕۗ�܂��T�C6�������ΉĂł��A�����Ȃ炨�悻10�x�ȉ��ɗ�p�ł��܂��B
�@
�@8-1-3 �E�@24���Ԓ~�A�ɕK�v�ȗp��@
���~�A�́A�u���鎞������A�����̓������܂ł́A1��24���Ԃɏo���A��S�����߂Ă��̗e�ʂ��͂���A���̈ꕔ�̔A��a�@�ɒ�o���āA�A����Cr�ʂ�.���������Ă��炤�v�ƌ����ȒP�Ȃ��ƂȂ̂ł����A�~�A���Ԃƒ~�A�ʂ̐��m�ȑ���ƁA�G�ۑ|�C���g�ł��B
�@
�@24���Ԓ~�A���������{���Ă���a�@�ł́A�P�ɁA�A��傫�ȗe��ɒ��߂āA24���Ԍ�ɗ��܂����A�̗e�ʂ�ʂ�A���̈ꕔ�������ȗe��ɓ���Ē�o����A�Ƃ����ȒP�ȍ�ƂȂ̂ŁA���ɋC���̍����ċG�ɂ͎G�ۂ���ʂɑ��B���Ă��܂��܂����A�~�A�ƌ������Ƃ��������Ă��邽�߁A�����̎G�ۂ̑��݂͖��������̂��Ǝv���܂��B
�@
�@�������A�~�A���������Ă��Ȃ��A��ʂ̃N���j�b�N�łQ�S���Ԓ~�A���������Ă��炤�ꍇ�A���̐����ʂ̑咰�ۂ����o���ꂽ�ꍇ�A�A�H�����ǂ��^���Ă��܂��܂��̂ŁA�l�Ŏ��ȐӔC��24���Ԓ~�A����������ꍇ�ɂ́A�����̌�f��h�~����ׂɁA�G�ۂ��ɗ͔r�����邱�ƂƁA�����Ē~�A���ɎG�ۂB�����Ȃ����߂ɁA10�x�ȉ��ł̗�p�ۑ����K�v�ɂȂ�܂��B�ʏ�̕a�@�ł̍̔A�́A�̔A��20���ȓ��ɂ͌�������ł��傤����A�咰�ۂ�1�C���Ă��A2�C�ɂ����Ȃ�܂���ˁE�E�ł��A24���ԕ����Ă����ƁA�ŏ��̂�����1�C��10���C�ɑ��B����炵���̂ŁE�E�܂��A�h�{���̔A�`���������ς����邱�Ƃ������ł����O�O�G
�@
�@���ׂ̈Ɏ��́A�ȉ��̂悤�ȓ�����g���Ă��܂��B
(�v�́A���m��24���Ԃɐt�������N���ɗ������A�����ׂč̔A���A���̈ꕔ��a�@�ɒ�o����A�ƌ������Ƃ����Ȃ̂ł����A�G�ۂB�����Ȃ��A���Ԃƌv�ʂ𐳊m�ɁE�E�ƌ������Ƃ̂��߂ɁA���̌�̐����ł́u���Ȃ肭�ǂ������v�ɂȂ��Ă��܂��Ă��܂��E�E)
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
���~�A�ɕK�v�ȗp��
�@
�@�u�o�n�ߔA�J�b�v�i200cc���x�j�v�E�E�o�n�߂̔A�ɂ͔A�����ӂ̎G�ۂ��������邽�߁A���̃J�b�v�Ŗ���A�o�n�߂̔A������(10�������x)����āA
�@
�A�́u�o�n�ߔA�ۑ��J�b�v200cc�ȏ�v�ɒ��߂Ă����܂��B
���̔A�͍Ō�ɏd�ʂ��͂���ׂɒ��߂Ă����܂����A��o�͂��܂���̂ŗ�p�͕s�v�ł��B
�@
�B�u��o�A�̎�J�b�v�i500cc���x�j�v�E�E�o�n�ߔA���̂�����ɁA��o�A�����̃J�b�v�̔A���āA
�@
�C�u��o�A�ۑ��J�b�v�i��o����A�𗭂߂�2.5L���x�̃J�b�v�v�ɒ��߂܂��B
�@
�D�ɔ��H�i�p�|���܁E�E�G�ۑ�Ƃ��āA��L(�C�j2.5L�̒�o�A�ۑ��J�b�v�̒��ɓ���ĔA�߂�u�|���܁v�ł��B�����傫�߂̕��ɂ��āA�J�b�v�̊O���ɐ܂�Ԃ���ʂ̑傫�����g���₷���ł��B
�@


�i2.5�k�J�b�v�̏ꍇ�A�|���܂́A��260×��380mm�O��A���i���Ƃ��Ắu�t�N���b�N�XNo.13�v�Ȃǂ��l�b�g��ɂ���܂��B�y�V�s��ł�200�����肪����悤�ł��j�B
�@
�G�ۑ��A�|���܂͐H�i�p�|���܂̐V�i�ł���K�v������܂��B�E�E�Ȃ��K���ȃT�C�Y�̃|���܂���ɓ���Ȃ��Ƃ��́A�|���ܖ����ł�邱�ƂɂȂ�܂����A���̏ꍇ�͒~�A���n�߂钩�ɒ�o�A�ۑ��p2.5�k�J�b�v��Ό��ƃX�|���W�ŗǂ���āA�����ŐΌ���������܂����A�����͐@�����ɕ��C��Ȃǂŕ����Ă����܂��B�i�@���ƕz�̎G�ۂ��t�����邽�߁E�E�������G��Ă��Ă�OK�ł��B
�@
�E�Rkg�̔��i�L�b�`���X�P�[���j�E�E�~�A�̗e�ʁiL�j�ł͂Ȃ��d���i���j��܂��B
�@
�F100mL���x�̐����ȃ|���{�g���u��o�p�A�����܂��v�E�E�ŋۃ{�g�����œK�ł����A��ɓ���Ȃ��Ƃ��́A���ʂ̃|���G�`�����{�g���i100cc���x�j���܂ŗǂ�����Ă��������B�L���r�̎��͑䏊�p��܂ŗǂ��ė��p�ł���Ǝv���܂��B���������Đ����ꍇ�́A���߂��䏊�p�Y���܁i�n�C�^�[�j�ŎE�ۂ��邩�A�ϔM���{�g���Ȃ�Ύϕ�����ė��p�ł���Ǝv���܂��B
�@
�@�Ȃ���x�g�����{�g���́A����|���܂ɓ���ė①�ɂŕۊǂ��邩�A�퉷�ۊǂȂ�A�g�p��ɐ�������A�g�p�O���ɍēx��܂��B�H��Ɠ������x���̐�������A��薳���Ǝv���܂��B(������čė��p���Ă��܂�)
�@
�@
�G�N�[���[�{�b�N�X�E�E�E�ނ�p�A�s�y�p�̃N�[���[�ł��B(���̂͂P�T�k�p�ł�)
�@
�H�ۗ�܁i5�C6�j�E�E�N�[���[�̒���10�x�ȉ��ɉ�����K�v������܂�
�@
�I���x�v
�@
(���ӎ���1)�@�J��Ԃ��ɂȂ�܂����A�S�ẴJ�b�v�͎��O�ɏd����ʂ�A�J�b�v�̑��ʂɖ����C��
�N�ŏ����Ă����ƕ֗��ł��B
�@
(���ӎ���2)�@�B��o�A�̎�J�b�v�i500cc�j�ƁA�C��o�A�ۑ��p2.5L�͒~�A�J�n�O�ɗǂ���Ă����K�v������܂�(�C2.5L�J�b�v�ɇD�̋ɔ��|���܂��g���Ƃ��͇C2.5L �J�b�v�̌����Ȑ��͕s�v�ŁE�E�y�����̓N�[���[���̐����x��ۂ��߂ɕK�v�ł�)
�@
�i���ӎ����R�j�E�E��֎��̒�o�A�̎�p�ɁA����������߂̃J�b�v�����邩���m��܂���B��o�A���̔A����J�b�v�͂��ׂėǂ���Ă����K�v������܂��B
�@
�i���ӎ����S�j�E�E�~�A�I����́A�S�Ă̗p��͐�A���C��Ȃǂ�1�ӊ��������Ă���A�N�[���[�{�b�N�X�̒��ɓ���āA����܂ŕۊǂ��܂��B�@����g�p�����ɂ�����x��܂��B
�@
�i���ӎ����T�j�E�E��o�p�A��ۑ�����J�b�v��2.5L�ł͏���������ꍇ�́A�J�b�v��傫�����邩�A�J�b�v��lj����܂��B�N�[���[�̃T�C�Y�ɂ������J�b�v���K�v�ł��B
�@
�@�i���ӎ����U�j�E�E�o�n�ߔA���R�̂��Ă��܂�Ȃ��悤�ɋC�����ĉ������B�A���̒����ɗ��܂�ʂŏ\���ł��B���܂��R�̂��Ccr.�̌v�Z��덷���傫���Ȃ��Ă��܂��܂��B
�@
�@8-1-4�@�E�@�̔A�菇�@ �@�@
�@�O���Ɠ����悤�ȓ��e�ɂȂ�܂����A�m�F�Ǝv���Ă݂ĉ������E�E
���̔A�J�n�O��(�̌�����2���O�j�̏����E�E�E�[���A��p�܂�Ⓚ�ɂɓ���Ă����܂��B���̓N�[���[�{�b�N�X�̒���10�x�ȉ��ɂ���̂ɕK�v�Ȑ��ƂȂ�܂����A�ď��5�ʕK�v�Ǝv���܂�(��3�N�[���[�ɓ���A�[��2�lj�)�B�g�C������10�x�ȉ��ɉ������Ă�

��G�߂͗�p�܂͕s�v�ł��B�B
�@
���f�@���̑O���ɒ~�A���J�n���܂�(24���Ԃ̔A����������̎�ł���A��������n�߂Ă��ǂ��킯�ł��B�@��o����A�͗①�ɂɕۊǂ����1�C2���͖�薳���Ǝv���܂����A�V�N�ȔA�ł�������ǂ����Ƃ͊m���ł��傤)
�@
�@
���̔A�菇�P
�@�f�@���̑O���̒��i�Ⴆ��6��00���j�A�����N���ɗ��܂��Ă���A�͕K�v����܂���̂ŁA�֊���ɔr�A�����A���S�ɔA���o����A24���Ԓ~�A�̃X�^�[�g�ƂȂ�܂��B
�@
�@���̂��ƁA�����̓������E�Ⴆ�Η���6��00���j�܂ł�24���Ԃɏo���A���N�[���[�{�b�N�X���́u��o�A�J�b�v�v�ɒ��߂܂����A�G�ۂ̑����u�o�n�ߔA�v�́u�o�n�ߔA�ۑ��J�b�v�v�ɕۑ����܂��B�o�n�ߔA�͒P�ɔA�ʂׂ�ׂ̂��̂ł��̂ŁA��₷�K�v�͂Ȃ��ł����A�����̐S�z������̂ŃN�[���[���ɂ͓���Ȃ��悤�ɂ��܂��B
�@
�@
���ŏ��̍̔A�܂łɁA���̂��Ƃ����Ă����܂��B
�@
�������P�E�u��o�A�̔A�J�b�v�E���}�B�v��Ό����Y��ȃX�|���W�Ő�Ă����܂�
�@
�������Q�E���o�p2.5L�J�b�v���}�C�v�̒��Ƀ|���܂����A�N�[���[�{�b�N�X�ɓ��܂��B�|���܂��g��Ȃ����́A�Ό��ŗǂ�����Ă����܂��B
�@
�������R�E�E��p�܂�3�����Ⓚ�ɂ���o���A�N�[���[�{�b�N�X�ɓ���Ă����܂�
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
���@�菇�Q�@�@
�A�ӂ����您������~�A���n�߂܂����A�܂��G�ۂ̑����o�n�߂̔A��10cc���x�u�@�o�n�ߔA�E�̎�J�b�v�v�ɍ̂�A
�@
�u�A�o�n�ߔA�E�ۑ��J�b�v�v�Ɉڂ������ۑ����܂��B
�@
�����̂��Ƃ̔A�͒�o�p�̔A�ƂȂ�܂��̂ŁA
�@
�B500cc�̒�o�A�i�̔A�j�J�b�v�ň�U�Ă���A�N�[���[�{�b�N�X�G�̒���
�@
�C2.5L�J�b�v�̃|���܂̒��Ɉڂ��܂��B���̍�Ƃ��Q4���ԁi�����̓������܂Łj����Ԃ��܂��B�@�Ȃ��A��֎��̔A���Y�ꂸ�̔A���ĉ������B��֎��ɍ̔A���邱�Ƃ́A�̔A�̓�Փx�������Ȃ�܂����A�G�ۂ��������₷���̂ŁA�o�n�ߔA�ƌ��Ȃ��ď��ʂȂ�·A�o�n�ߔA�ۑ��J�b�v�ɕۑ����Ă��ǂ��Ǝv���܂��B�A�̑��ʁi�d�ʁj��m��K�v�����邽�ߎ̂ĂȂ��ł��������B
�@
�@�菇�R�@�@
�~�A�I���E�E�����i�f�@���j��6��00���i�O���~�A���J�n���������j�ɂ͔A�ӂ������Ă��r�A�����݁A���S�ɏo�������Ă��������B
�����1��24���Ԃ̒~�A���I��������ɂȂ�܂��B
�@
�@�菇�S�@
�A�̑��d�ʂ̌v�ʂƋL�^�E�E�E�u��o�A��������2.5L�J�b�v�C�v�Ɓu�o�n�ߔA�J�b�v�A�v�̏d�ʂ�ʂ�A���̍��v����2�̃J�b�v�̕��܁i�J�b�v���ʂɏ������d���j�����������ƔA�̑��d�ʂ��o�܂��B�Y��Ȃ��悤�Ƀ��������܂��B�O��̔A�����ŔA�̔�d���������Ă�����́A�A�d�ʁi���j÷��d���A�̗e�ʁi�����j�ƂȂ�܂��B
��d��������Ȃ��ꍇ�́A1��ڂ͏d���i���j�ŗǂ��Ǝv���܂��B
�@
�@�菇�T�@
��o�p�A�̋ψꉻ�E�E�܂��A�̔Z�x���ψꉻ���邱�Ƃ��K�v�ł��E�E2.5L�J�b�v�̃|���܂̌�����Œ��߁A�ǂ��h�����ĔA�Z�x���ψ�ɂ��܂��B�|���܂��g��Ȃ��ꍇ�ɂ́A�V�i�̑ܓ��芄�蔢�ȂǂŔA�𝘝a���܂��B�g�p�������Ȃǂ͎̂Ă܂����A�K���X�_��X�e�����X�_�̏ꍇ�͐�ČJ��Ԃ��g���܂��B
�i���ӁF���̋ψꉻ���s�\�����ƔA���N���A�`�j���Z�x�����肵�Ȃ����߁ACcr.�̌v�Z

�̐M�����������܂���j
�@
�@�菇�U�@
��o�p�|���r�Ɉ����E�E�ψꉻ����2.5L�J�b�v�̔A����50cc���x���A�ŋۂ��ꂽ�e��i�ŋۃ{�g���A���͐Ό��ŗǂ�������v���X�`�b�N�{�g�����j�Ɉڂ��ĕa�@�֎����čs���܂��B���������čs���Ȃ��Ƃ��́A�①�ɂɕۊǂ����Ă��������B1��2���͖�薳���悤�ł��E�E
�@
�@�菇�V�@
�̌���ɓn���ꂽ�A�����̎��R�b�v�������ăg�C��(��)�ɍs���A�����ė����A�����R�b�v�Ɉڂ��āA�g�C�����̌��������ɒu���܂��B����ł��ׂ����͏I���ł��B
�@
�@�菇�W�@
Ccr�D�̌v�Z�E�E��t����̔A�E�̌��̌��ʂ̕\���������A���L�̌v�Z���ŃN���A�`�j���E�N���A�����X�l���v�Z�ł��܂��B
(��ʂɁA�ƒ�ł�24���Ԓ~�A�́A��֎��̔A�̎��ӂ����肷��l������̂ŁA�a�@�ł͐M�p���Ă���Ȃ��Ǝv���܂����A������Ǝ������~�A�����̂Ȃ�u�������ʂ͐������v�Ǝ����Ƃ��Ă͐M���邱�Ƃ��o����Ǝv���܂��j
�@
�@8-1-5�E�N���A�`�j���E�N���A�����X�ECcr�̌v�Z�@
�@
�@Ccr���i�ACr.�l÷����Cr.�l�j×�i�����A�ʂ�L�j×�i1.73�u÷�����̑̕\�ʐχu�j�@
�@
��{�����A��×1.73÷�����̑̕\�ʐ�}�̌v�Z�͎��O�ɂ��Ă����܂�(���̌v�Z���ł�)�B
�@
�������A�ʁi1���Ԃ̕��ϔA�ʁj���Q�S���Ԓ~�A�̑���÷24����÷60��
�@�܂聁24���Ԓ~�A�̑���÷1440�@�ɂȂ�܂��B
�@�A�ʂ̒P�ʂ�mL(cc)�ł����A�A��d�͔A�ʂ�1500cc�O��ȏ゠��l�ł�����w��1.00�ł��̂ŁA
�@1mL��1g�Ōv�Z����OK�ł��B
�i�����Ɍv�Z����ɂ́A�A�ʁimL�j���A�̏d�ʁi���j÷�A��d�ƂȂ�܂��j
�@
�������̑̕\�ʐς̓l�b�g��Ŏ����v�Z���Ă���܂��B
�@
�@
3��ނ̒l���o�܂����A3��ނ̒l�̒����l�ɂȂ�Du Bois���Ōv�Z���܂��B
�@
���ACr.�l�͔A�����\�ɏ�����Ă��܂��B�@�@
�@(�Ⴆ�@38.2mg/dl�j�@
�@
������Cr.�l�����t�����\�ɏ�����Ă��܂��B
�i�Ⴆ�� 1.36mg/dl�j
�@
�������A�ʂƑ̕\�ʐϕ�l�͎��O�Ɍv�Z�ł��܂��̂ŁA��o�p�̔A�̏������I������疈���A�ʂ�
�@
�v�Z���Ă����܂��B�o�i�����A�ʁj×�i1.73�u÷�����̑̕\�ʐχu�j�p�E�E�E�E�iA�j
�@
�iA�j�̒l�����炩���ߏ������Ă����A�������ʕ\�̔ACr.�ƌ���Cr.�l�@����
�@
�@�i�ACr.�l÷����Cr.�l�j×�iA�j��Ccr.
�i�N���A�`�j���N���A�����X�j�ƂȂ�܂��B
�@�@�P�ʂ́E�EmL/min/1.73�u�ƂȂ�܂��B
�@
�@���̒l��1.73�u�ɑ̕���Ccr.�ł��B�܂�A�����̐g�̂��A�W���I�̊i�i�̕\�ʐς�1.73�u�j���Ɖ��肵���ꍇ��Ccr�ł��B���ۂ�Ccr.�́A���������Ȑl�ł����班���������Ȃ�܂��E�E�Ⴆ�Α̕\�ʐς��W�����P�O����������A���ۂ�Ccr.�l���P�O���������ƌ������Ƃł��B�i���̎��ۂ�Ccr.�l�͖��_�H�̗ʂ����߂�Ƃ��Ɏg���܂��B�j
�@
�@ Ccr.=�i�ACr.÷����Cr.�j×�iA�j
�@�@3�̐����̌v�Z�ł�����X�}�z�̌v�Z���10�b�ŏo���܂��ˁE�E
�@
�@8-1-6 �E�@CCr.�̐����@
�N���A�`�j���N���A�����XCcr.���i�ACr.�l÷����Cr.�l�j×�i�P���Ԃ̔A�ʁj�@ �P�ʂ͂��k�^������
���̌v�Z�ł́A�̖ʐρi1.73�u�j������܂���̂ŁA���̐l�i�팱�ҁj�̌������̃N���A�`�j���̃N���A�����X�i�t�����g�̘̂V�p����r������\�́j�ł��B
�@
���̌v�Z���ƁA�����Ȑl�͔A�ʂ����Ȃ��ł��傤����ACcr�l���������Ȃ�A�啿�Ȑl�͑傫���Ȃ�܂��B����͎��R�Ȃ��Ƃł͂���̂ł����A�̊i�ɂ����Ccr�D�̕]���l���傫���ς��Ƃ����̂́A�t�@�\���r�]�����悤�Ƃ����ꍇ�ɂ͋�������ł��B�̊i�ɂ��Ccr.�̕]���̕ϓ��������߂ɁA�ʏ�Ccr.�l�͑̊i������܂��B
�@
�@�W���I�ȑ̊i�̐l�̑̕\�ʐρi�W���̕\�ʐρj��1.73�u�Ƃ��A�팱�҂��W���̕\�ʐ�1.73�u�ł���Ɖ���i��j�����ꍇ��Ccr.�l��������CKD�̐i�s���x�f���܂��B�������邱�Ƃ�Ccr.��]�������ŁA�X�̑̊i�ɂ�鍷�̖���������Ă��܂��B�݂�ȓ����̊i�Ɖ��肵���ꍇ��Ccr.�l�ł��B
�@
�@�]���Ď��ۂ�Ccr.�l�Ɂi�W���̕\�ʐ�1.73�u÷�����̑̕\�ʐρj���|�������̂�(��)����Ccr.�l�ƂȂ�܂��B���̏ꍇ�ɂ�Ccr.�̒P�ʂ�ml/min/1.73�u�ƂȂ�܂��B
�@
1.73�u�Ə�����Ă���ꍇ�͑̕\�ʐ�1.73�u�Ɂu������l�v�Ƃ������Ƃ��Ӗ����܂��B
�@
�i1.73�u�j�Ƃ����\��������Ccr.�l�͂��̐l�̎��ۂ̎������h�ߗʂł�����A���̒l����_�H�▃���̗ʂȂǂ����߂���Ƃ������Ƃł����E�E
�@
�@�̕\�ʐϕ�����Ȃ��Ə����Ȑl��Ccr.�l���������o�܂��̂ŁA����Ccr.�l�������悤�ȋC�����܂��ˁE�E1.73�u�ɑ̕����Ə����Ȑl�قǐ��l���ǂ��Ȃ�܂��O�O�j�B�@
���̕����Ccr.���i�ACr.�l÷����Cr.�l�j×�i�P���Ԃ̔A�ʁj×1.73/�����̑̕\�ʐ�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�P�ʂ́@ml/min/1.73�u
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i1���Ԃ̎������h�ߗʁj
�@
���]�k�ł���
�t�@�\�]���ɂ悭�g����eGFR(���Z�E�������h�ߗ�)�̌v�Z�ɂ͐g����̏d���s�v�ł��B���ʁA�N��ACr.�l�����Ő��Z���܂��B�̊i���K�v�Ȃ͂��ł����A�̊i�̕��͕��ϓI�ȑ̊i�Ɖ��肵�āA�܂�W���̕\�ʐς�1.73�u�i�Ⴆ�ΐg��167cm�A�̏d65kg�̐l�j�Ɖ��肵�Ď������h�ߗʂv�I�ɐ��肵�Ă��܂��B
�@
�@�ł������N�30���C�̏d��50kg�̕��Ō���Cr.1.2mg/dl �̕���eGFR��59.9ml/min/1.73�u�ŃX�e�[�W��G3a�A�iCockroft-Gault���́jCcr.��63.7ml/min�ƂȂ�܂����A
�@
�N��ACr.�������ő̏d���{��100kg�̐l��eGFR�͓���59.9ml/min/1.73�u�ŃX�e�[�W������G3a�ł����A��Ccr.�͔{��127.3�ɂȂ�܂��B
�@
�@�܂�A��l�̐l�̐t�@�\���ׂ�Ƃ��A���ۂ̎������h�ߗʂ��傫������Ă��Ă��A�N��ƌ���Cr.���ꏏ��������X�e�[�W�͓����ŁA��������̒��x�͓������ƌ������ƂɂȂ�܂��E�E
�@
�܂��A�̕\�ʐς͑̏d�����g���̕����e�����傫���Ȃ�܂��B
�@�Ⴆ�ΐg��160cm�A�̏d50kg�̐l�̐g��������10���L�т��Ƃ����ꍇ�A�̕\�ʐς�7.2%�傫���Ȃ�܂����A�̏d�̕���10�������Ă��̕\�ʐς�0.77�����������܂���B����͒P�ɂ������o�������ł��̂ŖʐϓI�����͋͂��ł��ˁO�O
�@
�@�܂�A�����̑̕\�ʐς͈�x�O�q�̃l�b�g��Ōv�Z���Ă����A�u1.73�u/�����̑̕\�ʐ�(�u)�v�̕�l�́A�g�����k�܂Ȃ����肩�Ȃ蒷�����Ǝg����ƌ������ƂɂȂ�܂��B
�@
�@8-1-7�@�E�@GFR.�Ƃ́@�@
�iGlomerular Filtration Rate�j�������h�ߗʁE�E�E�t���̎����̂ƌ����h�ߊ�����t���ʉ߂���ԂɁA���t������A(���A)���h���o�����ʂ̂��Ƃł��B������mL�icc)�h���o�����Ƃ����h�ߔ\�͂ŁA�t�@�\�̏�Ԃ�\�����߂ɗp���܂��B�P�ʂ�ml/min/1.73�u�B�@Ccr.�ƂقƂ�Ǔ����ł��ˁE�E
�@
�@���N�ŁA���ϓI�ȑ̊i�i�̕\�ʐς�1.73�u�j�̐l�́A���t������1���ɖ�144���b�g�����̔A�̌�(���A)��t�����̎����̂����h���o���ƌ����Ă��܂��̂ŁAeGFR�Ɋ��Z����ƁA144L÷�i24����×60���j��0.1L��100mL/min�E�E���܂���ɕ��ϓI�̊i�̌���҂�eGFR�͐�̗ǂ�100ml/min(����100cc)�ɂȂ�܂����I
�@
�@�����A���̐��l�͂����܂ł��̕\�ʐς�1.73�u����l�̏ꍇ�ł����āA�����Ȑl�̎��ۂ�GFR�͂����������Ȃ��Ȃ�܂��B eGFRml/min/1.73�u�l�Ɂi�l�̑̕\�ʐ�/1.73�u�j���|����Ǝ��ۂ̎������h�ߗʂ������܂��B�@
�@1.73�u�Ƃ����̕\�ʐς����l����ɂ��āA�u�������Ȃ��̐g�̂̑̕\�ʐς��W���̌^��1.73�u��������A�Ɖ��肵��GFR���r���邱�Ƃ͑̊i�ɊW�Ȃ�CKD�̈����f�o����ׁA�֗��ł͂���܂����A����(estimate)��e���t���Ă���悤�ɁA���v��̌v�Z�̊�Â������l�ł��̂ŁA��ΓI�Ȑ��l�Ƃ͌����܂���B��̂��ꂭ�炢�E�E�ƌ����Ƃ���ł��傤���E�E�����ł����Ă��A����Cr.�l����ȒP�ɐ��Z�ł���̂ŁA�d�v�ȏ��������l���Ǝv���܂��B
�@
�@�ܘ_�A�����eGFR�l����24���Ԓ~�A�ɂ��Ccr.�l�̕����Aestimated�i���Z�A����j���Ȃ������A�^���̐t�@�\�ɋ߂��ƌ����锤�ł����ACcr.�l�̕���GFR�l��菭���傫���o�܂��B���̌����́A�N���A�`�j���͔A�������̂����h�߂��ꂽ�i�o���j������ɒʉ߂���A�ǂŁA���͂̑g�D����N���A�`�j�����A�ǂ̒��ɔr�o����邩��ł��B��ʂɂ悭�u�A�ǂ��番�傷��v�A�ƈ�w�I�ȕ\��������Ă܂����C�A�ǂ���o�čs���̂ł͂Ȃ��A���͑g�D����A�Ǔ��ɕ��傳���A�����Ă���A�ƌ����Ӗ��ł��B�@���̕�������̂ŏ��X���l�������Ȃ��Ă��܂��B�������h�ߗʂƂ��ẮA�A�ǂ���̕��啪�͈����Ȃ���Ȃ�Ȃ��ł��傤���A�����t�����ŏ���������ł�����A�A�ǂł̕�����܂߂Đt�@�\�ƌ�����̂ł͂ƌl�I�ɂ͎v���܂��B�����̂��h�ߗʂɑ���A�ǂ���̕���ʂ͎����̂̒ɂ݂��i�s���A�����̂�����ɂȂ�Ȃ��Ȃ�قǑ������邱�Ƃł��傤�E�E���Ƃ���ACKD�������ɂȂ�قǁACcr.��GFR���܂��܂��傫���o�邱�ƂɂȂ�܂��E�E
�@
�@8-1-8�@�@�t�����h�߁i�납�j�@�\�̒m���@
���ϓI�̊i�̌����(�j�q)�ł����1���ɖ�140�`150���b�g�����̔A�i���A�j���h���o���܂����A�g�̂̌��t�͑̏d50kg�̐l�Ŗ�4���b�g����������܂���E�E���̂���ȑ�ʂ̌��A�������o����̂ł��傤���E�E
�@
�@���̗��R�́A�t�����h���o�������A��99%�͐g�̂�(���t���ɖ߂�)�ċz�����s������ł��B���A�̋͂��P���������N���֗�����̂ł��B���������łȂ��Ɛl�Ԃ͒������オ���Ă��܂��܂��B
�@�@
�@�t���́u�����́v�ł͐Ԍ����╪�q�ʂ̑傫�Ȃ���ς����Ȃǂ������������ƌĂ�铧���ȉt�̂��h���o���܂����A�傴���ςɔA���h�߂��āA���̂��Ƃ͐t�����o��܂ł̓r���ŗL�p�ȕ��i�����A�~�l�����A�u�h�E���A�����q�ʂ̒`�������E�E�j��g�̂ɖ߂��A�ƌ������Ƃ�����Ă��܂��B
�@
�@�܂�A�����̂̕��S�����炷���߂ɁA�h�߂̑S�Ă������̂ɂ�点��̂ł͂Ȃ��A�����̂ł͑傴���ς��h�߂��邾���ɂ��āA���Ƃ͐t�����o��܂ł̊ԂɗL�p�ȕ�����g�̂ɉ������Ƃ������Ƃ�����Ă��邱�ƂɂȂ�܂��B�Ȃ̂ŁA�����͖̂��Ȃ��Ă��A�����̂����h���o�����Ƃ̗L�p���̍ċz���Ƃ����@�\����肭�����Ȃ��ƁA������܂��t�@�\�Ƃ��Ă͑���Ƃ������ɂȂ�Ǝv���܂��E�E
�@
�@�܂�g�̂́A��SL�����Ȃ����t�����x���J��Ԃ��t���ɑ��荞��ł͑�R�̌��A�����A���A���̗L�p�ȕ��i�����͂X�X���j��g�̂ɖ߂��A�s�v�ȕ����͂������ʂ̐����Ƌ����N���֎̂Ă�i���̗ʂ͌��A�̂P���j�A�ƌ�����ƂU����Ԃ��Ă��܂��B
�@
�@�S����1��̎��k�ő���o�����t�ʁi1��S���o�ʁj��70cc���x�B����60��/���i���b1���j�̐l��1���i86400�b�j�ɁA70cc×86400����600��cc��6,000L��6�g�����̌��t��g�̂ɑ���o���Ă��邱�ƂɂȂ�܂��B
�@
�@�����Ă������A6�g���̂Q�O���͐t���ɑ��肱�܂�邻���ł��̂ŁA������1.2�g�����̌��t�̏����Ȃ���Ȃ�܂���B����͂SL�̑S���t��1��300���h�߂��Ă��邱�Ƃɑ������A��T����1��A�g�̂̑S���t���h�߁A���Ă��邱�ƂɂȂ�܂��I
�@
�@���a�����̖т�10����1���x�����Ȃ������̖̂э���(���a��4�ʁE�~�N����)�����O�a8��×���݂Q�ʂ̔����M��̐Ԍ������܂��t��1.2�g���������o�����āE�E�э��ǂ��C����̂��������Ȃ��ł��E�E
�@
�@���t�����Ő����i�Ԍ����j���o��A�Ƃ����̂́A�ׂ������̂̕ǂ��j��Ď����̂̓��a�����傫�ȐԌ������R��Ă���E�E�Ƃ������ƂȂ�ł��ˁE�E(��)�E�E�Ԍ����������Ə���������Ȃ�Ύ����̂�ɂ߂邱�Ƃ�����̂����m��܂��A������ĕ\�ʐς��ŏ��ł�����E�E�x�Ŏ_�f�ɐڐG���ďu���Ɏ_�f��ɂ͑傫�ȕ\�ʐς��K�v�Ȃ̂ŗ��ł͖𗧂����ł��ˁE�E
�@
�@���ׂĂ݂�ƁA�Ԍ����̒e�͐��ɂ�EPA���W���Ă���炵���A����H�ׂ����������Ƃ����̂͂��̕ӂɂ����R������悤�ŁE�E
�@
�@�Ȃ��A���a4�ʂ̎����̂̒����A�ǂ�����ĊO�a�W��×���݂Q�ʂ̐Ԍ������ʂ��̂��s�v�c�ł����E�E���ׂ܂�����A���ׂ������Ԍ����͓���Ɋۂ܂��čׂ������̂�ʉ߂��邻���ł��E�E�m���ɓ���Ɋۂ܂�A�����̂̊ۂ܂������a��2.6�ʈȉ��ɂȂ��̂ŁA���a�S�ʂ̎����̂̃`���[�u��Ԍ����͊y�X�ʂ�܂��ˁE�E
�@
�@�ł��A�����Ԍ����̒e�͂������Ȃ�����E�E�ۂ܂ꂸ�ɂ�������E�E���������Ď����̂������E�E�ň��j�������E�E�Ђ���Ƃ��āA�����̂��Đt�@�\������������Ɛl�͍d�������Ԍ����H�E�E�E���������ƐH�ׂ��������������O�O
�@
�@
�@�K���@���t���̍\���Ƌ@�\�i�Ō�q�n�n�j�E�E�E�t���̍\���@�\�������قǐ����ȃC���X�g�ł��B���̂悤�ȕ�����₷���C���X�g�A����͑��Ɍ������Ƃ�����܂���B���̐}����������������Ă����^�₪���U���邩������܂���E�E�����������I�@�@
https://www.kango-roo.com/learning/1677/
�@
�@
�@8-1-9�@�E�@Ccr.�Ƃ́@
�@�@�N���A�`�j���E�N���A�����X(Creatinine clearance : Ccr.)�̃N���A�����X�Ƃ́A��|����Ƃ����Ӗ��ł��B���X�̃N���A�����X�Z�[���̃N���A�����X�ł��B�N���A�`�j���E�N���A�����X�́A���t���i�����ɂ͌������j�̃N���A�`�j�����ǂ̒��x��|����A���ꂢ�ɂł��邩�A�ƌ����ړx�ɂȂ�܂��B
�@
�@Ccr.��50ml/min/1.73�u�Ƃ͕W���̌^�̌���҂̂��悻�����������t���̔p�����i�N���A�`�j���j�������o���Ă��Ȃ��A�܂�t�@�\������҂̖������Ȃ��A�ƌ������ƂɂȂ�܂��B
�@
�@�A�̃N���A�`�j���ׂ闝�R�́A�N���A�`�j���Ƃ����V�p���͐t�����h���ꂽ��A�N���ɗ�����܂łɎ��͂̑g�D�ɏo�čs���i�ċz�������j�����w�ǖ����A�܂����͂�����݂���ŗ���i���傷��j���Ƃ��������Ȃ���r�I���肵�Ă��邩��ł��B���ׁ̈A�����̃N���A�`�j���̗ʂƐt�������N���ɔr�o���ꂽ�N���A�`�j���̗ʂ��r���A�t�@�\��]�����܂��B
�@
�@���t���̃N���A�`�j��(Cr.)�́A�S����x�A�r�⑫�C�����ȂǑS�Ă̋ؓ�����V�p���Ƃ��Č��t���ɕ��o����镨���ƌ����Ă��܂��B�ؓ��ʂ͈��ł��̂ŁA�ʏ�̐������������C1���ɋؓ�����Y�o�����N���A�`�j���̗ʂ��قڈ��ł���A����҂ł���Ȃ�A������Cr.�͘V�p���Ƃ��ăR���X�^���g�ɐt������r�o����A���t�ɃN���A�`�j�����ǂ�ǂ܂�A�ƌ������Ƃ͂Ȃ����ł��B
�@
�����ł���Ȃ�A�P���ɋؓ����猌���ɕ��o���ꂽCr.�̗ʂƁA�t������A���ɏo���ꂽCr.�̗ʂ͓����ł���͂��ł��B�S�������ł���Ȃ�C���̐t���͌��S�ƌ�����ł��傤�E�E
�@
�@����A�t���̓����̈����l�ł́A�t�������Cr.�̔r�o���������߂ɁA�������^�������ċؓ����猌�t���ɑ�ʂ�Cr.�����o���ꂽ�ꍇ�Ȃǂł́A�t������̔r�o���ǂ����܂���E�E�E
�@
�@�ؓ����悭�g������ł͌����̃N���A�`�j���l����ɏ㏸���A�A�ɃN���A�`�j�����o�Ă���̂͂��Ȃ�x���Ɛ����ł��܂��B���Ƃ���ƁA�������^����������͌�����Cr.�Z�x�͏㏸���A�A��Cr.�Z�x�͂��قǏオ�炸�A�v�Z���Ccr�l�͈����Ȃ�E�E�Ƃ������ƂɂȂ�ł��傤�E�E
�@
�@�t�ɁA���i�������^��������l���A�~�A�̑O�������^�����ς�����~�߂�ƁA����Cr�Z�x�͒ቺ���A�A����Cr.�͈����܂ł̉^���̂����ő����邩������܂���E�E���̏ꍇ��Ccr.�͂����������P�������̂悤�ɂȂ�ł��傤�E�E
�@
�@������Ccr.�𑪒肷��ɂ́A�����O3���قǂ͓��ʂȂ��Ƃ͂����A���i�ʂ�̐��������邩�A���ƂȂ����ł���l�́A���ƂȂ������Ă����������l�����肷�鎖�ɂȂ�Ǝv���܂��B���ƂȂ������Ă���A����Cr.�l�́A�������^�������Ă�������́A�����͉�����Ǝv���܂��B
�@
�E�E�E(8-1-5�@�N���A�`�j���N���A�����X�̌v�Z���Q�Ƃ�������)
�@
�@Ccr�̌����ł����A���ł�CKD�ۑ����̎��ÂɎ��g��ł���a�@�ł͌��f���̑O���ɁA���ґ��24���Ԓ~�A�����Ă��炢�A���̈ꕔ�����Q���Ă��炢Ccr.�ׂ�A�Ƃ������Ƃ�����Ă��鏊�����Ȃ��炸����܂��B
�@
�@�܂���錧�̏�����w�����́u�ŊL�N���j�b�N�v�ł́A���҂łȂ��Ă��A�l�b�g�ʼn���o�^�����ĔN����U�荞�߂ACcr����������Ă���܂��B����A�����̓x�Ɏ�����̂ł����A�\�����ނƒ~�A�p�i��1�������Ă���܂��̂ŁA�������ɏ]���ĔA�߂āA���ʂ̔A���N�[���ւő�����@��Ccr.���������Ă���܂��B
�@
�@�܂����ʂ�X�����Ă���܂����A���_�A���P�_�̃A�h�o�C�X�����Ă��������܂��B�~�A�̗��K�ɂ��Ȃ�܂����A�L�Ӌ`���Ǝv���܂��B�A���ACcr.�̌v�Z�ɂ͌���Cr.�l�����K�v�ł��̂ŁA���߂��̃N���j�b�N��,�O�����Č��t���������Ă��炤�K�v������܂��B
�@
�@
�@ �A�ʂ̑�����ł����A��ʓI�ɂ́A�ڐ���̕t�����|���܂�K���Ȕ��ɓ���A�����݂͒邵�A24���Ԃ̔A�߁A�~�A�I����ɁA�|���܂���Ŏ����グ�A�܂Ɉ�����ꂽ�ڐ��肩��A�ʂ�m��A�ƌ������@�ł����A�܂̎������ɂ��덷�������ł��Ȃ��قǑ傫���Ȃ邽�߁A���Ƃ��Ă͂Rkg�̃L�b�`���X�P�[���ŏd�ʂ�ʂ�A�Ƃ��������������߂��܂��B�P�ʂ͂��ɂȂ�܂����A�A1g���Pcc�ƌ��Ȃ��āA�a�@�������߂�P��cc�imL�j�ŕ�����ǂ��Ǝv���܂��B�i�����ɂ́A�A��cc���A�̏d��÷�A��d�ł��j�A��d�͈�x����Ζ���傫�ȕϓ��͂Ȃ��Ǝv���܂��B���̏ꍇ�A�A�ʂ͖�1��1500cc�A�A��d�͖���1.005�ł��B�A�ʂ�����Z�k����Ă���ꍇ�͔�d�͑傫���Ȃ�܂��B
�@
�@���A��(�͂���F�X�P�[��)�̏�ɒ~�A�܂�u�����Ƃ͖����ł��̂ŁA�~�A�܂���ꂽ�����Ə悹�d����ʂ�A���ƃ|���܂̏d�������������ĔA�ʂƂ�����@���A���ڂ��S�z�������ǂ��Ǝv���܂��B�|���܂Ɣ��̏d���͎��O�ɗʂ��Ă��������������ł��ˁE�E�����傫���ꍇ�̓X�P�[���̐������ǂ߂Ȃ������m��܂���B�Ȃɂ��X�y�[�T�[��u���Ĕ������������グ�邩�A���邢�͔A���������ɂ��ďd����ʂ�A���v���đ��A�ʂ��o���̂��ǂ��Ǝv���܂��B
�i�a�@�ɂ��~�A�̕��@�͕ς��Ǝv���܂����A24���Ԓ~�A���āA���̈ꕔ��a�@�ɒ�o����A�Ƃ����_�͓����ł��B�j
�@
���~�A�����͂ǂ����ĕK�v�ł����H(���{���}�����E������ÃZ���^�[�j
�@
*24���Ԓ~�A�E�ECcr.�A�ێ�`���ʁA�ێ扖���ʂ̎����v�Z
�@(���M��w�E��X�a�@�j
�@
*�t���a�̊T�v����i�啪�s�E���R��@�j
�@
(�Տ��ɂ�����24h�~�A�����̈Ӌ`�A����ɂ�����j
�@
�@8-2�@�@���ۂ̉����A�`�����̐ێ�ʂ�A�������玩���Œ��ׂ���@�@
�@�b�j�c�̐l�̓O���[�h�ɊW�Ȃ��A�ȑO�͉�����1��6���ȉ��A�Ƃ�������������܂������A�����t�͏��Ȃ���Ώ��Ȃ��قǗǂ��ƌ����܂��̂ŁA���Ȃ��قǗǂ��ƂȂ�ƁA�^���ɐH�������Ɏ��g��ł���l�͐ێ扖���ʂ��Q���Ƃ����l���o�Ă��邱�Ƃł��傤�E�E���Ȃ�����ێ�ʂ��痈��傫�Ȗ��i��i�g���E�������j�����邽�߁A���݂ł͐t���w���3���ȏ�U�������ƌ����͈͂�t���܂����B
�@
�@���Ȃ�������͂�ǂ��̂��낤�Ƃ������������邽�߁A1���R����̐��������Ă���l�������Ǝv���܂����A�ʂ����Ė{���ɐ��m�ȉ����ێ悪�o���Ă���̂��͌v�Z�����ł͕�����܂���B���ɊO�H��X�����̉����ʂ͐��m�ɂ͕�����܂���B1�H�U���ȏ�ɂȂ�ꍇ������̂ŁA�O�H��X�[�p�[�̑y�ɂ͌��X�����ӂ��K�v�ł��B
�@
�@�����ʂ͖��o���炠����x�͌o���I�ɕ�����܂����A�`�����ƂȂ�ƁA���o�ł͕�����܂���B�M���M���̒`�����ێ�����킵�Ă���l�ɂƂ��ẮA���ۂɎ������ۂ��Ă��鐳�m�ȗʂ�m�肽�����̂ł��B���t�����ŔA����������̂ł���A����Œ~�A�����āA�A�̒`���A�i�g���E���iNa�j�A�A�f���f�iUN�j�̔A��ʌ��������Ă��炦�A�`������͒`�����r�o�ʁANa����͎��ۂɐH�ׂ������ʁA�A�f���f����͓������`�����ێ�ʂ�������܂��B
�@
�i�v�Z�͉��L�̃T�C�g�Ŋe�l����͂���Ύ����v�Z���Ă���܂��j
��24h�~�A�ɂ�鉖���A�`�����ێ�ʂ̎����v�Z�i���M��w��ÃZ���^�[�j
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@
�@8-3�@�@�����̔A�ʓ����L�^����@
�@���͂����Ă��Ȃ�G1�`G4��CKD���҂ɂƂ��ė��z�I�ȔA�ʂ͂ǂ̈ʂȂ̂��E�E�l�b�g��ɂ����m�Ȑ��l��������Ȃ��̂ł����E�E�t���w��ɂ��ƁA����҂̕��ς�1��1�`1.5L�ŁA0.4L�ȉ���R�A�A2.5L�ȏ�𑽔A�ƌ��������ł��B�R�A�Ƒ��A�𑫂���2�Ŋ���ƒ����l�Ƃ��āA1.45L�ƂȂ�܂��B���ꂩ��l����Ƃ����悻1��1�`2L���x�Ȃ�ǂ��̂ł͂Ȃ����ƌ������ƂɂȂ�܂��E�X�ɂ��̒����l��1.5L(1500cc)��ڕW�l�Ƃ��A�u1.5L±0.5L�v�Ƃ���A�ǂ���������傪�o�Ȃ��悤�Ɏv���܂��E�E
�@
�@�A�ʂ������قڈ��Ƃ������Ƃ͐��������肵�Ă���E�E�Ƃ�������悤�Ɏv���܂����A�������̔A�ʂ��������������S�ł��܂��B
�@�������ǂ̈ʐۂ����炢���̂��́A�A�ʂ�1500cc�O��ɂȂ�悤�ɉ��������Ĉ��ސ��̗ʂ����߂�ΊȒP�ł��B���߂��ʂ̈��ݕ���ۉ��|�b�g�ɓ���āA1���ň��݊����A���̓��̃m���}�͒B���ł��B
�@
�@�����A�ʂ����Ȃ��āA�̏d�������Ă���Ε���i�ނ��݁j�E�E�d����^���̂��߂��Őt���������グ�Ă���\��������܂��B�ߌ�ɂȂ��Ă��A�ʂ����Ȃ��Ƃ��́A���̓��͂�������ȏ㓭�����ƁA�^�������邱�Ƃ͐t���ɂƂ��ėǂ��Ȃ��ƌ����T�C����������܂���B�ł���Ȃ�A������Ɖ��ɂȂ�Ƃ����Đt���ւ̌����𑝂₷�悤�ɂ�������������������܂���B
�@
�@�֎q�ɍ�������Ԃ��痧�����Őt���ւ̌����͂P�O������A������20��������ƌ����܂��E�E�K�x�ȗL�_�f�^��(�����E�H�[�L���O20�`60��)�̗͈͑ێ��ɗL���ƌ����Ă��܂����A��肷���͋֕��ł��傤�E�E
�@
�@
�@8-3-1 �E�@�O�o��ł̔A�ʂ̐�����@�@
�@�ƂŖ����̔A�ʂ��L�^���Ă�����́A����̔A�ʑ���̎��ɁA���̔r�A�ɉ��b�������������L�^����ƁA���������b���ω�cc�r�A������̂���������A�O�o��Ŕr�A���ɕb���𑪂�A���ꂩ�牽cc����������������x�v�Z�ł��܂��BCcr�����ł͂Ȃ��̂ŁA��̂̔A�ʂ��킩������̂ŁA���̌��ʂ��X�}�z�ȂǂɋL�^���āA�Ƃł̋L�^�ƍ��Z����1���̔A�ʂ����߂܂��B����1���̔A�ʂ��\�肵���������Ȃ��ꍇ�ɂ͌������l���Ȃ���Ȃ�܂���B
�@
������i�ނ��݁j�͂ǂ����E�E���������̌������l���܂��E�E�����d���A��J�A
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����ߑ�
�@
�����������Ȃ�����������ď�͒ʏ�̐�����+���������l�����A���������߂̐����⋋���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�K�v���Ǝv���܂��B
�@
�������������������E�E�E�ď�Ɋ���~���ĒE���C���̎��̐����⋋�́A��500cc�̃y�b�@�@�@�@�@�@�@�@�@�g�{�g���ɐH��1.5g��������ƁA���Ȃ̉���0.3���o���␅�t�ɂȁ@�@�@�@�@�@�@�@�@��܂��B��ʂɊ���~���āA������������⋋�����̂ł́A���t���@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�g���E���s���ɂȂ邩���m��܂���E�E�E�ӎ������邤���ɁA���@�@�@�@�@�@�@�@�@���Ɖ�����⋋���܂��傤�E�E
�@
�@
�@
�@8-3-2�@�E�@�r�ւ̎������L�^�����@
�@�A�̋L�^�\�ɔr�֎������L�^���Ă����ƁA�����̃��Y�������m�ɕ�����܂��B�܂��Â��Ȃ����ǁE�E�ƌ����Ƃ��ł��A�ւ�́A���������܂ŗ��Ă���̂ɁA�������ɖ����ɂȂ��ĕւ�̍��}�i�m�b�N�j�ɋC�Â����ɂ���ƁA�����A�d���ւ�ŋꂵ�ނ����m��܂���E�E�����̎��Ԃ�������A�������낻�낾�ȁE�E�ƕւ���C�Ɋ|���鎖���K�v���Ǝv���܂��B
�@
���֔�͐t���Ɉ�����������܂���E�E�s�v�ȕւ�͑����o���������ǂ��ƌ������Ƃ��Ǝv���܂��B���̈Ӗ��ł͐H���@�ۂ̑������ނ�H�ׂ邱�Ƃ͐t���ɗǂ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă��܂��B�@�i8-5�u�֔��v���Q�Ɖ������j
�@
 �@8-3-3 �@ �x�X�g�̏d��m��
�@8-3-3 �@ �x�X�g�̏d��m�� �E�E�����Ɠ������x�̐H��(�K��̃J�����[)��ۂ�A�������x�̘J����^���������̂Ȃ�A�������A��̑̏d�͂قړ����ɂȂ�͂��ł��B�����̏d�������Ă�����A�O���H�߂������A�����̎�肷����A�����̐ۂ肷���Őg�̂��ނ��̂����m��܂���B�����̏d��ʂ�A���ʂɐH�����Ƃ��Ă����Ԃōł����Ȃ��̏d���x�X�g�̏d�ł��B�����A�����̏d�v���x�X�g�̏d����������A�����͐�D���ȓ��ł��B
�@
�@8-4�@�@�A�����M�[��������@
�@
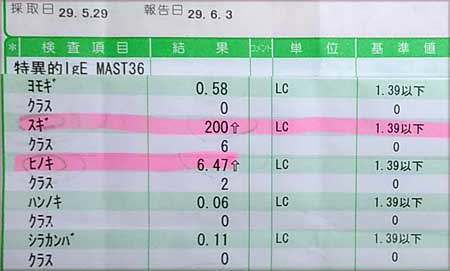
�E�E�������Ǝ��͖��N�t��ɂȂ�ƝG������炵�A���M�����܂�Ȃ����߂ɓ��Ȉ�ɍs���ƁA��t����͍A���^���Ԃł���E�E�ƌ����čR�ۍ܂��M�܂�2�C3������������O�ɂȂ��Ă��܂����B
�@
�@���������ׂŃ_���_���ƝG�������āu���M�v�Ƃ����̂͂��������E�E�ۂ�E�C���X�Ȃ�����ƍ��M���o��͂����E�E�ԕ��ǂł͂Ȃ��̂��H�ƌ����^�₪�킫�A���@�Ȃ֍s���܂����B
�@
�@���@�Ȃł��R�ۍ܂����ނ悤�Ɍ����܂������A2��ނ̃l�u���C�U�[�����Ȃ����܂̖��O���o���ċA���ɒ��ׂ܂�����A2��ނ̂�����1���A�����M�[��}��������̂ł��B
�@
�@����̃l�u���C�U�[�̎��ɁA�A�����M�[���t�����������Ƌ����\���o�܂����B�h�N�^�[�͏a���Ă܂������E�E�E
�@
�@���t�������ċ����܂����E�E�B
�@
�@���ԕ���200�i�N���X�U�j�Əo���̂ł��I���̐��l�͌��o���E�l���z���Ă��鎖���Ӗ�����̂ł��傤�E�E�O��6.47�i�N���X�Q�j�ŏ����A�����M�[������܂��E�E���N�̏t���3�����ȏ㑱�������M�͕��ׂł͂Ȃ��A���ԕ��ɂ��A�����M�[�����������̂ł��B
�@
�@����ȗ��A�A���ɂ��Ȃ��Ă�����A�A�����M�[��}�����i�I�m���A�܂��̓W�F�l���b�N�̃v�������J�X�g�j�����ނ��ƂŁA�A�̎��͏o�Ȃ��Ȃ�܂����E�E�E�������ł͂Ȃ��A�I�m�������ނ悤�ɂȂ���2017�N(����29�N)6���ȍ~�t�@�\�̈��������܂�悤�ȌX�����o�Ă����悤�Ɏv����̂ł��E�E�O�y�[�W�̃A�����M�[�����\�̓��t�ƁA�ŏI�y�[�W�̕\���ׂĂ����������E�E2017�N�̌㔼����1/CR�������I�ȗl�q�ɂȂ��Ă���悤�Ɏv���܂��E�E�E
�@
�@���t��ɝG������炷�l��@�����o��l�͈�x�A�����M�[�̌��t���������Ă݂܂��H.�ی��K���Ō��������܂��B
�@
�����A�����M�[�ŝG������炷�A�Ƃ����̂�IgE�R�̂������炵���ł����AIgA�t�ǂ̍R�̂Ƃ͌Z��̂悤�ȊW�ƌ����Ă��܂��̂ŁAIgA�R�̂��t���ɒ������邱�Ƃ������Ȃ�AIgE�R�̂������悤�Ȃ��Ƃ��N���Ă���\��������̂ł͂Ȃ��ł��傤���E�E�����A�ǂ�����G������炷�Ƃ����_�ł͋��ʂ��Ă��܂��B�����͂ǂ�����A�A�����M�[��}�����p���邱�ƂŝG�������Ȃ��Ȃ邱�Ƃ͐g�̂ɂƂ��ėǂ����Ƃł����A���Ԃ�t���ɂƂ��Ă��ǂ����ƂȂ̂ł́E�E�O�O
�@�@
 �@8-5�@�@�֔��@
�@8-5�@�@�֔��@�E�E�E�ő��A�}�b�V�����[���ŁA���ցB�E�ECKD�ۑ����̍ŏI�X�e�[�W�ł͊����Y�p���A�����̓őf���z�����鎡�Â��s���Ă��܂��B����ԂɃI���[�u�I�C���������P�t�����݁A���ނȂǂ̐H���@�ۂ�H�ׂ�ƈ�ʓI�ɕ֒ʂ��ǂ��Ȃ�Ǝv���܂��B���͐��̒ő����Z�Ŗ���45���̒ő���H�ׂ�悤�ɂ��Ă��܂��B
�@
�@�ő��͐��ő��ł������ł����A���ő��ł������ł��B���ő��̏ꍇ�͐��Ɉ�ӐZ���Ė߂��A���������Ďϕ����āA��܂��či���ď��������āA�Ⓚ���Ă����āA���H�̗����ɍ����ĐH�ׂ܂����A���s�p�ɂ͎ϕ���ɍ����������ĊÂ��ϋl�߁A�r�ɋl�߂ė①���Ă����A1��60g�̌v�Z�ŏ��r�ɋl�ߒ����Ď����čs���܂��B
�܂��A�①�ɂɓ��ꂽ�甒������悤�ȗǎ��ȃI���[�u�I�C�����A�������A�����[�ɏ���1�t���ށA�Ƃ����̂����ʂ�����Ǝv���܂��B�I�C���̎h���Ə������\�����ʂ����銴�������܂��B�@
�@
�@�ނ��֔�ǂŃ}�O�l�V�E�������ޕ��ɂ̓L�m�R��I�C���Ƃ��������ԗÖ@�͌��ʂ��シ���邩���m��܂���E�E�C�O�̃z�e���̃r���b�t�F���H�ŋ����̂́A�����ʂ̔��������}�b�V�����[�����������Ԃ��Ƃł��E�E�����A�`���I�ȕ֔���Ɛ������܂����O�O
�@
�@�r�[���y�ꂩ����u�킩���Ɓv��u�G�r�I�X�v�ɂ��������ʂ�����Ǝv���Ă��܂��B�ꏏ�ɐH���@�ۂ�ۂ�Ɨǂ��ƌ����Ă��܂����A���Ȃ�K�X���o�܂��ˁE�E���̃K�X������従��^�����h�����Ă���悤�Ȋ��������܂��E�E�^���N���j�b�N�ł͍d���܂̓����Ă��Ȃ�������G�r�I�X������߂Ă��܂��B
�@
���̕�����������ŔO�̂��߂Ƀl�b�g������������A�Ȃ�ƕ֔邪CKD������������A�Ƃ���������w�I�b��ɂȂ��Ă��܂����B�֔邪���ǂ������A��������őf���i�����A�t����������Ƃ������ł��B
�@
�X�ɓ��k��w�ł́A���������ŁA�֔�̉��P��i���r�v���X�g���j�Œ����������P���邱�ƂŔA�őf�����ǂ��畳�ւƂ��Ĕr�o����A�t�@�\�����P����A�Ƃ����������ʂŏo�Ă���悤�ł��B�@���ꂪ�l�ɂ����Ă͂܂�Ȃ疾�邢�j���[�X�ł��B
�@
�@���u���������P�ɂ��t���a���Ö�̊J��/�֔�ǂ̎��Ö����t���a�̎��Ö�ɂȂ�\���v�i���k��w�j�E�E�E�A�őf�̔r�o�o�H�́A�]���@�t������A�@�A�l�H���͂ŏ����A�����Ȃ��������A��B�̔r�o�o�H�Ƃ��Ē��ǂ��畳�ւƂ��Ĕr�o�ł���\�����o�Ă����B�i�����E���O�����\���ς݁j
�@
�@
�@
�@
������ȊO�ɂ��F�X�b��ɂȂ��Ă��܂��B�uCKD �@�֔�v�Ō������Ă݂ĉ������B
�@
�@8-6�@�@�S�ẴT�v�������g���~�߂��@
�@�T�v�������g�͈��i�łȂ����߁A����p�Ȃǂ̍��̐R�����Ă��܂���B���Y�҂��A���̃T�v�������g���t�@�\�ɉe�����Ȃ����A�܂ł͏ڂ������ׂĂȂ���������܂���B�]���āA�t���ɂƂ��ėL�Q�Ȑ������܂܂�Ă���\������ɐS�z����܂��B��������h�{�f���s�����Ă��Ė��ɂȂ��Ă��鎞�͈�t����Ƃ��ďo���Ă���邱�Ƃł��傤�B�T�v�������g�������ŋ}���t���ɂȂ鎖�͌����ċH�ł͂���܂���B
�@
�E�E�E�Ō�̕��ɃT�v���Ɋւ��钍�ӂ�����܂�
�@
�@8-7�@�@�y���^�����n�߂�@
�E�E�K�x�ȉ^���͐t���w��ł��ȑO���琄�����Ă��܂����A�ł����₷�����@�͗L�_�f�^���ƂȂ�u�E�H�[�L���O�v���Ǝv���܂��B�^����CKD���҂ɗL�v�Ȃ��Ƃ́u���{�t�����n�r���w��v���[�֒��ł��B �t�����n�r���e�[�V�����̎�������l�b�g�ォ��_�E�����[�h�ł��܂��B
�@
�@�ŋ߁u�t���a�͉^���ŗǂ��Ȃ�v�ƌ����т����肷��\��̖{���l�b�g�Ō����A�������Ă��܂��܂������A�^���Őt���a�����P����ƌ�����m�ł���f�[�^�͎��ɂ͌������܂���ł����B

�@�������K�x�ȉ^����CKD���҂́u�̗͈ێ��v�Ƃ����ϓ_���琄������邱�Ƃ́A�K�x�ł���Γ��R���Ǝv���܂��B
�@
�@
���u�t�����n�r���v�i�^���Ö@�j�̎�����_�E�����[�h
�@
�@8-8�@�@�������ʂ̈��艻�̍H�v
�E�E�������ʂ��ǂ������舫��������ň���J���܂����A�������̏��Ȃ������l�ɂȂ�悤�ɂ���ׂɂ́A�����O1�T�ԐH���Ɖ^���ʂ������ɂȂ�悤��������̂ł͂Ȃ����A�Ǝv���܂��B
�@
�@�N���A�`�j���iCr�D�j�͋ؓ����g�����Ƃŋؓ����猌�t���ɕ��o�����V�p���Ȃ̂ŁA���f�̑O3���Ԃ͌������^�����T���A�Ȃ�ׂ����Â�ۂ��A�܂��H�ו��������O1�T�Ԃ͊O�H���T���A����̌��������������Ō}����ACr.�l�Ȃǂ̐��l�̗�����������A�����͈��肷��̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă��܂��B
�@
�������̕����A�����O���ɂ�������J����^���������̂ɐ����⋋���\���łȂ��ƁA�g�̂͌y���E����ԂɂȂ��Ă��邩������܂���B�E����ԂŌ��t���Z�k����Ă���A�N���A�`�j���Z�x�������͂��ł��B�ƂȂ�Ό���Cr.�l���㏸���邱�ƂɂȂ�ł��傤�B
�@
�@���Ƃ���A�������̌��t���̐����ʂ���ɂł���A�������ʂ����肷��̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��E�E�����Ƃ����t���̐����ʁi���t�ʂ�Na.�Z�x�j�����ɂ���d���͔]�̍ŏd�v�̎d���ł��̂ŁA�l������������ƌ����āA�����ȒP�ɂ͌��t�ʂ͑��₹�Ȃ��ł��傤�E�E
�@
�����R���ނ��A���t���̃i�g���E���Z�x�������邽�߁A���t�ʂ��\������A�]�͐t���ɗ��A�𑣂��Đ����ʂ����炵�܂��B�����̐��������Ȃ��Ȃ�A�����i�g���E���Z�x�������Ȃ��Ă���ƁA���x�͗��A���Ȃ��悤�ɍR���A�z�������iADH�Fantidiuretic�@hormone�j���o���ė��A���������A�����ɍA���������o��^���܂��E�E�̂ɂƂ��ĉ��������������̂͌��t�ʂ��K�v�ʂ�茸�����邱�Ƃł��̂ŁANa�Z�x���]���ɂ��Ăł����̌��t�ʂ����炵�悤�Ƃ���E�E�Ƃ������Ƃł��E�E�B
�@
���̂��Ƃ�Cr.�l�̖ʂ��猩��ƁE�E
������ۂ���A����Na.�Z�x�����܂�A�]��ADH���߂ŗ��A��}����Ƌ��ɍA�̊�����^���A�l�͐������ނ��Ƃ�Na�Z�x�͈��肵�܂����A���t�ʂ͑�����̂ŁACr.�l�͑�����������ł��傤�E�E�Ȃ̂ŁA������6g�������ŁA���߂ɐۂ��������A�����͏オ��܂����ACr.�l�͉�����X���ɂ���Ǝv���܂��E�E
�@
�E�E�E���āA�ꌩCr.�l�������������̂悤�Ɍ����邱�ƂƁA�������オ���Ă��܂����ƂƂ�V���ɂ��������ǂ������邩�ł��ˁE�E�E
�@
�E�E�������オ��ΒZ���I�ɂ�Cr.�l�͉��P���邩���m��܂��A�t���̏��݂͑����Ȃ邱�Ƃ͑z���ɓ�Ȃ��ł��傤�E�E���Ƃ��ƁA�g�̂��t�@�\�������Ă��āA�����̂��ǂ�ǂ���ł���ƁA�������グ�Ď����̂��h�ߗʂ𑝂₻���Ƃ��Ă��܂��E�E
�@
���̌��ʂ͎����̂̍X�Ȃ鑹���Ƃ������z�Ɋׂ�킯�ł����A�����͈̂��z�ɂȂ��Ă��A�h�ߗʂ��m�ۂ�������ɓ����ƌ��������́E�E�u���ʂ܂ł͊撣��v�E�E�Ƃ����l�̂̐v�̊�{���j�Ȃ̂ł��傤�E�E
�@
�@�������������Ƃ����t���a�E�E�t�d���ǂ̎��Â͌����������邱�Ƃ����I���ƌ����Ă��܂��B������������ΐt�@�\�͏��������܂��iCr.�l�͏��������Ȃ�܂��j���t���͒���������E�E�Ƃ������Ƃł��傤�E�E
�@
�t�ɉ����ێ�ʂ����Ȃ����A���̋t�̂��Ƃ��N���āA���t�ʂ͎��������ׁACr.�l�͏オ�邱�Ƃł��傤�E�E���ɂ�����邽�߁A���t�ʂ͈��ȏ�ɂ͌������܂���B��Na.
���NjC���̏�Ԃł����琅������ł��A�����͂����A�ƂȂ�ACr.�l�͉�����Ȃ��ł��傤�E�E���̏ꍇ�́A�����ێ������������Ƒ��₵�āA1��3g�ł���Ă���l�́A�����グ��1��3.5���ʂ��Œ�C���ɂ��������ǂ������m��܂���E�E
�@
�@�Z���I�ɂ́A�t�@�\�Ƃ͊W�Ȃ��ACr.�l�͂�����x�͐l�דI�ɃR���g���[���ł��邩������܂��A��ÓI�ɂ́A����ȃR���g���[���͖��Ӗ��Ȏ����Ǝv���܂��E�E�����A�����������Ƃ�CKD���҂ɂƂ��ẮA���̗V�т̂悤�Ȃ��̂ŁE�E����������������ł݂���A���Ȃ����Ă݂���A�����͉����ێ�ʂ�ς��āA�������ʂ��ǂ��ς�邩���ׂ�V�т́E�E������������CKD�̗����ɖ𗧂�������܂���E�E�E
......................................................................................................................................................................................
�@
�@�����ێ�ʂ����Ȃ������(���t�̐Z������������̂�)�]�̒��ɐ��������邱�Ƃ�����܂��B�����Ȃ�ƁA�����A�z���A�������N���邩���m��܂���E�E�����Ǘ��͖��f���Ȃ��悤�ɋC�����������̂ł��E�E�������Ȃ��č����ƁA�������č������ɂ��]�����E�E����͂ǂ�������������ł����A腖��剤�ɂǂ��炩�I�ׂƌ���ꂽ��E�E�E�]�����œV���s�������͑I�Ԃ��ȁO�O
...............................................................................�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�����������̐g�̂̏�Ԃ𐳏�ȏ�ԁi�E�����N���Ă��Ȃ���ԁj�ɂ��邽�߂ɁA����������ێ�ʂ��R�`�U�i��/���j�ۂ�A�������O���͏\��������ۂ�A�������^�����T���E�E�����Č����������̒�������傫�߂̃R�b�v��t���x���߂ΐg�̂͒E����Ԃɂ͂Ȃ�Ȃ��ł��傤�B
�@�g�̂��E���C���̎��A���������������t��������N���A�`�j���Z�x�͐����Ŕ��܂�̂�Cr.�l�͂��̕��ǂ��Ȃ锤�ł��ˁE�E�i���ɒE����Ԃ̎��ɁA����200cc����ŁA�������t�ʂ�200cc�߂��������Ȃ�A���t�ʂ͖�4000cc�Ȃ̂łT�����x���t�������A�N���A�`�j���Z�x�͂T�����܂�Cr.�l���T�����x�ǂ��ł�Ȃ�͂��ł��E�ECr.��2.0�̐l��1.95�Əo�邩������܂���E�E�j
�@
�@�����A�����������Ƃ͈ꎞ�I�ł���A�t�@�\�����P�����킯�ł͂Ȃ��ł����A���������̑̂̒E����h�~���邱�ƂŁA�����̌����l�����肷��Ƃ����琸�_�I�ɂ͗ǂ����Ƃ��Ǝv���܂��E�E
�@
�i���j�������̒��̃R�b�v1�t�̐����⋋�́A�����܂Őg�̂��E���̏�Ԃō̌�����邱�Ƃ�h���̂��ړI�ł��B���t�����̖ړI�ɂ���Ă͌����O�̐����݂͈�؋֎~����Ă��邱�Ƃ�����܂��q����H�r�A���̏ꍇ�͓������͐������߂Ȃ��ƌ������ƂɂȂ�܂��ˁE�E���X�O���ɂ������萅���⋋�����܂��傤�E�E
�@
�@8-9�@�@�C�O��CKD�����Q�l�ɂ���
�@���{�ł͖{��l�b�g��̏��͐t���w��̃K�C�h���C���Ŏ����ꂽ�͈͓������̖���ȋL�q�������ł��B���͈̔͂����l�I�Ȏ咣�荞�����͋ɂ߂ď��Ȃ��Ɗ����Ă��܂��E�E
�@�@
�@�C�O�ł���{�͖w�Ǔ��������ł����A���̍��̐H�ו���K���̈Ⴂ�Ƃ��ŁA�L�q�̓��e�ɂ͂��������������邱�Ƃ�����܂��B�Ⴆ�Γ��H�̍��ł͒`�����������Ɋɂ����Ƃ�����܂��B���̑���A�����A�J���E���A�����̐����͏�����Ă��܂��B�����𐧌�����Ƃ������͓����i����A���Ȃǒ`�����������Ɛ�������邱�ƂɂȂ�܂��B���т�H�ׂȂ����Ăł̓V���A�����`���p�X�^�Ƃ���`���p���Ȃǂ���H�ƂȂ�A���ʂ̓��Ɠ��ނɖ�T���_��Y���ĐH�ׂĂ�悤�ł��B
�@
�@�I�����Ƃ����_�ł͓��{�͘a�H����A�m�H����̑����АH�ł��̂őI�������L���Ǝv���܂��B������j���[�̎�ނ������ƌ������Ƃ́A�H�������������ł͌v�Z����ςŁA����܂��B�F����s�m�̂悤�Ƀ`���[�u�ɓ������h�{�H�����߂���Ŋ����I�Ƃ����̂����C�Ȃ��ł����A�����ȐH���������������قǁA�H���̓��e�͗����ƌ������h�{�d���̑f�ނ̏o���̂͂����肵�����j���ɂȂ��Ă��܂��B
�@
�@�Ⴆ�A�����A�u��H�̍����A���Ƌ��Ɠ��ށA�����i�A�ʎq�A��A�ʕ��v�E�E����͈�ʉƒ�ł͂悭�H�ׂ镨�ł��傤�E�E�Ƃ���ƁA��̐H�ׂ�H�ނ͌��܂��Ă��Ă��܂��܂��E�E���̂悤�Ȓj�����̃��j���́A�ǂ��݂Ă������Ƃ͂قlj����A�P�ɉh�{�̂͂����肵���������X�ɕ��ׂ邾���E�E�E�Ƃ����E���Ƃ��������ɂȂ��Ă��܂��܂��E�E��͂�F����s�m�̐H���ɂǂ����ʂ������ɂȂ��Ă��܂��܂��ˁO�O
�@
�@�č��̐t���L�����y�[���́u�t�ڐA�v���ő�̃e�[�}�ɂ��Ă���悤�Ɏv���܂��B�č��Őt���ڐA�������̂́A���{�ƈႢ���l����̌��t��F�߂Ă���Ƃ������Ƃ����邩������܂���E�E���l�̑���ƂȂ�Ƒ��프���Ƃ������œ��{�ł͂܂��������ɂ��蓾�Ȃ����Ƃł��傤�E
�@���߂Č��t�ȂǑ���̗L���̈ӎv�\����Ƌ����ɋL�ڂ��邱�Ƃ��u�Ƌ���t�̏����v�ɂł���A���{���傫���ς��悤�Ɏv���̂ł����E�E�E
�@
���C�O�ŃT�C�g
�@
�@
�@
�@
�@
�@
����ł́A�H����5�̗v�f�ɕ����A���ꂼ��̗ʁi�����ڂ̑̐ρj��傴���ςɎ�����
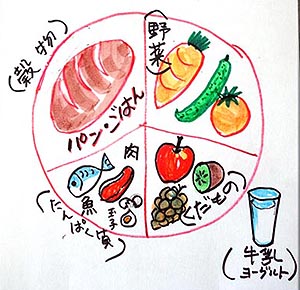
���܂��B
�@
�P�D�����E�E�p���A���сA�V���A�����E�E�M�̂R�O��
�Q�D�`�����E�E�ʎq�A���A���A���ȂǁE�E�M�̂Q�O��
�R�D��E�E�E�S�Ă̖�ؗށE�E�E�E�E�E�M�̂R�O��
�S�D�ʕ��E�E�E�S�Ẳʕ��E�E�E�E�E�E�E�M�̂Q�O��
�@�@�@�@ +
�T�D�����i�E�E�ᎉ�b�����A���[�O���g�E�E�J�b�v1�t
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@
���������ƁA�����A��A�ʕ��ł��M�̂W�O�����߂Ă��鎖�ɋ����܂��E�E
�@
�@8-10�@���̌����̑�����̍H�v�@
�@���̌�������͋N����1���Ԉȓ��ɑ��邱�ƁA�ƂȂ��Ă��܂��B����͑����Ɍ������オ���Ĕ]�����ɂȂ�l����������ł��傤�E�E�B
�@
�@��ʂɏA�Q���͂�����������������A�N����ɂ́A�A�Q���ɉ�������������߂����߂ƁA�N���ɂ��n����h�����ߌ����͈�U���파�����������オ��A���̌�A���X�ɉ������Ĉ��肷��p�^�[���̐l�������Ǝv���܂��B
�@
�������������̌��������Ԃ̌o�߂Ƌ��ɕϓ�����l�̏ꍇ�́A�N���㉽����ɑ��邩�����߂����������͈��肷��Ǝv���܂��B���̏ꍇ�͋N����30����(�N����1���Ԉȓ��̒����l)�Ɍ����𑪂�悤�ɂ��Ă��܂��B
�@
�����̑��������̕ω�(����v�ł̑���)
�@�P�D�ڊo�߂�����́A�Q����Ԃł̌����E�E�E�P�Q�W�^�W�O�^�U�O
�@�Q�D�Q�����痧���オ��������̌����E�E�E�E�E�P�T�U�^�W�V�^�W�O
�@�R�D�N��30����i�֎q�ɍ�����10����̌����j�E�E�P�Q�O�^�V�S�^�U�T
�@�S�D�N��1���Ԍ�i�֎q�ɍ�����40����̌����j�E�E�P�P�X�^�V�U�^�U�W
�i ���̏ꍇ�A�A�����W�s���ȂǃJ���V�E���h�R������ނƁA�������N�����ォ�猌���͂قڕ��파���ɂȂ�܂��B�j
�@
�������v�̎�ނƓ����E�E��{�I�ɐS���ɋ߂����𑪂�قǐ��x�������Ȃ�͂��ł��E�E��r�������������̂͐S���ɋ߂��A�S���Ɠ�������������ł��傤�E�E
�P�D
����v�i�ʐ^�E�E�j�E�E��������ԁA��������ԁA�Q����ԁA����̌����ȂǗl

�X�Ȍ������ȒP�ɑ����B�~�G�Œ�����Ԃł������܂���K�v���Ȃ��̂ŁA��O�I�Ɏ��������v�������m�ɑ���邩���m��Ȃ����A��ʘ_�Ƃ��ẮA��r�ł̑���̕����M������Ă��܂��B����v�́A���e�̉��ɓ����Ȃǂ��āA�����v���S���̍����ɂȂ�悤�ɂ��đ���K�v������܂��B
�@
2�D���������v�i�ʐ^���j�E�E�ŋ߂͉ƒ�p�Ƃ��Ă����y���Ă��Ă���悤�Ɏv���܂��B�����r�����邾���Ȃ̂ŁA���삪�ȒP�Ȃ̂������ł��ˁE�E
�@
�R�D��r�J�t�������i�ʐ^�����j�E�E�̂��炠��^�C�v�ł��E�E�~�ȂǂɌ���������Ԃł͑���ɂ����ł��B
�@
�@8�|11�@ ���ʂȑ̗͎͂g��Ȃ��@
�@�g����͋x�e����i�ł���Ή��ɂȂ��Ė{�ł��ǂށj�E�E
�̂���CKD�ɂƂ��ĉ^���͗ǂ��Ȃ��E�E�ƌ����l����������܂��E�E�����Ԃ̗͎d����A�K���ɑ������肷��^���͖��_�f�^���ł�����A���t�͋ؓ��̕��ɑ�ʂɑ����A�t���ւ̌������傫���ቺ����ƌ����Ă��܂��B
�@
�@�Ȃ̂ŃY�[�Ƌx�ݖ����d�J���𑱂���A�t���͌����s���Ń_���[�W���邱�Ƃ��낤�ƌ������Ƃł��ˁE�E���̍l�������ԈႢ�Ƃ͌�����ł����A������Ƃ����Ĉ�����Q���ɉ��ɂȂ�K����������A�g�̂͐����A�V���i���s�̌��t�ł̓t���C��/frail/����j�����Ă��܂��܂��B�X�N���b�g��r���ĕ����Ȃǂ̋g�����h�����̂ł�����A���l���y���߂��ł͂Ȃ��Ǝv���܂��B�y�����ĉ^���ɂȂ鉽����������Ƃ����̂ł����E�E���̏ꍇ�͍ŋ߂͐��ꂽ��30���E�H�[�L���O�A�J���~������y���싅��1��30�����Ă��܂��E�E
�@8-12�@�@�������̐������Ƃ�
�E�ECKD���҂��C��t���Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ̈�͒E���ɂȂ�Ȃ����Ƃł��傤�E�E���̏ꍇ�́A�|�b�g�ɋɔ����g�������āA1�������đS������ł܂��E�E���݂̃��j���ł͖�1500cc�̔������I����̍g�����ӂ̐H������10���A3����1���T��ɕ����Ĉ���ł��܂����A1���300cc�ɂȂ�܂��B
�@�~���N�e�B�[�Ƃ��A���̂�������Ȃ�300cc���炢�ȒP�Ɉ��߂܂����A���̂Ȃ������g����280cc�A���َq���Ȃ����ނ̂͌��\��ςȂ̂ŁA10����3���̍g���ɂ̓N���[�v�����������1�t�Ɗp����1�������A���݂�1���H���Ă��܂��B�B
�@
�@1���Ɉ��ސ��ʂ́A�厡��̌��t����́A�A�ʖ�1500cc���K���Ƃ̂��Ƃł��̂ŁA�����Ȃ�悤�ɂ����̗ʂ��������Ă��܂��B�����̓K���A�ʂ͎厡��Ƒ��k���ꂽ��ǂ��Ǝv���܂��B
�@�@�@�@
�@8-13�@�@�����������n�߂�@�E�E���N�O�ɓ��������Ŏ�������t�ۂ������߂��A�E���ɔ�������������悤�ɂȂ蓮���d�����S�z�ɂȂ��āA�S�N�قǑO�ɓ����d������Ƃ���v���Ďs�́u�^���N���j�b�N�v����f���Ă݂܂����B�^����t�́A�����\�G�R�[�Ō��ǂ̒f�ʂ��f���o���A���Ǔ����̃v���[�N�ʂ𐔒l���肷��A�Ƃ����X�y�V�����X�g�ł����A�v���[�N�����炷�ɂ͎�������������K�v������Ƃ��������咣���Ă��܂��B
�@�@
�@�@�����d���̎���̓v���[�N�ł���A�v���[�N�����点�Ό��t�̏z���ǂ��Ȃ�A������������A�t�@�\��������x�ł������P����A�ƌ������Ƃł����B���̖����t���a�̌����́u�{�Ԑ��������v�ƌ������ƂɂȂ��Ă��܂����A�u�{�Ԑ��v�Ƃ́A�u�����s���v�ƌ������Ƃ炵���ł��B�������オ�闝�R�����������ɕs�����ĕs�v�c�ł��E�E�E
�@
�@�@�^����t�́u�v���[�N�Ō��ǂ������Ȃ邱�Ƃ��������̌����ł��v�Ƃ̃V���v���Ȑ����͑f�l�ɂ�������₷���A�����͂��L��Ǝv���܂����B�����ŁA���͓������������]���Đ^�t�̎����������n�߂Ă݂邱�Ƃɂ��܂����B
�@
�@���������́A�ȒP�Ɍ����ƁA���ǂ̃v���[�N�����炷�H���ɂ���ƌ������Ƃł����A��̓I�ɂ́A�����̐H���ŁA���̎��g��o�^�[�ȂnjŌ`���i�O�a���b�_�j�̐ێ����߂�A�����͌��炷�A�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�g�̂̌��ǂ̕���_(�O���H)�Ȃǂł͌��t�̗������N���A���Ǖǂ������₷���A�������������玉���iLDL�R���X�e���[���j�����荞��Ńv���[�N�ƂȂ邽�߂Ɍ��ǂ������Ȃ�A�Ƃ����������C���[�W�Ƃ��Ă͕�����₷���Ǝv���܂��B�@
�@�@
�@�@�^���N���j�b�N�Ő���������EPA���܂ł��BEPA�̃T�v�������g�͐V���`���V��e���r��CM�Ő���ɐ�`����Ă��܂����A���Ö�Ƃ��ĔF���ꂽEPA���܁i�G�p�f�[��900�A�Ⴕ���͂��̃W�F�l���b�N�j�p���܂��B1�܂ɗ����EPA��900mg�܂�ł��܂��B���[���p���܂��B
�@
�@����������EPA���܂����ݏo���Đg�̂ɋN�����傫�ȕω��́A�Y�܂���Ă������̎��ӂ̓�������̔��������Ȃ��Ȃ������ƂƁA�~���܂炭����ł�������Ȃ������g����������90�䁨70��ɉ����������Ƃł����A���ꂪEPA�̂��A���ǂ����͕�����܂���E�E�B
�@
���@�V���͌��ǂ���(�c��`�m��w)
�@
�@
8-14�@�K�{�A�~�m�_�������ꂽ�H�����n�߂�
����芮�S�Ȓ`���������̃��j�����l����ƁA�l�����ۂɉh�{�Ƃ��ė��p����̂́A�H�ׂ��H�i���̒`�����i���q�ʂ��傫���j�����ڐg�̂ɋz������邱�Ƃ͂ł����A���ň�U���q�ʂ̏����ȃA�~�m�_�ɕ�������ď��߂Đg�̂ɋz�������B�g�̂ɓ������A�~�m�_�͐g�̂����`�����ɍč��������d�g�݂Ȃ̂ŁA�H�i���̒`�����Ƃ����l�������A��蒼�ړI�ȕK�{�A�~�m�_�̊ܗL�ʂ��猣�����l��������A��萳�m�Ȃ̂ł͂Ȃ����Ǝv�������A�K�{�A�~�m�_�������ꂽ�H���̌������n�߂܂����B�@
�@
�@8-14�|�P�@�@�K�{�A�~�m�_���烁�j�����l����@
�܂��͉��L�̃T�C�g�������������B�`�������������ŕK�{�A�~�m�_�̏d�含����������ɂȂ�Ǝv���܂�
�@
�@
����t�E�R���f�B�J���̂��߂̖����t���a�@�����E�H���w���}�j���A���i���{�t���w��j
���PDF��52�y�[�W�ɁA�K�{�A�~�m�_�̐ۂ���̒��ӓ_�i���p�����A�~�m�_�A���ʂɂȂ�A�~�m�_�j����ϕ�����₷���A�����ɂ͌����Ȃ����m�Ȑ}�����������Ă��܂��B
�@
��̊e�T�C�g�ɏo�Ă���u�`�����̉��v�ŕ�����悤�ɁA�`�����Ɋ܂܂��9��ނ̕K�{�A�~�m�_���ߕs�������ۂ邱�Ƃ���ł����A�]���̂b�j�c�̐H�����{�ɂ͕K�{�A�~�m�_���v�Z�ɓ��ꂽ���j���Ƃ������̂͌�������܂���B
�@���Ȃ��l�߂��`�����������邤���ŁA�K�{�A�~�m�_�̊T�O�������ꂸ�ɁA�P�ɒ`�����̗ʂ������炷���Ƃ͊댯���Ƃ������Ƃ��A���ɂ��̌��㕪�����Ă��܂����B
�@�K�{�A�~�m�_�̐ێ悪�K�v�ʂ�菭�Ȃ��̂͘_�O�ł����A�K�v�ȗʂ�葽�����镔���́A����ς����̍����ɕK�v��9��̕K�{�A�~�m�_���S�đ����Ă���A�畆������ق��܂�E��A100��ނɋy�Ԋe��z�������ȂǂɎ���܂ŗ��p�ł���̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂����A�E�E���������ĂȂ��ߏ�ȕ����ŒP�Ƃŗ��p����Ȃ������A�~�m�_�́A�ŏI�I�ɂ̓J�����[�Ƃ��đ�Ӂi�R�āj����A���̔R���J�X�ł���A�f���f�͐t�����炵���r�o�ł��Ȃ����ߐt���ɕ��S���|���邱�ƂɂȂ�܂��B
�@
�@�K�{�A�~�m�_���ǂ̒��x�ۂ����炢���̂��Ƃ������Ƃł����AWHO���u�����K�{�A�~�m�_�ێ�ʁv���߂Ă��܂��B��{�I�ɂ͑̏d1kg������̕K�{�A�~�m�_�ʂɎ����̑̏d���|�����ʂ�ۂ�Ηǂ��̂ł����A�ʂ����Ă���ŏ\�����͋^�₪�c��܂��B�܂��A�g�̂��ǂ̒��x�z���ł��邩�͌l��������Ǝv���܂����A�����z���̋ɒ[�Ɉ����l�����܂��B�܂��V�R�̐H�i�̐����́A������G�߁A�̂ꂽ�ꏊ�A�Ȃǂɂ���Ă��Ȃ�̃o���c�L������͂��ł��B����Ɏϕ��Ȃǂ̂悤�ɐ��m�Ȑ�����������Ȃ���������܂��B
�@
�@
�@�̏d1kg������̐ێ搄���ʂ��ڂ��Ă��܂��B�@�����AWHO���������Ă���̂ł����A���̗ʂ����ۂ�Ηǂ��ƁA���l�ɐ����ł���ʂƂ͎v���܂���E�E�����̌o������A���̗ʂł͏��Ȃ��Ƃ�CKD���҂ɂƂ��Ă͕s������Ǝv���Ă��܂��B���������ʂ�100���@�y��120���ۂ��Ă����Ƃ��ɂ͎������Ȃǂ����ǂ��܂����B�Q�ĂĐ����ʂ�150���Ŏb�����܂������A������Ƒ������銴���������ׁA���݂͐����ʂ�140���ɂ��Ă��܂��B�N���A�`�j���l�͖w�Ǖς��܂��A�̒��͗ǂ��ł��B140���ێ�ŁA�]���̂���ς������Z��0.64g/kg�W���̏d�ɂȂ�܂��B�A�~�m�_�g���ɂ�邽��ς����ʂł�0.57g/kg�̏d�ł��B�@�i�Q�l�܂łɁA120���̏ꍇ�A�]���̂���ς����ʂł́A0.55g/kg�̏d�A�A�~�m�_�g���ɂ�邽��ς����ʂł�0.47g/kg�̏d�ŁA�t���w���������0.6�`0.8g/kg�̏d�����ɂȂ�܂����B�j
�@
���́u�����ێ�ʁv�́g�ێ�h�Ƃ������t�E�E�h�ہh�͂Ƃ邱�ƁE�E�܂�H�ׂ鎖�ł��B�ێ�́h��h�́h�Ƃ�A�����̂��̂ɂ���C�Ƃ����Ӗ��ŁA�܂�ێ�Ƃ͐H�ׂĎ����̂��̂ɂ��邱�ƁE�E�ƂȂ�܂��B
�@
�@�����z���̈����l�E�E�Ⴆ�Ώ����z����70���̐l�́A100�H�ׂĂ�70���������̂��̂ɂł��Ȃ����Ƃł��傤�E�E�B�܂萄���ێ�ʂƂ́A�g�̂��z�����ׂ������ʂƌ������ƂɂȂ�܂��E�E�Ȃ̂ŁA�����z�����V�O���̐l�́A������100�����ɂ́A100÷0.7��143�E�E143�ۂ�Ȃ���100���ɂȂ�Ȃ��Ƃ��������ƂɂȂ�܂��B����A������Ƃ����ӓ_�ł��ˁE�E�E
�@
�@�t���w��̋K�肷��A����ς����ێ��0.6�`0.8/kg�W���̏d�E�E���āA�Ђ���Ƃ��āA�H�ׂȂ���Ȃ�Ȃ��ʂł͂Ȃ��A�z�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��ʂȂ̂ł͂Ȃ��ł��傤���E�E�H����͑傫�Ȗ��ł��E�E
�@
�t���w��̕��̖���24���Ԓ~�A�ŔA�̔A�f���f�iBUN�j�̒�ʌ���������A���ۂɒ`������g�H�ׂ�����������܂��E�E�E���̂��Ƃ�����A�ێ�Ƃ͐H�ׂ��ʂł͂Ȃ��A�g�̂��z�������ʂ��Ƃ������Ƃ�������܂��ˁE�E
�@
(�NjL)����ς����̏������₷���A���ɂ����A�Ƃ������̂��傫�ȈӖ������̂ł͂Ȃ����ƁA�����^��Ō������܂�����A�����̓������ς����A�A�~�m�_������ƌ������Ƃ���E�E�E�l�������ł�����x�����������V�����K�{�A�~�m�_�̕]����Ƃ���DIAAS�@�i Digestible Indispensable Amino Acid Score�F�����\�ȕK�{�A�~�m�_�X�R�A�j�Ƃ����̂��ŋߒ��ڂ������ƌ������Ƃ�m��܂����B���Ȃ�ȑO�����Ă���Ă��邱�Ƃ̂悤�ł����A����Ɏ������Ȃ��̂́A�����z���̗ǂ���\�ʂɏo���ƁA��������A�Տ������̔���̓�������邱�ƂȂ���A�����i�ȂǓ������`�������L���ɂȂ�A�A�����`�����̖�⍒�ނ��s���Ȉ�������E�E�Ƃ������Ƃ����邩��ł��傤���E�E�Ƃɂ����A��͂萄���ێ��100�����u�H�ׂ�v�ƌ������Ƃł͑���Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ƃ������̏d�v�����͂����肵�Ă����悤�Ɏv���܂��E�E�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
150���ɑ��₵�����R���A�E�E�E�����ȉh�{�w�̏��̒��ɁACKD���җp�Ǝv����u�`����30g�A�����U���̊�H�v�ƌ����̂������āA������A�~�m�_�g���ɂ��`�����ʂ�1���̉h�{�����\������Ă݂܂��ƁA���W���������ق�WHO�����ʂ�150���ŁA���̑��͐����ʂ�200���O��ɂȂ��Ă����̂ł��B
�i������A�z�������l�ʂ������ʁA�����Ȃ����̂����m��܂���j
�@
�@�h�{�w�̃v�����̃v���������ʂ�150���ȏ�Ń��j�������̂ł�����A������������K���āA150���ł���Ă݂悤�Ǝv�������A���ݎ��s���Ă��܂��B�E�E150������������A�ƌ����\��������܂��B����͍����̌��f���ɕ����邩���m��܂���E�E���t�����ŔA�f���f�i�a�t�m�j��Cr.�A�@Ccr.���������Ă��Ȃ���n�j�ł��B�オ���Ă�����A�Č����ł��E�E�E
�i�Z���Ԃ̃e�X�g�Ȃ̂ŐM�����͂Ȃ��ł����ACr.1.63 ��1.57mg/dl�ɁACcr.��40.1��43.2ml/min/1.73�u�ɉ��P���Ă��܂����I�@�A�f���f�͏����オ����13.5�ł����A�܂��܂��ł��E�E�j
�@
�@�A�f���f�iBUN�j���������̂͒`���ێ�ʂ�1.5�{�ɑ��₵�������ł����A��l�̒����l�t�߂Ȃ̂ŗǂ��Ǝv���܂��ACr.�����P�����̂́A�����O3���Ԃقǂ��ƂȂ������Ă��������ƁA�����ێ�𑝂₵�Č��t�ʂ������Ă����E�ECcr.���P�����̂�Cr.���������������ƁA�~�A���ɍg����������葽������ŁA�A�ʂ����������������邱�Ƃł��傤�E�E���ʂ��ǂ��������߂ɍŏI�y�[�W�̃O���t��V�����܂����B����̌����ł܂����~���Ȃ��悤�Ɋ撣��܂��I�j
�@
���H�i�Ɋ܂܂��K�{�A�~�m�_�̗ʂƃo�����X�E�E���}�̍����̐��l�i0�`200�j�̓A�~�m�_���i�A�~�m�_�X�R�A�Ƃ������܂��j�B�@�A�~�m�_��100�Ƃ͗��z�I�ȃA�~�m�_�ʂ����H�ނł��B����H�ނ�����ς����Ƃ��Đg�̂����p�ł���ʂ́A9��ނ̃A�~�m�_�̒��ōł��A�~�m�_���̒Ⴂ�A�~�m�_�i��ꐧ���A�~�m�_�ƌ����܂��j�̃��x���ɂȂ��Ă��܂��܂��B
�@���p�ł��Ȃ��A�~�m�_�ł��A���̐H�i�ƈꏏ�ɐH�ׂ�A�A�~�m�_�X�R�A100�ɂȂ�\��������܂��B�܂�100���z���Ă��镔���ł���ꐧ���A�~�m�_�̃��x���܂ł͗��p�����\��������܂��B��ꐧ���A�~�m�_�ȏ�̕��͗��p�ł����ɔM(�_�����ĔR��)�ɂȂ��Ă��܂��\��������A���̏ꍇ�A�R������ɔA�f�������Ă��܂��A�t���̕��S�ƂȂ�ƌ����Ă��܂��B
�@
�Â��זE�̓���ւ���E�E�E�@
�E�E�t���̍זE��1�����ł��̂X�O�����V�����זE�Ɠ���ւ��Ƃ���Ă��܂�
�i�Â��זE���V�����זE�Ɠ���ւ�邾���ŁA�c�O�Ȃ��玅���̂�������킯�ł͂Ȃ��悤�ł��j
�@
���l�̂̍זE�X�V���x�iGoogle�j�@�E
�����ł���A�V�����זE�����ɂ́A���̌��ƂȂ�`�����A�A�~�m�_���s�����Ă��Ă͍��܂���E�E�ł���A�`�����ɍ����ł���u�����o�[���������K�{�A�~�m�_�v�͏\���ۂ��������ǂ��̂ł͂Ȃ����Ƃ����C�����ɂȂ�܂��E�E
�@
����ς�����A�~�m�_�Őt���ɕ��S��������ƌ����Ă���̂́A�A�~�m�_��1�g�ɂȂ��Ă���ς����ɍ�������ہA�g�ɂȂ�Ȃ������u�����o�[�̑����Ă��Ȃ��K�{�A�~�m�_�v�A�͔R�₳��A���̔R���J�X�̔A�f���f�������̂�ɂ߂�Ƃ����̂ł�����A�������������A�~�m�_�̉����炠�ӂ�o��u���ӂ�A�~�m�_�v���ŏ����ɂ���E�E�Ƃ������j�����l���邱�Ƃ����z�Ȃ̂ł͂Ȃ����E�E�Ǝv���Ă��܂��B
�@
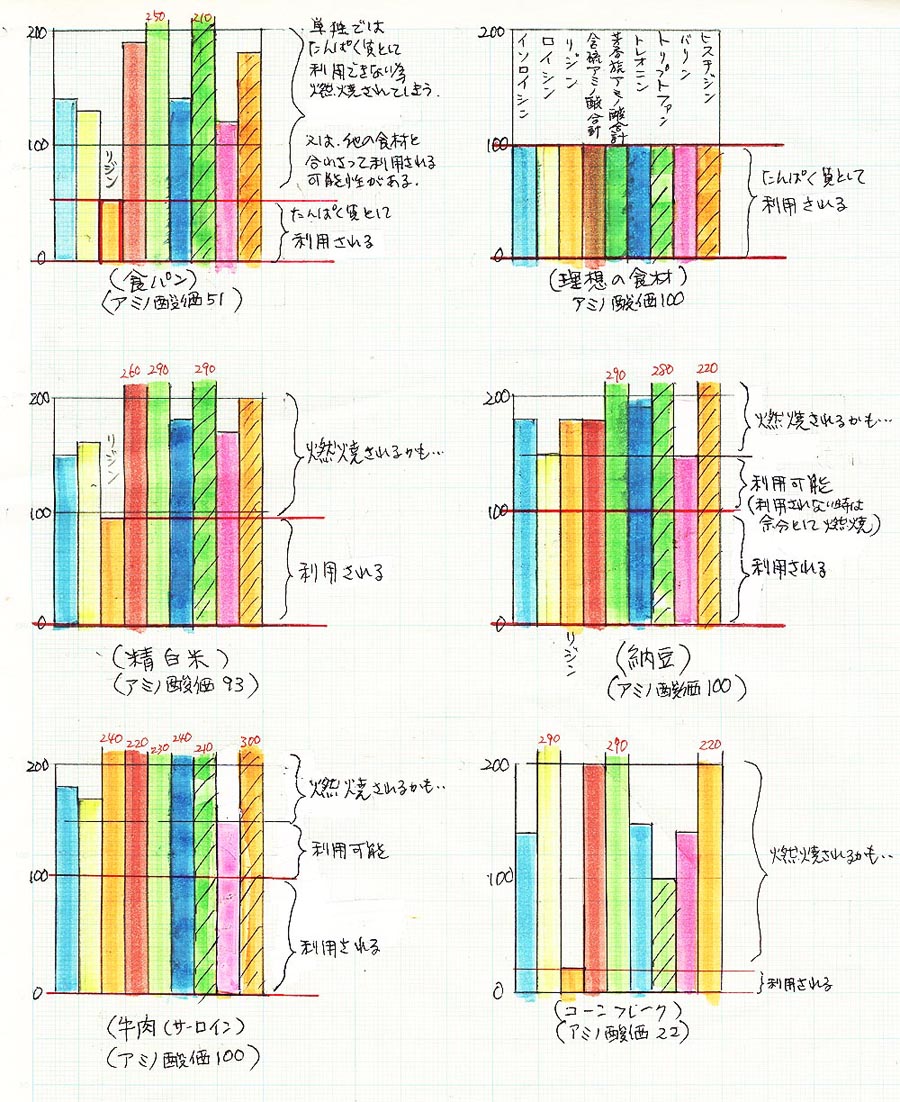
����̃O���t�́A���낢��ȐH�ނ��A�K�{�A�~�m�_�̐ێ�K�v�ʂ��ǂ̒��x�������Ă��邩������
�O���t�ŁA�u�c�����A�~�m�_�X�R�A�ł��v�B�@���z�̐H�ނ͑S�ẴA�~�m�_�X�R�A��100�ȏ�ŁA�S�Ă̕K�{�A�~�m�_�̃X�R�A���������l�ł��邱�ƁE�E�ł����̂悤�ȐH�ނ͑��݂��܂���i�����ɂƂ��ĕ���͂قڗ��z�ƌ�������̂ƌ����Ă܂����E�E�j
�@
�@���j���͕K�{�A�~�m�_�ێ搄���ʂ�140���ō���Ă���܂��B����ƁA�A�~�m�_�ɂ��`�����̍ۂɑg�O��ƂȂ�ߏ�ȕK�{�A�~�m�_�����炷���A�X�ɑ̓��œŐ��̂���C���h�L�V�����_�����̌��������ƂȂ�\���̂���u�ߏ�g���v�g�t�@���v��K�v�ŏ����ɂ��ׂ��w�͂����Ă��܂��B���̌��ʁA����������ς����͂S�T���A�A�~�m�_�g���ɂ�邽��ς����ʂ�1��32.4g�A�]���̂���ς����ʂɊ��Z�����35.4g�A�����/kg�̏d�ɂȂ�܂��B
�@
���j����2020�N7��25���̒�ԃ��j���ł��B���j���́A�قږ��������ɐi�����Ă��܂��B
��ԍ��̐H�i�̗ʁi���j��ł����ނƁA�����A�`�����ʁA�J�����[�A9��̕K�{�A�~�_�A����������ς����ʁA�J���E���A�����A�����ʁA�Ȃǂ��A�����ďo�Ă��܂��B
�@
�@��ԉ��ɂ́A�e���l�̍��v�A�{���̕K�{�A�~�m�_�ێ�ʂ̍��v�A����ς��������ɗ��p�ł��Ȃ��K�{�A�~�m�_�̗ʁA�y�іڕW�l�ɑ��道�A�`�����ێ旦�A�������`�����̊����A�O��̒~�A�ɂ��J���E���ێ�ʂ̎��сi����͎���́j�B���j�������ۂ̃J���E���ێ�ʂ��啝�ɏ��Ȃ��̂́A�卪��W���K�C���Ȃǂ��Q�x�R�x�ς��ڂ��Ă��邱�ƁA����ƗⓀ�H�i�̉𓀎��ɏo�Ă��鐅���i�h���b�v�j�̔j���ɂ��h���b�v���̃J���E�����j�����ꂽ���Ƃɂ����̂Ǝv���܂��B
�@
��0.6��/kg�̏d�E�����̒�`�������������s����ꍇ�A�����̌o������A�����`���ʂ����炷�����ł́A����̕K�{�A�~�m�_�̕s���ɂ��h�{��Q�Ɋׂ�̂��\�����o�ė���Ǝv���܂��B9��ނ̕K�{�A�~�m�_���A�ǂ���v�g�n�����ʂɑ��āi���炭�j���Ȃ��Ƃ�30���ȏ�̑��ʂ����āA����̕K�{�A�~�m�_���A�s�����邱�ƂȂ��ێ悷��Ƃ����ׂ��Ȍv�Z������K�v������܂��B�K�{�A�~�m�_�̃o�����X�����āA�����`�����̐ێ�ʂ����炷�����ł́A�h�{��Q�ɂȂ�A���X�̂̎ア�ӏ��ʼn��ǂȂǂ��N����\��������ƐS�z���܂��E�E
�@
�����L�̃T�C�g�ŐF�X�ȐH���̕K�{�A�~�m�_�ʂׂ��܂��B���̕\�ŁA�u�H�i�P�O�O��������̕K�{�A�~�m�_�ʁv�ƁA�u�H�i�̃A�~�m�_�g���ɂ�邽��ς����P��������̕K�{�A�~�m�_�ʁv��������܂��B
�@���m�ɕK�{�A�~�m�_���W�v����ɂ́A�A�~�m�_�ʂ��������Ă���P��̑f�ނ�H�ׂ�̂���Ԃł����E�E�X�[�p�[�̑y�Ƃ��A���G�ȗ����ł́A�s���m�ɂȂ�₷���ł��B�i���G�ȗ����ł��A�Ⴆ�Q�l����f�ނ�����A����1�l�ō������ɑS���H�ׂ�ꍇ�ɂ͐��m����ۂĂ܂��ˁE�E�܂����i�S���j15���Ƃ����悤�Ȕ��[�ȗʂ̎��́A�X�N�����u���G�b�O�ɂ���A��r�I���m�ɗʂ�܂��B�����̎��͗��p�����̓_�Łu��ŗ��v���ǂ��Ǝv���܂��B�@
�@
�@�ꂽ�ѕK�{�A�~�m�_�̐��E��m��ƁA�����K�{�A�~�m�_�̌v�Z�Ȃ����āA�����͍��Ȃ��Ȃ邩���m��܂���E�E�E�����͂����܂ł�邱�Ƃ́u�����т�ׂ��v�Ȃ̂�������܂��E�E
�@
�@�t���͌Â��Ȃ��Ď���Ă����זE�����C�ȍזE�Ɠ���ւ��邽�߂ɁA�A�~�m�_�X�R�A�̍����A�זE���Ɏ�荞��Ŗ��ʂȂ�����ς����������ł���K�{�A�~�m�_���\���ȗʕK�v�Ƃ��Ă��邱�Ƃł��傤�E�E�����A���́A�u�K�{�A�~�m�_�̗��z�I�ێ�ʁv�Ƃ����̂��A�ǂ������������Ă��Ȃ����Ƃł��E�E�E�m���ɐ����ێ�ʂƂ����̂�����܂����A�p�H�ނ̐l�̂ł̏����z�������s���ȏ�Ԃł́A�ǂꂾ���H�ׂ���100���ێ�ɂȂ�̂���������Ȃ��̂ł��E�E
�@
�@���ȐӔC�Ń��j������邵���Ȃ��A�Ƃ����͕̂s���Ȃ��Ƃł��E�E���͌��݂͐����ʂ�150���Ń��j��������Ă��܂����A150���Ȃ�Ώ��Ȃ�����ƌ������Ƃ͂Ȃ��E�E�Ƃ��������͎����Ă��܂��B����145���ł��\�����ǂ����E�E������140���ł��\���Ȃ̂��E�E����͎������邵���Ȃ��ł��B����140���ł��\���Ȃ�A����ς��������������A�����̔A�f���f�͌��邱�Ƃł��傤����A�t���ւ̕��S�͌��邱�ƂɂȂ�Ǝv���܂��E�E�i2020.7.16��150����140���ɕύX���܂����B�g�̂̒��q�͗ǂ��ł��E�E�j
�@
�@�@���{�H�i�W�������\2015�N��(����)�@�A�~�m�_�����\�ҁ@�@�@
�i�����N���Ȃ����́A�R�s�[���y�[�X�g�A�����͏�̏����Ō����������Ă݂ĉ������B�j
�@
��̕\�́A�@���{�H�i�����\�E�A�~�m�_�����\�̒��g�ł��B
�������u�H�i�H��100g������̕K�{�A�~�m�_�̗ʁv�ł��B���ꂾ���Œʏ�̕K�{�A�~�m�_�̌v�Z���ł��܂����A�E�̕��ɂ͍X�ɐ��m�ȁu�A�~�m�_�g���ɂ��A����ς���1��������̕K�{�A�~�m�_�̗ʁv���ڂ��Ă܂��B�ꗗ�\�ɂȂ��Ă���̂Ń_�E�����[�h���ăv�����g���Ă����ƕ֗��ł��B
�@
�@�����A�c�O�Ȃ���A�u�e�H�i�́A�A�~�m�_�g���ɂ�邽��ς����̗ʁv������ɂ͏�����Ă��܂���E�E�E�����m��ɂ́@�����A���{�H�i�����\���_�E�����[�h���v�����g����K�v������܂��B
�R�s�y�ŏo�Ă��Ȃ��Ƃ��́A�u����}���@���{�H�i�����\�@�A�~�m�_�����\�v�Ō�������A�����邩���m��܂���B���e�͖c��ł��̂ŁA�p�\�R����ʂł͌����炢�Ǝv���܂��B�{�͏��X���l�b�g�V���b�v�Ŕ����܂��B
�@
�@
�@�A���{�H�i�����\�@
�@
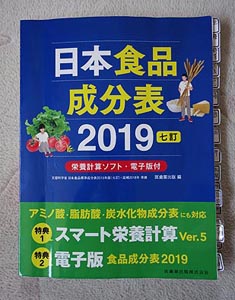
�u�A�~�m�_�g���ɂ��A����ς����̗ʁv��������܂��B����ŐH�i100g���ɃA�~�m�_�g���ɂ��`�����ʂ���g���邩�ׁA��̕\�́u�@�A�~�m�_�g���ɂ��`�����P��������̗ʁv��������ƁA���̐H�i�P�O�O��������̐��m�ȕK�{�A�~�m�_�ʂ�������܂��B�E�E�E�@�@����ł�2���̖{�����Ȃ���Ȃ炸�A���Ȍv�Z�@�ɂȂ��Ă��܂��܂����A������A1���̖{�ŕ������������Ǝv���܂��B
�i�����N���Ȃ��Ƃ��̓R�s�y���A�����Ō��������Ă݂Ă��������j
�@
�@�W�|�P�S�|�Q�@�@�K�{�A�~�m�_���j���̍����@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
��̕\�͕K�{�A�~�m�_�ێ搄���ʂ�150���̏ꍇ�̃T���v���ł��B���̕\�ł͊e�ێ�ʂ�1�����̂P�^�R�ɂ��Ă��܂��B�����͐H�i���A��̗��͉����ʁA����ς����ʁA�J�����[�A���̉E��9��ނ̕K�{�A�~�m�_�ł��B�����̗ʂ́A�W���H�i�����\���璲�ׂ��܂��B�H�i100g������̕K�{�A�~�m�_�ʂׂ�̂���ԊȒP�ł��B�X�ɁA��萳�m�ȕK�{�A�~�m�_�ʂׂ�ɂ́A�A�~�m�_�g���ɂ�邽��ς����P��������̕K�{�A�~�m�_�ʂׂāA���̒l�ɃA�~�m�_�g���ɂ�邽��ς����ʁi���j���|���ċ��߂܂�����Ԃ�������܂��B���̕\�͐����ʂ�150���ō���Ă��܂����A���݂͎��͐����ʂ�140���ɂ��Ă��܂��B�ȑO120���Ŏ����a�ǂ����Ă���̂ŁA�ێ�ʂ�����ȏ��l�߂邱�Ƃɂ͂�≰�a�ɂȂ��Ă��܂��O�O
�@
�@�K�{�A�~�m�_���烁�j�������ۂ́A���߂̂����͐ێ搄���ʂ�150���ʂ���n�߁A���������炵�Ă����E�E�Ƃ������@������Ǝv���܂��E�E������H�i�̐����덷�A�v�ʂ̌덷�A������̌덷(��������)�A�z�����������s���A�ȂǐF�X�Ȍ덷��s���ȓ_���l����Ƒ��߂̐ێ悪���S���Ǝv���܂��E�E�K�{�A�~�m�_���x�[�X�ɂ���9��ނ̃A�~�m�_�X�R�A�𑵂���悤�ɓw�͂������j���ł���Ȃ�A���������ێ悵�Ă��A���̖т�܂��L�т�����Ƃ��͂���ł��傤���A�債�����ɂ͂Ȃ�Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă��܂��E�E
�@
�\�̍����̇@�͒��H�̍��v�B�A�͒��H�Őۂ�ׂ��h�{�f�̗ʂł��B�K�{�A�~�m�_�́u�ێ搄���ʂ�150���v�̂P�^�R�ɂ��Ă��܂��B�D�͐��l�̕W���̏d�Pkg������̂P���̐ۂ�ׂ��A�K�{�A�~�m�_��WHO�����ʁimg�j�ł��B���̒l�ɕW���̏d�i�\�ł�55kg�j���|�������̂��K�v�ʂɂȂ�܂����A���̕\�ł͂���1.5�{�������ɂƂ��Ă̕K�v�ʂƂ��Ă��܂��B1.5�{�ɂ��Ă��^���p�N���ʂ͖�0.6��/�̏d�ƂȂ�A�t���w��̐�������ʂ̉����ɂȂ��Ă��܂��B�J�����[�ƂȂ邩���m��Ȃ��ߏ�ȕK�{�A�~�m�_�̗ʂ͖�11���ł��B89���͑̓��ł���ς����Ƃ��Ċ��Ă��邱�Ƃł��傤�E�E�E�ŋߒ܂��ǂ��L�т܂��E�E�������������n�߂Ă���Δ��̖т��t�T�t�T�����������E�E�O�O
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@�W�|�P�S�|3�@�@�K�{�A�~�m�_���j���̃T���v���@
�@
�@�W�|�P�S�[3-1�@�@�@��ԃ��j�������@
�@
1���ɕK�v�ȉh�{�f�̂R���̂P����������ۂ��A��ԐH������Ă����ƕ֗��ł��B����3�H���̃��j����H�ׂĂ������ł����A���Ԃ̂���Ƃ��͕ʃ��j���𗿗����܂��B ���̃��j���̓����̓g���v�g�t�@�����ŏ��ɂ��Ă��邱�Ƃł��B���̈׃A�~�m�_�̉�������o��i���p�ł��Ȃ��j�A�~�m�_��8-14-2�̕\����⑽���Ȃ��Ă��܂��B
�@
�@��ԐH�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
����̒�ԐH�ŁA�u䥂ŃW���K�C���v�́A������A䥂ł邱�ƂŃJ���E�������炵�Ă��܂��B
���u�i���R�v�́A�g���v�g�t�@�������Ȃ��ł��B���i���R�i������94���j100��+�f����25g�Ŏd�オ��d��148g��100���ł��B�����d�オ�肪133g�Ȃ�A90����H�ׂ�悢���ƂɂȂ�܂��B
���u�؊����卪�v�E�E�؊��卪100���ɍ���60g�A���ݖ�98g�A�T���_�I�C��40g�B�d�オ��1170�@����100���ł��B����585g�Ɏd�オ������v�Z���g����50����H�ׂ�悢���ƂɂȂ�܂��B
�@
�@
�@
�@�W�|�P�S�|3�|2�@�@�@����u�߁@/�@���i�A�W�j
���̃��j���̍ŏ��Ɂu�i���P�j1��3�H�̓���2�H���v�A�Ƃ�����������܂��B�O�y�[�W�̒�Ԃ�1��2�H�H�ׁA�c���1�H�����L�́u��ԐH�ȊO�̃��j���v�ŐH�ׂ��ꍇ�̍��v���{���̍��v�ێ�ʁi��2�j�v�ƂȂ��Ă��܂��B
����u�߂͋����Q�O���A���i�A�W�j��16.4g�E�E�ǂ�����߂������ȁA�ق��1��ł��B�B�B
�B
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@�W�|�P�S�|3�|3�@�@�@���Ԑg�ē��@/�@�Ă�����
�����̐Ԑg�����̏ē��ł��B���̗�18g�E�E�ē����A�Ƃ�����Ȃ��ʂł����A�ē��ł��邱�Ƃ͊m���ł��B����1�x�Ȃ�150g�H�ׂ鎖�����Ȃ��A�Ƃ���Ă܂����A���̃��j���Ȃ�ΏT��3��A�ē���H�ׂ鎖���\�ł��B����ȗʂȂ��������}�V�E�E�Ǝv������������ł��傤�ˁE�E
���Ă����̖˂́u�A�v���e���@����ς������@���ˁ@�p�X�^�@���ؖˁv�Ƃ����̂��g���܂��B
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@�W�|�P�S�[3-4�@�@�@�p�X�^�@/�@�M���[�U�@
�@�����P�`���b�v�ƒ�`���˂��g�����A�p�X�^�ł��B�˂͑O�y�[�W�̏Ă����Ɠ������ł��B�p�X�^�����ł́A�h�{�o�����X���������߁A���[�O���g��s�X�^�b�`�I�A�花���卪�A�i���R�ϓ��������܂��B
���L�q�́A�{��s�̊ۉ��L�q�̏ꍇ�ł��B���Ɛ��ł�����H�Ƃ��Ă�4�ʂ��Ǝv���܂��B
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@�W�|�P�S�|3�|5�@�@�@���g���g�J���[�@/�@�����߂�@
�J���[�Ƒf�˂ł����A����H�̂��߁A�ǂ�������Ȃ�T���߂ȗʂł��B�B
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@�W�|�P�S�[3-6�@�@�@�O�H�@/�@�X�^�[�o�b�N�X�@/�@�J�v���`���[�U
����H�̊O�H�̗�Ƃ��āA�X�^-�o�b�N�X�ƃp�X�^���X���ɋ����܂����B
�X�^�o�́A�u�n�����}���{�[�`�[�Y �Ηq�t�B���[�l�v�����������̂ł����A��1�x�̂��J���H�Ȃ炢���ł��傤���A����I�ɂ́A���b�t��1���ƈ��ݕ��E�E�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�J�v���`���[�U�͉��u��̃o�^�[�����v�Ɓu�g�}�g�ƃj���j�N�̃p�X�^�v���ǂ����1�M�̂R�T���ʂ�H�ׂ鎖�ɂȂ�܂��i�܁j
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@
�@8-14-3�@�@�g���v�g�t�@�������炷���ʁH�@
�A�ŏǂ̌����ƂȂ�őf�̓A�����j�A�����ߑ�R����܂����ACKD�̌㔼�ɂ����Ċ����Y�f�̔�����������Œ����őf�u�C���h�[���v���z���������悤�Ƃ��鎡�Â��s���Ă��܂��B���̃C���h�[���Ƃ��������́A�l���ێ悵���K�{�A�~�m�_�̃g���v�g�t�@���̈ꕔ�������ۂɂ��ϊ����ꂽ���ƌ������Ƃł��B
�@
���̃C���h�[���͒�����̓��ɋz�������Ɗ̑��Łu�C���h�L�V�����_�v�Ƃ����Ő��̍��������ɕϊ�����Ă��܂��܂��B���̃C���h�L�V�����_�͕��q�ʂ̑傫�Ȓ`�����ƌ��ѕt�����߁A�����ׂ̂̍����Ԃ̖ڂ͒ʉ߂ł��Ȃ����߁A�A�ǂ�����荞����N���ɔr�o�����悤�ł����A���̍ۂɔA�ǂ������A�A�ǂ̑������N�����āA�����̂��܂ޑg�D�S�́i�l�t�����j���@�\�s�S�ɂ���Ƃ���Ă��܂��B�i�����y���F�uCKD���������E���Á@�x�X�g�K�C�h�v��w���@�E���j
���̂��Ƃ���A�g���v�g�t�@���̉ߏ�ێ�����点��A�����Ȃ�Ƃ��C���h�[��������̂ł͂Ȃ����Ɗ��҂��Ă��܂��E�E
�@
���̃��j���Ńg���v�g�t�@�������炷�悤�ɓw�͂��Ĉȗ��A�v�Z��̐ۂ肷���g���v�g�t�@���A1��159mg��111mg�Ɍ��点�Ă��邽�߁A�ߏ蕪�̃g���v�g�t�@������30�����������ƂɂȂ�܂��B�����Ȃ�Ƃ����ʂ�����Ɨǂ��̂ł����E�E
�@
�@�X�@�@���̑����낢��@
�@9-1�@�@��`���Ă̂��Ɓ@�@�@�@�@�@�@�@�@
�u�t���җp����H�i�v�̔F�̂�����̂����S�ł����ӊO�Ə��Ȃ��ł��B�������F����������ƌ����Ė�肪����Ƃ����킯�ł͂Ȃ��Ǝv���܂��E�E��`�����т̓���H�i�F��ɂ͒`�����ʂ�

���ʂ̂��т̔����ȉ��ŁA���̑��̉h�{�f�͕��ʕĂƓ����ł��邱�ƁE�E�܂�`�������������炵�����A�Ƃ������Ƃł��傤�E�E���_�ۂ������Ē`�����������鏈�����ɂ��낢�뉻�w�ω����N���A�Ă̑g���ɂ��e�������邱�Ƃ͑z���ł��܂��B
�@
�@�����{���̕ĂƂ͉h�{�������ς���Ă����Ƃ��Ă��A�F�X�Ȏ�ނ̐H�i�ՂȂ��H�ׂĂ���l�ɂƂ��ẮA��`���Ă͒`�������Ȃ��āA�J�����[���K��ʂ����āACKD�ɂƂ��ėǂ��Ȃ��������������Ă��Ȃ��������A�ƌ������ɂȂ�̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
�@
�@��ʂɒ`�������͉��������ɔ�ׂ��邢���Ƃ������ł��B
��`�����тɑ��ɋ��߂���̂͒�`���ł��邱�Ƃł����A��Ԗڂ͖��ł͂Ȃ��ł��傤���E�E���������Ȃ����т͒����������Ȃ����A�H�������������܂���E�E
�@
�����т̂��������͒`���ʂɔ�Ⴕ�܂��B�`������1/25���1/5�̒`���Ă̕����f�R���������ł��B��ʓI�ɗǂ����p�����̂�1/25��������1/20�ł��傤�B�@�`��1/25�A180g�p�b�N���т��ƒ`���ʂ�0.18g�ł��A�ŋߔ���o���ꂽ�`����1/50�͒`������0.09g�ƂȂ�A1/25�Ɣ�ג`���ʂ�0.09g���点�܂����A���Ă���0.09g�̒`���ʂ̌������ǂ��l���邩�ł��ˁE�E0.09���̒`�����Ƃ́A�ؓ��i�����A�ԓ��j0.36���ɑ������܂��B���ŋ��߂Ȃ��قǂ̋͂��ȗʂł��E�E�E�y�x�Ȃb�j�c�̐l�ɂƂ��ẮA���㉽�\�N���H�������������킯�ł�����A���������Ĉ���1/20�A���邢��1/10��H�ׂ����E�E�ƂȂ邱�Ƃł��傤�B
�@

�����Ő��т���u�ė��^�C�v�v�̓p�b�N���т���4���������Ȃ�܂��B�@�ł�������������Ŏ��R�ł����A�H�ׂ�ʂ�1���P�ʂŎ��R�ɕς����܂��B�@��`���Ă͊�{�I�ɖ����Ăł��̂Ő��т͊y�ł��B��`���Ă͌y�����ɂ���ɂ��ėⓀ����ƁA�������Ă����ނ��남�������Ȃ�悤�Ɋ����܂��B
�@
�@�����A��ʘ_�Ƃ��ẮA���т����������Ă��т����A�p�b�N���т̕������͔��������Ǝv���܂��B���̌����́A���т��ƕ���1����3�H���𐆂����Ƃ������Ǝv���܂����A�`���������Ȃ����߂��тɒe�͐��������A���т���Ă̗ʂ������Ȃ�ƁA�����オ�������ɂ��т̏d���ł��т��ׂ�C���ɂȂ��Čł��Ȃ邩��ł��B���ׁ̈A�܂ɂ́A���ъ�̗e�ʂ̔����ȉ��̗ʂŐ��т��Ă��������A�Ƃ̒��ӏ����������܂��B
�@
�@���̓_�A�p�b�N�̂��т͌��݂�2cm���X�ł��̂ŕĂ̏d���Œׂ�邱�Ƃ��Ȃ��A�ł��Ȃ炸�ɔ��������Ȃ��Ă��܂��B�@�]�����p�b�N���т͗Ⓚ���Ă����������H�ׂ��܂��B
���i�̔�r�����Ă݂܂��ƁE�E���������Ɖ䂪�Ƃł͌���҂̍Ȃɂ��D�]��PLC�`��1/10�A180g����p�b�N���т�300kcal�ŁA1�p�b�N�i����ō��j189�~�i2019�N12���r�[�X�^�C���{�X�j�ł��B�ė��^�C�v��PLC�`��1/20�ɂȂ�܂����A�p�b�N���тƓ��� 300kcal��87.7g�ɑ������A���̉��i�͐ō�113�~�ɑ������܂��̂ŁA�p�b�N���т��S�O���������A1�H�i300kcal�j������76�~�̐ߖ�ɂȂ�܂��B����3�H���ׂ��ꍇ�A1�N��8��3��~�A20�N�������170���~���̐ߖ�ɂȂ�܂��B
�@
��`�����т𐆔т��������̃����b�g�́A�J�����[�̔�����������1���P�ʂłł���Ƃ����_���Ǝv���܂��B�p�b�N���тł͔������͍���ł����A���ʂɂȂ�ꍇ������܂��B
�@
�@
�@
�@9-2�@�@�a�@�I�с@
�s���ׂ��Ȃ́u�t�����ȁv�ł����A�߂��ɖ����Ƃ��͓��Ȃ��A�z��ȂɂȂ�Ǝv���܂��B�����̃N���j�b�N�ł����t�����͏o���܂����A�����̏ꍇ�A���̌������ʂ���n�����͎̂���̌��f���ł��傤�E�E
�@���Ԃ���1������A�x�����2������E�E�B�������ʂ𑁂��m�肽���Ǝv���܂����A���������_�ł́A��a�@���A�����͋߂��̃N���j�b�N���ǂ��Ǝv���܂��E�E��a�@�Ȃ��1���Ԉȓ��Ɍ��ʂ��o�܂��E�E�߂��̃N���j�b�N�Ȃ�A3����ɂ͌��ʂ����炦�܂��ˁE�E�@
�@
�@
�b�j�c�ۑ����͐H�����d�v�ɂȂ��Ă��܂����A���j���[���l���A�H�ނ�I�сA��������̂͊��҂ł���A��t�͉���ł��܂���B�@�܂����@�{�݂̂Ȃ��N���j�b�N�ɂ͒ʏ�Ǘ��h�{�m�͂��܂���)�E�E�܂芳�Ҏ��g���Ɗw�ʼnh�{�w���w�сA���j������邵���Ȃ��̂ł��E�E������IgA�t�ǂ�}���ȊO�̖����t���a�͊�{�I�Ɏ���Ȃ����A�ǂ�ȂɊ撣���Ă��t�����Đ�����邱�Ƃ͍��̂Ƃ���Ȃ��̂ŁA����ێ���ڕW�Ƃ��Ȃ���Ȃ�܂���E�E�@�ۑ����̎��Âɗ����̂���a�@�i�Ⴆ�Q�S���~�A�����A�ۑ����̖{�i�I�ȉh�{�w���ȂǂɔM�S�ȕa�@�j���t�ɏ������l�͍K���ł��B
�@
�@CKD�Ƃ́A���͂ƌ����I���_�ւ������Ɨ����Ă����A����̒��������G�X�J���[�^�[�̂悤�Ȃ��̂ł��E�E������ăG�X�J���[�^�[��o���Ă����Ȃ��ƁA���̊Ԃɓ��͂ւƑ��Ă��܂��܂��E�E
�@
�@9-3�@�@���N�f�f�ɖ]�ނ����@�@
�@
�t���a�̎��Â͂����ɑ����Ɏn�߂邩�����ł��B�@�ŋߋ������̂ł����A40�ˌ��f�ł́A�����������t����������̂Ɍ����N���A�`�j���l�͒��ׂȂ��̂ł��ˁI�H
�@
�@�̋@�\��R���X�e���[���͒��ׂ�̂ɁA���̐t�@�\�͒��ׂȂ��̂ł��傤���H�@40�ˌ��f�ŔA�`���͈ꉞ�������Ō���悤�ł����A�Ԏ����t����t�d���ǂȂǂł͔A�`���͖w�Ǐo�Ȃ����Ƃ�����A�A�`�����������ł�CKD�̏����ł͔����ł��Ȃ��\��������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�܂�ŏ����̊��Ҕ������̈ӂɒx�点�Ă��邩�̂悤�Ȉ�ۂ��܂��E�E
�@
�@40�˂Őt�@�\�̒ቺ�ɋC�Â��A�ۑ����̐����w�����A�H�������̎d���������A�\���\�H������A�d�J���������ȂǁA�������̉��P������ACKD�̈������x���ɂ߁A�����̓��͂̉\�������Ȃ茸�点��A�����͉�������ҏo����̂ł͂Ȃ��ł��傤���E�E
�@
�@�����I�ɂ͕ی���������a�@�̋@�\���g�債�āA�u�����t���a�E�ۑ����ȁv��u���A�߈�ƘA�т��Ď��ÂƎw�����s�����Ƃ��`��������Ƃ��]�܂�܂��E�E
�@
�@9-4 �@�����������@
�@
�@������������ŁA�N����1���Ԉȓ��̌����A�Ƃ���͍̂��f����\�����Ǝv���܂��E�E
�~���܂p���Ă��Ȃ��l�́A��ʂɏA�Q���͌����͎������A�N����ɂ͈ꎞ�I�ɏ����������オ����̂��Ǝv���܂��B�N������ɑ��������߂̌����Łu���̌����������ł��ˁE�E�����~��������݂܂��傤�E�������@���ĉ������v�ƂȂ��Ă͂��܂�܂���E�E�B
�@
���������A�f�l�ɂ�������悤�ɁA���J�ȑ��������̑�������}�j���A�������ė~�����Ǝv���܂��B
���́A�u�N����P���Ԉȓ��v�̒����l�́u�N��30����v�ƌ��߂Č����𑪂��Ă��܂��B���̏ꍇ�A�N���R�O����Ȃ�A���̌����͗��z�����Ɉ��肵�܂��B�N������ɑ�������A���͌��������߂��A�Ƃ������ƂɂȂ��āA�~���܂̒lj������Ȃ���Ȃ�܂���E�E
(�~���܂�����������߂A���N������̌������|�����Əオ�邱�Ƃ͂Ȃ��悤�ł����E)
�@
���łɁA�a�@�ł̌����̑�����ł����E�E�ŋ߂͑ҍ����Ɍ����v���u����Ă��邱�Ƃ������Ȃ�܂����E�E�a�@�ɒ����Ă�������̂ł͂Ȃ��A�����\�t�@�[�ɍ����Ă���A�����Ō����𑪂��āA�o�Ă��������Ō�t����Ɍ�����E�E���̕��@�ŁA���ߍ������i�p: white-coat hypertension�j�ɂ��~���܂̌�p�����Ȃ�h����悤�ɂȂ����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�@���ʂȈ�Ô�܂Ȃ����߂ɁA���ׂĂ̕a�@�ŁA���Ҏ��g�Ō����𑪂���@���������ׂ��Ǝv���܂��B(�ܘ_�A����Ō����𑁒��ƐQ��O�ɑ�����1�������̃f�[�^����t�Ɍ��Ă��炤�̂���ԗǂ����@�ł�)
�@
�@10�@�E�E���s���������݁C�����Ȃǁ@
�@
�@10-1�@�@�@���������Ŏ��s�@
�@�ȑO�A�m�荇���̈�t�̑E�߂œ����������n�߂܂����B�������ɒ[�ɐ�������ƁA���܂Ŏ�Ƃ��ē�������G�l���M�[�Ă����g�̂͊�@�I�ȏ�Ԃ��@���A��@�����邽�ߓ����ȊO����A��Ƃ��Ď�������G�l���M�[��悤�傫�ȑ̎����P�����܂��B���̌��ʐV��ӂ��ǂ��Ȃ�A�������ǂ��Ȃ�A�]���Đt�������C�ɂȂ�E�E�Ƃ������������̂ł����E�E
�@
�@�����A������1��45g�ɐ����A�`����100g�A������125g�A�J�����[1700kcal�O��̐H���������܂����B�m���ɓ��������ő�ӂ������ɂȂ�A�g�̓I�ω��Ƃ��ẮA�g�̂��_��ɂȂ�A�g�̂��Ȃ��Ď�̕����y�ɏ��ɓ͂��悤�ɂȂ�܂����B�ォ�����݂���v�ɂȂ�,������H�ׂĂ��݂����ꂷ�邱�Ƃ��Ȃ��Ȃ�A�����Ĉ�N�����b�ɂȂ������������s�v�ƂȂ�܂����B�܂��ǂ��L�сA�V��ӂ��������������Ƃ������܂����B�����������H���������H�����ɕϐg�������̗l�ł����B
�@
�@�����܂ł͗ǂ������̂ł����A�����������n�߂Ă���͌����A�f���f�̒l�͐t�s�S�̖ڈ��ɂȂ�50mg/dl�ɂ��㏸���Ă��܂����i��l�X�`21mg/dl�j�B������ ��펖�Ԑ錾�����Ă���g�̂͊m���ɐV��ӂ��i�i�Ƀp���[�A�b�v���A�ꌩ�A����Cr.�l�̈����͎~�܂������̂悤�ł����B�@����������9�����Ԏ��{�����̂ł����A6�����ڈȍ~����Cr.�l�͏��X�ɋ͂��ł͂���܂������������Ă����܂����B�g�̂����������ɑς����Ԃł͂Ȃ������̂ł��傤�E�E���܂肩�˂ăZ�J���h�I�s�j�I�������A�����Ȑt���a�ۑ������ォ��̓����������~�̋����x���œ��������͏I���ƂȂ�܂����B
���������œ������Ƃ́A�̎����P�ɂ��݂���v�ɂȂ���,�ƌ������Ƃ����ł������A������������Ȃ��Ȃ����Ƃ������Ƃ́A�B��ǂ����������Ǝv���Ă��܂��B���������łނ�݂Ƀ^���p�N���𑽂ɐۂ邱�Ƃ͂�͂�t���̕��S����������̂��Ǝv�����炳��܂����B
�@
�@
�@
���O���t�͓����������̒`�����ێ�ʂƌ����A�f���f�A����Cr.�l�̊W�ׂ����̂ł��B
�A�f���f�͒`�����ێ�ʂɗǂ��Ǐ]���Ă��܂����ACr.�l�͖w�lje���Ă��܂���E�E�ނ���t���ցi-0.35�j�ɂȂ��Ă��܂��B�@�A������͖�1�N�Ԃ̒Z���I�ȑ��ւł��B�@��������ς����ێ�����N�������Ă�����ACr.���e�������ɂ͂����Ȃ������ł��傤�E�E
�@
��24���Ԓ~�A����v�Z�����A�H���̉����ێ�ʂƒ`�����ێ�ʂ̐��x�ɂ��āE�E�E
24���Ԓ~�A���n�߂����́A�����̃��j����̉����A�`�����̗ʂƁA�~�A���ʂ���v�Z�����ێ�ʂ��ׂĂ݂�ƁA�`�����ʂ͂҂����荇���̂ł����A�������Ȃ��Ȃ������܂���ł����B���̌����ׂ����ʁA���L�̂悤�Ȏ�������܂����B
�@
�����E�E��������5���O�ɐe���ʼn�Ȃ�H�ׂ����̉����̉e�����c���Ă����i���̉e������ԑ傫���ł��j�E�ECKD���҂͉����iNa�j�̐t������̔r�o���������߁A�P�O���Ԃ��炢�r�o���ꂸ�Ɏc�邻���ł��E�E�E�i�܂茟�����O10���Ԃ͋ސT���ƌ������Ƃł��ˁj�E�E
�@
�@�O�H�ʼn����ʂɐۂ�ƁC���̉e��(����)Na�Z�x�̏㏸)��1�T�ԁ`10�����x�����܂��B�]���ď��Ȃ��Ƃ�������1�T�ԑO����͗p�S���āA�v�Z��������Ƃł��Ă����ԃ��j���[�ȊO�̐H�����Ȃ�ׂ��ۂ�Ȃ��悤�ɂ��������ǂ��Ǝv���܂��B�����A�������̑O�������i�ȐH��������������ƌ������Ƃ́A�܂����������ׂ̈ɂȂ�Ȃ��ł��ˁE�E
�@
�ł��A�C�O�̈�w���ł��A��T�ԐH���������o�����l�́A���J���Ƃ��ďT���ɂ͐H�ׂ����������ʐH��H�ׂĂ��ǂ����A����͐t�@�\�ɂƂ��Ė��ɂȂ�قǂ̉e���͂Ȃ����A�ނ��늈�͂����܂�Ē���������A�Ƃ����f�[�^�����邻���ł��B���{�ł��T�Ɉ�x�A���ʂ̂��̂�H�ׂ�A�Ƃ������ƂɊ���ɂȂ��Ă��܂����B�������A����͕��i������ƐH�����������Ă���l�̏ꍇ�̘b�ł��B
�@
�@
�@
�@
�@10-2�@�@����`���������Ŏ��s�@ �@
�@ �t���w��u�K�C�h���C���v�ɑ��ĕ�W����2009�N�́w�p�u���b�N�R�����g�x�W�ɁA�u�`�����������ɂ����ĈӖ����Ȃ��v�A�Ƃ����ᔻ���Տ��ォ�琔�������Ă��܂��B�l�b�g��ŋ��R�����܂������A�Ȃ��Ȃ�����������̐��ł��B���̒��Ŏ��́w�`����������0.6�`0.8g/kg/day�x�ł�CKD�̐i�s���~�߂���ʂ��Ȃ����Ƃ��A0.3�`0.5g/kg/day�ŏ��߂Č��ʂ��o�邱�Ƃ������̘_���ŏؖ�����Ă���A�Ȃ����̂��Ƃ������Ȃ��̂��A�����Ӑ}������̂��E�E�ƌ������Տ���̈ӌ��ɋ����܂����B
�@�`���������͂Q�O��/���łȂ���Ό��ʂ��o�Ȃ��A�ƌ����咣�͊���̃T�C�g�Œm���Ă��܂������A���ʂ���w���ᔻ�����E�C�ɂ͐S�ł���܂����B�m����0.3�`0.5g/kg/day�Ƃ����͕̂W���̏d55kg�̐l��1��16.5�`27.5g�ƂȂ�A���Ȃ菭�Ȃ��v����`�����ʂł����A��`���H�����y�������݂ł͎��s�͏�����������ł͂���܂���B�w��͒�`���H�����y���Ă��Ȃ��Ƃ����O��ŃK�C�h���C��������Ă��邩�̂悤�ł��B
�@
�����ŁA�������ȐӔC�ŁA1���̒`������0.4g/kgIBW�iIBW�FIdeal Body Weight���W���̏d�j���������Ƃ���E�E�E�E13���ڂɌ������o���E�E15���ڂɎ��̃C���v�����g�����̎������A�X�ɃC���v�����g���ӂ̎��s�S�̂ɉ��ǂ����ǂ��A�ً}�̏��u���邱�ƂɂȂ�܂����B���܂��܋��R�̏o���������������m��܂��A���̑z���ł����A�����A����`���ɂ��h�{��Q�������Ƃ��鎕�������ǂł͂Ȃ����Ǝv���Ă��܂��B
�@
���̔��Ȃ���A�h�{�̕����n�߁A0.6g/kg�W���̏d�����̒��Ⴝ��ς����������s����ꍇ�́A9��ނ̕K�{�A�~�m�_�ʂ��A���������A���Ȃ������A�œK�ȗʂɃR���g���[������K�v������ƌ������Ƃ�m��܂����B�u�@8-14-1�@�K�{�A�~�m�_�������ꂽ�H���v�͂��̔��Ȃ���A���s���܂����B
�@
���t���w��K�C�h���C���ɑ���p�u���b�N�R�����g�i2009�N�j
�@
�@10-3�@�@�a�b�`�`�T�v�������g�Ŏ��s�@
�@�K�{�A�~�m�_�̌v�Z��������ă��j�������ꍇ�A�������`�������R�ۂ�A�K�{�A�~�m�_�͕s�����邱�ƂȂ����j�������܂����A��������ɓ������`�������R�ۂ��Ă��A�K�{�A�~�m�_�o�����X�������ƁA�̓��ɂ����Ē`�����̍č����Ƃ��ė��p�ł����A�P�ɓ����⎉���Ɠ������J�����[�ƂȂ��ď���邱�ƂɂȂ�܂��B�����J�����[�ɂȂ�̂Ȃ�ǂ��̂ł����A�����⎉���ƈ���ĕK�{�A�~�m�_�͔M�ʂƂ��Ďg����ꍇ�A�A�����j�A�����A�̑��Ł��A�f�ƕς��A�A�f�͐t������r�o���Ȃ���Ȃ炸�t���ɕ��S���|���܂��B�]���āA���j���[�͕K�{�A�~�m�_�̃o�����X���l���đg�ݗ��ĂȂ���Ȃ�܂���B
�@�Ⴝ��ς������т𗘗p���Ă���l�̏ꍇ�A����ς����̐ێ�ʂ����炵�Ă����ƍŏ��ɕs��������̂͑����̏ꍇ�u�o�����v���Ǝv���܂��B���̑��ɂ����C�V���A���s���������ł����A���C�V���̓R�[���t���[�N�A�C�\���C�V����W���͋���w�ǑS�Ă̓������`�����ɂ͖L�x�ɂ���܂��B
�@
�@���̓o�����������������`�����ɏ��Ȃ��̂ł��B�o�������������̂Ƃ����ƁA�卪�A�����A�i�b�c�ށi�s�X�^�b�`�I�Ȃǁj�ł����A����قǑ�R�����Ă����ł͂���܂���B
�@
�@�����Ŗڂ�t�����̂��A�A�X���[�g�����ނa�b�`�`�ł��B�a�b�`�`�Ƃ̓o�����A���C�V���A�C�\���C�V�����P�F�Q�F�P�̊����Ŋ܂܂�镨���ł��B���ɗn�����Ĉ��ނƑf�����g�̂ɋz������A�ɂؓ����C�����A��������A�Ƃ������̂ł��B����𗘗p����ƁA�s�������o���������Ă��A�����ɑ�����̂̓��C�V���ƃC�\���C�V�������ŁA���̃t�F�j���A���j���Ȃǂ̐ێ�ߏ�X���̂���K�{�A�~�m�_�𑝂₵�܂���B�]���Ė��ʂȕK�{�A�~�m�_�̉ߏ�ێ悪�h���܂��B
�@
���̂a�b�`�`��1�����قǐێ悵���Ƃ���A�܂��܂��������ǂ��܂����B���ɂ��A�s�����̂悤�Ȋ������o�āA�y�������������肵�āA�Ȃɂ��|���Ȃ�܂����B
�@
�a�b�`�`���ڂ������ׂ�ƁA���������A���܂ōs���Ȃ������ɁA���������ɋz������A�����Z�x�͐ێ�30����ɂ͍ő�ɂȂ�E�E�����ĂQ���Ԍ�ʂɂ͖w�ǃJ�����[�ƂȂ��ď����A�R���J�X�͊̑��o�R�ŔA�f�ɂȂ��Đt������r�o�����Ƃ���܂����E�E�E
�@
�@�Q���Ԍ�ƌ����A���ʂɐH�ׂ����⍒���̂���ς������{�`�{�`������z�����n�߂悤�Ƃ��Ă��鍠�ł͂Ȃ��ł��傤���E�E���ł���ς������A�~�m�_�ɕς��A�����ɋz������A�����ABCAA�T�v���ƍ��̂��Đg�̂���낤�Ƃ���Ƃ��ɁA�̐S��BCAA�͖w�Ǐ����Ă��܂��Ă���̂ł́ABCAA�s���ƂȂ�A�זE�ł̂���ς����������ł����A�A�f���f��������E�E�ƌ����ň��ȏ�ԂɂȂ��Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���E�E���̕s���́A���܂��܋��R�������̂����m��܂��A�ȏ�̂悤�ȉߒ����l����ƁA���R�̐H�ו��Ɖh�{�܂��ꏏ�ɐۂ�̂͋z�����Ԃ̕s��v�Ƃ����_�Ŗ���������E�E�Ǝv���悤�ɂȂ�A�K�b�N���E�E���ӂ̓��ɂ�߂܂����E�E�E
�@
���ǁA���͎��R�̐H������̂݉h�{��ۂ�悤�ɂ��Ă��܂��B���̌��ʁA���p�ł��Ȃ��K�{�A�~�m�_�̗ʂ͂a�b�`�`���p�̎����\�̏�ł͑����Ă��܂����A�����I�ɂ͖��ʂƂȂ�K�{�A�~�m�_�͌���A�t���ւ̕��S���y�������Ǝv���Ă��܂��B�܂��A�����g�̏����������Ⴂ�\�����l���A�܂��H�ނ̕K�{�A�~�m�_�ܗL�ʂ̃o���c�L�Ȃǂ��l���A���������K�{�A�~�m�_�ʂ��50�������ʂ�ێ悷��悤�ɐH�����e��ύX���Ă��܂��B�@���̌��ʁA�A�~�m�_�g���ɂ��`������33g��0.6g/kg�W���̏d�ŁA��ʂ̂���ς����Ɋ��Z����ƁA��0.7/kg�W���̏d�ɂȂ��Ă��܂��B�i���݂͐����ʂ�40�����Ŏ��{���j
�@
�@
�@10-4�@�@�^�����߂��Ď��s�@
�u�^���Őt���a���ǂ��Ȃ�v�E�E�ƌ����h���I�ȕ\��̖{��ǂ��1��1�����̃E�H�[�L���O���J�n�B1�T�Ԍ�ɌÏ��̕ό`���G�ߏǂ��Ĕ��E�E�ǂ����A�����͕������L���������ƁA���x���グ�����ƁE�E�܂薳�����������Ƃ̂悤�ł��E�E���`�O�ȂŃq�A�������_���˂��܂����B�ߓ����˂͐̂ƈ���Đj���ׂ��Ȃ����̂ł��傤���E�E�ɂ������Ȃ�܂����ˁE�E�r�̍̌����x�̒ɂ݂ł����O�O
�@���̌���V�C�̗ǂ����ɂ͕����܂����A�����L�����U���āE�E�Ƃ����E�H�[�L���O�ł͂Ȃ��A�����͕��ʂŎU�����x��4000�����x�ƌ��߂ĕ����Ă܂��B�߂�����͋y���邪�@���E�E�ł��B
�@
�@
�@11�@�@���Ɛt���a�@
�@
�@���̕�͎������w5�N�̎��ɐt�s�S���痈��A�ŏǂɂ��48�˂̎Ⴓ�ő��E���܂����B���O��͌����ݖ����g������`�����������Ă��܂����B�����g�C������o��ƃJ�b�v�Ɏ�����A�Ɏ�������`���ɂ�锒���̗l�q�����Ă��܂����B�܂�A���݂̂b�j�c�̕ۑ����Ö@�Ƃقړ�����������Ă����̂ł��B�ɂ�������炸�A�Ƃ����ׂ����A��������Ă�����ς�Ƃ����ׂ����A�t���a�͐i�s���A���ɂ�f���C�ɋꂵ���ɔA�ŏǂŖS���Ȃ�܂����B�ꂪ�ꂵ��ŋꂵ��Ŏ��Ɏ���܂ł̈ꕔ�n�I��c�����͌��Ă��܂����B
�@
�@������̐t���a���������ł��A�����͒P�ɓ����������̂��A2011�N�ɔA�`��+2�ACr.1.22�ŁA�t���a�̏����Ƃ������Ƃ�������A��t�͐��������߂Ă���܂������A�����d�����Z�����������@�̂��߂Ɏd�����x�ގ����o�����܂���ł������A�a�C�̔��o����3�N��ɁA�厡��Ɂu���̐t���a�͂ǂ�������ނȂ�ł��傤���H�v�ƕ������Ƃ���A������������A�`�������Ȃ��̂ő����t�d���ǂł��傤�ƌ����܂����B���̌�A�����t���a�֘A�̖{��ǂ݂�����A���ȗ��ŐH��������������Ă݂܂������ACKD�֘A�̖{��ǂޓ���,�t�d���ǂɂ͌��݂ł��L���Ȏ��Ö@���Ȃ��A�ƌ������Ƃ�m��܂����B
�@
�@���݂ł�1968�N�Ƀt�����X�l�����҂���������IgA�t�ǂ������A�ߔN�A1983�N�ɉ��R��A�D�y���A�L�O�傩��G���E�o�̗L���������ꂽ���Ƃɒ[���A�x�c�C��t��ɂ��J�����ꂽ�u�G���E�o�ƃX�e���C�h�܂̑�ʗÖ@�i�G�E�p���X�Ö@�j�v�ɂ�薝���t���a�̒��ŁAIgA�t�NJ��Ґ����������N�傫���������Ă��܂��E�E���݂��̎��Ö@�͓��{���������s���Ă��Ȃ��炵���ł����A�₪�Đ��E�I�ɍL�܂���ʂ������]�������ΗՏ��I�ɂ̓m�[�x���܋��̎��Ö@���Ǝv���Ă��܂��E�E������A�i�s���̕s���̕a�ƌ�����t���a�̂����̈�uIgA�t�ǁv�Ɏ����Ⴊ���v�I�ɖ��m�ɏo�Ă����̂ł�����E�E�B
�@
�����͎Ґ��̐��ځE�E���L�T�C�g�̂P�Q�y�[�W�ڂ������������B�����ׂ�������������܂��B �����N���Ȃ��ꍇ�́A�O�[�O����URL��\��t����ƃ_�E�����[�h�Ɏ��Ԃ͂�����܂���pdf�����邱�Ƃ��ł���Ǝv���܂��B12�y�[�W�ɕ\������܂��B
�@
�iIgA�t�ǂ̌��I�Ȍ����j
�@
�i���A���炩�ɂ��ꂽ�G����IgA �t�ǂ����т���G�r�f���X�j
�@
��������IgA�t�LjȊO�̖����t���a�͈ˑR�Ƃ��Č������i��ł��Ȃ��悤�Ɏv���܂��B�u���́v�Ƃ����Z�p���������{�ł͐��E��̃��x���ɔ��B���A�u���͂̔�p�͑S�z�������S����̂����A�������ʂ��Ƃ͂Ȃ��Ȃ�������A��������Ȃ����v�Ƃ�����ۂ��܂��B
�@
�@��̂���A�����t���a�͂ǂ�Ȏ��Â�H���̉��P���撣���Ă������ėǂ��Ȃ邱�Ƃ͂Ȃ��A���������̓w�͂����Ȃ���Ίm���Ɉ�������E�E�E
�@
�@�܂茻�݂ł���t���a�̎��ẤA�t���a�Ƃ����a�C�̌�������菜�����߂̎���(�����Ö@�j�ł͂Ȃ��A�u�Ǐ�̊ɘa�A����ێ��v��ړI�Ƃ��鎡�ÁE�E�ƂȂ��Ă���̂ł��傤�E�E����ł������A�V���Ŏ��ʂ܂Ō���ێ����ł���Ȃ�Ζ��͉������������R�ł��E�E
�@�@
�@�l�H���͂ɂ͔���Ȑŋ����N�X���Ȃ��o��ɓ��������Ƃ����d��Ȗ�������܂����A���͂���l���g�̐����̎����傫���������܂��B���t���͂̏ꍇ�A�T3��A1��4���Ԉȏ�K�v�ŁA���͂̕a�@�ʂ��ⓧ�͌�̋}�ȒE������N����ጌ���̏������Ԃ���������A�u���͂̓��͖w�lj����o���Ȃ��A���C���N���Ȃ��v�Ɠ��͂��Ă���F�l���畷�����ꂽ���Ƃ�����܂��E�E�E�܂葽���̕��ɂƂ��ē��͊J�n��͎c��̐l���̔����������ɂ��������A�S�����ꂽ�����ɂȂ��Ă��܂��Ǝv���̂ł��E�E
�@
�@��t���Ƒn�I�Ȍ��������A����������ɂ܂Ŏ����čs�����Ƃ͑�ςȂ��ƂƎv���܂��B�w��̃K�C�h���C�������ꂽ���Â����Ď��s�����犳�҂���i�����邩���m��܂���B�@���������͉��������ɍ~���܂Ȃǂ����ނ����ŁA�����������͂�҂i�̂Ȃ玀��҂j�̂ł͂Ȃ��A�v�������Ƃ�F�X�����̐g�̂Ŏ����Ă݂����Ǝv���Ă��܂��B�@
�@���҂łȂ���Ώo���Ȃ��悤�Ȏ��݂̒��ɁA�����ۑ����̗Ö@�Ƃ��Ăق�̏����ł����ʓI�Ȃ��Ƃ����邩���m��Ȃ��Ƃ�����ՂƂ��v�����]�����������̂ł��B
�@
12�@�@����CKD�̐��� �@
�@
���y�[�W�̃O���t��2011�N1�����猻�݁i2020�N6���j���̂P�^Cr.�̋L�^�ł��B�@�@�@
2017�N6������A�����M�[��}���������ݎn�߂�������A��≡���ɂȂ��ė������������܂��E�E
�@
13�@�A����@�i���������z�z�j �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@
��880-0841 �{�茧�{��s�g�����ʕ{���b1716-27�@���V�����Y�@
�i���[���jk-yazawa��miyazaki-catv.ne.jp�@
�i�������ɕς��Ă��������j
�@�d�b�i�X�}�z�j080-4313-1719
�@
���u�����R�s�[�v������]�̕��ɂ͎���ɂėX���������܂��B
�i��p�F1���̏ꍇ�j
�@�@�����v�����g��@ 94��×3�~��280�~
�@�@��`�O�X�ց@�i1��380���j�@ 370�~
�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@ �@ ���v650�~
�@
(���[�����d�b�ł��\�����݂����������A�����؎�ŏ�L�Z���ɗX�����Ă��\�����݉������E�@�U�荞�݂�����]�̍ۂ̓��[���ł��m�点�������B�j
�@
�����ɗ�����ꍇ��1��280�~�ł��B
�ꏊ�͋{��s�̓����w�@���Z�̋߂��ł��B
���i�q�{��w�����A�����͒����������ԏ�ł��n�����ł��܂��B(�\�����ݒ����Ă���ŐV�����v�����g���܂��̂Ŏ��O�Ɍ�\������)
�@
�@
�i���w�I�G�r�f���X�̂Ȃ����e���܂܂�Ă��܂��̂ŁA���́A�摜���ɖ��f�]�ڂ����������������j
 5-2 �E�E�e�h�{�f�̊Ǘ����@�@�@�@�@
5-2 �E�E�e�h�{�f�̊Ǘ����@�@�@�@�@
 5-2 �E�E�e�h�{�f�̊Ǘ����@�@�@�@�@
5-2 �E�E�e�h�{�f�̊Ǘ����@�@�@�@�@
 7-2 �E�E�A�~�m�_�X�R�A�̒Ⴂ����ς����̐ێ�@ �@
7-2 �E�E�A�~�m�_�X�R�A�̒Ⴂ����ς����̐ێ�@ �@
 8-1-2 �E�E24���Ԓ~�A������@�@
8-1-2 �E�E24���Ԓ~�A������@�@
 �@9�@�@���̑����낢��@�@�@
�@9�@�@���̑����낢��@�@�@
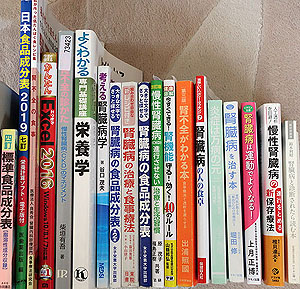 ���̂����S���Ǝv���܂��B�Ȃ��A��w�I�ȓ��e�̕����Ɋւ��ẮA���͈�t�ł͂Ȃ��̂Œf��I�ȕ\�����ł��Ȃ����Ƃ����������������B
���̂����S���Ǝv���܂��B�Ȃ��A��w�I�ȓ��e�̕����Ɋւ��ẮA���͈�t�ł͂Ȃ��̂Œf��I�ȕ\�����ł��Ȃ����Ƃ����������������B
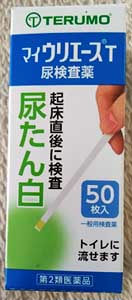
 �����g���Ύ����Œ��ׂ鎖���o���܂�)�B�@�@�@
�����g���Ύ����Œ��ׂ鎖���o���܂�)�B�@�@�@
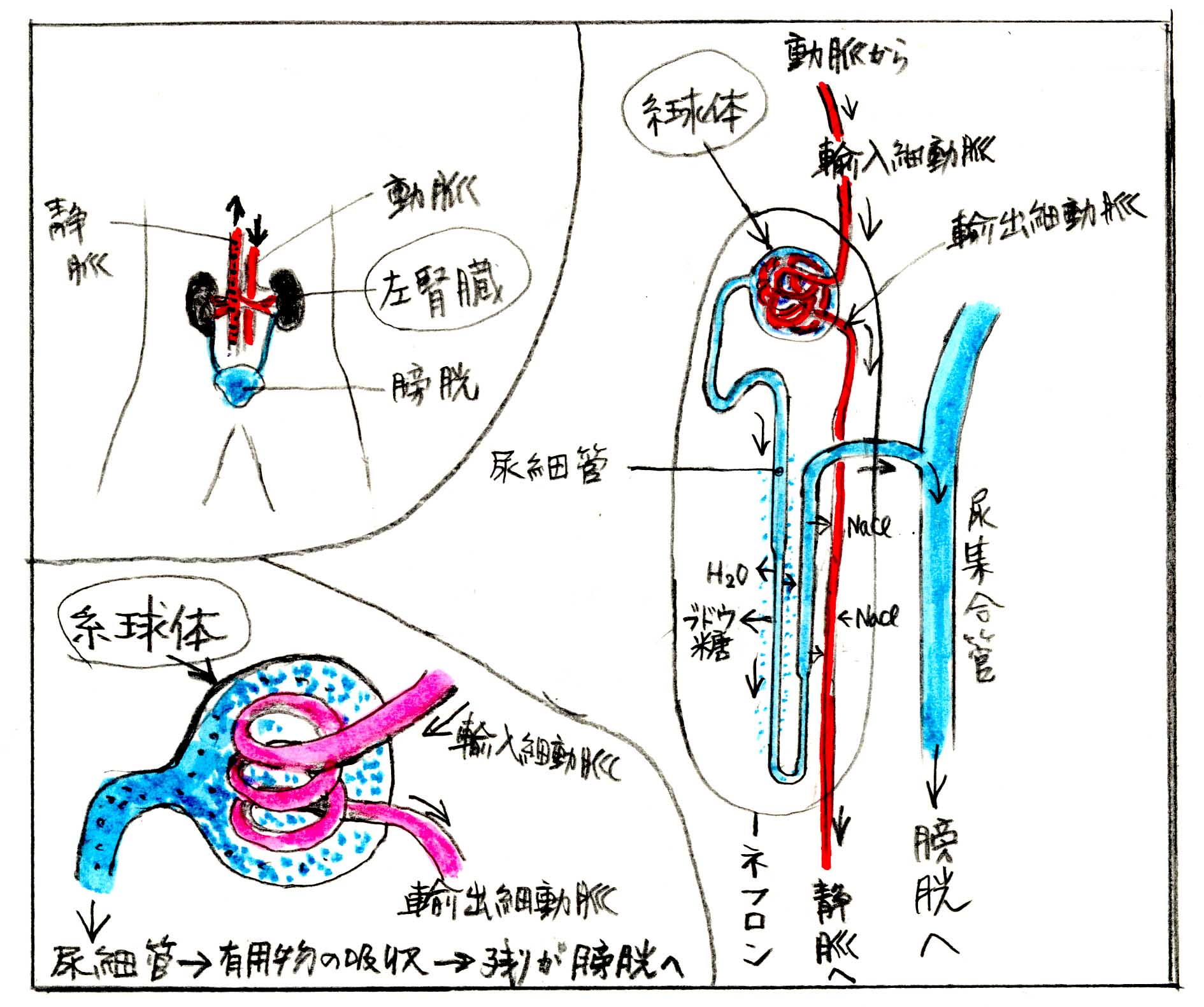
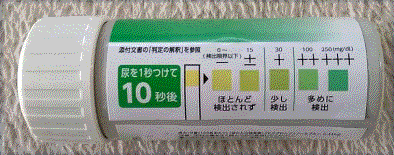

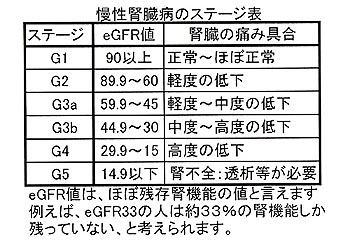 �i��1)���͂Ƃ́E�E�@�\���Ȃ��Ȃ����t���̑���Ɍ��t��l�H�I�ɏ����ƂŁA�r�̐Ö��ɓ_�H�̂悤�ɐj���h�����t���A���̌��t���h�ߊ�ɑ����ĘV�p���̖w�ǂ��h�߁A�������A���ꂢ�ɂȂ������t���̐Ö��ɖ߂��܂��B
�i��1)���͂Ƃ́E�E�@�\���Ȃ��Ȃ����t���̑���Ɍ��t��l�H�I�ɏ����ƂŁA�r�̐Ö��ɓ_�H�̂悤�ɐj���h�����t���A���̌��t���h�ߊ�ɑ����ĘV�p���̖w�ǂ��h�߁A�������A���ꂢ�ɂȂ������t���̐Ö��ɖ߂��܂��B
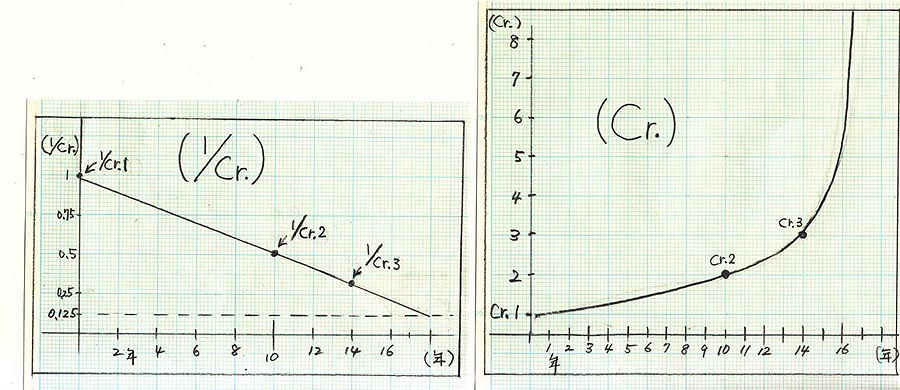 �@
�@
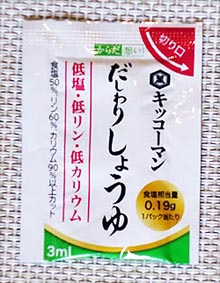


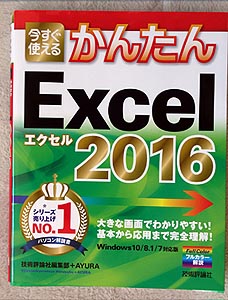
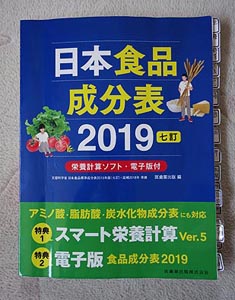

 �@�T-�Q�@�@�e�h�{�f�̊Ǘ����@�@
�@�T-�Q�@�@�e�h�{�f�̊Ǘ����@�@
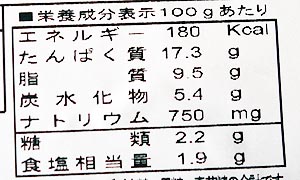

 �����������炷�ɂ́A�H���̌��������K�v�ł��E�E�a�H�̏ꍇ�A���������̂��߂ɂ͊���̓`���H����߂Ȃ���Ȃ�Ȃ���������܂���B
�����������炷�ɂ́A�H���̌��������K�v�ł��E�E�a�H�̏ꍇ�A���������̂��߂ɂ͊���̓`���H����߂Ȃ���Ȃ�Ȃ���������܂���B
 ��ʂ̃p��50���i��130kcal�j�ɂ͉�����0.6g�ʓ����Ă܂��B����A��`���p���ł́A�Ⴆ�A�ł������̏��Ȃ��u��`���p���v�ł�50���i146kcal�j�ʼn����͕��ʃp����10����1�ŁA�͂�0.06���ł��B�W������h���ĐH�ׂ�Ή���0.1g���x�ŐH�ׂ�܂��B�@������т̕��͈�ʓI�ɂ͉����̗��������̂��~�����Ȃ�܂��B���̂��Ƃ���A�����𐧌�����ɂ͂��ѐH�����p���H�̕����ȒP�ƌ����܂��B���ѐH�̗ǂ��_�́A���т���ꍇ�ɂ́A�J�����[�̔����ȃR���g���[�������Ղ��_�ł��傤�E�E�p���H�̏ꍇ�ɂ̓J�����[�̔�������
��ʂ̃p��50���i��130kcal�j�ɂ͉�����0.6g�ʓ����Ă܂��B����A��`���p���ł́A�Ⴆ�A�ł������̏��Ȃ��u��`���p���v�ł�50���i146kcal�j�ʼn����͕��ʃp����10����1�ŁA�͂�0.06���ł��B�W������h���ĐH�ׂ�Ή���0.1g���x�ŐH�ׂ�܂��B�@������т̕��͈�ʓI�ɂ͉����̗��������̂��~�����Ȃ�܂��B���̂��Ƃ���A�����𐧌�����ɂ͂��ѐH�����p���H�̕����ȒP�ƌ����܂��B���ѐH�̗ǂ��_�́A���т���ꍇ�ɂ́A�J�����[�̔����ȃR���g���[�������Ղ��_�ł��傤�E�E�p���H�̏ꍇ�ɂ̓J�����[�̔�������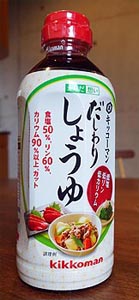 �u�����v���ł��邱�ƂɂȂ�ł��傤�E�E������1g ��4kcal�ł��B
�u�����v���ł��邱�ƂɂȂ�ł��傤�E�E������1g ��4kcal�ł��B

 ������������������ƕs�������Ƃ��E�E�P���ɉ���U�肩���܂��B��~�肪���O�����ɂȂ邩�A�v�Z���Ă����Ɨǂ��Ǝv���܂��B�Ⴆ��100��U���ďo�Ă������̏d�����T���Ȃ�Έ�~���0.05���ł��B�r�̌��̌�����������Ƃ��̓Z���e�[�v�łӂ����܂��B���C�͗v���ӂł��B�܂��A�s�̕i�ł�0.3g�A1g�A 2g���̏��ܓ���H��������܂��B�o������ݖ��̂R������Ȃǂ��֗��ł��B
������������������ƕs�������Ƃ��E�E�P���ɉ���U�肩���܂��B��~�肪���O�����ɂȂ邩�A�v�Z���Ă����Ɨǂ��Ǝv���܂��B�Ⴆ��100��U���ďo�Ă������̏d�����T���Ȃ�Έ�~���0.05���ł��B�r�̌��̌�����������Ƃ��̓Z���e�[�v�łӂ����܂��B���C�͗v���ӂł��B�܂��A�s�̕i�ł�0.3g�A1g�A 2g���̏��ܓ���H��������܂��B�o������ݖ��̂R������Ȃǂ��֗��ł��B
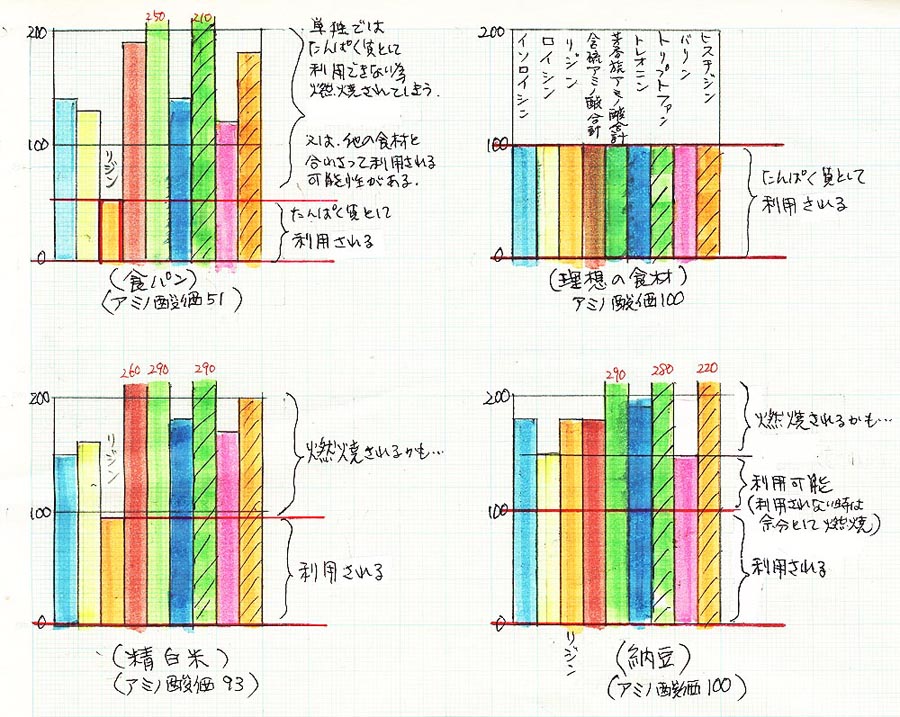
 �ł͔����������������܂����A��������1/35�ɂȂ�Ƃ�����Ɩ��C�Ȃ���������܂���B���A��`�����тɂ͐t���җp����H�i�̔F���擾���Ă��镨������܂��B�F�i���ƈ��S���Ƃ͎v���܂�����ނ͏��Ȃ��ł��B���ʗʂƂ��Ă͒`����1/25�������悤�Ɏv���܂��B
�ł͔����������������܂����A��������1/35�ɂȂ�Ƃ�����Ɩ��C�Ȃ���������܂���B���A��`�����тɂ͐t���җp����H�i�̔F���擾���Ă��镨������܂��B�F�i���ƈ��S���Ƃ͎v���܂�����ނ͏��Ȃ��ł��B���ʗʂƂ��Ă͒`����1/25�������悤�Ɏv���܂��B

 �@5-2-3�@�J���E�E���Ǘ��@
�@5-2-3�@�J���E�E���Ǘ��@
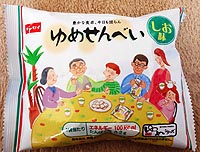

 �@
�@
 �@5-2-6�@�����Ǘ��@
�@5-2-6�@�����Ǘ��@

 ���J�����[�ɂȂ�h�{�f�́A�`�����A�����A�����ē��������ł��B�`�����𐧌����A�����d�����Ă����鎉�����قǂقǂɂ���ƁA�J�����[���Ƃ��Ďc��͓�����������܂���B�����̖L�x�ȕ��ʂ̂��т�p���͒`��������R����̂ŁA��`���̓���H�i���g�킴��܂���B �@����𗘗p����ƁA�H��R�O����������Ƃ������Z������܂����A�m����1���R�p�b�N�H�ׂ�ƁA3�p�b�N×��200×365����219,000�~/�N�ł��B���̑��ɂ��F�X�o��������ő�ςł��E�E���߂ď���ł͖����ɂ��ė~�����Ƃ���ł��E�E
���J�����[�ɂȂ�h�{�f�́A�`�����A�����A�����ē��������ł��B�`�����𐧌����A�����d�����Ă����鎉�����قǂقǂɂ���ƁA�J�����[���Ƃ��Ďc��͓�����������܂���B�����̖L�x�ȕ��ʂ̂��т�p���͒`��������R����̂ŁA��`���̓���H�i���g�킴��܂���B �@����𗘗p����ƁA�H��R�O����������Ƃ������Z������܂����A�m����1���R�p�b�N�H�ׂ�ƁA3�p�b�N×��200×365����219,000�~/�N�ł��B���̑��ɂ��F�X�o��������ő�ςł��E�E���߂ď���ł͖����ɂ��ė~�����Ƃ���ł��E�E
 �j��������Ă��܂��B
�j��������Ă��܂��B
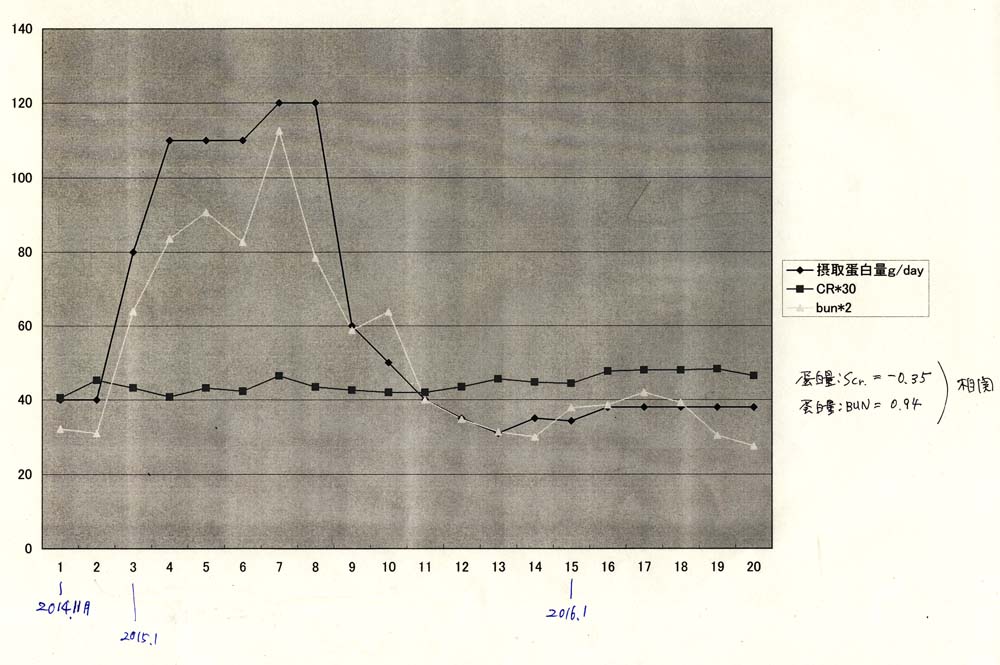 �@
�@

 �u����Ȃ��̂ł��傤���H(����ł́A�̔������̒i�K�ŁA���p�҂ɐ������K�v�Ȃ̂ň��i�I�Ȉ����Ƃ����ׁA��ʏ����X�ɂ͒u���Ȃ������ƕ��������Ƃ�����܂��E�E)�@��`���ĂȂǂ̓���H�i�̐��X�̓l�b�g��ɑ�R����܂����A1���P�ʁi20�`30����j�ł��������Ă��Ȃ��Ƃ��낪�����A��`���Ăɋ����������Ă���ʂɔ����A�Ƃ����̂��S�O����l������Ǝv���܂��B�����ƐϋɓI�ɃX�[�p�[�Ƀo������Œu���Ă����A������1�g���ĐH�ׂĂ݂悤�E�E�Ƃ���������CKD���҂��o�Ă���̂ɂƎv���܂��B
�u����Ȃ��̂ł��傤���H(����ł́A�̔������̒i�K�ŁA���p�҂ɐ������K�v�Ȃ̂ň��i�I�Ȉ����Ƃ����ׁA��ʏ����X�ɂ͒u���Ȃ������ƕ��������Ƃ�����܂��E�E)�@��`���ĂȂǂ̓���H�i�̐��X�̓l�b�g��ɑ�R����܂����A1���P�ʁi20�`30����j�ł��������Ă��Ȃ��Ƃ��낪�����A��`���Ăɋ����������Ă���ʂɔ����A�Ƃ����̂��S�O����l������Ǝv���܂��B�����ƐϋɓI�ɃX�[�p�[�Ƀo������Œu���Ă����A������1�g���ĐH�ׂĂ݂悤�E�E�Ƃ���������CKD���҂��o�Ă���̂ɂƎv���܂��B
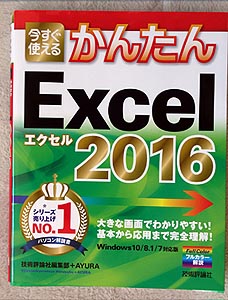 �@5-5�@�@�h�{�Ǘ��̓G�N�Z����
�@5-5�@�@�h�{�Ǘ��̓G�N�Z����




 �@�@�@
�@�@�@
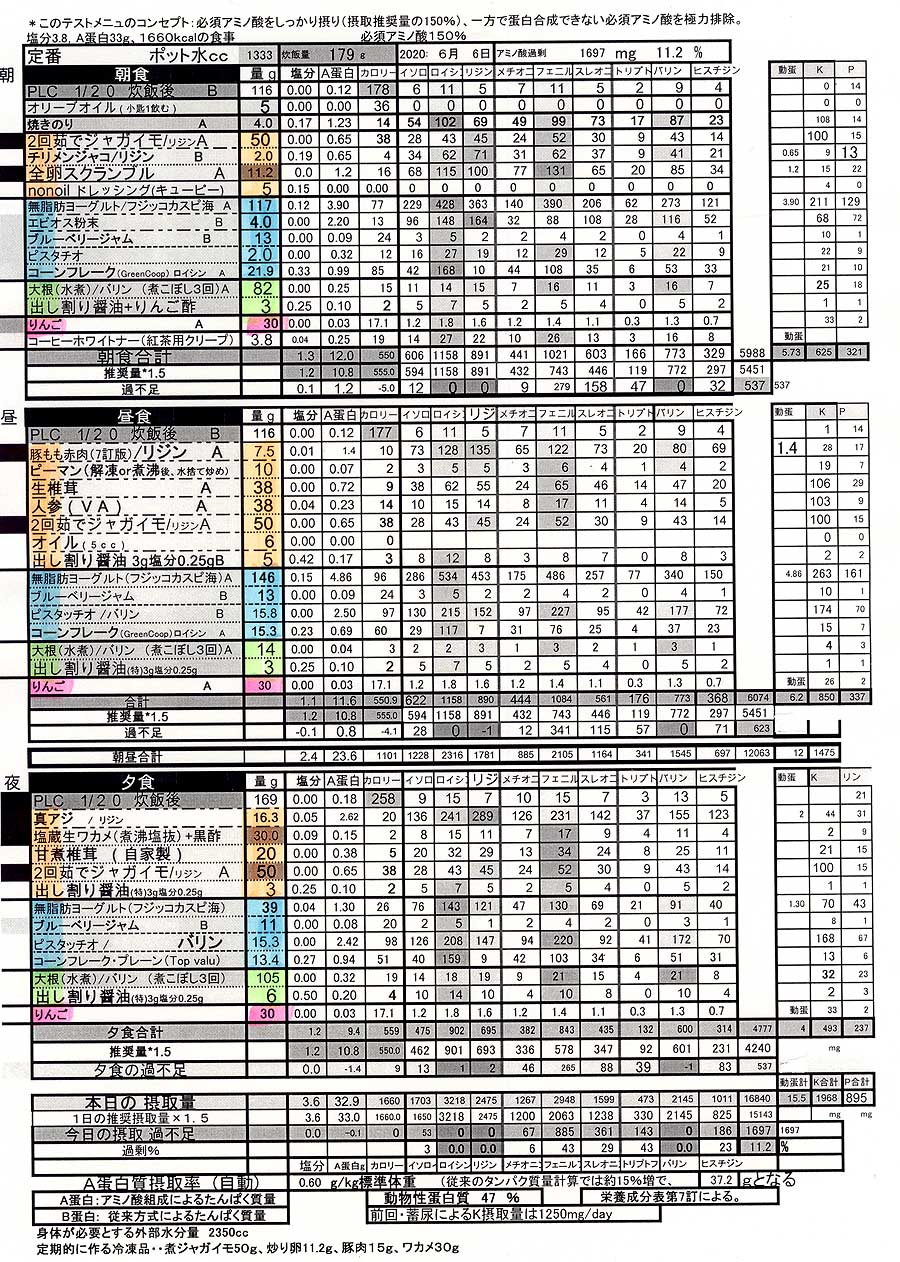
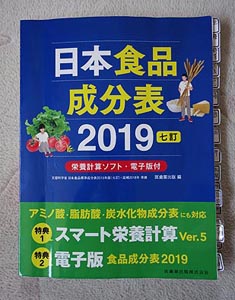 ��8�|14�|1�ɂ��L��������܂�
��8�|14�|1�ɂ��L��������܂�
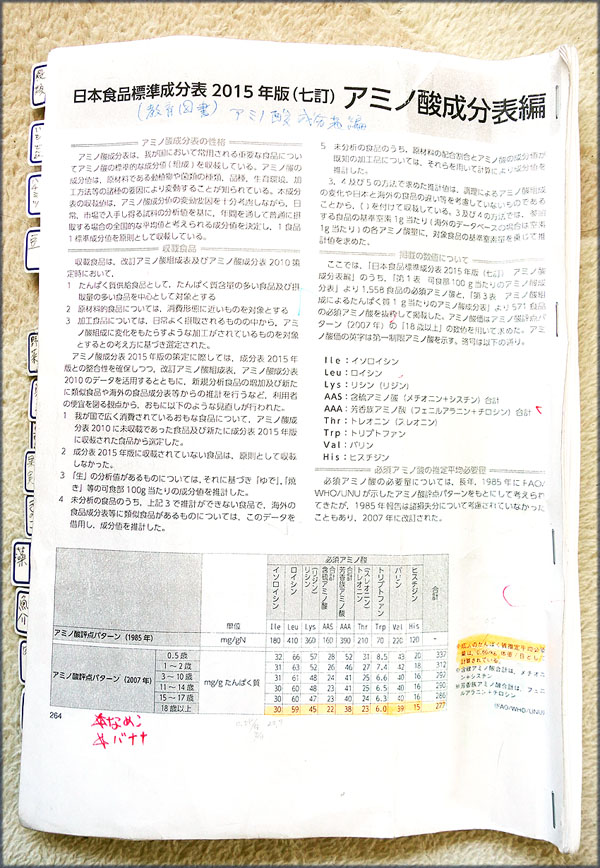 �{��T���Ă݂Ă��������B�j�@�X�ɁA�K�{�A�~�m�_�ʂׂ�ɂ́A
�{��T���Ă݂Ă��������B�j�@�X�ɁA�K�{�A�~�m�_�ʂׂ�ɂ́A
 ��悤�ɁA�{���̕��Î������Ƃ͌����Ȃ��ꍇ������܂��B�~���܂�K�v�ȏ�Ɉ��܂Ȃ��čςނ悤�A��t�ɓI�m�Ȕ��f�����Ă��炤���߂ɂ́A�ƒ�ő������������O1�������́u�����A�A�Q�O�����̕\�v���������Ɏ��Q����K�v������Ǝv���܂��B
��悤�ɁA�{���̕��Î������Ƃ͌����Ȃ��ꍇ������܂��B�~���܂�K�v�ȏ�Ɉ��܂Ȃ��čςނ悤�A��t�ɓI�m�Ȕ��f�����Ă��炤���߂ɂ́A�ƒ�ő������������O1�������́u�����A�A�Q�O�����̕\�v���������Ɏ��Q����K�v������Ǝv���܂��B
 �@7-11�@�@�O�a���b�_�@
�@7-11�@�@�O�a���b�_�@
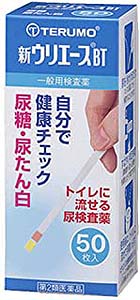 �@7-13�@�@���A�a�@
�@7-13�@�@���A�a�@
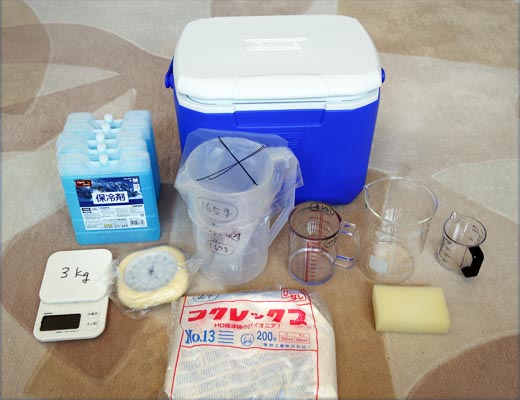






 �i2.5�k�J�b�v�̏ꍇ�A�|���܂́A��260×��380mm�O��A���i���Ƃ��Ắu�t�N���b�N�XNo.13�v�Ȃǂ��l�b�g��ɂ���܂��B�y�V�s��ł�200�����肪����悤�ł��j�B
�i2.5�k�J�b�v�̏ꍇ�A�|���܂́A��260×��380mm�O��A���i���Ƃ��Ắu�t�N���b�N�XNo.13�v�Ȃǂ��l�b�g��ɂ���܂��B�y�V�s��ł�200�����肪����悤�ł��j�B




 ��G�߂͗�p�܂͕s�v�ł��B�B
��G�߂͗�p�܂͕s�v�ł��B�B




 �̐M�����������܂���j
�̐M�����������܂���j
 �@8-3-3 �@ �x�X�g�̏d��m�� �E�E�����Ɠ������x�̐H��(�K��̃J�����[)��ۂ�A�������x�̘J����^���������̂Ȃ�A�������A��̑̏d�͂قړ����ɂȂ�͂��ł��B�����̏d�������Ă�����A�O���H�߂������A�����̎�肷����A�����̐ۂ肷���Őg�̂��ނ��̂����m��܂���B�����̏d��ʂ�A���ʂɐH�����Ƃ��Ă����Ԃōł����Ȃ��̏d���x�X�g�̏d�ł��B�����A�����̏d�v���x�X�g�̏d����������A�����͐�D���ȓ��ł��B
�@8-3-3 �@ �x�X�g�̏d��m�� �E�E�����Ɠ������x�̐H��(�K��̃J�����[)��ۂ�A�������x�̘J����^���������̂Ȃ�A�������A��̑̏d�͂قړ����ɂȂ�͂��ł��B�����̏d�������Ă�����A�O���H�߂������A�����̎�肷����A�����̐ۂ肷���Őg�̂��ނ��̂����m��܂���B�����̏d��ʂ�A���ʂɐH�����Ƃ��Ă����Ԃōł����Ȃ��̏d���x�X�g�̏d�ł��B�����A�����̏d�v���x�X�g�̏d����������A�����͐�D���ȓ��ł��B
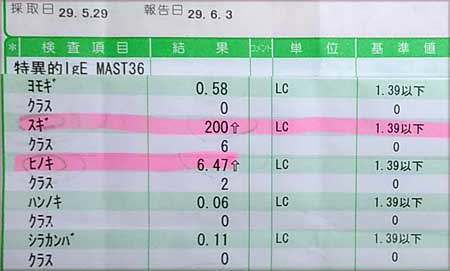 �E�E�������Ǝ��͖��N�t��ɂȂ�ƝG������炵�A���M�����܂�Ȃ����߂ɓ��Ȉ�ɍs���ƁA��t����͍A���^���Ԃł���E�E�ƌ����čR�ۍ܂��M�܂�2�C3������������O�ɂȂ��Ă��܂����B
�E�E�������Ǝ��͖��N�t��ɂȂ�ƝG������炵�A���M�����܂�Ȃ����߂ɓ��Ȉ�ɍs���ƁA��t����͍A���^���Ԃł���E�E�ƌ����čR�ۍ܂��M�܂�2�C3������������O�ɂȂ��Ă��܂����B
 �@8-5�@�@�֔��@�E�E�E�ő��A�}�b�V�����[���ŁA���ցB�E�ECKD�ۑ����̍ŏI�X�e�[�W�ł͊����Y�p���A�����̓őf���z�����鎡�Â��s���Ă��܂��B����ԂɃI���[�u�I�C���������P�t�����݁A���ނȂǂ̐H���@�ۂ�H�ׂ�ƈ�ʓI�ɕ֒ʂ��ǂ��Ȃ�Ǝv���܂��B���͐��̒ő����Z�Ŗ���45���̒ő���H�ׂ�悤�ɂ��Ă��܂��B
�@8-5�@�@�֔��@�E�E�E�ő��A�}�b�V�����[���ŁA���ցB�E�ECKD�ۑ����̍ŏI�X�e�[�W�ł͊����Y�p���A�����̓őf���z�����鎡�Â��s���Ă��܂��B����ԂɃI���[�u�I�C���������P�t�����݁A���ނȂǂ̐H���@�ۂ�H�ׂ�ƈ�ʓI�ɕ֒ʂ��ǂ��Ȃ�Ǝv���܂��B���͐��̒ő����Z�Ŗ���45���̒ő���H�ׂ�悤�ɂ��Ă��܂��B
 �@�������K�x�ȉ^����CKD���҂́u�̗͈ێ��v�Ƃ����ϓ_���琄������邱�Ƃ́A�K�x�ł���Γ��R���Ǝv���܂��B
�@�������K�x�ȉ^����CKD���҂́u�̗͈ێ��v�Ƃ����ϓ_���琄������邱�Ƃ́A�K�x�ł���Γ��R���Ǝv���܂��B
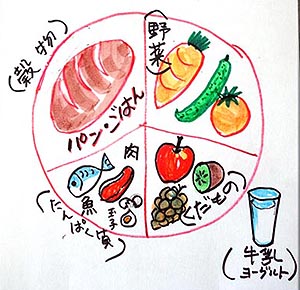 ���܂��B
���܂��B
 �X�Ȍ������ȒP�ɑ����B�~�G�Œ�����Ԃł������܂���K�v���Ȃ��̂ŁA��O�I�Ɏ��������v�������m�ɑ���邩���m��Ȃ����A��ʘ_�Ƃ��ẮA��r�ł̑���̕����M������Ă��܂��B����v�́A���e�̉��ɓ����Ȃǂ��āA�����v���S���̍����ɂȂ�悤�ɂ��đ���K�v������܂��B
�X�Ȍ������ȒP�ɑ����B�~�G�Œ�����Ԃł������܂���K�v���Ȃ��̂ŁA��O�I�Ɏ��������v�������m�ɑ���邩���m��Ȃ����A��ʘ_�Ƃ��ẮA��r�ł̑���̕����M������Ă��܂��B����v�́A���e�̉��ɓ����Ȃǂ��āA�����v���S���̍����ɂȂ�悤�ɂ��đ���K�v������܂��B

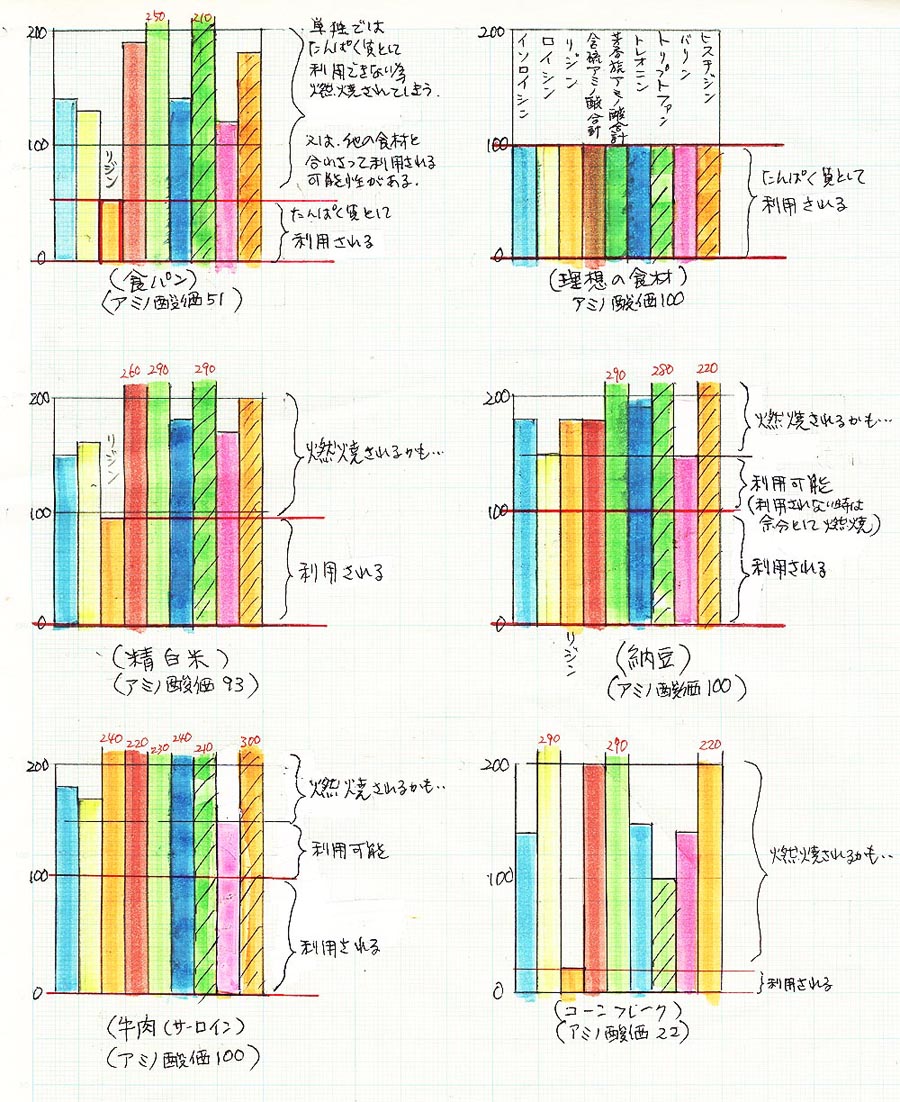 ����̃O���t�́A���낢��ȐH�ނ��A�K�{�A�~�m�_�̐ێ�K�v�ʂ��ǂ̒��x�������Ă��邩������
����̃O���t�́A���낢��ȐH�ނ��A�K�{�A�~�m�_�̐ێ�K�v�ʂ��ǂ̒��x�������Ă��邩������
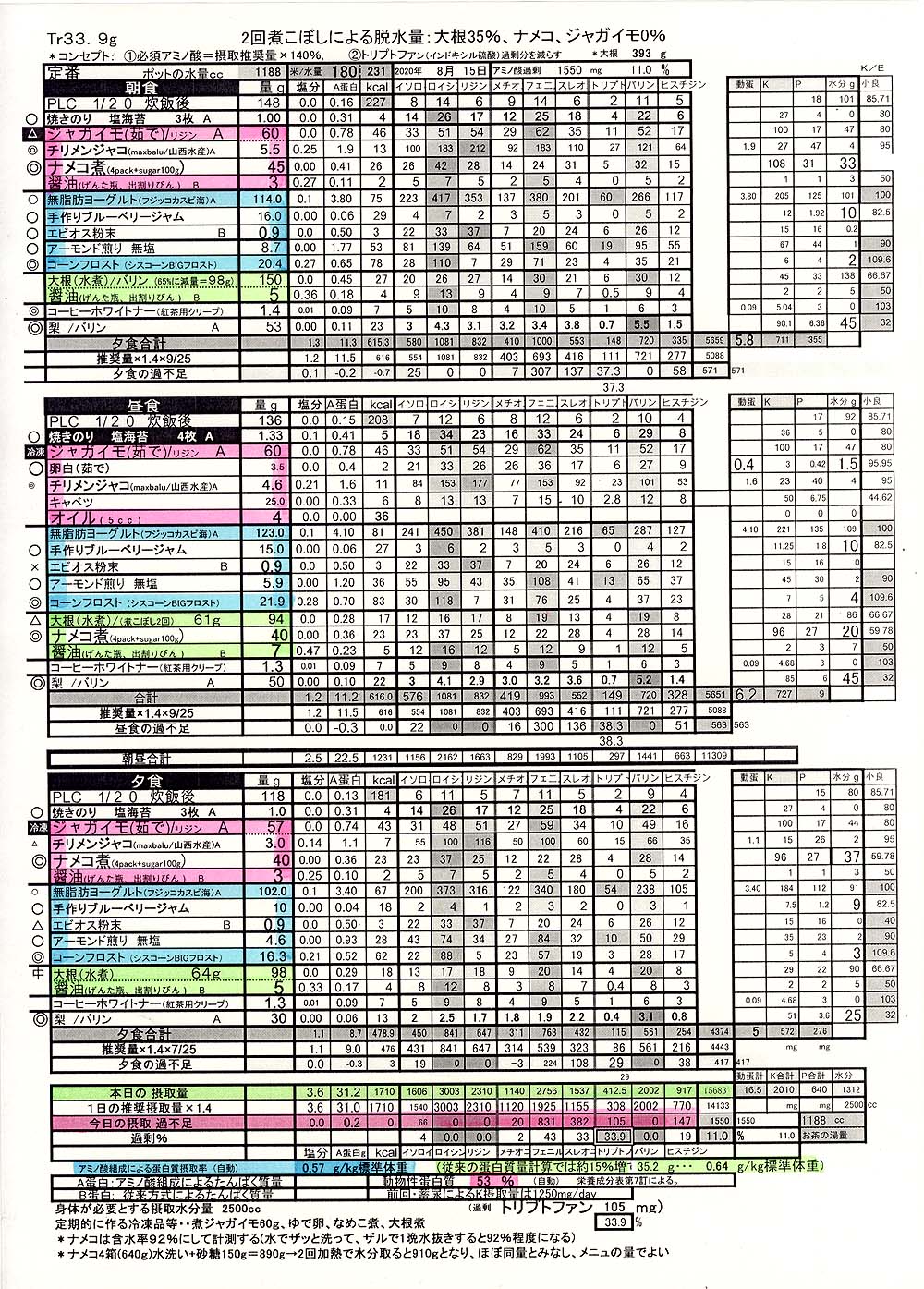
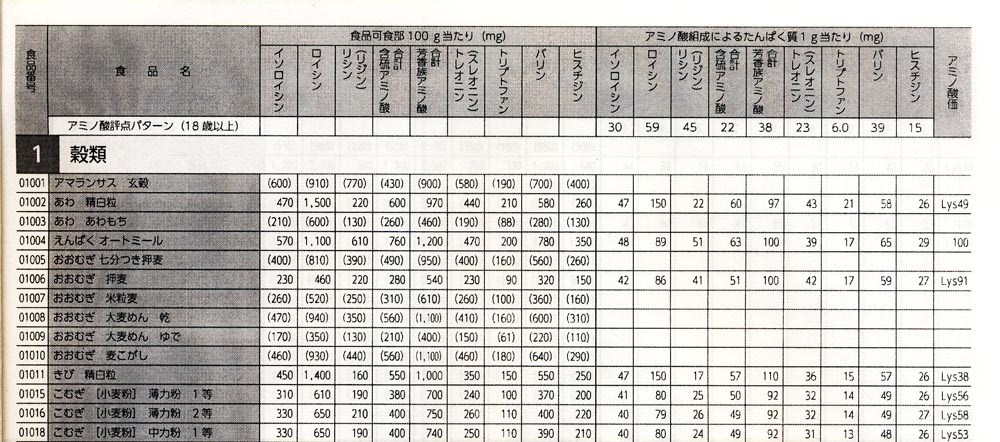
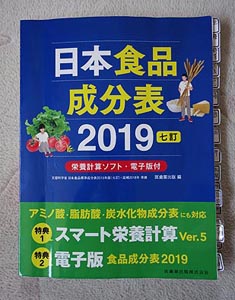 �u�A�~�m�_�g���ɂ��A����ς����̗ʁv��������܂��B����ŐH�i100g���ɃA�~�m�_�g���ɂ��`�����ʂ���g���邩�ׁA��̕\�́u�@�A�~�m�_�g���ɂ��`�����P��������̗ʁv��������ƁA���̐H�i�P�O�O��������̐��m�ȕK�{�A�~�m�_�ʂ�������܂��B�E�E�E�@�@����ł�2���̖{�����Ȃ���Ȃ炸�A���Ȍv�Z�@�ɂȂ��Ă��܂��܂����A������A1���̖{�ŕ������������Ǝv���܂��B
�u�A�~�m�_�g���ɂ��A����ς����̗ʁv��������܂��B����ŐH�i100g���ɃA�~�m�_�g���ɂ��`�����ʂ���g���邩�ׁA��̕\�́u�@�A�~�m�_�g���ɂ��`�����P��������̗ʁv��������ƁA���̐H�i�P�O�O��������̐��m�ȕK�{�A�~�m�_�ʂ�������܂��B�E�E�E�@�@����ł�2���̖{�����Ȃ���Ȃ炸�A���Ȍv�Z�@�ɂȂ��Ă��܂��܂����A������A1���̖{�ŕ������������Ǝv���܂��B
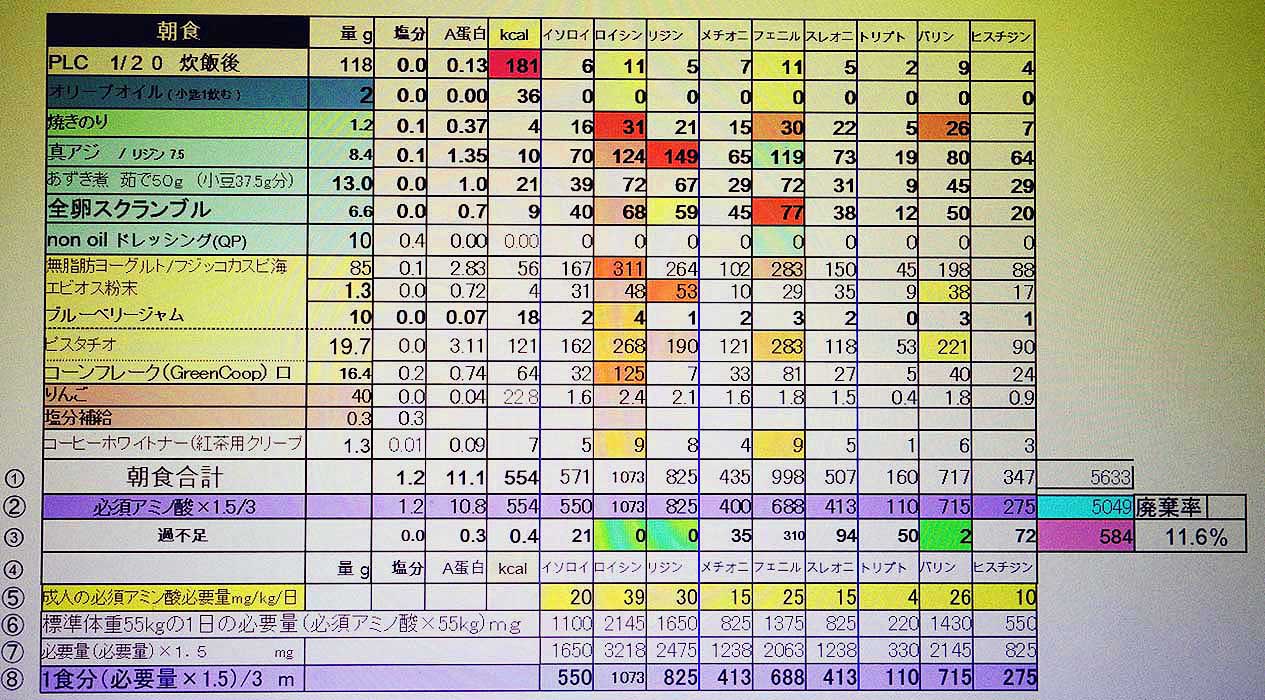
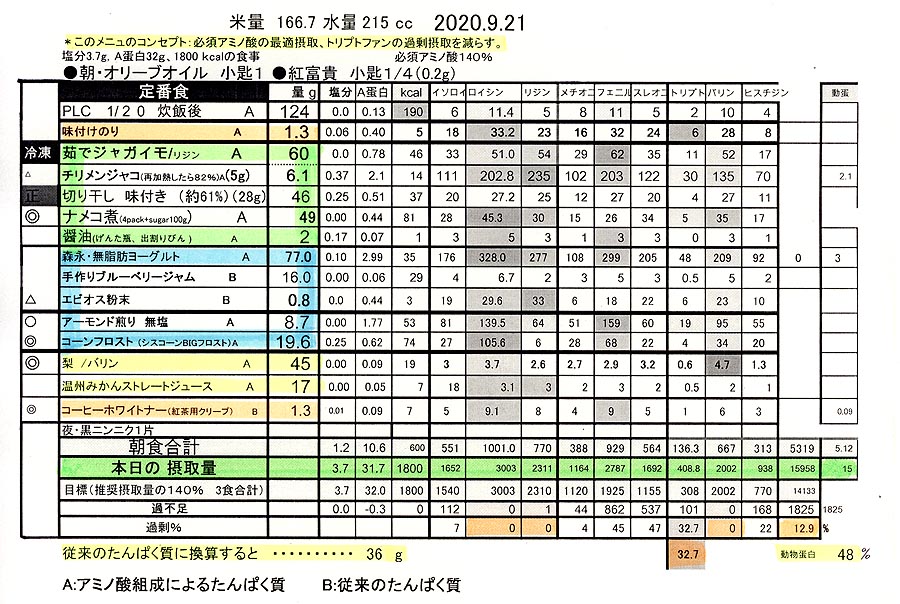
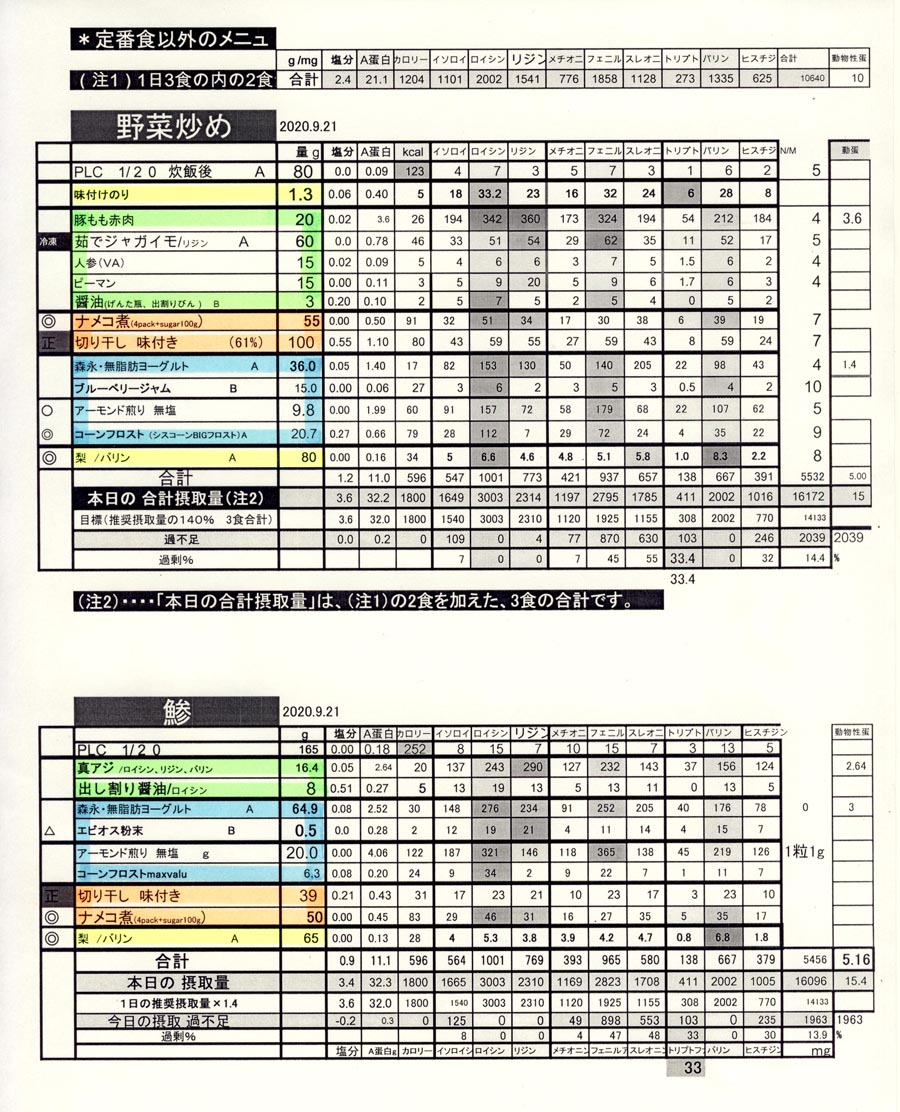
.jpg)
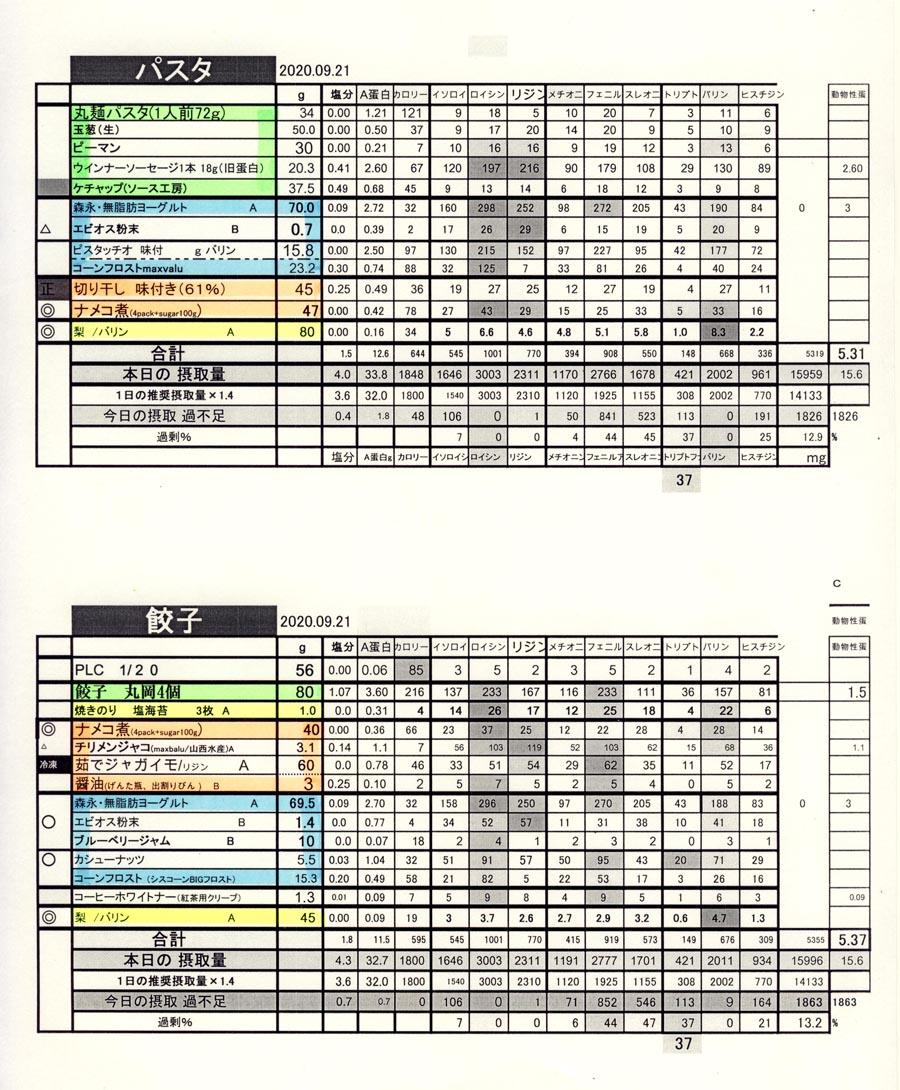
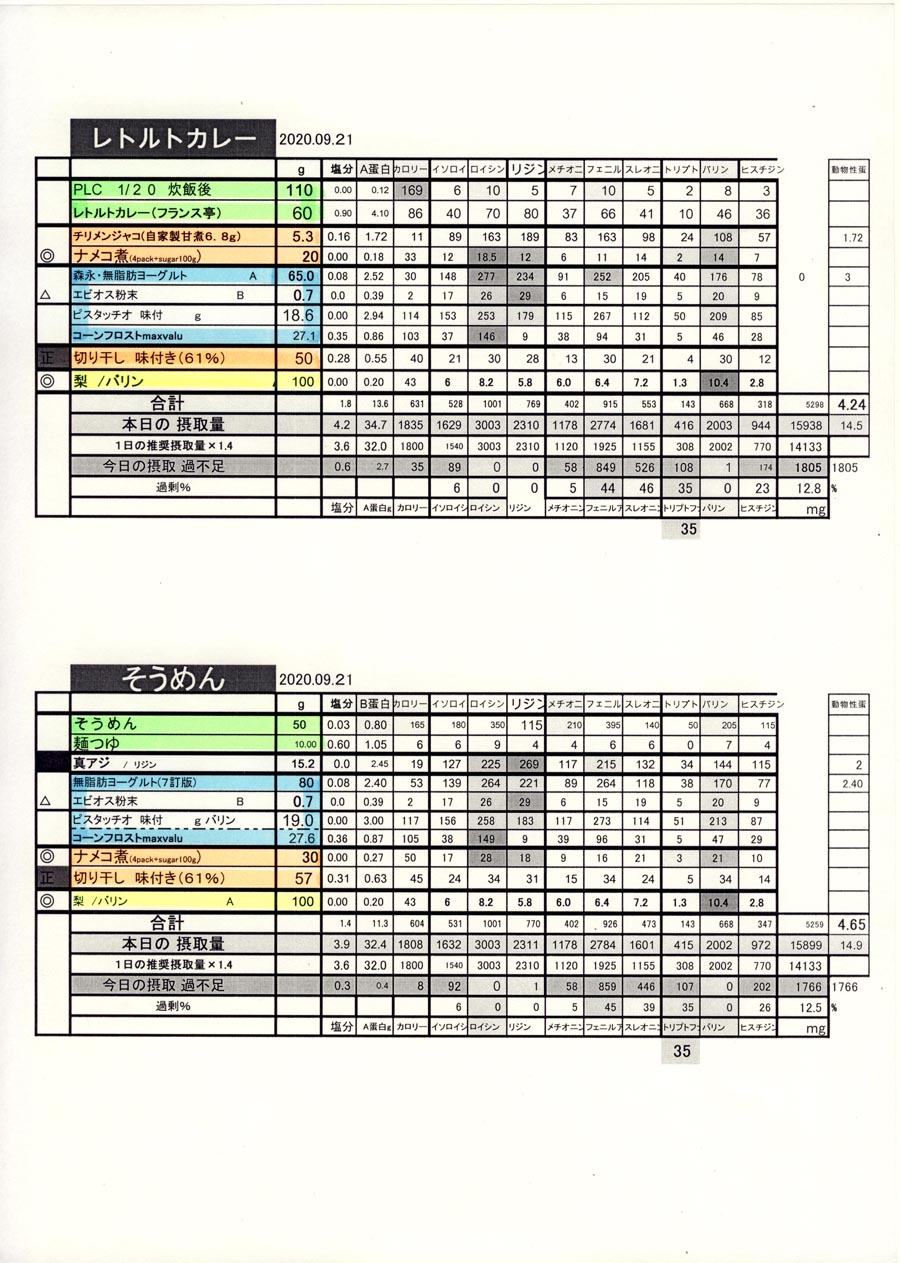
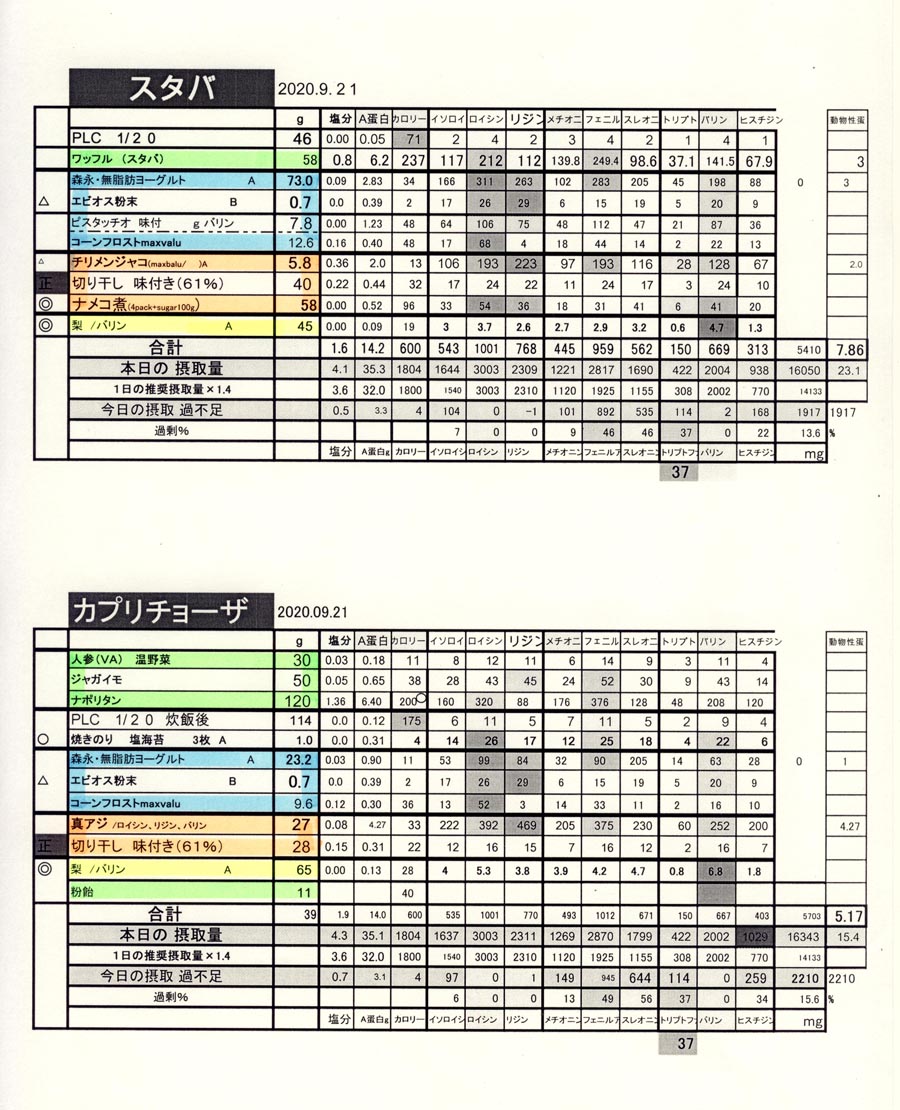
 ���ʂ̂��т̔����ȉ��ŁA���̑��̉h�{�f�͕��ʕĂƓ����ł��邱�ƁE�E�܂�`�������������炵�����A�Ƃ������Ƃł��傤�E�E���_�ۂ������Ē`�����������鏈�����ɂ��낢�뉻�w�ω����N���A�Ă̑g���ɂ��e�������邱�Ƃ͑z���ł��܂��B
���ʂ̂��т̔����ȉ��ŁA���̑��̉h�{�f�͕��ʕĂƓ����ł��邱�ƁE�E�܂�`�������������炵�����A�Ƃ������Ƃł��傤�E�E���_�ۂ������Ē`�����������鏈�����ɂ��낢�뉻�w�ω����N���A�Ă̑g���ɂ��e�������邱�Ƃ͑z���ł��܂��B
 �����Ő��т���u�ė��^�C�v�v�̓p�b�N���т���4���������Ȃ�܂��B�@�ł�������������Ŏ��R�ł����A�H�ׂ�ʂ�1���P�ʂŎ��R�ɕς����܂��B�@��`���Ă͊�{�I�ɖ����Ăł��̂Ő��т͊y�ł��B��`���Ă͌y�����ɂ���ɂ��ėⓀ����ƁA�������Ă����ނ��남�������Ȃ�悤�Ɋ����܂��B
�����Ő��т���u�ė��^�C�v�v�̓p�b�N���т���4���������Ȃ�܂��B�@�ł�������������Ŏ��R�ł����A�H�ׂ�ʂ�1���P�ʂŎ��R�ɕς����܂��B�@��`���Ă͊�{�I�ɖ����Ăł��̂Ő��т͊y�ł��B��`���Ă͌y�����ɂ���ɂ��ėⓀ����ƁA�������Ă����ނ��남�������Ȃ�悤�Ɋ����܂��B